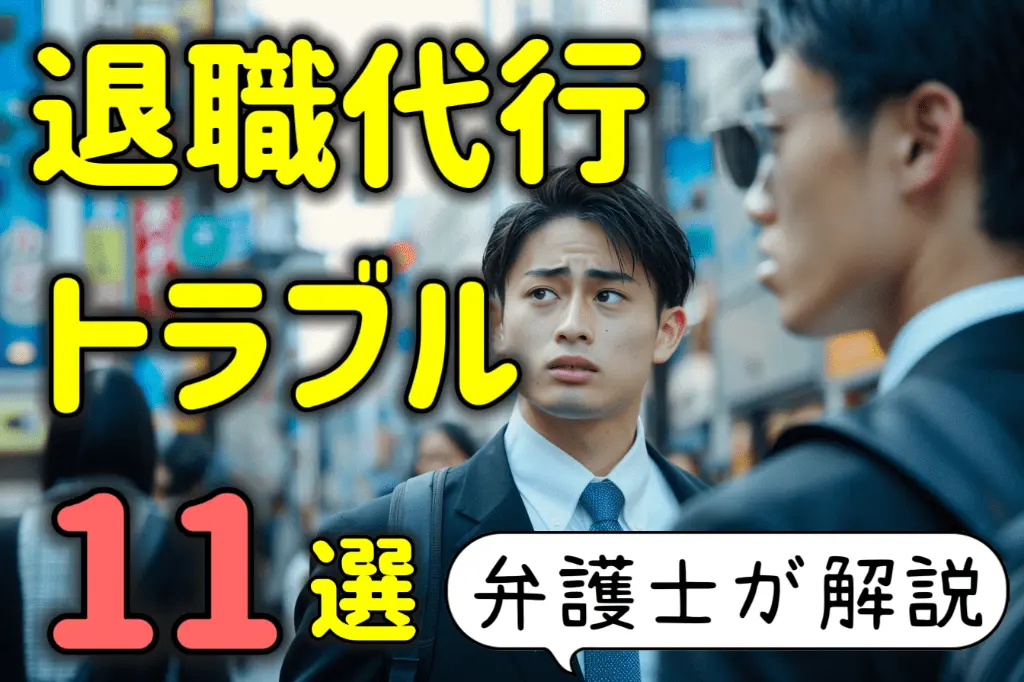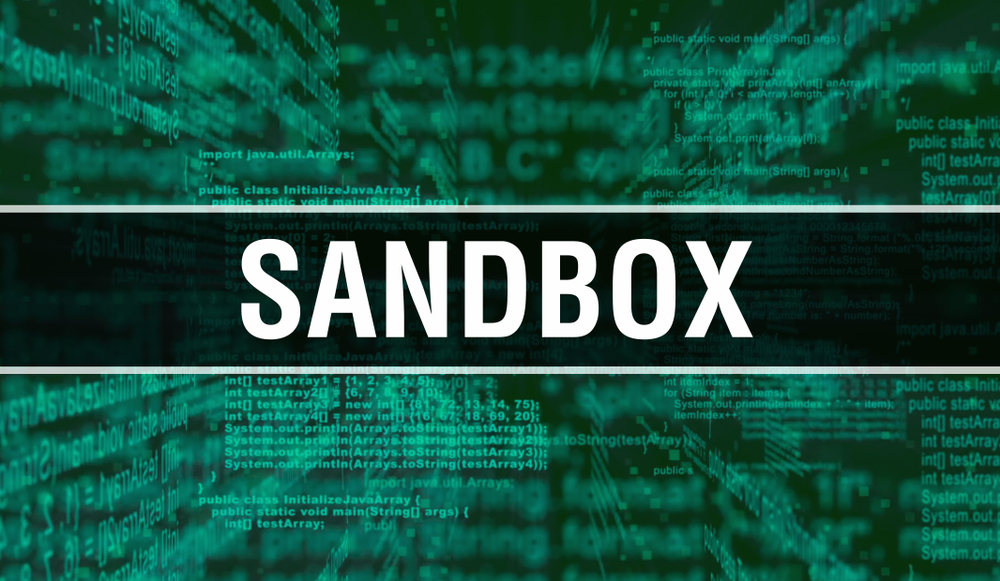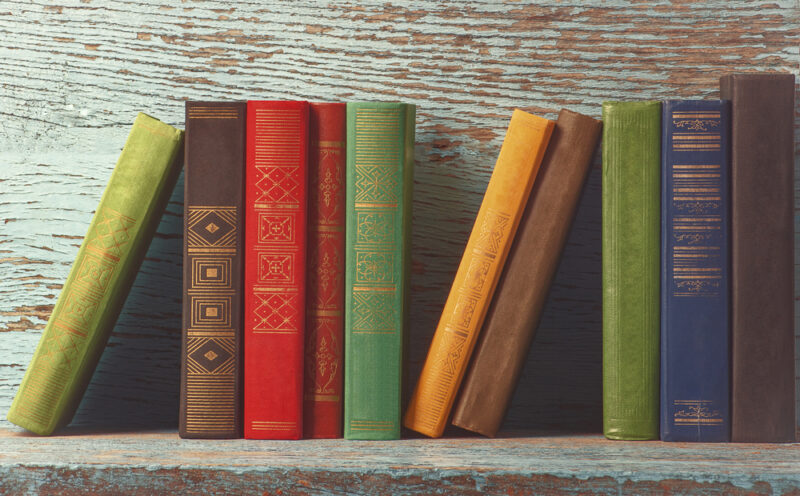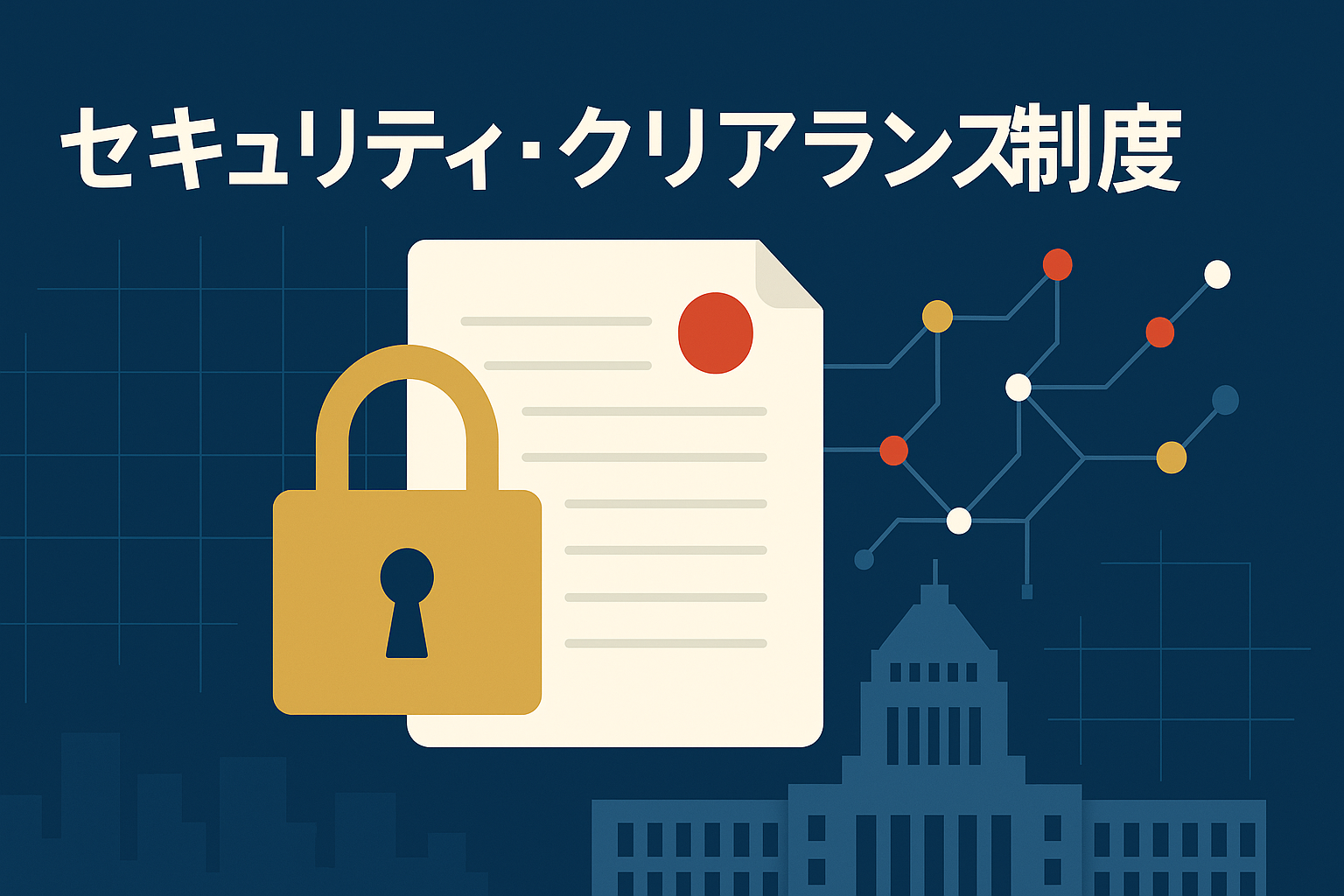資金決済法にいう「6ヶ月」とは?前払式支払手段の有効期限を解説!

はじめに
お金を扱う事業を行ううえで、密接に関わってくる法律のうちの一つが「資金決済法」です。
特に、ゲームアプリやフリマアプリ、オークションサイトなどを開発する場合には、必ずこの法律の規定を確認しておく必要があります。
さて「資金決済法」には、「6ヶ月」という期間が登場しますが、この期間が何を意味しているのか、ご存じでしょうか。
「6ヶ月」という期間が持つ意味は、スタートアップなどにとっては、とても有難いものであるといえますが、この意味を正確に理解するためには、その前提として資金決済法が規制する「前払式支払手段」を理解しておくことが必要になります。
そこでこの記事では、資金決済法における「6ヶ月」の意味について、弁護士がわかりやすく解説していきます。
1 資金決済法にいう「6ヶ月」とは?

「資金決済法」とは、お金の取り扱いや決済に関するルールを定めた法律ですが、その中に「6ヶ月」という期間が関係する規制が存在します。
それは「前払式支払手段」に関する規制です。
前払式支払手段における「6ヶ月」がどのような意味を持つのかを理解しておくことで、負担の重い義務を回避することもできます。
2 前払式支払手段とは?

まずは、「6ヶ月」の意味を紹介する前に、前払式支払手段とはどのようなものなのかを見ていきましょう。
(1)前払式支払手段
「前払式支払手段」とは、何らかの商品を手に入れるために、事前にお金から変換しておいたコインやポイント、チケットなどのことです。
具体的には、以下の条件すべてに合致しているものを「前払式支払手段」といいます。
- 金額等の財産的価値が記載・記録されること(価値の保存)
- 対価を得て発行されること(対価発行)
- 代価の支払いなどに使用できること(権利行使)
身近なものでは、交通系電子マネーの「Suica」やゲーム内で使用するコイン・ポイント、商品券、カタログギフト券などが前払式支払手段に該当します。
(2)「自家型」と「第三者型」
前払式支払手段は、利用目的に応じて、以下の2つに分類されます。
- 自家型前払式支払手段
- 第三者型前払式支払手段
それぞれ、どういったものなのでしょうか。
①自家型前払式支払手段
「自家型前払式支払手段」とは、発行している事業者が提供するサービス内でのみ利用できるものをいいます。
例えば、以下のようなものが「自家型」に該当します。
- ゲーム内コイン・ポイント
- 発行店舗のみ使える商品券
自家型前払式支払手段は、誰でも気軽に発行することが可能です。
②第三者型前払式支払手段
「第三者型前払式支払手段」とは、発行している事業者だけでなく、ほかの事業者が提供するサービスでも利用できるものをいいます。
例えば、以下のようなものが「第三者型」に該当します。
- 交通系電子マネー
- 加盟店で使える商品券
ただし、第三者型は、誰でも簡単に発行できるものではありません。
第三者型前払式支払手段を発行するときは、財務(支)局等から第三者型前払式支払手段発行者として登録を受ける必要があります。
(3)前払式支払手段発行者に発生する義務
前払式支払手段の発行者には、いくつか義務が発生します。この義務は、自家型であるか第三者型であるかを問わず、前払式支払手段を発行していれば、必ず発生するものです。
前払式支払手段発行者に課される主な規制は、以下の2つです。
- 情報の提供義務
- 発行保証金の供託義務
「情報の提供義務」は、発行者の氏名や苦情相談窓口の所在地・連絡先などを、利用者にわかりやすく情報提供する義務です。
何かしらのトラブルが発生したとき、利用者が発行者への問い合わせをするときなどに必要とされる情報を提示するよう定められています。
一方、「発行保証金の供託義務」は、資金決済法にいう「6ヶ月」と密接に関わっています。
どのような義務なのか、次の項目で解説します。
3 供託義務とは?

そもそも、「発行保証金の供託義務」とは、どういった義務なのでしょうか。
詳しく解説していきます。
(1)倒産などのトラブルへの備えが目的
「供託義務」とは、倒産やサービス終了などが原因で、すでに入手している前払式支払手段が使用できなくなる利用者への保証を目的として、事業者に対し、一定のお金を保全しておくように義務付けたものです。
もしも発行事業者が倒産した場合、供託所に預けている「発行保証金(供託金)」から、利用者に対して返金が行われるのです。
(2)供託義務が発生する基準
供託義務は、毎年3月末か9月末の時点(基準日)で、前払式支払手段の未使用残高が1,000万円以上ある事業者に対して発生します。
「未使用残高」とは、現金から前払式支払手段に変換後、まだ使われていないもののことです。
たとえば、1ポイント10円という価格設定でゲーム内コインを提供していた場合、使われていないコインが100万コイン(=1,000万円)あると、供託義務が発生することになります。
1,000万円以上の未使用残高がある前払式支払手段の場合、利用できなくなると多くの被害者数が生じると考えられます。そのため、未使用残高が1,000万円以上になると、発行者に対して供託義務が発生するのです。
供託所(法務局など)に供託する額は、未使用残高の半額。つまり、最低でも500万円を供託しなくてはなりません。
このように、供託義務はスタートアップなどにとっては、非常に重い義務であるため、できれば供託義務を回避する形でサービス設計をしたいと考えるのが自然でしょう。
そこで用いられるのが「6ヶ月」という期間です。
(3)有効期限が6ヶ月以内であれば、供託義務が発生しない
前払式支払手段の有効期限を6ヶ月以内と設定すれば、供託義務は発生しません。
有効期限が6ヶ月を超えない前払式支払手段は、前払式支払手段に関する規制が適用されないこととなっているため、供託義務を回避することができます。
4 有効期限を設けて供託義務を回避する方法
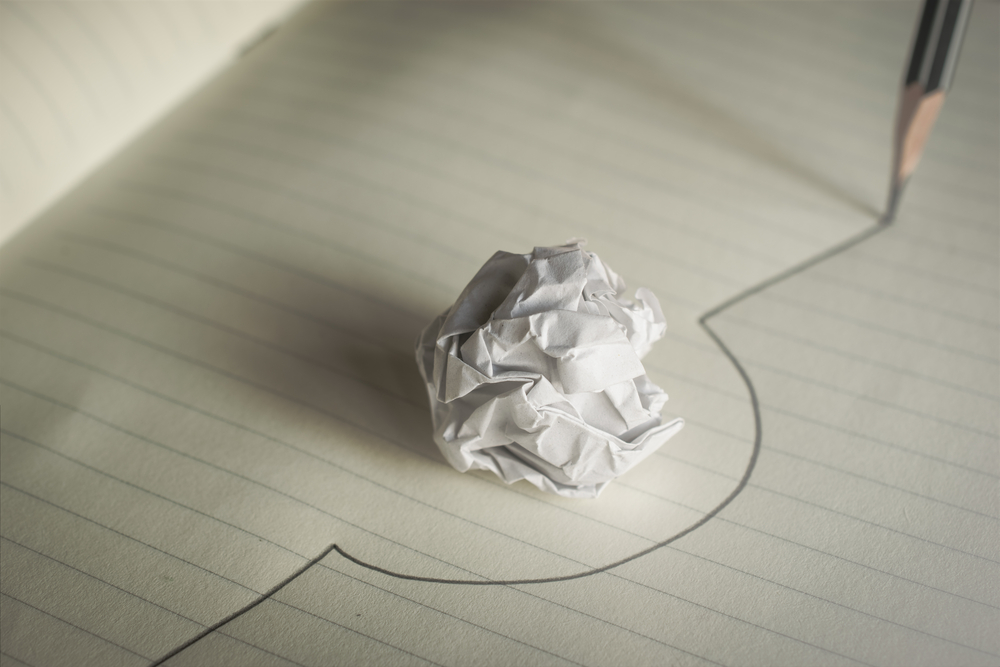
それでは、どのように有効期限を設ければいいのでしょうか。
(1)利用規約にエクスパイア条項を設ける
主にインターネットやアプリで前払式支払手段を発行する場合、利用規約にエクスパイア条項を設ける方法が一般的です。
エクスパイア条項とは、有効期限について定めた項目のことをいいます。
それでは、何故利用規約にエクスパイア条項を設けるのでしょうか。
そもそも、利用者は、サービスを利用する前に、必ず利用規約に同意することを求められます。利用者は、利用規約に同意すると、利用規約の内容を守り、また、そのルールのもとでサービスを利用することを承諾することになるのです。
そのため、利用規約にエクスパイア条項を設けておくことで、利用者の同意を得て、有効期限のルールを適用することができます。
利用規約では、以下のように記載します。
○○コイン(前払式支払手段の名称)の有効期間は、ポイントが付与された日から180日とし、有効期間が過ぎたコインは無効とする。
(2)チケットなどに有効期限を印字する
前払式支払手段が商品券やカタログギフト券などの場合、そのチケットに「2020年11月30日まで有効」など、発行日から6ヶ月以内の期間を有効期限として記載する方法があります。
(3)有効期限を設けられないケース
このように、前払式支払手段に有効期限を設けることで、供託義務を回避できますが、実は有効期限を設けられないケースがあります。
例えば、ゲーム内コインを発行するアプリケーションをリリースする場合、Google PlayとApp Storeが主なリリース候補先となります。
しかし、「App Store Reviewガイドライン」の規定には、「ゲーム内通貨への有効期限の設定を禁止する」という旨の記載があるため、有効期限を設けることができません。
それでは、有効期限を設けることができない場合に、供託義務を回避する方法はあるのでしょうか。
5 供託義務を回避するその他の方法

有効期限を設ける以外で供託義務を回避する方法としては、「消費を促すイベントを開催する」ということが考えられます。
以下の2ケースに分けて、手順やポイントを見ていきましょう。
- ゲーム内コイン・ポイントの場合
- 商品券などの場合
(1)ゲーム内コイン・ポイントの場合
ゲーム内でコインやポイントを発行している場合、以下の2ステップを行ってみましょう。
- 無料コインと有料コインの管理体制を構築する
- 有料コインの消費を促すイベントを企画・実施する
これらの方法は、供託義務を回避できなかったとしても、発行保証金(供託金)の額を下げることにつながる可能性もあるため、チェックしておいてください。
①無料コインと有料コインの管理体制を構築する
まず、無料で配布するコインと、利用者が購入した有料コインを分けて管理しておく必要があります。
先ほど解説した通り、供託義務は対価に応じて発行された「前払式支払手段」に対して発生するため、無料で配布したコインには、発生しません。
しかし、無料コインと有効コインをまとめて管理していると、いくら分が有料コインか判断できないため、全額有料コインとして扱われてしまい、無料コインの分まで発行保証金(供託金)の金額を決める際の基準に含まれることになってしまいます。
例えば、未使用残高として無料コイン300万円分+有料コイン750万円分が残っていたケースを考えてみましょう。
無料コイン・有料コインを分けて管理しておけば、有料コインは750万円分であるため供託義務は発生しませんが、合わせて管理していると、合算して1,000万円となるため、供託義務が発生してしまいます。
また、もともと未使用の有料コインが1,000万円分あった場合に、無料コインを合わせて管理していると、発行保証金(供託金)の金額は500万円よりも上がってしまいます。
このように、無料コインと有料コインを合わせて管理していると、
- 本来、供託義務が発生しないケースでも供託せざるを得なくなる可能性がある
- もともと供託義務が発生するケースであっても、支払う発行保証金(供託金)が高額になる可能性がある
という事態を招いてしまうため、必ず分けて管理するようにしてください。
なお、管理するときは、利用者にも無料・有料コインがそれぞれいくら分あるのか分かるように、ゲーム内で表示しておきましょう。
②有料コインの消費を促すイベントを企画・実施する
無料コインと有料コインを分けて管理するシステムを整えたうえで、有料コインが先に消費されるシステムを組みましょう。
有料コインが優先して消費される仕組みにしておくことで、イベント開催による有料コインの利用促進をより効果的に行うことができます。
このように、供託義務の基準日である3月末か9月末の前に、積極的にコイン消費を促すイベントを企画・実施することで、未使用残高を減らし1,000万円のボーダーを下回ることが期待できるのです。
(2)商品券などの場合
たとえば、「商品券を使って買い物すると、粗品プレゼント」などのイベントを企画してみてください。
商店街で使える商品券であれば、その商店街と協力し、セールや福袋、子供向けの大会の開催など、何かしらのイベントを併せて開催することで、より一層、商品券の利用を促進できます。
発行している前払式支払手段の特性に合わせて、企画を立案してみましょう。
6 小括

資金決済法における「6ヶ月」が持つ意味は、同法が規制する前払式支払手段の「発行保証金の供託義務」を回避するために必要な「有効期限」の期間です。
供託義務は、特に経済的基盤の弱いスタートアップなどにとっては、負担が重いため、できるだけ回避できるよう、前払式支払手段に有効期限を設けるなどの対策を行ってください。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 「価値の保存性」「対価発行」「権利行使」の要素に合致するものは、前払式支払手段として定義される
- 前払式支払手段は、発行した事業者との関係でのみ利用できる「自家型前払式支払手段」と、発行した事業者以外の事業者との関係でも利用できる「第三者型前払式支払手段」の2タイプに分かれている
- 「自家型」「第三者型」関係なく、前払式支払手段発行者には、主に、「情報の提供義務」「発行保証金(供託金)の供託義務」の2つが課せられる
- 「発行保証金(供託金)の供託義務」とは、毎年3月末か9月末時点で、未使用残高が1,000万円を超えていた場合、その半額を供託所(法務局など)に預けなければならないとする義務である
- 「供託義務」を回避する術として、前払式支払手段の有効期限を「6ヶ月」を超えない範囲で設定する方法がある
- 有効期限を設けるときは、①利用規約にエクスパイア条項を設ける、②チケットそのものに有効期限を記載する などの方法が考えられる
- 有効期限を設けられない状況で供託義務を回避したいときは、前払式支払手段の消費を促すイベントの開催などを行う方法が考えられる
- ゲーム内コイン・ポイントの場合は、①無料コインと有料コインの管理体制を構築する、②有料コインの消費を促すイベントを企画・実施する、という2ステップをとり、有料コインが先に消費されるシステムとしておくことが考えられる
- 商品券の場合は、使用すると粗品をプレゼントするなどのイベントを企画することが考えられる