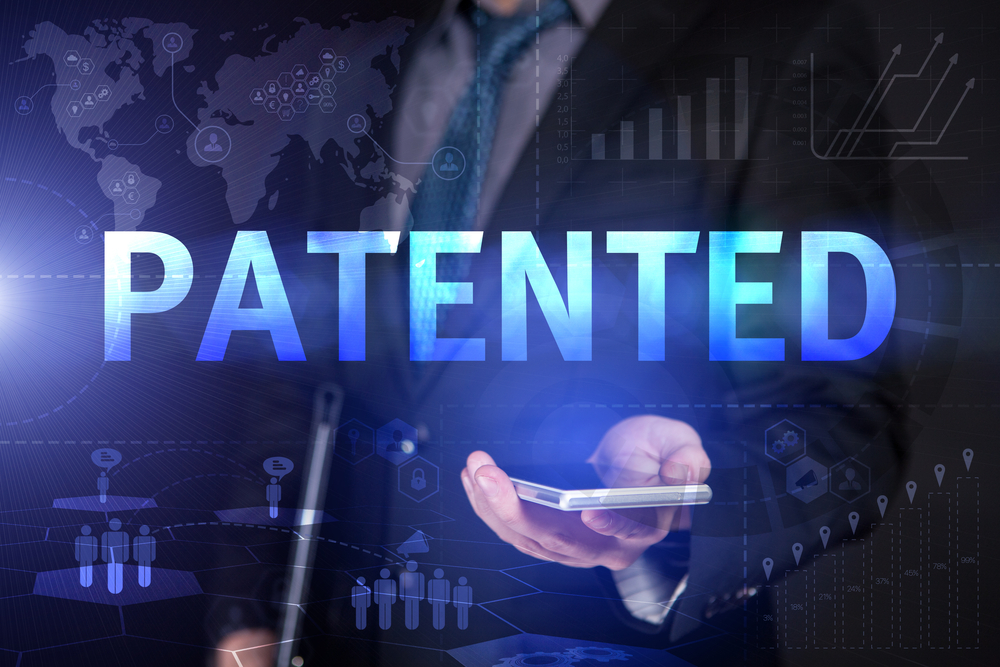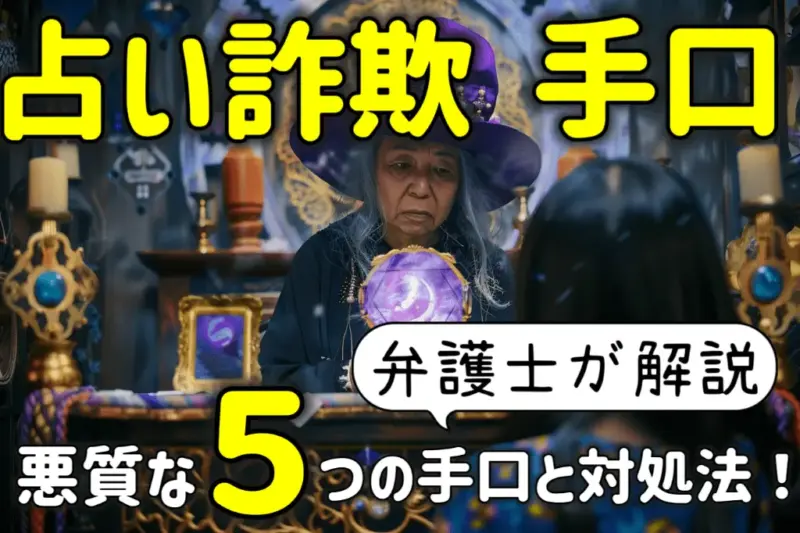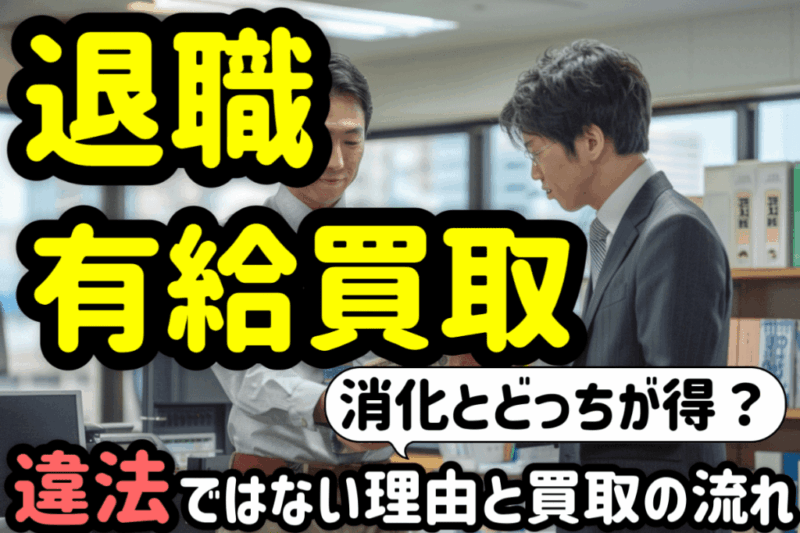特許侵害の判断方法は?4つの救済方法とともに弁護士が解説!
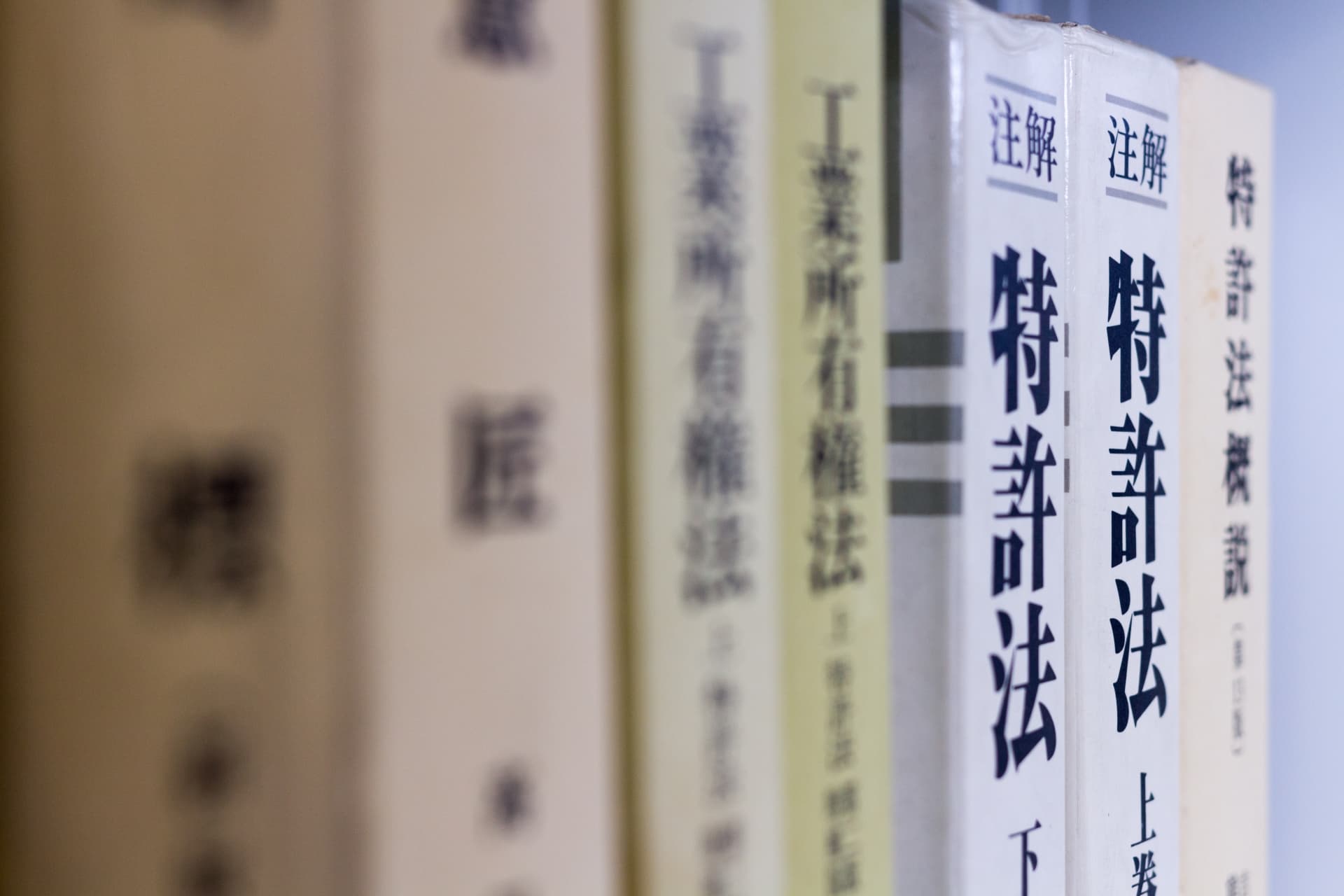
はじめに
権原のない第三者が、自社の特許発明を実施している場合には「特許侵害」となりますが、ときに特許侵害となるか否かの判断が簡単でないケースがあります。
とはいえ、「特許」は事業者にとって大切な財産であるため、どのような場合に特許侵害となるかを正確に理解しておくことが必要であり、また、そのような事態が生じた場合にどのような救済方法をとることができるかを押さえておくことが必要です。
そこで今回は、特許侵害を見極めるための判断方法と特許侵害に遭った場合の救済方法を弁護士がわかりやすく解説します。
1 特許侵害とは?|見極めるための判断方法
「特許侵害」とは、特許発明の実施について特許権者からライセンス許諾を受けていないにもかかわらず、第三者が業として特許発明を実施することをいいます。
特許侵害といえるためには、以下の3つの条件が揃っていることが必要です。
- 有効な特許権が存在していること
- 技術的範囲内の実施であること
- 実施につき正当な権限がないこと
(1)有効な特許権が存在していること
特許侵害といえるためには、その対象となる特許権が有効に存在していることが必要です。
具体的には、特許権が設定登録されていて、かつ、存続期間中であることが必要です。
(2)技術的範囲内の実施であること
第三者が実施している発明が、技術的に特許発明の技術的範囲内であることが必要です。
ここでいう「実施」とは、以下の3つの行為のことを指します。
-
【物の発明の場合】
物の生産や使用、譲渡、輸出入または譲渡などの申出をする行為
【方法の発明の場合】
方法を使用する行為
【物を生産する方法の発明の場合】
上記にあたる行為のほか、その方法により生産した物の使用、譲渡、輸出入または譲渡などの申出を
する行為
特許発明に関してこれらの行為を行った場合は、特許発明の実施となります。
特許発明は、特許請求の範囲(クレーム)に記載された構成要件(発明を特定するために必要な構成要素)によって一体として構成されるものです。
そのため、侵害の態様がクレームに記載された構成要件を一部でも欠いている場合には、特許侵害にはあたりません。
つまりは、対象となっている製品や方法がクレームに記載された構成要件をすべて満たしている場合には、特許侵害にあたるということです。
また、特許製品の部品のように、構成要件をすべて満たしていない場合であっても、特許発明の実施にのみ使用する物の製造・販売行為については、特許侵害にあたると考えられています。
(3)実施につき正当な権原がないこと
特許権者からライセンス許諾を受けていないなど、第三者が特許発明の実施につき、正当な権原を有していないことが必要です。
2 特許侵害に遭った場合の救済方法
特許侵害であるとの確証が得られた場合、まずは、侵害者に警告するなどして、任意で解決を図ることが考えられます。
もっとも、任意の交渉では解決に至らないケースもあり、その場合には、以下のような方法を検討することが必要になってきます。
- 差止請求
- 損害賠償請求
- 信用回復措置請求
- 刑事責任の追及
(1)差止請求
特許を侵害する行為に対して、差止めを請求することができます。
差止請求には、以下の3つの種類があるため、状況に応じて選択する必要があります。
- 侵害行為の停止請求
- 侵害の予防請求
- 侵害を予防するために必要な措置の請求
差止請求は、侵害者の故意・過失を要件としていないため、特許侵害の事実・侵害されるおそれのある事実が存在すれば、請求することが可能です。
また、すでに特許侵害の事実が認められ、緊急性が高いような場合には、上記請求を行う前に侵害行為の停止を内容とする仮処分を申立てることも可能です。
(2)損害賠償請求
特許侵害となる製品を製造・販売などする者に対して、損害賠償を請求することができます。
もっとも、損害賠償を請求する場合には、差止請求のときとは異なり、侵害者に故意・過失があることが必要です。
そのため、本来であれば、侵害者の故意・過失や侵害行為によって生じた損害の額については、請求者側で立証しなければなりません。
ですが、事案の性質上、これらを立証することは困難なケースが多いです。
そこで、特許法は、侵害者の故意・過失については、推定規定を設けており、侵害者に過失があったものと推定されるため、請求者側でこれらを立証する必要はありません。
加えて、特許法は、侵害行為によって生じた損害の額について算定規定を設けており、特許権者から侵害者に対する損害賠償請求を容易にしています。
※損害額の算定規定について詳しく知りたい方は、「特許侵害をされた場合の損害賠償額は?3つの類型と対応方法を解説!」をご覧ください。
(3)信用回復措置請求
侵害行為により、業務上の信用を害された場合、信用を回復するための措置を請求することができます。
信用回復のための措置としては、たとえば、謝罪広告の掲載などが挙げられます。
(4)刑事責任の追及
特許を侵害した者は、
- 最大10年の懲役
- 最大1000万円の罰金
のいずれか、または、両方を科される可能性があります。
また、法人である場合には、行為者とは別に、法人に対しても、
- 最大3億円の罰金
が科される可能性があります。
特許侵害の罪は、非親告罪であるため、告訴がなくても起訴される可能性があります。
3 まとめ
特許侵害が疑われる場合、すぐに救済方法を採るのではなく、まずは、慎重に調査をするなどして、特許侵害について確証を得る必要があります。
そのためには、特許侵害となるための条件を正確に理解し、その条件に照らし合わせて判断することが必要です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。