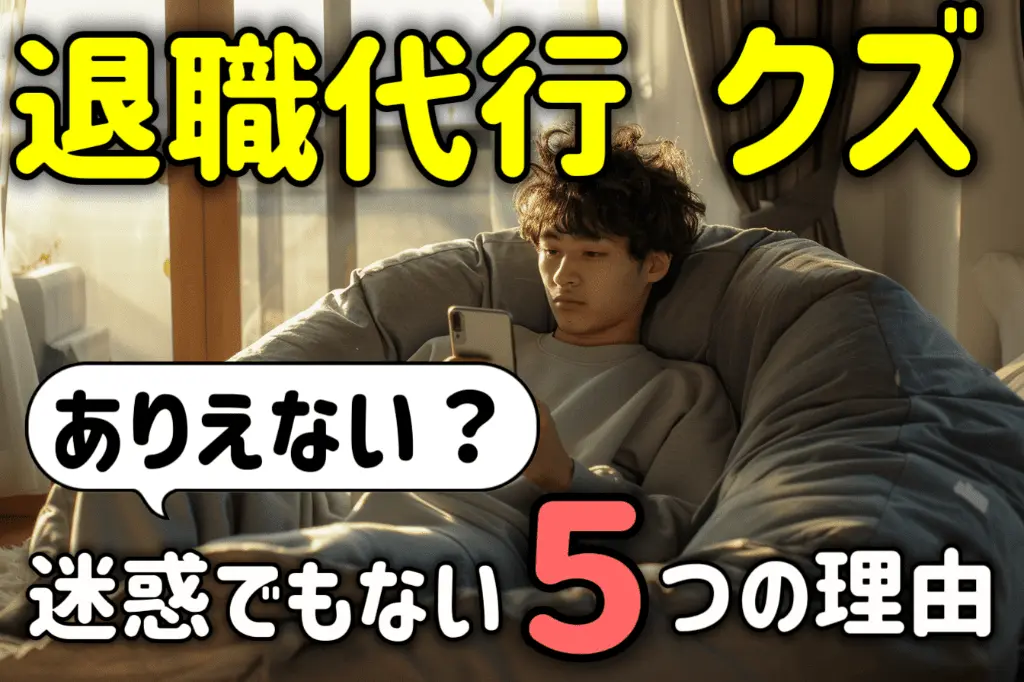古物商が注意すべき「本人確認」とは?具体的な方法を弁護士が解説!

はじめに
古物商として許可を受けた者は、古物営業を行うにあたり、さまざまな規制を課されます。
そのなかでも重要なのが「本人確認義務」です。
簡単に義務を履行できるようにも思えますが、どのような場合にどのような方法で本人確認をすべきかをご存知でしょうか。
本人確認義務に違反すると、行政処分だけでなく刑事罰の対象となるため、事業者は正確に理解しておくことが必要です。
そこで今回は、古物商が注意すべき「本人確認義務」について、弁護士がわかりやすく解説します。
1 本人確認が必要となる3つの取引
古物営業について規制する「古物営業法」は、盗品等の売買防止、迅速な被害回復などを目的とする法律です。
古物営業法は以下の3つの取引について、古物商に本人確認をすることを義務付けています。
- 古物の買い受け
- 古物の交換
- 古物の売却・交換に関して委託を受けるとき
古物を「売却」する際には、本人確認をする必要はありません。
また、以下のいずれかにあてはまる場合は、例外的に本人確認は不要とされています。
(1)対価の総額が1万円未満の取引
古物営業に関する取引で、対価の総額(買取価格など)が1万円未満である場合は本人確認は不要です。
もっとも、自動二輪車や原動機付自転車、ゲームソフト、書籍などについては、買取価格が1万円未満であっても本人確認が必要となります。
これらについては、たとえ買取価格が低くても小遣い稼ぎ目的で万引き・盗難の対象となることが少なくないためです。
(2)自己が売却した相手から買い取る場合
過去に自己が売却した物品を、その売却の相手方から買い取る場合は本人確認は不要です。
この場合、その物品が盗品等である可能性は低いといえるため、本人確認義務は免除されています。
2 本人確認の方法
本人確認の方法は、対面もしくは非対面で行うかによって異なります。
(1)対面での本人確認
対面で本人確認を行う場合には、以下の3つの方法が挙げられます。
- 身分証明書(運転免許証や健康保険証など)の提示を受ける
- 身元確認できる者(保護者など)に問い合わせる
- 目前で書面や画面に氏名等の確認事項を記載(入力)してもらう
本人確認では、取引相手の氏名・年齢と住所、職業を確認することが必要になります。
(2)非対面での本人確認
非対面で本人確認を行う場合には、たとえば以下のような方法が挙げられます。
①取引相手から印鑑証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受ける
取引相手から「自己の印鑑証明書」と「登録している印鑑を押した書面」をセットで送ってもらう方法です。
②本人確認書類(コピー)をもらい、転送不要扱いで簡易書留等を送付し到達を確認する
取引相手から本人確認書類(運転免許証等)のコピーと古物を送付してもらい、簡易書留などを使って転送不要扱いで見積書を送付します。
その後、取引相手から承諾を得たうえで、古物の代金を本人名義の預貯金口座に振り込むという方法です。
到達を確認する方法としては、転送不要扱いで簡易書留を送付するほか、たとえば、以下のような方法が挙げられます。
- 本人限定受取郵便を送付し、古物を同封させて返送させる方法
- 受付番号を記載した本人限定受取郵便を送付し、当該受付番号等を電話や電子メールなどで連絡させる方法
- 本人限定受取郵便で往復葉書を送付し、その返信部を送付させる方法
③eKYCによる確認
「eKYC(electronic Know Your Customer)」とは、オンライン上での本人確認のことを意味します。
二つ目の方法は、このeKYCを使った方法です。
具体的には、古物商が提供するソフトウェアを使って、取引相手から自己の容貌や本人確認書類を撮影した画像を送ってもらう方法です。
また、取引相手から自己の容貌を撮影した画像と写真付身分証明書についているICチップ情報を送ってもらうという方法もあります。
3 本人確認義務に違反した場合のペナルティ
本人確認義務に違反した場合、事業者は、行政処分および刑事罰を受ける可能性があります。
(1)行政処分
本人確認義務を怠った事業者は、行政処分として、
- 営業許可の取消し
- 最大6ヶ月の営業停止
のいずれかを受ける可能性があります。
(2)刑事罰
本人確認義務を怠った事業者は、刑事罰として、
- 最大6ヶ月の懲役
- 最大30万円の罰金
のいずれかを科される可能性があります。
また、事業者が法人の場合には、行為者とは別に法人に対しても、
- 最大30万円の罰金
が科される可能性があります。
4 まとめ
古物商は、「本人確認」が必要となる取引を正確に押さえるとともに、本人確認の実施方法を具体的に決める必要があります。
確認の方法が不十分だと、本人確認義務を履行していないと判断される可能性もあるため、注意するようにしましょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。