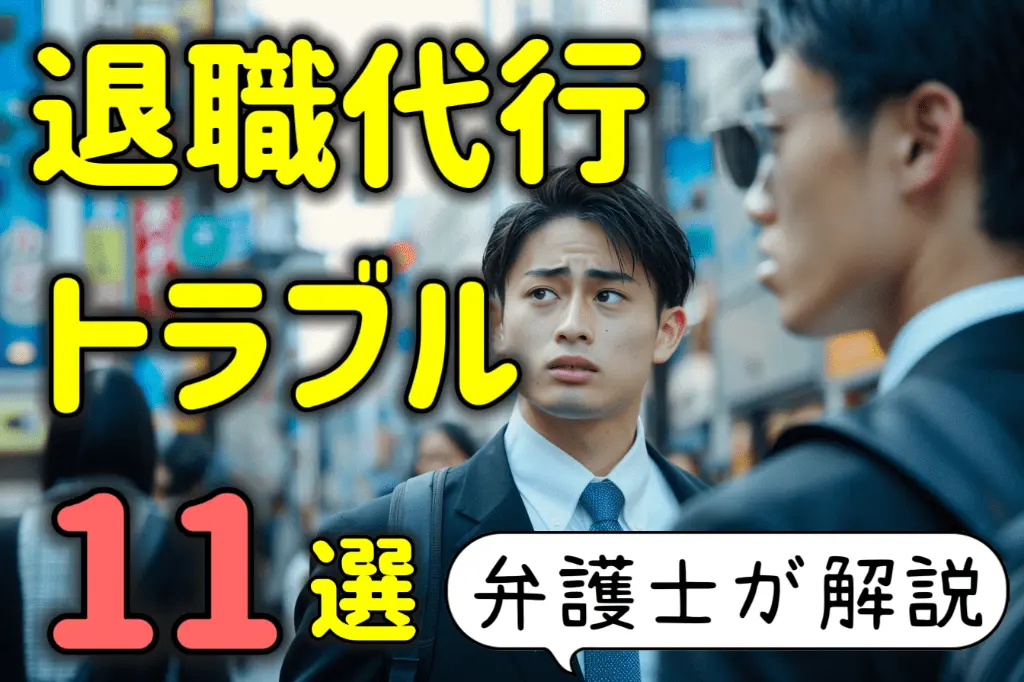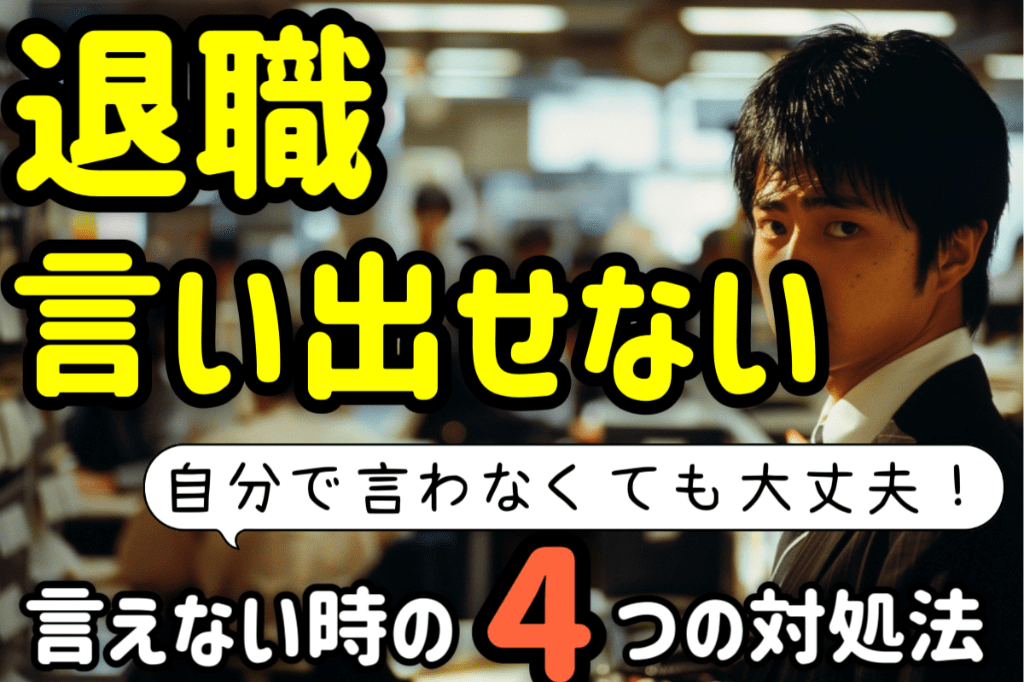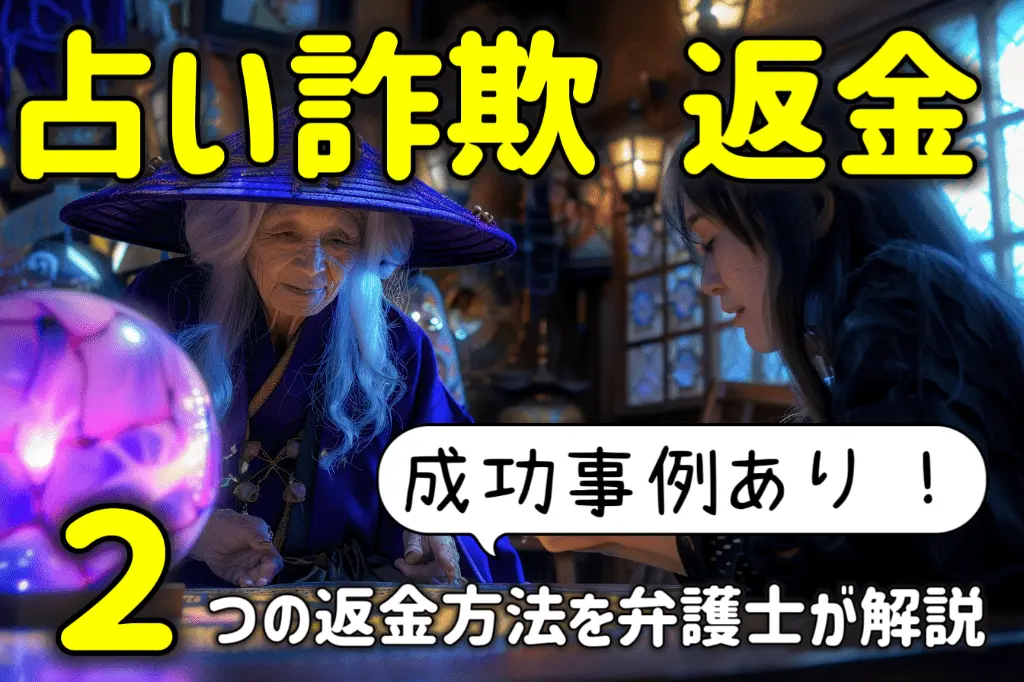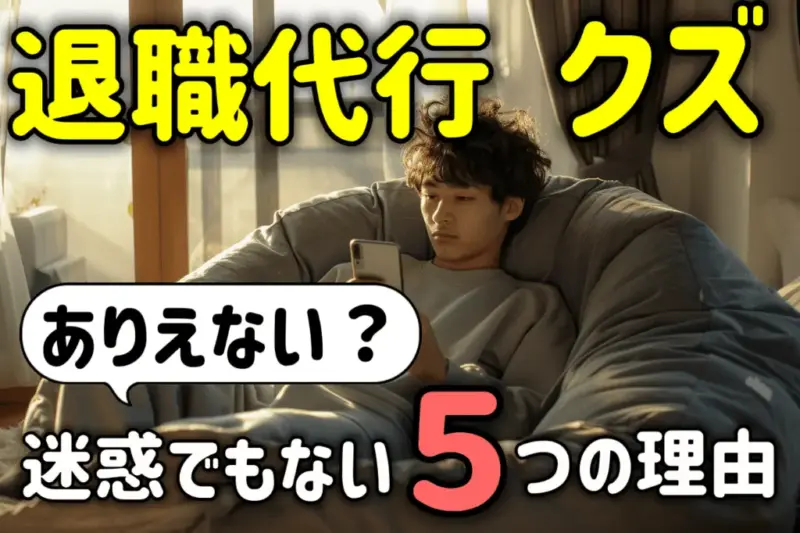フリーランスと取引をする事業者が注意すべき3つの法律を解説!
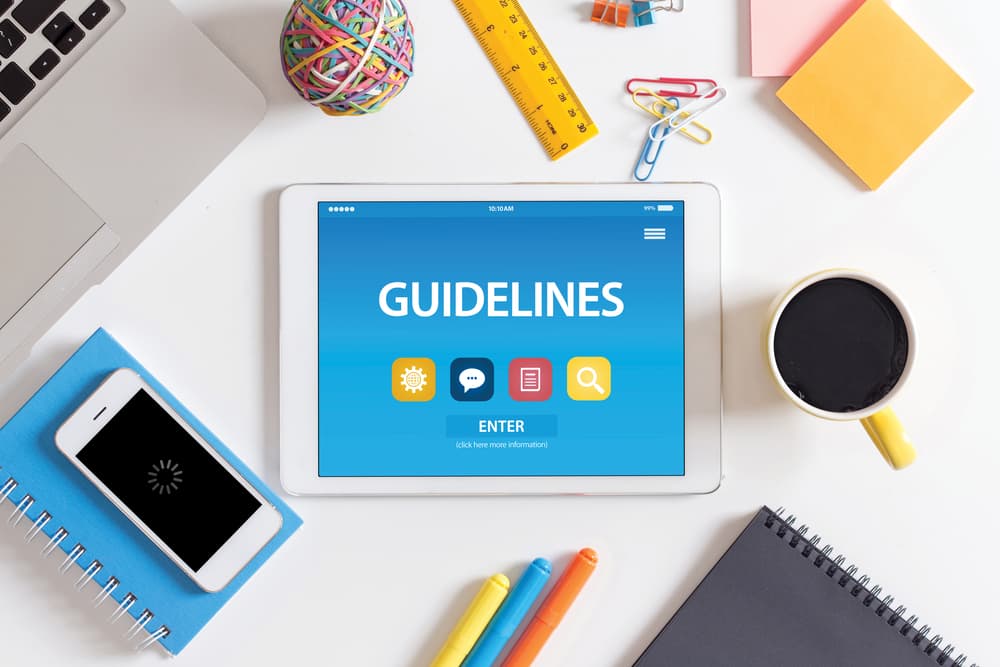
はじめに
近年、フリーランスが増加傾向にあり、内閣府によればその数は300万人前後とされています。
副業をする人が増加し、また、IT技術が進歩したことにより執務場所に制約がなくなったことなどがその背景としてあるようです。
これに伴い、フリーランスを活用する企業も増えてきています。
もっとも、フリーランスという個人の立場はまだ弱く、そのことが取引関係に影響することも少なくありません。
このような状況のなか、2021年3月、経済産業省は、内閣官房や公正取引委員会、厚生労働省などと連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を公表しました。
企業は、フリーランスとの取引において、同ガイドラインを遵守することが求められます。
今回は、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について、わかりやすく解説します。
1 適用関係の有無を検討すべき3つの法律
「フリーランス」に決まった定義はありませんが、本ガイドラインでは、「実店舗をもっておらず、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自己の経験や知識などを活用して収入を得る者」と定義しています。
フリーランスと取引をする場合、以下の3つの法律について適用関係の有無を検討する必要があります。
- 独占禁止法(独禁法)
- 下請法
- 労働関係法令
(1)独占禁止法(独禁法)
独禁法は、取引関係にある発注者が事業者であれば、相手方の属性を問わず適用されます。
そのため、事業者がフリーランスと取引をする場合には、独禁法が適用されることになります。
(2)下請法
下請法は、取引関係にある発注者において、資本金が1000万円を超える場合には、相手方の属性を問わず適用されます。
そのため、資本金要件を満たす事業者がフリーランスと取引をする場合には、下請法が適用されることになります。
(3)労働関係法令
フリーランスとして業務に従事していても、実質的には、事業者との間に指揮命令関係があるなど、「雇用」にあたると見られる場合には、労働関係法令が適用されます。
2 独禁法・下請法との関係で注意すべきポイント
事業者がフリーランスと取引を行う場合、独禁法・下請法との関係で以下の2点に注意する必要があります。
(1)優越的地位の濫用
事業者とフリーランスとでは、取引条件などに係る情報の量や質、交渉力の面で格差があることが一般的です。
そのため、フリーランスは事業者との取引条件などについて、自主的・合理的に判断できないことがあり、その結果、取引条件が事業者に一方的に有利になりやすい側面があります。
にもかかわらず、事業者がこのような優越的地位を利用して、フリーランスに対し不当に不利益を与えることは、フリーランスがその競争者との関係で競争上不利となる一方で、事業者はその競争者との関係で競争上有利となるおそれがあります。
独禁法は、公正な競争を阻害するおそれのある行為を、不公正な取引方法の一つである「優越的地位の濫用」として規制しています。
たとえば、事業者が多数のフリーランスを対象に不利益を与える場合、特定のフリーランスに対して強度の不利益を与える場合などは、公正な競争を阻害するおそれがあると判断される可能性が高いです。
(2)書面の交付
事業者は、取引条件を明確化した書面をフリーランスに交付する必要があります。
仮に、書面が交付されなかった場合や書面に記載される取引条件が明確でない場合、事業者は、後から取引条件を自由に変更しやすくなります。
このような状況は、先に見た「優越的地位の濫用」にあたる行為を誘発する要因にもなります。
また、取引が下請法の適用対象となる場合、事業者がフリーランスに対して、取引条件を記載した書面を交付しないと、下請法違反となります。
3 労働関係法令との関係で注意すべきポイント
フリーランスとの間で、雇用契約ではなく、「請負契約」や「準委任契約」などを締結している場合であっても、フリーランスが労働基準法上の「労働者」にあたるかどうかは、働き方の実態により判断されます。
労働者にあたると判断された場合、事業者との関係では労働基準法や労働組合法などの労働関係法令が適用されることになります。
(1)労働基準法の適用
取引を行うフリーランスが、労働基準法上の「労働者」にあたる場合、事業者との関係では、労働基準法が定めるルール(たとえば、賃金や労働時間)が適用されることになります。
ここでいう「労働者」にあたるかどうかは、主に、以下の2点から判断されます。
- 他人の指揮監督下で労働が行われているかどうか
- 指揮監督下における労働の対価として報酬が支払われているかどうか
たとえば、仕事の依頼や業務の指示などに対してフリーランスに諾否の自由が認められていない場合、業務を遂行するうえで指揮監督を受ける場合などには、「他人の指揮監督下で労働が行われている」といえます。
また、事業者が支払う報酬が、主に作業時間を基準に決定されていて、仕事の成果による変動が小さいような場合には、「指揮監督下における労働の対価としての報酬」といえます。
さらに、業務に必要な機械などをどちらが負担しているか、事業者への専属性の程度なども、「労働者性」を判断するうえで補強要素となります。
(2)労働組合法の適用
取引を行うフリーランスが、労働組合法上の「労働者」にあたる場合、フリーランスには、同法による団体交渉権が保障されることになります。
そのため、事業者が正当な理由なく労働組合からの団体交渉を拒んだり、労働組合の組合員となったことを理由として契約を解除したりすると、労働組合法違反となります。
労働組合法上の「労働者」にあたるかどうかは、主に、以下の3点から判断されます。
- 業務遂行に不可欠な労働力として組織内に確保されているかどうか
- 事業者が労働条件などを一方的に決定しているかどうか
- 労務供給の対価として報酬が支払われているかどうか
たとえば、研修制度を設けていたり、業務日を割り振ったりするなど、事業者がフリーランスを管理しているといえる場合は、「業務遂行に不可欠な労働力として組織内に確保」しているといえます。
また、契約締結時などに、フリーランスが事業者と交渉してその内容を変更することが認められていない場合は、「事業者が一方的に労働条件を決定」しているといえ、残業代や休日手当に類するものが支払われている場合には、「労務供給の対価としての報酬」にあたるといえます。
さらに、事業者からの業務依頼に対し、フリーランスが応ずべき関係にあるか、フリーランスが事業者の指揮監督の下で労務提供を行っているかといったことも、「労働者性」を判断するうえで補強要素となります。
4 まとめ
フリーランスの活用を検討している事業者や現に活用している事業者は、今回見てきたガイドラインを一読することをおすすめします。
独禁法は、ほぼすべての取引において適用されるため、特に注意すべきなのは、下請法と労働関係法令です。
ガイドラインには、適用の有無を判断する基準が記載されているため、自社のケースにあてはめて、適切な対応をとる必要があります。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。