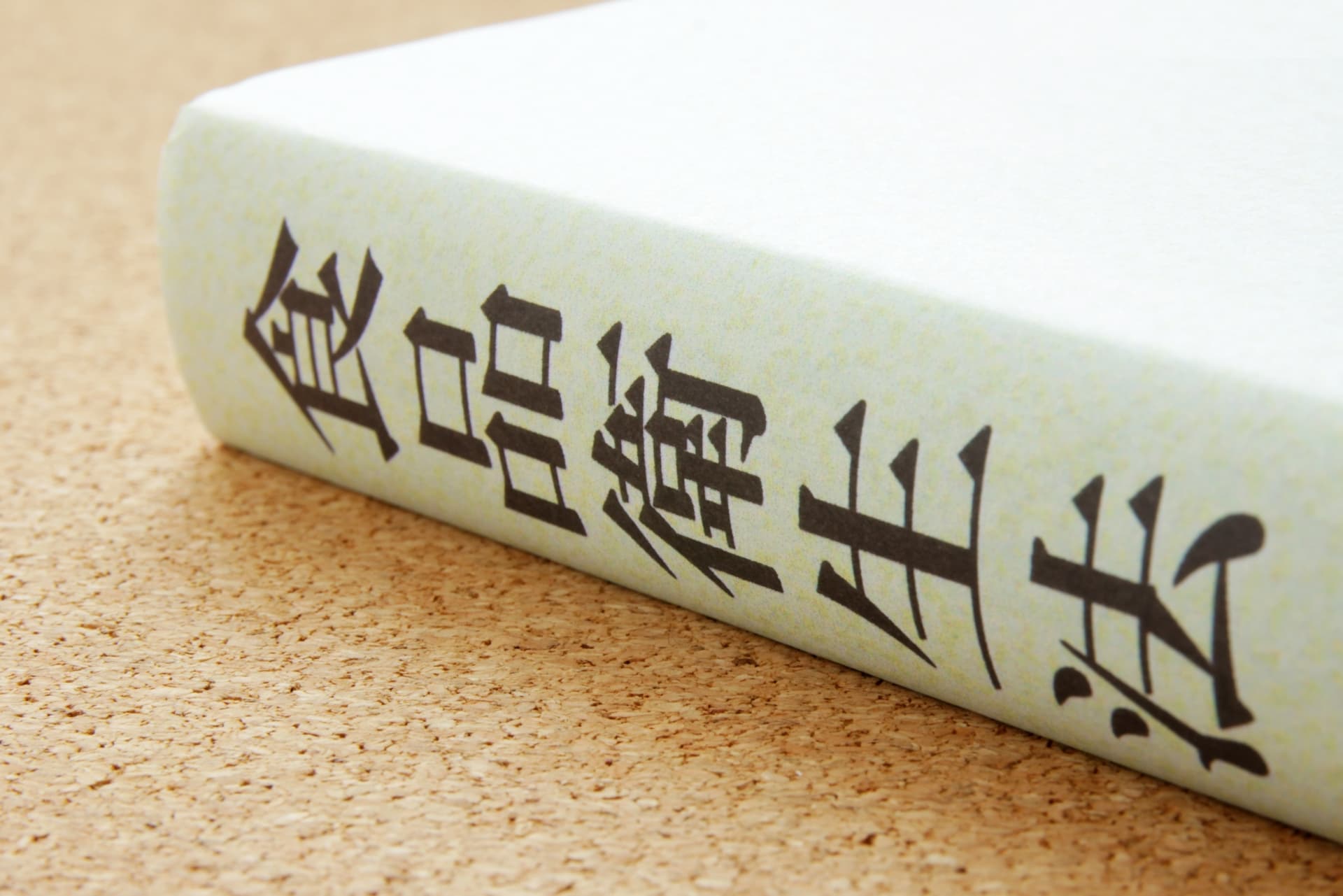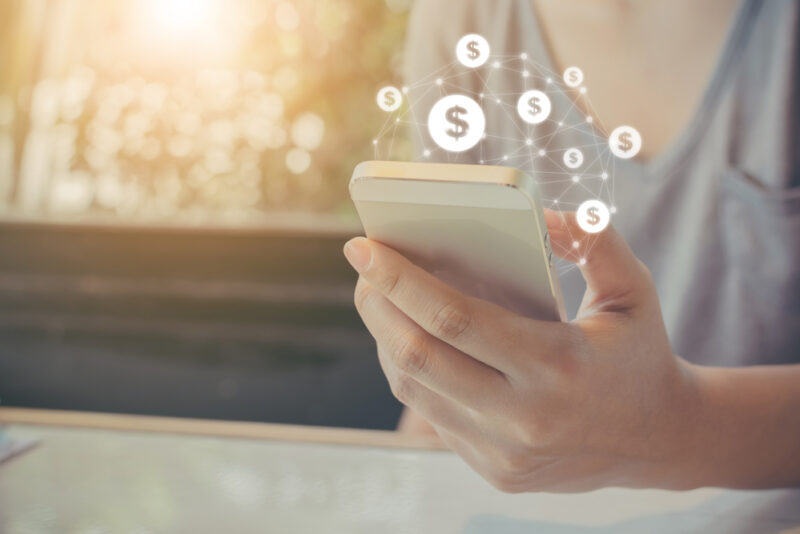投資契約において定めるべき5つの事項を弁護士がわかりやすく解説!

はじめに
事業を運営するにあたり、投資を受ける場合には、投資契約を締結することが一般的です。
とはいえ、初めて投資契約を締結する場合、何を定めていいのかわからないという事業者も多いと思います。
ネット上に転がっている雛形を適当に流用するようなことをしてしまうと、後に投資家とのトラブルに発展するおそれもあります。
今回は、「投資契約」で定めるべき事項について、弁護士がわかりやすく解説します。
1 投資契約とは
「投資契約」とは、事業者が投資を受ける際に、投資家との間で締結する契約のことをいいます。
投資契約では、主に、「株式を発行する相手」「発行する株式の内容・数」などについて、定めることになります。
事業者と投資家の間で、利害調整をきめ細やかに行うとともに、不測の事態が生じた場合の処理方法などについて共通認識をもつことが目的でもあります。
一方で、「投資契約」とは別に「株主間契約」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
「株主間契約」は、会社経営のルールについて定めた株主間の契約のことをいいます。
株主間契約で定める内容を「投資契約」にまとめてしまうことも可能で、実際にスタートアップ企業やベンチャー企業などにおいて、そのような方法を採ることが増えています。
2 投資契約で定めるべき事項
投資契約で定めるべき事項は多岐にわたりますが、今回はその中でも特に重要な事項について見ていきたいと思います。
具体的には、以下の6点です。
- 契約当事者
- 払込条件
- 表明保証
- 誓約事項
- ペナルティ
3 契約当事者
投資契約の当事者を特定する必要があります。
具体的には、株式を発行する事業者とその創業株主、投資家が契約当事者となることが一般的です。
-
株式会社●●●●(以下「発行会社」という。)、●●●●(以下「創業株主」という。)と●●●●(以下「投資家」という。)は、投資家による発行会社の株式の取得に関し、下記のとおり投資契約(以下「本契約」という。)を締結する
また、上記のように、事業者が株式を発行して投資家から資金を調達するという投資契約の趣旨・目的を併せて定めます。
4 払込条件
「払込条件」とは、投資家が出資金を払い込むにあたって、事業者において満たさなければならない条件のことをいいます。
-
1 投資家の前条の払込義務は、投資家が書面により放棄しない限り、本条に定める全ての条件が充足されることを条件とする
2 投資家が前条の払込をする日(以下「払込日」という。)までに、発行会社および創業株主(以下あわせて「発行会社等」という)は、以下各号に定める書 面を投資家に交付すること
①本株式の発行ならびに割当を決議した発行会社の取締役会および株主総会の各議事録の写し
②発行会社の登記簿謄本、定款、財務諸表、税務申告書
③発行会社の事業計画書、収支計画書
3 発行会社等の第6条に基づいて表明保証をした事項、ならびに本契約締結に関して発行会社等が交付した前項の書面および提供した全ての情報が、払込日時 点においても真実かつ正確であり、誤解を生じさせないために必要な記載を欠いていないこと
4 本契約締結日以後払込日までに、発行会社の経営、財政状態、経営成績、信用状況等に重大な悪影響を及ぼす事態が発生していないこと
5 全ての投資家からの払込金額の総額が●●●●円以上で最低調達額を満たしていること
6 ●●●●に関する知的財産権の移管を受けていること
7 ●●●●に関する知的財産権についてライセンス契約を締結していること
8 ●●●●が取締役に就任していること
9 発行会社の組織再編が完了していること
投資契約の締結から投資の実行までに、一定の期間が空くことがあります。
この期間に事業者に重大な事項が発生してしまうと、投資判断の前提が崩れてしまうおそれがあります。
そのような事態にそなえて、「払込条件」を定めておくことが必要になります。
もっとも、上記5~9項については、必要に応じて定めることになります。
5 表明保証
「表明保証」とは、事業者が投資家に対し、ある時点において一定の事項が真実かつ正確であることを表明して保証することをいいます。
-
発行会社等は、連帯して、投資家に対し、以下各号の事実が真実であることを表明し、保証する
①発行会社は適法に設立され有効に存続していること
②発行会社の事業運営が適法、適正に行われており、その事業に免許、許可、認可、登録、届出を要する場合には適正に実施されていること
③発行会社に対する訴訟が係属していないこと
④発行会社の資産に対する差押え等がなされていないこと
⑤発行会社が事業に必要な知的財産権またはそのライセンスを保有しており、第三者の知的財産を侵害していないこと
⑥発行会社の事業計画書、財務諸表、その他発行会社の事業運営、財務等に関連して、発行会社が投資家に交付した書面の記載および情報が真実かつ正確であること
⑦発行会社、創業株主および発行会社の特別利害関係者、株主または取引先等が、反社会的勢力またはこれに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という)ではなく、資金提供もしくはそれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力等の維持、運営に協力または関与していないこと、または反社会的勢力等と交流をもっていないこと
⑧創業株主は、他の会社や団体または組織の役員、従業員を兼任、兼職していないこと
投資を行う場合、投資家はさまざまな調査を行うことにより投資判断をするのが通常です(これを「デューデリジェンス」といいます)。
もっとも、調査のために事業者から開示された資料の内容が事実に反したものだと、投資家は合理的な投資判断ができなくなります。
事業者に一定の事項を表明保証してもらうことにより、その事項が虚偽であったり不正確であったりした場合に、投資を中止したり、事業者に対して責任を追及したりすることができるようになります。
表明保証の対象となる事項としては、事業者が法律に則って適切に事業を運営していることや、開示された文書が正確であること、リーガルリスクがないこと、反社会的勢力との関りがないことなどが挙げられます。
事業者は、投資家から表明保証を求められた場合はその対象事項をきちんと確認し、仮に表明保証することができない事項があれば、交渉段階において投資家にその理由を説明しておくことが大切です。
※「デューデリジェンス」について詳しく知りたい方は、「デューデリジェンスとは?注意すべき5つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。
※「表明保証」について詳しく知りたい方は、「投資契約における表明保証とは?事業者の3つの対応策を弁護士が解説」をご覧ください。
6 誓約事項
「誓約事項」とは、事業者と創業株主が、投資契約を締結した日から投資が実行されるまでの間、または投資が実行された後に投資家との間で守らなければならない事項を定めたものです。
-
1 発行会社等は、投資家に対し、本契約締結日から払込日までの間、自らの責任と費用において、以下に定める事項を遵守することを誓約する
①株式の発行のために必要な手続(株主総会決議等)を適法かつ有効に実施すること
②善良な管理者の注意をもってその事業の運営及び資産の管理を行い、通常の業務の範囲外の行為を行わないこと
③表明保証をした事項について真実でないことが判明した場合、またはそのおそれがあることを知った場合に投資家に通知すること
2 発行会社等は、投資家に対し、払込後、自らの責任と費用において、以下に定める事項を遵守することを誓約する
①払い込まれた資金を、事業の拡大・発展に合理的に必要と認められる人材採用、研究開発、設備投資、販路開拓に使用すること
②事業計画が変更になった場合には、最新の事業計画を投資家に提出すること
③定款や登記事項に変更が生じた場合に投資家に通知すること
投資家は、事業者が誠実に事業を運営してくれることを見込んで投資をしているため、投資契約を締結したとたん、ずさんな経営を行われてしまうと、投資判断の前提が崩れてしまいます。
そのようなことがないように、投資家との間で取り決めた約束事が「誓約事項」ということになります。
先に見た「表明保証」は、「ある時点において」一定の事項が真実かつ正確であることを表明保証するものであるのに対し、誓約事項は「将来的に」事業者と創業株主が守らなければならない事項を定めたものであるという点で違いがあります。
また、投資家が事業会社である場合、投資先の事業から何らかのシナジーを得たいと考えて投資をすることも多いため、投資した資金の使途を誓約事項で定めることもあります。
7 ペナルティ
「ペナルティ」とは、言葉のとおり、契約に違反した場合に課される制裁のことをいいます。
-
1 投資家は、発行会社等が本契約に違反し、損害を被った場合、発行会社等に対し損害賠償を請求することができる
2 投資家は、以下各号のいずれかの事由が生じた場合、発行会社等または発行会社が指定した第三者に対し投資家が保有する株式の全部又は一部を買い取るよう請求することができる
①表明保証した事項について真実でないことが判明し、かつ、その内容が重要な場合
②発行会社等が本契約に定める義務に違反し、一定期間内に是正できなかった場合
3 前項に定める買取価額は、以下各号に定める金額のうち最も高い金額に基づいて算出するものとする
①投資家が出資した時の1株当たりの払込金額
②直近の増資事例における1株当たりの払込金額
③直近の発行会社の1株当たりの純資産額
④直近の譲渡事例における1株当たりの価額
契約に違反した場合は、損害賠償責任を負わせることが一般的です。
もっとも、スタートアップ企業のように資力が十分でない場合、損害賠償を請求されてしまうと、資金が流出して企業価値が低下する結果、かえって投資家が損をしてしまうことが想定されます。
そこで上記2項で定められているように、投資家において買取請求ができる旨を定めることもあります。
そうすることで、投資家は、投下資本を回収することが可能になります。
8 まとめ
投資契約には、定めるべき事項が数多くあります。
投資家側で契約書を用意することもありますが、すぐにサインするのではなく、自社に不利な内容になっていないかなど、丁寧に内容を確認することが大切です。
弊所は、投資契約書や株主間契約書の作成等、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。