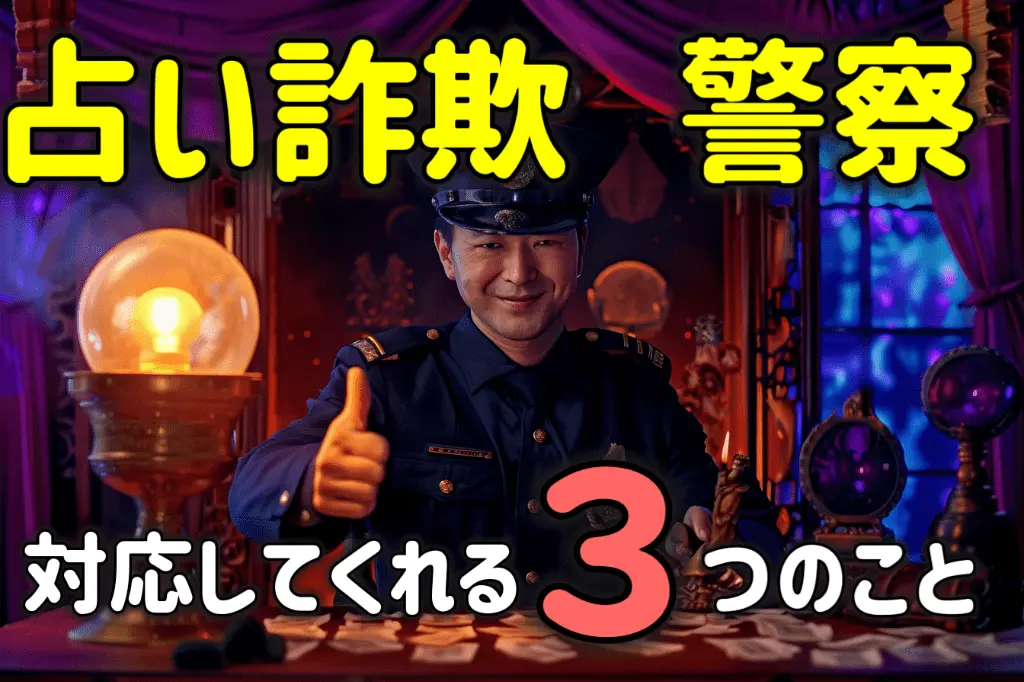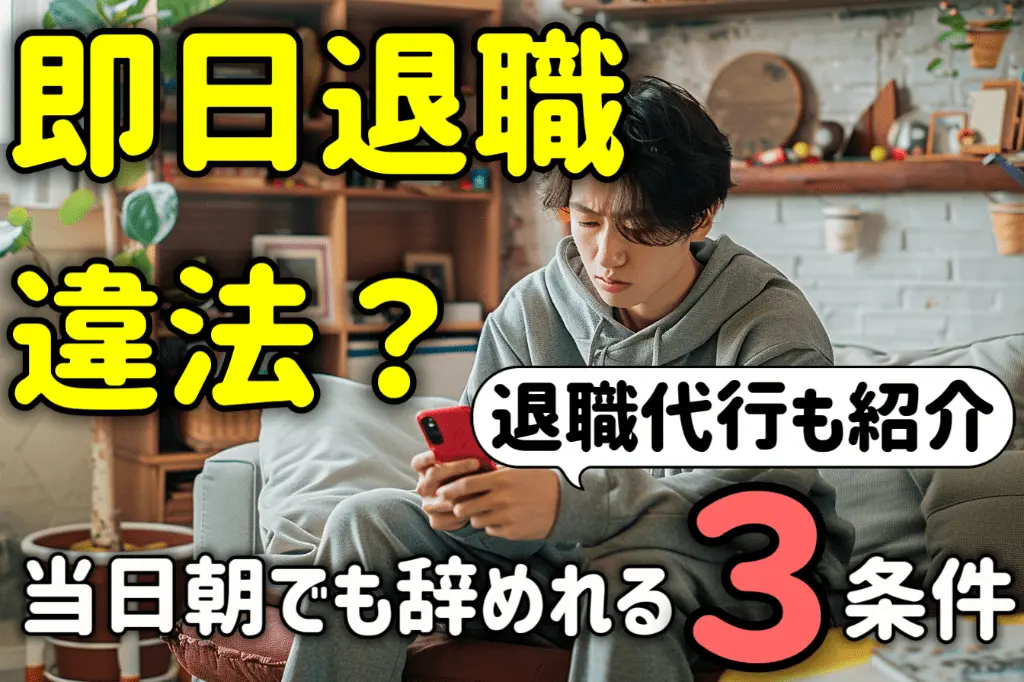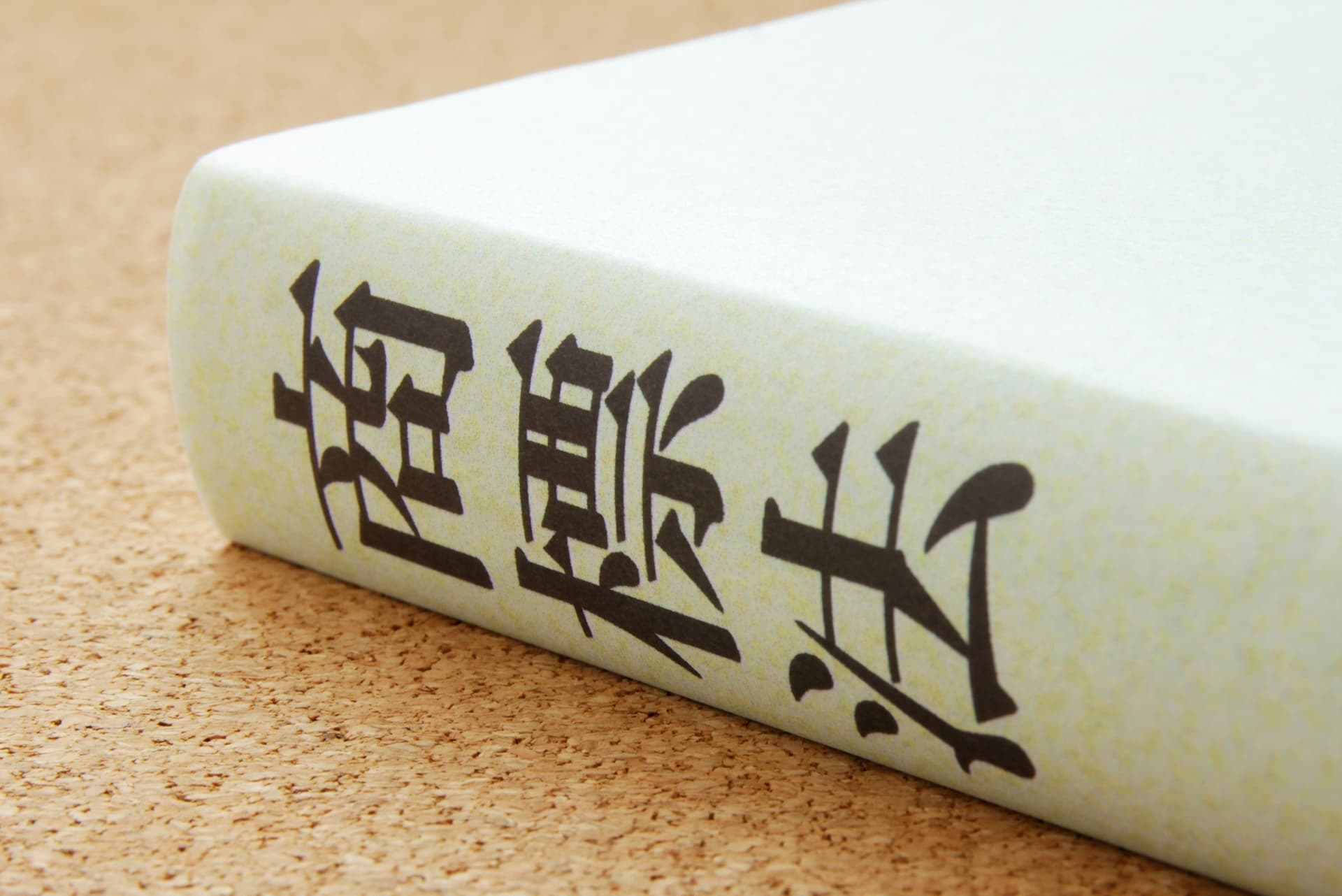セキュリティ・クリアランス制度(重要経済安保情報保護活用法)最新まとめ――企業が今すぐ備えるべき実務ポイント
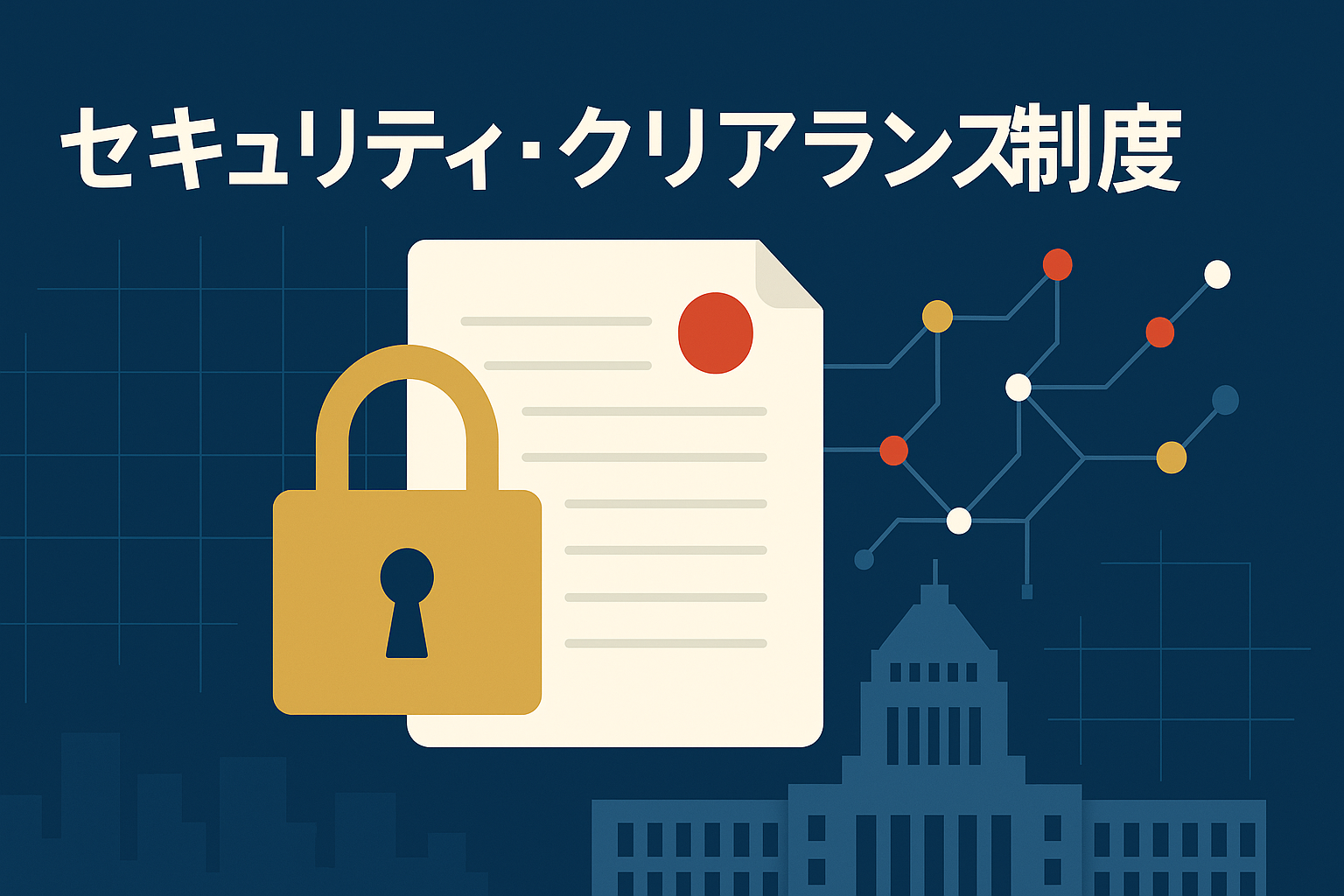
はじめに:なぜ今「経済安保×情報保全」なのか
日本では、経済・技術分野の機微情報を政府と民間で安全に共有するための枠組み(いわゆるセキュリティ・クリアランス制度)を導入する法律「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」(以下、本法)が成立・公布され、2025年5月16日に施行されています。
これにより、政府が指定する「重要経済安保情報」を扱う事業者・従業者に対し、認定(適合事業者)や適性評価(従業者クリアランス)が本格運用されています。
本法は、同盟国との情報連携や国内産業の技術保全を進める基盤として構想されたもので、立法過程や制度の狙いは内閣府および国会資料に整理されています。国会審議では2024年5月10日に可決、同年5月17日に法律第27号として公布、公布から1年以内の施行という枠組みが示され、施行日に向け各種政令・ガイドラインが整備されました。
https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/doc/jigyousyagl.pdf
制度の骨子:何が「重要経済安保情報」で、誰がアクセスできるのか
本法の目的は、「我が国の安全保障を確保するために特に秘匿が必要な重要経済基盤に関する情報」を、適切に保護する体制の下で収集・整理・活用することです。対象となる情報の例として、重要インフラや重要物資のサプライチェーン、先端技術等に関する情報が挙げられます
アクセスの仕組みは大きく二層です。
1)適合事業者(企業側の認定):行政機関が提供の必要性を認め、かつ情報保護体制等が一定基準に適合すると認定された事業者だけが、契約に基づき重要経済安保情報の提供を受けられます。
2)従業者の適性評価(個人側のクリアランス):適合事業者の中で当該情報を扱う従業者に対し、国が適性評価(身辺・財務・遵法性等の観点を含む)を実施し、アクセス可否を判断します。具体像はガイドライン・Q&Aに整理されています。
なお、制度活用の「入口」は、行政機関からの事前の打診(情報提供の必要性の見込み提示)が前提とされ、打診を受けた事業者が認定申請→審査→契約→従業者の適性評価、という流れを辿ります。行政機関が保有していない将来情報の創出(調査研究)を見込む場合でも、事前同意の上で認定が想定されています。
実務がイメージしやすくなる想定シチュエーション
1. 重要インフラの脆弱性情報を含む保守案件(電力・通信ベンダー)
行政機関から「設備構成・冗長化・障害復旧手順」など脆弱性に直結する情報の提供を受け、障害対策を共同で立案するケース。受け手は適合事業者の認定が前提で、当該情報に触れる担当者は適性評価(従業者クリアランス)が必要。図面・ログ・復旧手順は持出し制限・媒体管理・ゾーニングが求められます。ガイドラインは、組織体制、アクセス権、監査ログ、委託先統制、事故対応まで具体的要求を列挙(「規程のひな型」「契約書のひな型」も付属)しています。
2. 官主導の調査・研究で将来創出される情報を保有(サプライチェーン監視)
行政機関がまだ保有していない将来情報(例:重要物資のサプライチェーン断絶リスク評価)を、契約に基づき事業者側で作成・保有させるパターン。運用上は、行政からの打診→適合事業者認定→契約→従業者の適性評価→取扱い運用の順。ここで生じるデータの第三国アクセスや越境移転、共同研究先(大学・スタートアップ)への再提供は条項設計と技術的統制の併走が不可欠。
3. 人材調達:派遣・請負の“クラッシュポイント”対応
適合事業者に派遣就労するスタッフが機微情報に触れる場合、その派遣労働者も事業者の従業者として取り扱われます。労働契約の当事関係を前提に、適性評価の同意取得や職務範囲の限定、教育・遵守義務、監査権限等の整理が必要になります。
他制度との関係(特定秘密・国際連携)
本法は特定秘密保護法を置き換えるものではなく、より経済安保領域(インフラ・サプライチェーン・先端技術等)にフォーカスした新たな保全レイヤーを作る位置づけです。
これにより、政府‐産業界間での情報共有の幅が広がり、同盟国との防衛・技術協力で必要となる機微情報の取扱い基盤を補強する狙いがあります。国際連携の観点や国内企業の国際ビジネス機会との関係性は、報道・論考でも指摘されています。
罰則とコンプライアンス要求
本法は、重要経済安保情報の漏えいに対し、個人・法人ともに厳格な罰則を設けています(量刑の枠組みは特定秘密保護法と同程度の水準が参照される一方、経済安保分野特有の指定・取扱義務が追加)。
罰則の具体は条文・政令・運用基準のほか、各種解説が整理しています。制度趣旨と併せ、「漏えい防止のための組織的・技術的・人的管理」が実体として問われます。
企業が直ちに取り組むべき「7つの実務ポイント」
1. 自社の関与可能性の洗い出し(事業・取引マッピング)
まず、自社の事業が「重要インフラ」「重要物資サプライチェーン」「先端技術の研究開発・運用」等とどの程度関係するかを棚卸しします。該当可能性がある部門(電力・通信・物流・水道等のインフラ向け、半導体・材料・計測・AI・量子・宇宙・海洋・防災関連等)を特定し、行政機関からの「打診」を受け得るポジションかを検討します。
2. 適合事業者の認定に向けた組織・規程の整備
ガイドライン(適合事業者編)は、情報管理体制(責任者・権限・分掌)、人事・教育、物理セキュリティ、アクセス管理、ログ・監査、委託先管理、事故対応計画(インシデント・通報)など、内部統制の基準を具体的に示します。既存のISMS等の枠組みに、本法特有の指定情報の区分・保全要件を上乗せする設計が必要です。
3. 従業者の適性評価に備えた人事・労務対応
適性評価は、対象従業者の同意の下で実施され、信用・遵法性・財務状況等が確認されます。企業は対象者の選定基準、説明・同意取得のプロセス、評価結果の取扱い(配置・職務限定・不利益取扱い回避の配慮)を就業規則・個別同意書に反映させる必要があります。
Q&Aは実務上の疑問点(範囲・頻度・再評価等)に触れており、社内規程作成の手引になります。
4. 契約実務:行政機関との契約・秘密管理条項の見直し
情報提供の前提として、行政機関と提供契約を締結します。既存の秘密保持契約(NDA)や再委託契約についても、重要経済安保情報の定義・アクセス権管理・流通経路の限定・国外移転・外国関係者の関与等を明確化し、違反時の是正・通報・終了後の返還/廃棄まで条項設計をアップデートすることが不可欠です。
5. サプライヤー・再委託先の統制
適合事業者の認定は自社だけで完結しません。再委託・共同研究・共同開発で社外に情報が触れるポイントを特定し、委託先の適合性評価・契約義務(教育・設備・アクセス制御・監査権限)を設けます。研究機関・大学・スタートアップとの連携でも、国外とのデータ共有や越境移転の管理が要諦です。
6. インシデント対応計画と通報フロー
本法では、事故・漏えい時の対応が重視されます。ガイドラインは、検知→封じ込め→根本原因分析→関係当局・契約当事者への通報→再発防止のプロセスを求めます。サイバー事案を含む多様なシナリオ(不正持出し、誤送信、端末紛失、物理侵入等)に備え、机上訓練(TTX)の実施が推奨されます。
7. 経営レベルの統合:投資・人材・国際案件の意思決定
セキュリティ・クリアランスは単なる「情報管理」ではなく、国際共同開発・防衛産業参入・同盟国サプライチェーンの案件獲得に直結します。経営は、制度活用のROI、認定維持コスト(設備・人件・監査)、調達・M&A・合弁における制約を踏まえた資源配分を設計すべきです。外部論考も、制度が国際ビジネス機会の増大やトラスト形成に資する点を示唆しています。
よくある論点・誤解への短答
Q. 特定秘密との関係は?
A. 本法は経済安保領域の新レイヤーで、特定秘密保護法の代替ではない。重要経済安保情報のうち、より高い秘匿性を要するものは特定秘密の対象となり得ます(運用上の整理)。
Q. どの企業もすぐ申請できる?
A. 原則、行政機関からの打診→認定申請の流れ。自社からの任意申出だけで直ちに進む制度設計ではありません。
Q. 罰則は重い?
A. 厳格です。個人・法人とも漏えい時の責任が問われ、組織的・技術的管理の実効性が前提となります(詳細は条文・政令・ガイドライン参照)。
まとめ
本法は、日本版セキュリティ・クリアランスの経済安保版として2025/5/16に施行。運用基準・ガイドライン・Q&Aが整備され、適合事業者の認定と従業者の適性評価を柱に、政府と民間の安全な情報共有を実装する枠組みが動き出しています。
企業は、事業マッピング→体制・規程整備→契約見直し→人事・労務対応→委託先統制→訓練・監査まで、一気通貫の実装計画が必要です。
制度対応はコストであると同時に、国際共同開発・官民連携のチャンスを拡げる投資でもあります。迅速に差分把握を行い、「打診が来たら即応できる状態」を目標に準備を進めましょう。