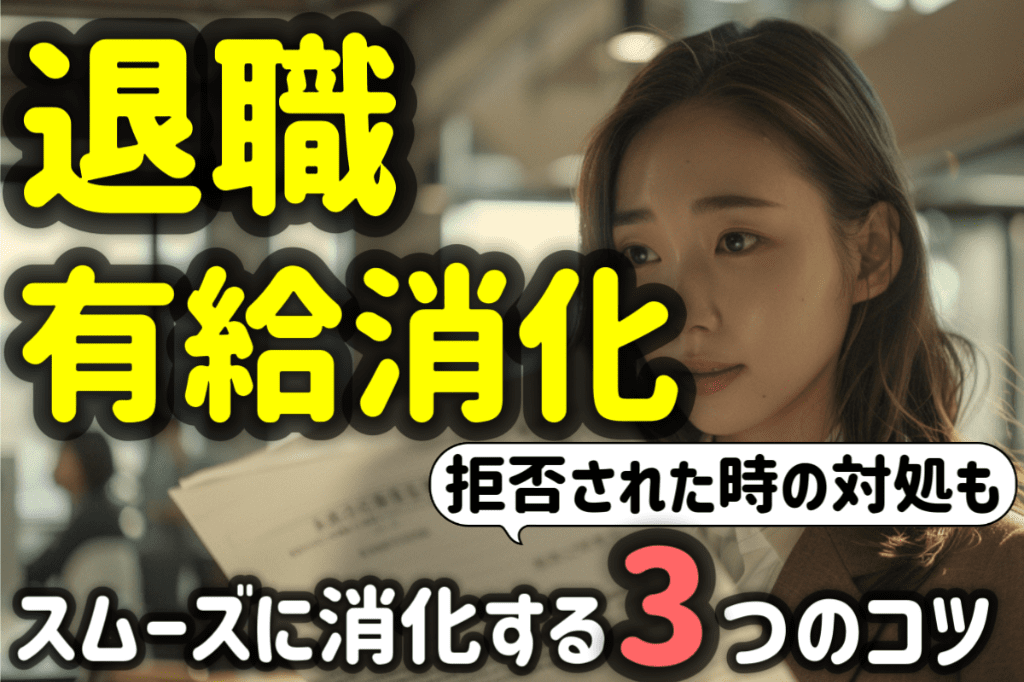株主間契約とは?定める4つの事項と作成時の注意点を弁護士が解説!

はじめに
「株主間契約」は、ベンチャー企業などが資金調達を行う際に重要となる契約の一つです。
株主間契約は、会社経営に関する事項を拘束する契約であるため、事業者は、契約を締結する際にはその内容を十分に確認することが必要です。
ろくに内容も確認せずに契約をしてしまうと、後にさまざまなトラブルを引き起こすおそれがあります。
今回は、「株主間契約」について、その全体像を弁護士がわかりやすく解説します。
1 株主間契約とは
「株主間契約」とは、言葉のとおり、株主の間で締結される契約のことをいい、具体的には、会社経営にあたり経営陣が遵守すべきルールなどが取り決められた契約のことです。
一般的に、株主間契約は、ベンチャー企業などが投資家から出資を受ける場合に、株主間において、その後の会社経営に関するルールを取り決めるために締結されることが多く、契約当事者となるのは、投資家と出資を受ける事業者、そして、既存の主要株主であることが多いです。
また、投資契約(事業者と投資家との間で締結する契約)と併せて締結されることが多く、投資契約では、主に投資が実行されるまでの条件が定められますが、株主間契約では、投資が実行された後の会社経営などについてさまざまな条件が定められます。
2 株主間契約で定める事項
株主間契約で定める一般的事項は、主に以下の4点です。
- 事前承認に関する事項
- 株式譲渡に関する事項
- 情報開示に関する事項
- 専念義務に関する事項
(1)事前承認に関する事項
会社運営において、一定の重要事項については、事前に株主の承認を得なければならないとするものです。
ここでいう「一定の重要事項」とは、たとえば、定款変更や取締役の選任・解任、上場予定時期の変更などが挙げられます。
少数派の株主についても、その意向を反映させることが可能となるため、出資者から契約に盛り込むことを求められることがあります。
(2)株式譲渡に関する事項
株式譲渡に関する事項は、さらに、以下の3つに分類することができます。
- 先買権に関する事項
- 共同売却請求権に関する事項
- 強制売却権に関する事項
①先買権に関する事項
「先買権」とは、創業株主が発行会社の株式を第三者に譲渡しようとするときに、出資者がその株式を自己に譲渡するよう求めることができる権利のことをいいます。
先買権に係る具体的な内容については、その一部行使を認めるかどうか、また、一度行使しなかった権利の再行使を認めるかどうかなど、事業者の事情によってその内容も大きく変わってきます。
たとえば、出資者(株主)と敵対的な関係にある創業株主に株式が譲渡されるのを防ぐために、出資者の求めにより、先買権に関する事項が契約に盛り込まれることがあります。
②共同売却請求権に関する事項
「共同売却請求権」とは、創業株主が発行会社の株式を第三者に譲渡しようとするときに、出資者も一緒に株式をその第三者に売却することを求めることができる権利のことをいいます。
投資家が投資を行う目的の一つは、売却益(キャピタルゲイン)の獲得です。
そのため、投資家としては、共同売却請求権に関する事項を契約に盛り込むことにより、創業株主が自己の株式を売却するタイミングで一緒に株式を売却することができ、売却益を得る機会を確保することができます。
③強制売却権に関する事項
「強制売却権」とは、発行会社の株式を買い取りたいという第三者が現れたときに、一定の条件を満たしていれば(一定割合以上の株主の賛成)、創業株主もこれに賛同しなければならないというものです。
たとえば、M&Aにおいて、第三者に株式を買い取らせて売却益を得たい場合に、創業株主が反対してM&Aが白紙になることを封じるために盛り込まれることがあります。
(3)情報開示に関する事項
事業者から出資者に開示する情報を取り決めます。
典型例として挙げられるのは、決算内容や貸借対照表・損益計算書などの財務情報ですが、それだけでなく、新規事業立ち上げに至るまでの意思決定に係る情報、訴訟を起こされた場合のそれまでの経緯などが開示対象となることもあります。
(4)専念義務に関する事項
出資者側からすれば、投資を実行した後に、創業株主が独断で代表取締役を辞任したり、発行会社とは別の会社の事業に注力して発行会社の経営を疎かにされては困ります。
このようなことがないように、「一定期間は発行会社の代表取締役を辞任できないこと」「他の会社の役員に就任するような場合には事前承認を得ること」といった取り決めを、専念義務に関する事項として契約に盛り込むことがあります。
3 株主間契約を締結する際の注意点
創業者や事業者が株主間契約を締結する際には、主に、以下の2点に注意することが必要です。
(1)事前承認に関する事項
株主間契約では、一定の重要事項について、出資者側の事前承認を要する旨の条項が盛り込まれていることが通常です。
そのため、事前承認を要する事項について、事業者は社内における承認手続きに加え、出資者の承認も得なければならず、意思決定の機動性が失われるおそれがあります。
事業者としては、事前承認を要する事項が不必要に広範囲に及んでいないか、また、出資者から承認・不承認の意思表示がなされない場合の取扱いをどうするか、といったことについてもきちんと確認しておく必要があります。
(2)株式譲渡に関する事項
先に見たように、株主間契約には、「強制売却権に関する事項」が盛り込まれることがあります。
このような事項を安易に盛り込んでしまうと、たとえば、IPOを目指していても、出資者の一定割合以上がM&Aによる株式売却に賛同した場合は、創業株主の株式も強制的に売却される可能性があります。
以上のような観点から、株式譲渡に関する事項についても、必要に応じてその内容を出資者と交渉することが必要です。
4 まとめ
株主間契約は、会社経営に一定の制限(ルール)を課すための契約です。
そのため、事業者は一つ一つの条項がどのような意味をもつのか、また、どのような効果が生ずるのか、などをきちんと理解したうえで、契約を締結することが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。