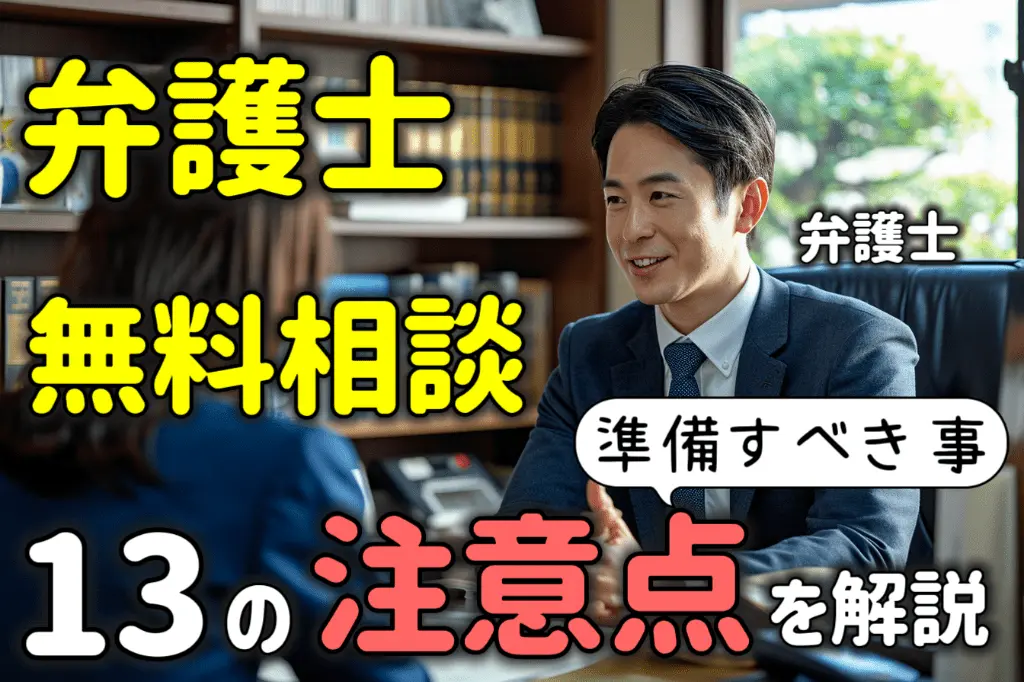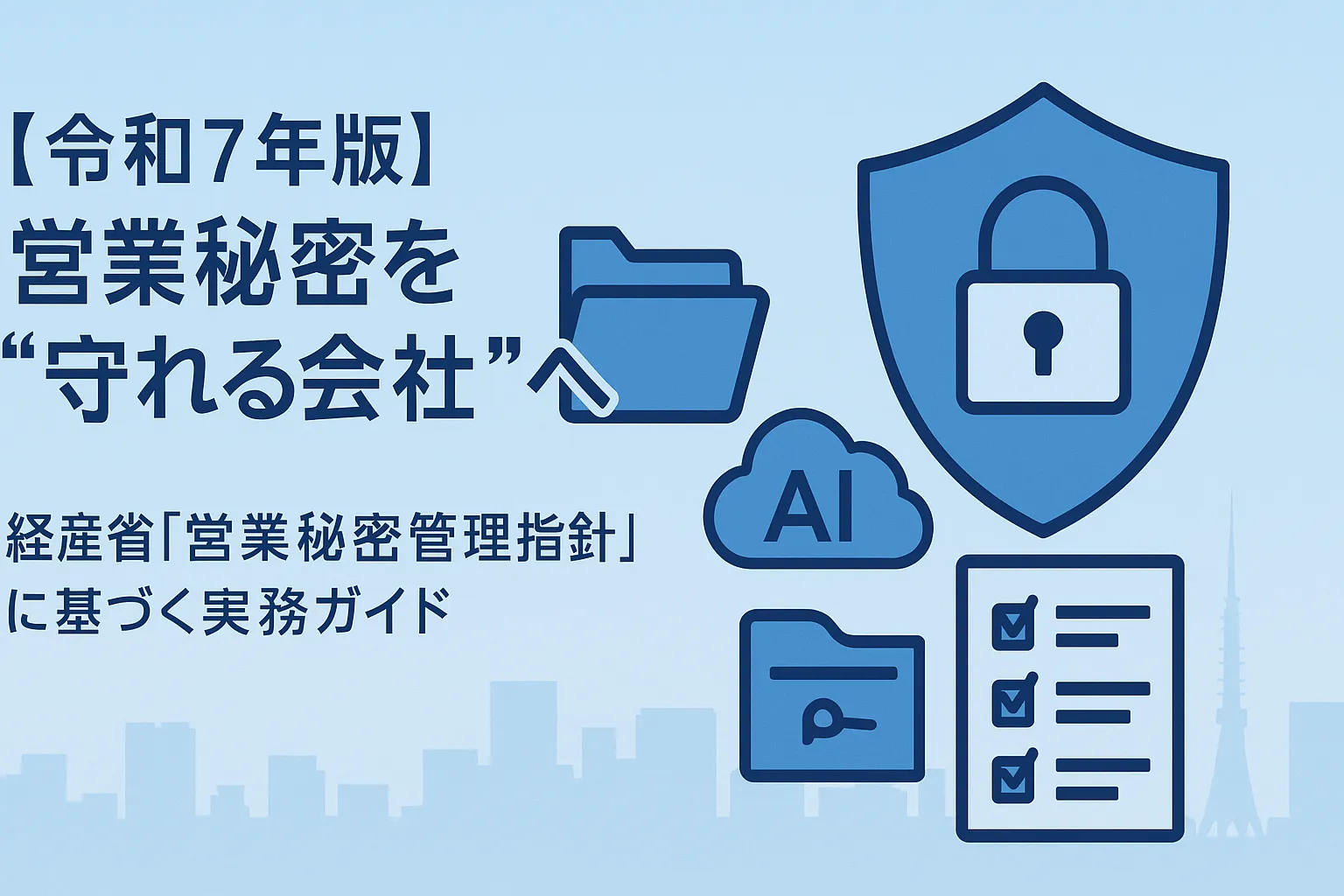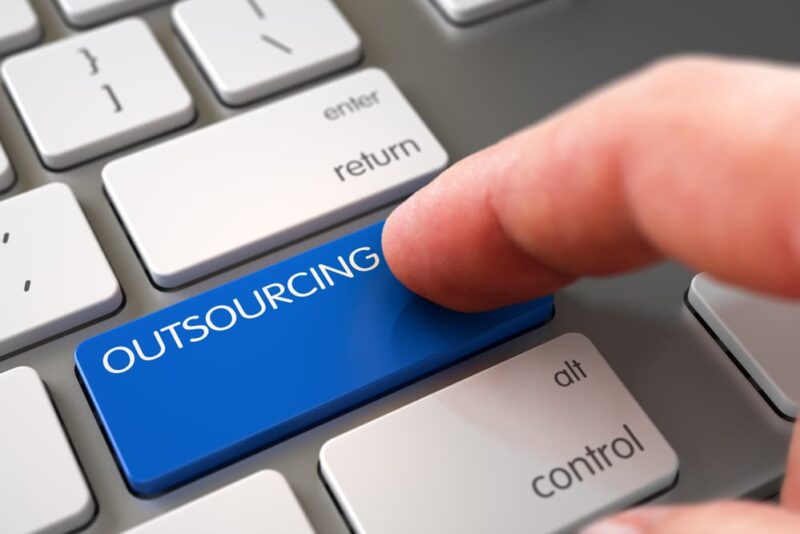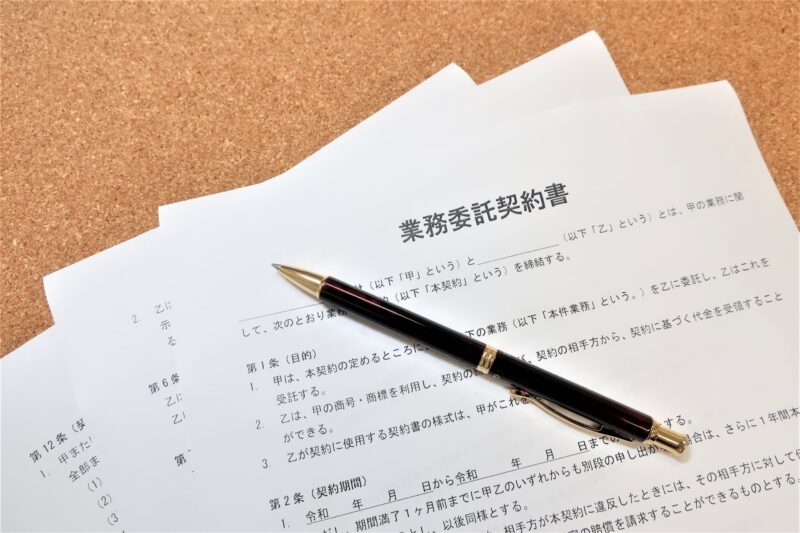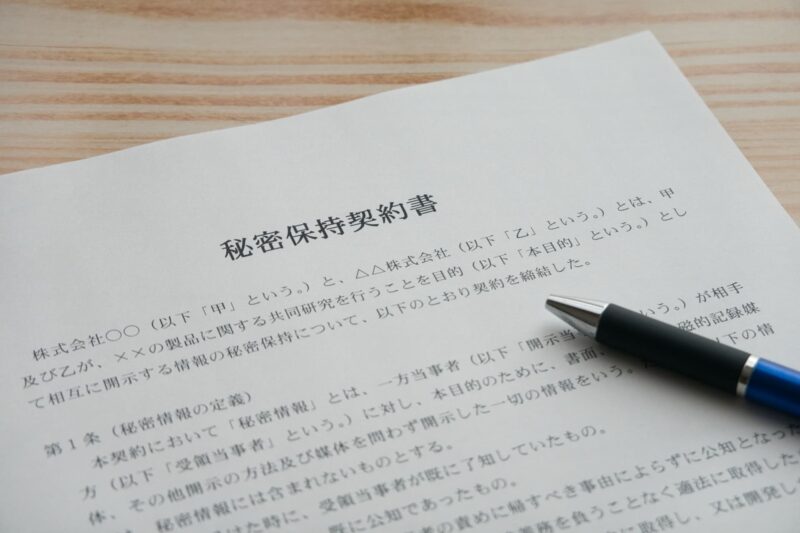FC契約で定めるべき4つの基本的事項とその際の注意点を解説!

はじめに
フランチャイズ契約を締結する際、インターネット上に転がっている契約書の雛形を適当に使うようなことをしてしまうと、後のトラブルに繋がる可能性があります。
実際に、できもしないことが定められていたり、トラブルに対する解決方法が定められていなかったりするケースがあるのです。
今回は、フランチャイズ契約で定めるべき事項を中心にわかりやすく解説します。
1 FC(フランチャイズ)契約とは

「FC(Franchise:フランチャイズ)契約」とは、本部と加盟店の間で締結される契約のことをいいます。
具体的には、本部が加盟店に対して、商標などを使う権利を与え、事業経営について指導などを行い、加盟店がその対価を支払うことを内容とする契約です。
FC契約の当事者である本部と加盟店は、それぞれ「フランチャイザー」「フランチャイジー」と呼ばれます。
私たちが日常的に利用するコンビニは、典型例といえます。
本部から商標(たとえば、セブンイレブンのマーク)の使用権を与えられることにより、加盟店はコンビニを経営できる仕組みになっているのです。
コンビニやスーパーといった小売業のほか、飲食店やサービス業などを展開する際に、FC契約が締結されることもあります。
2 FC契約で定める一般的な事項

FC契約を締結する際には、まずはじめに、基本的な事項を定め、そのうえで、自社の事業に特有の事項を定めていくことがポイントになってきます。
ここでいう「基本的な事項」としては、たとえば、以下のようなことが挙げられます。
- 商標の使用許諾
- ノウハウの提供とその権利帰属
- 加盟金・ロイヤリティ
- 契約解除
このほかにも、加盟店による事業が独立したものであることの定めや契約上の権利譲渡を禁止する定め、損害賠償に関する定めなど、基本的な事項だけでも、多くの項目を定める必要があります。
(1)商標の使用許諾
FC契約において、もっとも重要となるのが「商標の使用許諾」に関する定めです。
フランチャイズビジネスでは、本部によって使用権を与えられた名称やマークなどが、加盟店の売上にも大きく影響します。
コンビニを例にとって考えてみるとわかりやすいと思いますが、コンビニの名称やマーク等は、既に一般消費者から一定の信頼を得ているため、これらを使用すること自体が売上に繋がるわけです。
FC契約では、商標を使用する際のルールを定めることが一般的です。
たとえば、FC契約で定めた店舗以外で商標を使用することを禁止する旨の定めや本部の商標と類似する商標を加盟店が商標登録することを禁止する旨の定め、無断で商標を使用する第三者を発見した場合に、本部に対して報告することを義務付ける定めなどが挙げられます。
商標は、本部にとっては財産でもあるため、使用する際のルールを細かく決めておくことが大切です。
ルールを定めていなかったり、曖昧なルールを定めていたりすると、加盟店や第三者に想定外の使い方をされてしまい、損失を被るおそれがあります。
(2)ノウハウの提供とその権利帰属
加盟店がFC契約を締結する意義は、主に、ブランド力や集客力のある商標を使うことができる、また、本部からノウハウの提供を受けられるという点にあります。
提供されるノウハウが不十分だと、中途解約や加盟店とのトラブルを招く要因にもなります。
そのため、本部は加盟店から支払われる対価に見合ったノウハウを確立しておくことが大切です。
また、ノウハウについても、本部にとっては、商標と同様に貴重な財産ですので、その提供方法をFC契約できちんと定めておくことが必要です。
たとえば、ノウハウをまとめたマニュアルを作成・交付するとともに、開店前や開店後に研修・指導を行うといった方法が挙げられます。
この点、提供されたノウハウが対価に見合わないとして、加盟店が本部を相手取って損害賠償を請求した事例もあるため、注意が必要です。
さらに、提供したノウハウを無断で譲渡したり使用したりされることがないように、ノウハウの権利が本部に帰属することを定めておくことも必要です。
(3)加盟金・ロイヤリティ
フランチャイズチェーンに加入する場合、加盟店は本部に加盟金を支払う必要があります。
FC契約では、加盟金の金額や支払時期、支払方法を定めることが一般的であり、また、理由に関わらず、加盟金は返金されない旨も併せて定めることが多いです。
また、毎月加盟店が本部に支払うこととなるロイヤリティについても、その金額や支払時期、支払方法を定めます。
「ロイヤリティ」とは、商標の使用や本部による指導・援助の対価として、加盟店から本部に支払われる金銭のことをいいます。
ロイヤリティについては、どのような計算方法で算出するかということを決めておくことが重要になります。
計算方法には、「定額制」と「変動制」の2通りがありますが、それぞれにメリット・デメリットがあるため、これらを踏まえて計算方法を決定する必要があります。
(4)契約解除
本部が加盟店とのFC契約を解除できる事由を定めます。
一般的な解除事由としては、加盟店が契約に違反した場合や加盟店が破産した場合などが挙げられます。
また、中途解約についてもその可否や条件などを定めておくことが必要になるでしょう。
3 FC契約を締結する場合の注意点

FC契約を締結する場合、その業種に応じて各種業法の規制が及ぶこともあるため、関連する法令を十分に確認することが必要です。
たとえば、コンビニをはじめとした小売商業におけるFC契約では、中小小売商業振興法が契約締結時の説明義務を本部に課しています。
また、本部は必要な情報を加盟店に提供する義務を負っていると考えられているため、これに違反したことが原因となって、加盟店が損害を受けたような場合には損害賠償義務を負う可能性があります。
さらに、商標の使用許諾に関する定めとの関係では、独占禁止法を念頭に置いておく必要があるなど、FC契約で定める内容に応じて、どのような法規制が関係してくるかをきちんと確認する必要があります。
4 まとめ
FC契約を締結する場合、基本的事項はもちろんのこと、個別の事情に応じた定めを設けておくことが非常に重要になってきます。
もっとも、契約で定めるべき事項は多岐にわたり、検討すべき法規制も業種によって異なります。
契約で定めるべき事項が不足していたり、内容が曖昧なものになっていると、加盟店とのトラブルに発展するおそれがあるため、注意するようにしましょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。