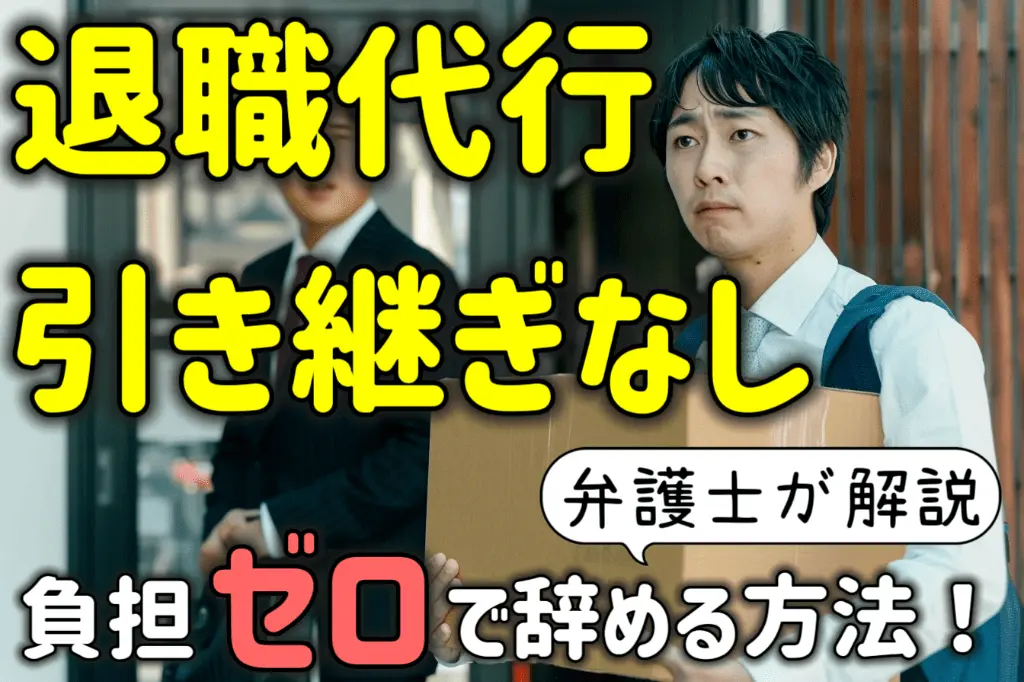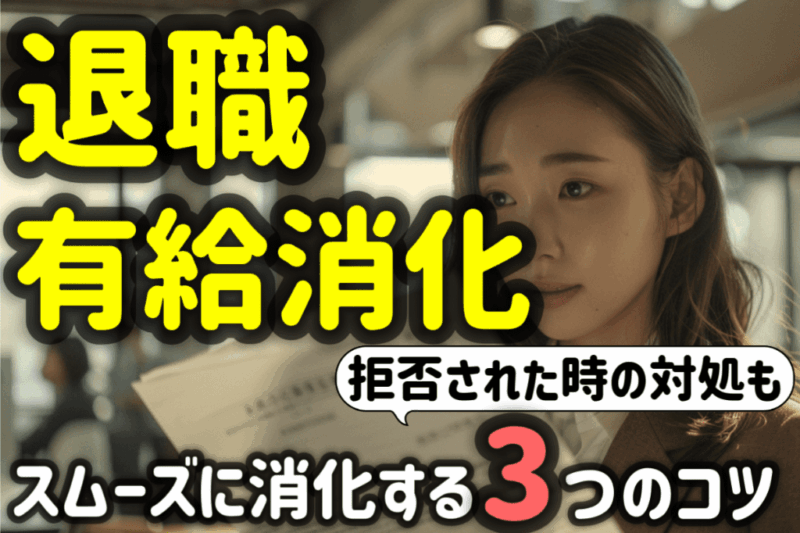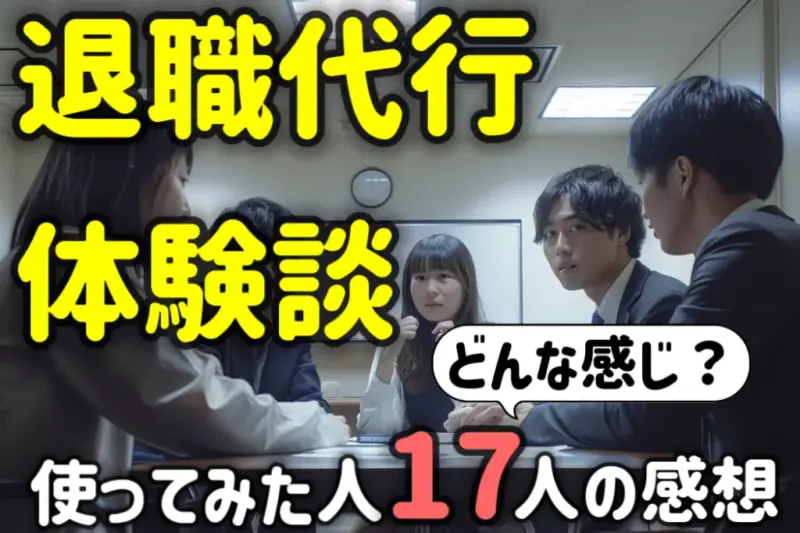覚書とは?法的拘束力の有無や書き方について弁護士が3分で解説!

はじめに
事業者であれば「覚書」という言葉を知っている方は多いと思います。
覚書は、契約書の内容を変更する場合に使われることもありますが、そもそも覚書と契約書とでは、法的拘束力に何か違いがあるの?と疑問を持っている方もいらっしゃると思います。
今回は、「覚書」の法的拘束力を中心に、わかりやすく解説します。
1 覚書とは
「覚書」とは、当事者間で取り決めた内容を記載した文書のことをいいます。
覚書を交わす目的というと、取り決めた内容を明確にしておくことにより、後のトラブルを防止する点にあります。
口頭で取り決めただけでは、その取り決めを証するものがありません。
そうすると、後になって「そんなことは約束していない」「約束した内容と違う」などと言われた場合に、反論できなくなってしまいます。
このようなことがないように、覚書により相手方と取り決めた内容をきちんと書面化しておくことが必要になってくるのです。
2 覚書の法的拘束力
みなさんもご存知のとおり、契約書には、法的に当事者を拘束する力が認められています(「法的拘束力」といいます)。
契約違反をした場合に民事上の責任が問題となるのは、契約書に法的拘束力が認められているからなのです。
それでは、覚書に法的拘束力は認められているのでしょうか。
この点、「覚書」であっても、契約書と同等の法的拘束力が認められると考えて差し支えありません。
たとえば、文書のタイトルが「覚書」であっても、実質において契約書と同じといえる覚書には法的拘束力が認められます。
もっとも、すべての覚書に法的拘束力が認められるわけではありません。
たとえば、以下の条件を満たしていないような覚書には、法的拘束力は認められません。
(1)当事者が合意していない場合
契約は、当事者の一方が契約の締結を申し込み、もう一方の当事者がその申込みを承諾したときに成立します。
このように、契約内容について当事者が合意することにより、契約が成立し、法的拘束力が発生します。
これは、覚書を交わす場合であっても同じです。
たとえば、当事者の一方が契約の内容を一方的に変更し、その内容を記載した覚書を作成したとしましょう。
これだけでは、契約内容を変更することについて、相手方が合意していないため、覚書に法的拘束力は認められません。
契約書と同様、覚書に法的拘束力が認められるためには、当事者が覚書に記載されている内容について合意していることが必要なのです。
(2)覚書の内容が抽象的である場合
たとえ当事者が合意していても、契約内容があまりに抽象的だったり、実現不能であったり、また、公序良俗に反していたりする場合には、その契約が無効になることがあります。
この点も、覚書にそのままあてはまります。
覚書を作成する際には、可能な限り、具体的に内容を定める必要があり、実現可能性等も念頭に置きながら作成することが必要です。
3 覚書の書き方
覚書に決まった書き方はありませんが、以下の事項を記載することが一般的です。
- 文書のタイトル
- 前文
- 合意の内容
- 署名
(1)文書のタイトル
覚書で重要となるのは、タイトルではなく、その内容です。
そのため、タイトルは、単に「覚書」としても良く、また、よりわかりやすくするのであれば、「〇〇についての覚書」としても問題ありません。
(2)前文
「前文」とは、合意する当事者や何についての覚書であるかを明確にする部分のことです。
何らかの契約書で見たことがある人も多いと思いますが、「〇〇社(以下、甲という)と〇〇さん(以下、乙という)は、〇〇に関して、本日以下のとおり合意する」といった記載の部分が前文にあたります。
前文を置くことにより、覚書を交わす当事者が特定でき、何についての覚書かが明確になるわけです。
(3)合意の内容
「合意の内容」は、覚書においてもっとも核となる部分です。
「合意の内容」と一言でいっても、そこにはいくつかのパターンが存在します。
たとえば、「甲と乙は、相互に〇〇を確認する」「甲は乙に対し、〇〇することを相互に確認する」といったように、一定の事項を確認するために、覚書を交わすこともあります。
また、既に締結されている契約書の内容を変更するために、覚書を交わすこともあります。
この場合は、変更前の契約内容と変更後の契約内容を併記するなどして、合意の内容がわかるように記載します。
(4)署名
覚書に当事者の署名がないと、「本当に覚書を交わしたのだろうか」などと疑われても仕方ありません。
当事者の署名があることにより、確かに、覚書の内容を確認して、その内容に合意したんだな、ということがわかります。
一般的に、署名欄には、名前だけでなく、住所と会社名、役職等を記載します。
また、覚書をいつ交わしたのかということも非常に重要であるため、日付欄を設けることが一般的です。
※覚書の雛形は、「【雛形付き】覚書の書き方をフォーマットを基に弁護士が詳しく解説!」からダウンロードできるようになっています。
4 まとめ
法的拘束力という意味で、「覚書」は契約書に比べ弱いと思っている方が少なくありません。
ですが、条件さえきちんと満たしていれば、「覚書」と題していても、法的拘束力は契約書と何ら変わりはありません。
覚書を作成する際には、その点を念頭に置きながら、適切な内容にすることが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。