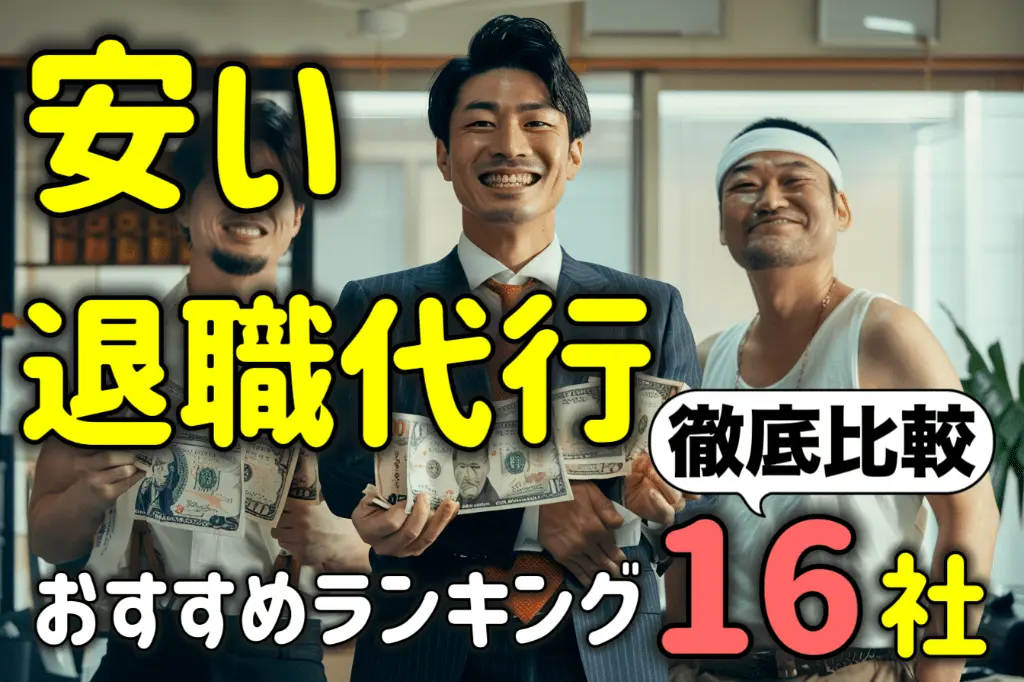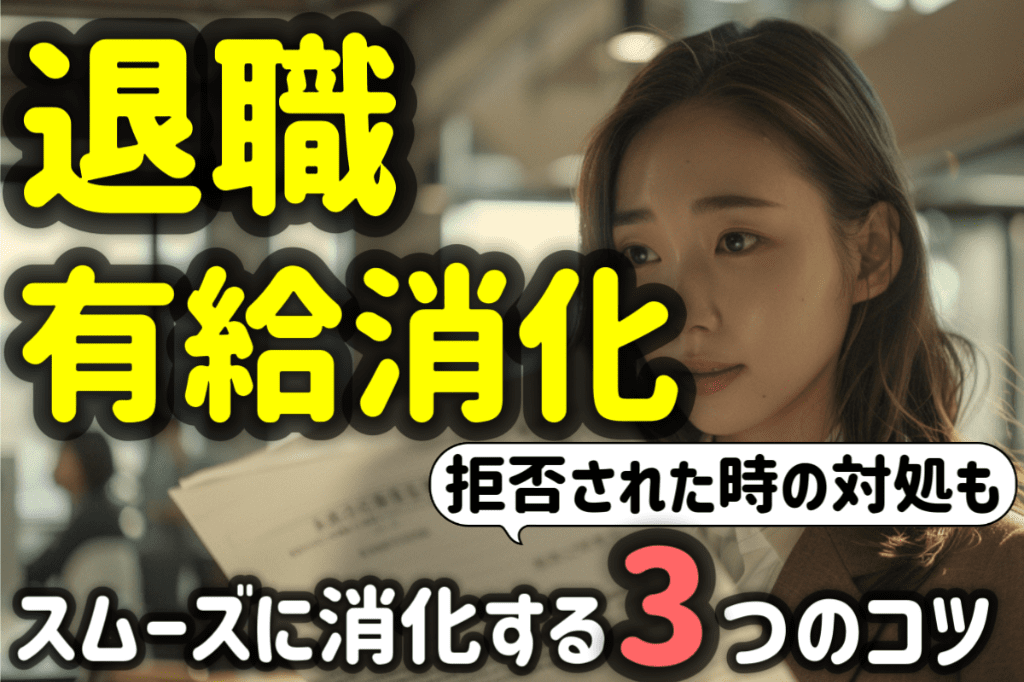株主提案権の濫用対策はどう変わる?個数制限・要件見直しの論点を徹底解説

1. 導入:株主提案権の意義と、改正議論が浮上する背景
株主提案権は、株主が会社の経営に参加するために、会社が招集する株主総会の議題や具体的な議案を提案する権利です(会社法第303条、第305条)。
株主提案権は、主に以下の3つの権利に分けられます。
1. 議題提案権(議題追加請求権)
議題提案権は、株主総会の目的となる事項(議題)の追加を請求する権利です。
概要: 株主は、株主総会の会日の8週間前までに、代表取締役(指名委員会等設置会社では代表執行役)に対し、一定の事項を株主総会の目的とすること(たとえば、取締役選任の件や定款変更の件など)を請求できます。
2. 議案通知請求権
議案通知請求権は、株主総会の目的となる事項について、株主が提出しようとする具体的な議案の要領を他の株主に通知すること(書面で招集通知をする場合には、その通知に記載・記録すること)を請求する権利です。
概要: 株主は、株主総会の会日の8週間前までに、代表取締役(指名委員会等設置会社では代表執行役)に対し、議案の要領を他の株主に通知することを請求できます。
3. 議案提出権(動議の提出)
議案提出権は、株主総会の議場において、株主総会の目的である事項(議題)につき、具体的な議案を提出する権利です。
• 行使要件: 議決権を行使することができるすべての株主に認められており、議題提案権や議案通知請求権のような議決権割合や継続保有期間の要件は課されません。
• 効果: 議案提出が無視された場合、決議方法に法令違反があるものとして、総会決議取消しの訴えの対象となります。
しかし、この重要な権利が一部の株主によって濫用的に行使され、株主総会の円滑な運営が阻害されたり、他の株主の共同の利益が害されたりする事例が増加したことで、会社法における株主提案権の濫用対策のあり方が、喫緊の課題として浮上しています。
2. 株主提案権の現行制度と濫用対策の土台
現行の株主提案権の行使には、濫用防止と少数株主保護のバランスを取るための要件が設けられています。
2-1. 現行の行使要件
取締役会設置会社(特に公開会社)の場合、議題提案権や議案通知請求権を行使できるのは、「総株主の議決権の100分の1以上、または300個以上の議決権を6か月以上継続保有する株主」に限られます。
この「継続保有期間」(公開会社の場合6か月以上)は、株主が提案について真摯な関心を持ち、投機的な目的ではないことを担保し、濫訴を防止するための要件です。また、「議決権割合」(100分の1以上または300個以上)の要件は、株主総会の議題設定にある程度の合理的な支持基盤を要求するものです。
2-2. 現行の濫用対策と限界
現行法では、株主総会の円滑な運営を確保するため、会社側が提案を拒否できる具体的な事由が定められています。
会社は、提出された議案が以下のいずれかに該当する場合、招集通知への記載や、株主総会の議場での提出を拒否できます。
- 法令または定款に違反する議案:提案内容が法や会社の自治規範(定款)に反する場合。
- 実質的に同一な議案の反復提案:過去3年以内に、株主総会で総議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった実質的に同一の議案を再度提出する場合。
さらに、株主の権利行使が「自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または会社に損害を加えることを目的とする場合」には、会社に対して責任追及等の訴えの提起を請求できないという規定があります(会社法第847条第1項ただし書)。これは、権利行使の濫用を禁じる一般原則(信義則や権利濫用)に基づくものであり、濫訴防止のためには、裁判所が悪意による訴えの提起と認めた場合、原告株主に担保提供命令を命じることができます。
しかし、現実の総会運営においては、上記のような形式的な拒否事由に該当しないものの、総会を混乱させることのみを目的とした多数の議案が提出されたり、実現可能性の低い詳細な議案が大量に提出されたりするケースが問題となっています。現行の濫用対策では、このような悪質な「議案の量的な多さ」や「提案の目的の不純さ」に十分に対応できていないという限界が指摘されています。
3. 改正議論の核心:濫用対策の見直し論点(アップデート版)
株主提案権の濫用対策は、「少数株主の正当な意見表明の機会」と「総会運営の効率」の両立がテーマです。
以下、2021年改正法で対応済みの論点と今後の検討を分けて記載します。
3-1. 論点1:株主提案の「個数制限」
[2021年改正・改正済み]
一株主あたりの提案数上限=10個が法定化。上限を超える部分は会社は不掲載可。
提案者が優先順位を示さないときは、会社側で上程する議案を選定可。
→ 導入の是非は既に決着。現在は運用(重複提案の束ね方、上程順、参考書類記載の簡潔化など)が実務論点。
[今後の検討]
上限10の運用明確化(実質的重複の扱い、分割提案への対応指針、議案の様式標準化)。
電子提供制度との接続(オンラインでの閲覧可能性を前提に、参考書類の分量・体裁をどう最適化するか)。
3-2. 論点2:行使要件の「見直し」と濫用の「目的」への着目
[2021年改正・改正済み]
“泡沫提案”の再提出制限が導入。直近3年のいずれかの総会で賛成率10%未満の実質的同一議案は、会社は不掲載可。
→ 事後的な決議取消しより、事前段階での不掲載により濫用抑止を図る枠組みが整備済み。
[今後の検討]
行使要件(要株数・継続保有)の再設計:
現行の“議決権数300個”基準の撤廃を視野に、投資金額要件や複数株主の連名(人数)要件など、アクセス確保と濫用抑止のバランスをとる代替案が俎上に。
“目的・合理性”ベースの不掲載事由の明確化:
私的な不当目的(攪乱・報復等)や実行可能性が著しく欠ける提案への事前拒否基準の明確化。
ただし、主観的な動機判断の困難さに配慮し、客観的基準(反復性、実質同一性、実行可能性、費用対効果等)での運用指針整備が課題。
バーチャル(ハイブリッド)総会との整合:
動議・質問の濫用を抑えつつ、議長の議事整理権や事前ルールの明示をガイドライン化。
4. まとめ:バランスの追求と今後の展望
株主提案権の濫用対策の議論は、常に「少数派株主の保護」と「総会運営の効率性」という、会社法の二大柱の間の緊張関係の中で進められます。
少数派株主は、資本多数決の原則の下で、多数派株主や経営陣の恣意的な権限行使の犠牲になるおそれがあります。そのため、株主提案権や、会計帳簿閲覧請求権、責任追及等の訴え(代表訴訟)などの監督是正権は、少数派株主の権利として極めて重要です。
しかし、これらの権利が「濫用的に行使される危険」も同時に存在します。現行法では、訴権の濫用を防ぐための担保提供命令 などが設けられていますが、株主提案権の濫用に対しては、提案の個数制限の導入や、提案目的の審査基準の明確化など、より実効的な規制が求められることになります。
これらの見直しは、株主提案権という民主的な機能を損なわないよう、悪意の提案者を特定し、その影響を限定することに注力しつつ、会社経営の自由と効率性を高める方向で進むことが期待されます。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。