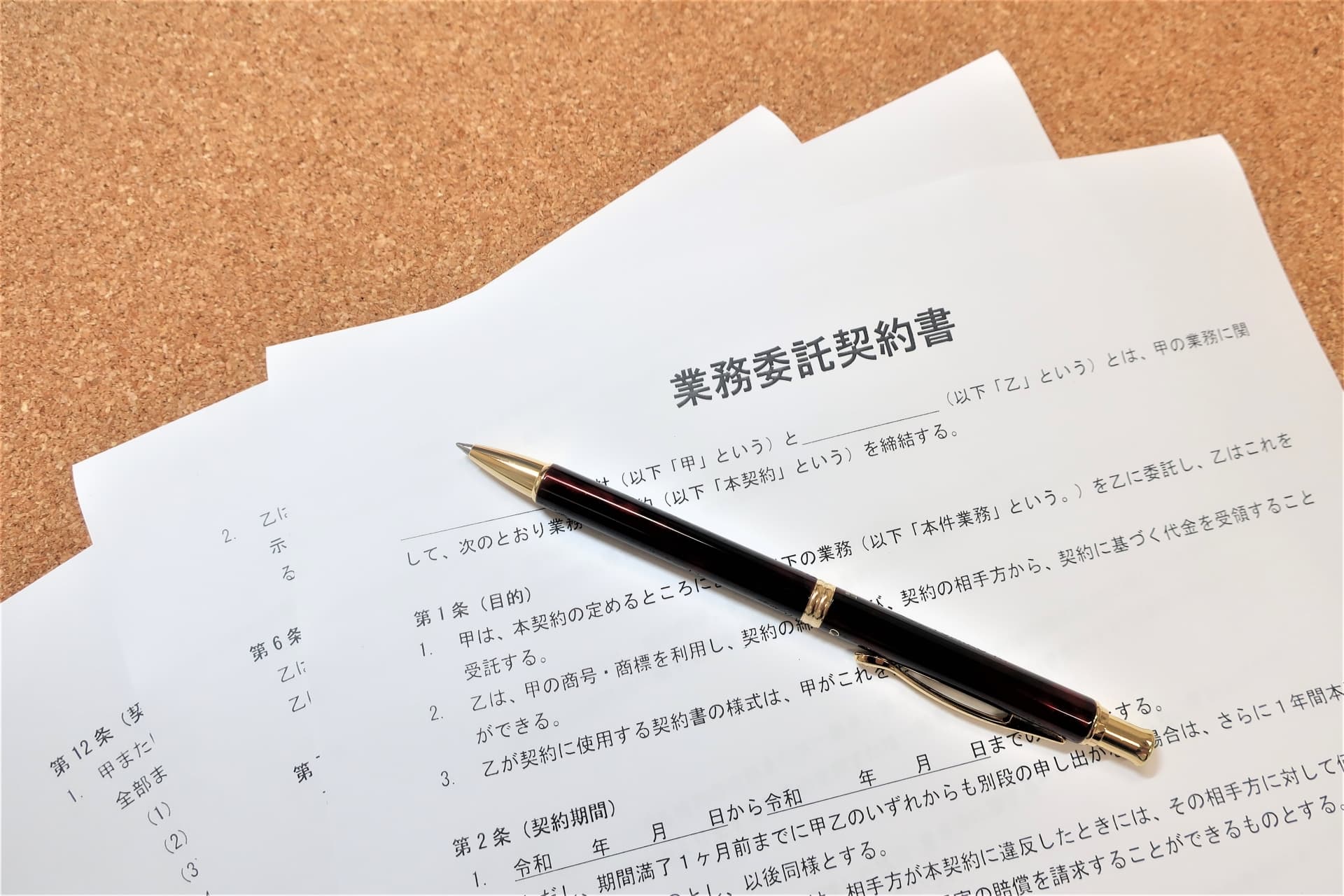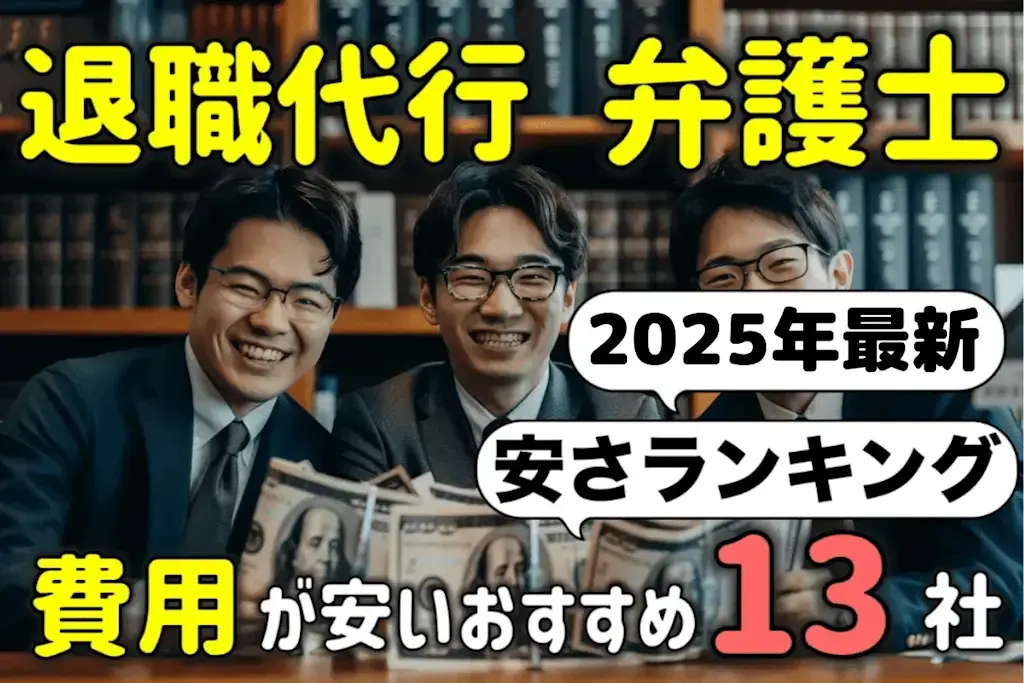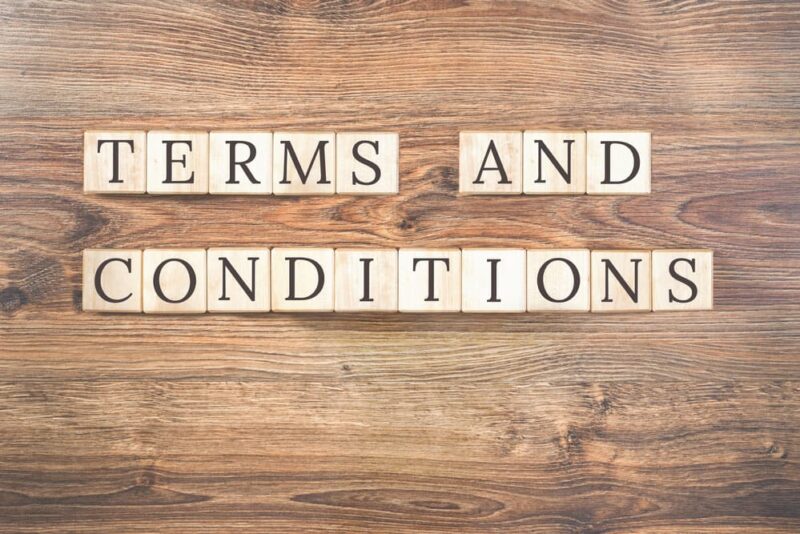消費者契約法とは?利用規約の作成時に注意すべき4つのルールを解説

はじめに
サービスを開始する場合に必須となる「利用規約」ですが、利用規約にはサービスの利用上のルールを定めるとともに、防御する目的で自社に免責を与えておくことが一般的です。
事業者としては、できるだけ自社に責任が生じないような免責条項を設けておきたいところですが、あまりに一方的な内容で定めてしまうと、「消費者契約法」に違反する可能性があります。
利用規約に「当社は一切損害賠償責任を負わない」といった免責事項を設けている事業者は、いまいちど利用規約を見直す必要があります。
今回は、利用規約を作成する際に注意すべき消費者契約法について、わかりやすく解説します。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 消費者契約法とは
事業者が消費者と契約を締結する場面では、情報の量や質、交渉力などにおいて、両者の間には格差があることが一般的です。
このような状況を受けて、消費者の利益を保護するために作られたのが「消費者契約法」です。
消費者契約法は、消費者の利益を守るという観点から、以下の事項についてルールを定めています。
- 事業者の損害賠償責任に関する事項
- 消費者の解除権に関する事項
- 消費者が支払う損害賠償額に関する事項
- 消費者の利益に関する事項
以下で詳しく説明しますが、これらのルールに違反した内容を利用規約で定めてしまうと、その条項は無効となるため、注意が必要です。
2 事業者の損害賠償責任に関する事項|消費者契約法8条
消費者契約法は、事業者の損害賠償責任に関して、以下のようなルールを定めています。
-
- 【消費者契約法8条1項】
-
- 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
-
- 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
-
- 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
-
- 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
- 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
このように、事業者に係る損害賠償責任の全部を免除する旨の条項や、事業者の故意・重過失による損害賠償責任の一部を免除する旨の条項は無効となります。
たとえば、ソフトウェアやコンピューターシステムの故障などにより生じた障害について、事業者は一切責任を負わないとする条項、サービスの利用にあたりいかなる損害が発生しても事業者は一切責任を負わないとするような条項は、無効となる可能性があるということです。
また、事業者による債務不履行・不法行為に起因して消費者に損害が生じた場合において、その責任の有無や限度の決定権を事業者に与えるといった内容の条項も無効となります。
3 消費者の解除権に関する事項|消費者契約法8条の2
消費者契約法は、消費者の解除権に関して、以下のようなルールを定めています。
-
- 【消費者契約法8条の2】
- 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
このように、事業者の債務不履行に起因して消費者に発生した解除権を放棄させる旨の条項は、不当性が高いため、無効とされます。
たとえば、販売した商品について、契約後のキャンセルを一切認めないとするような条項は無効となります。
また、上記の場合において、解除権が発生したかどうかの決定権を事業者に与える旨の条項も無効となります。
4 消費者が支払う損害賠償額に関する事項|消費者契約法9条
消費者契約法は、消費者が支払う損害賠償額について、以下のようなルールを定めています。
-
- 【消費者契約法9条】
-
- 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
-
- 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
- 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
違約金を定める条項において、契約の解除に伴い事業者に発生する平均的な損害額を超える部分、遅延損害金について年利14.6%を超える部分が定められている場合は、その条項は無効となります。
言い換えれば、著しく高額なキャンセル料を定める条項や、解約をしても返金はしないこととする旨の条項を設けると、その条項は無効になるということです。
たとえば、サービス料の支払いについて、支払期限を過ぎた場合には1ヶ月のサービス料に対し年30%の遅延損害金を支払うものとするといった条項は、無効となります。
5 消費者の利益に関する事項|消費者契約法10条
消費者契約法は、消費者の利益を保護する観点から、以下のようなルールを定めています。
-
- 【消費者契約法10条】
- 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
任意規定(当事者の意思によって適用を排除できる規定)を適用した場合に比べ、消費者の権利義務を制限・加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効となります。
たとえば、商品の購入時にその商品と併せて別の商品が同封されていた場合において、電話などにより別の商品を購入しない旨の意思表示をしないかぎり、別の商品を購入したものとみなす旨の条項は無効となります。
また、消費者の不作為(何もしないこと)をもって、消費者が新たな契約の申込みやその承諾の意思表示をしたものとみなす条項も無効となります。
6 まとめ
利用規約は、利用者とのトラブルを未然に防止するためにも、必ず作成する必要があります。
もっとも、自社に一方的に有利となるような利用規約は、消費者契約法により無効となる可能性があるため注意が必要です。
利用規約を作成する際には、事業者と利用者のバランスに注意しながら作成するようにしましょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。