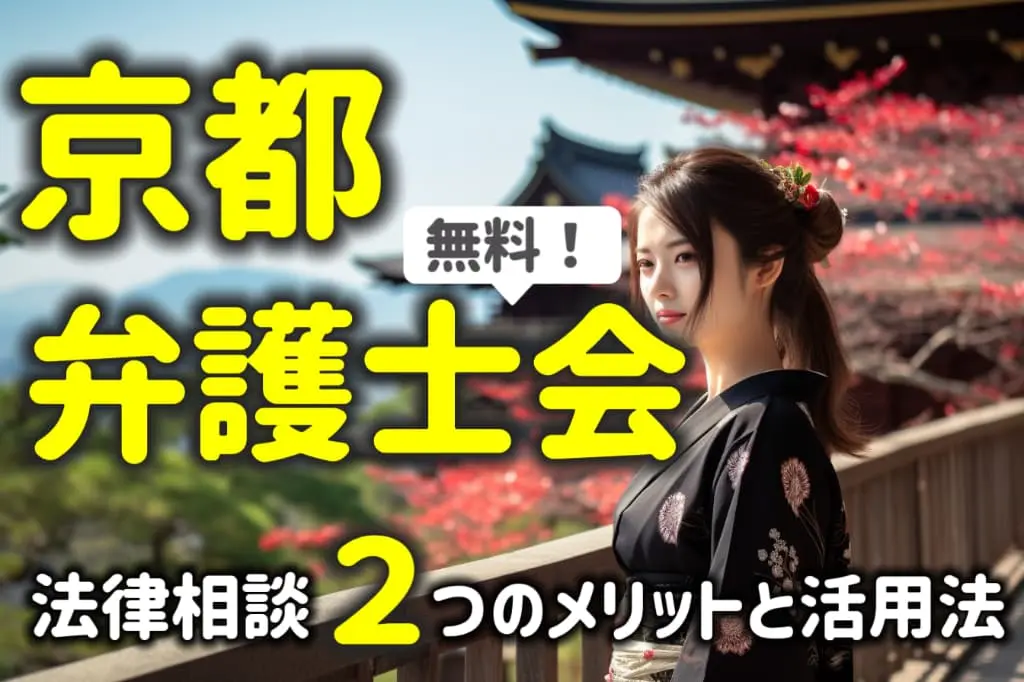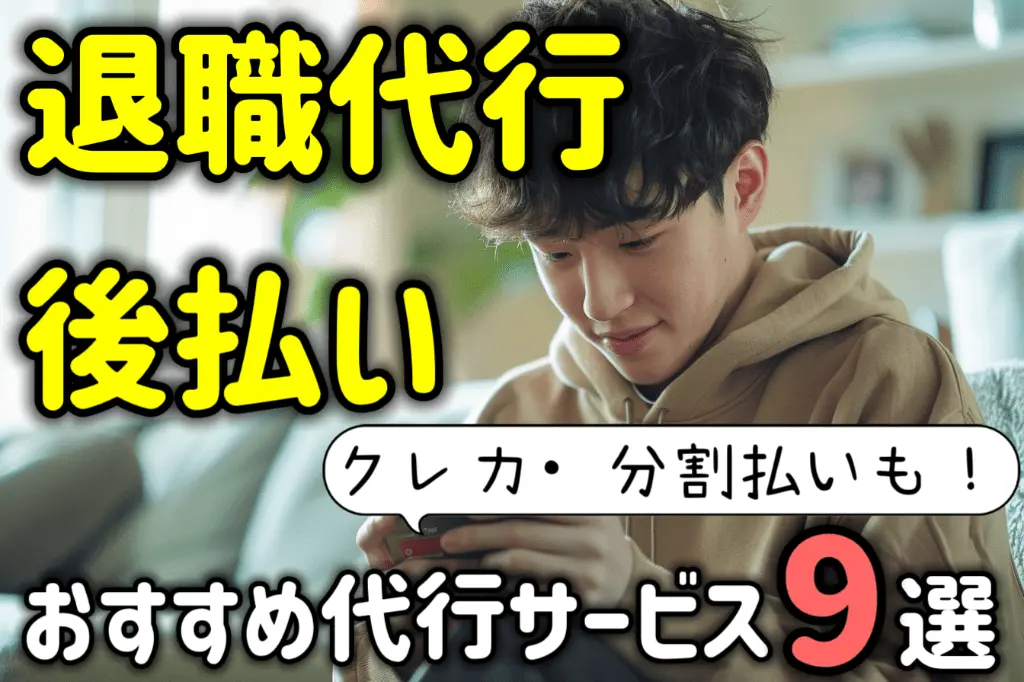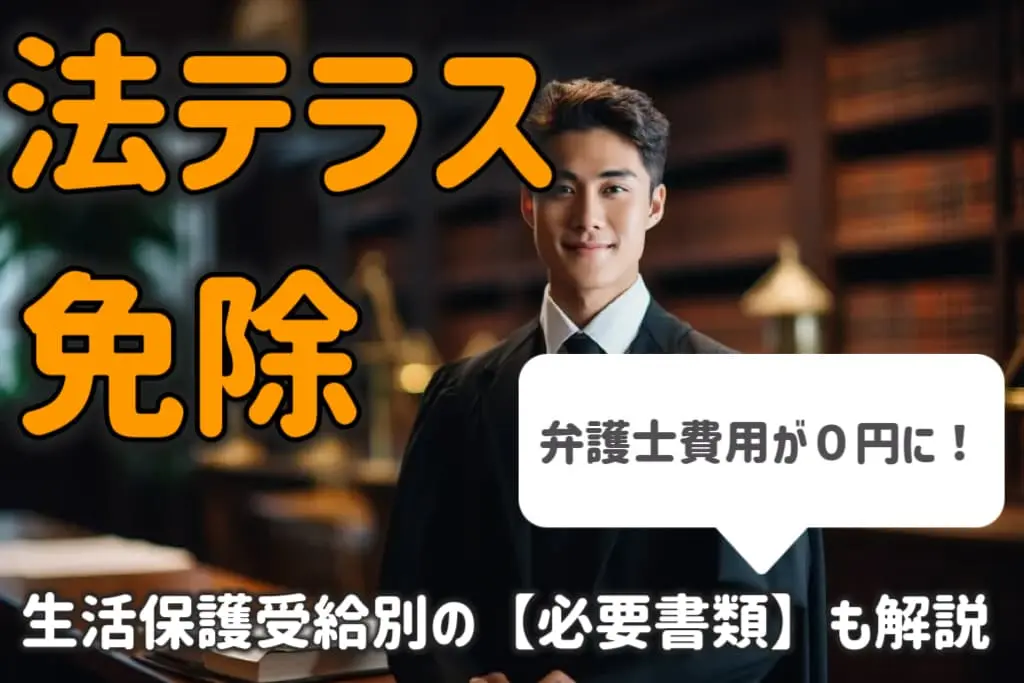盛りすぎ広告に注意!5分でわかる景表法に違反しないためのポイント

はじめに
みなさんが広告を出すとしたら、どのような言葉を使い、どのような内容にしますか?
自分たちが売り出す商品をより多くの人に知ってもらいたい、買ってもらいたいという思いから、ついつい盛った内容の広告にしてしまいがちではないでしょか。
日常生活で「一粒飲むだけで簡単に痩せる!」や、「これだけでスッキリ小顔に!」など、ちょっとおおげさだなぁ・・・という広告を見たことがありますよね。
このような、セールストークの範囲を超えて消費者をダマすような大げさな広告については、「景品表示法(けいひん ひょうじほう)」という法律によって規制されており、これに違反すると、
- 社名公表
- 課徴金という制裁を受けたり、
- 悪質なケースについては、“刑事罰”として、最大2年間の懲役
を受けるリスクがあります。
実際に、平成26年には楽天株式会社が価格の二重表示をしたことが問題となりましたし、直近の違反事例では、アディーレ法律事務所の弁護士費用についての広告がこの景表法に違反するとして、大幅なイメージダウンと数億円の損失が出ましたよね(アディーレ業務停止の理由とは?を参照)。
このような事態にならないためにも、以下では、景表法のポイントについてアプリやwebサービスに関連する広告(表示)に焦点をあてて解説していきます。
1 景表法とは

「景表法(けいひょうほう)」とは、企業が商品・サービスの広告をする際のルールを定めた法律です。
私たちが普段商品やサービスを買うとき、買うかどうかはその内容や値段を見て判断しますよね。
そのため、商品やサービスに関する情報について、ウソはもちろんのこと、オーバーな表現をされた場合、その商品の本当の価値を判断できなくなります。その結果、本来であれば買わないような物まで買わされてしまうおそれがあります。
このような、盛りすぎ広告などによって、ユーザーの「安くていい物を買いたい」という判断がねじまげられないように作られたのが景表法です。
2 景表法規制の概要

さて、景表法による「表示(広告)」のルールは、大きく分けると3種類あります。
いずれも、盛りすぎな広告によって、消費者の判断を誤らせないために作られたルールです。
- 「優良誤認」(ゆうりょうごにん)
- 「有利誤認」(ゆうりごにん)
- 内閣総理大臣が指定する表示
なお、ここでいう「表示(広告)」の種類としては、以下のようなものがあります。
- チラシ・パンフレット、カタログ
- 容器、パッケージ、ラベル
- ダイレクトメール、FAX広告
- ディスプレイ(陳列)、実演販売
- 新聞、雑誌、出版物、テレビ、ラジオCM
- ポスター、看板
- 訪問・電話によるセールストーク
- インターネット上の広告、メール
それでは次の項目から、規制される類型ごとに、詳しく見ていきましょう。
3 優良誤認表示

(1)優良誤認表示とは
「優良誤認表示」とは、商品やサービスの品質・企画などの内容面について、
- 実際のものよりも著しく優良にみせかけるような表示
- 事実と違うのに他者の競合サービスよりも著しく優良に見せかけるような表示
のことをいいます。
簡単にいうと、実際は大してよい商品じゃないのに、「これはとっても良いものだ!」というように、商品・サービスの「質」を偽ることをいいます。
(2)具体例
優良誤認表示の具体例としては、
- まったくダウンロードされていないのに、「100万ダウンロード突破!」と記載
- 「コンプガチャ」といって、イケてるアイテムが当たる率がほとんどないのに、「〇〇%の確立で当たる!」と記載
- ソフトウェアの広告などにおいて認可がないのに「○○省認可」などと表示すること
- 古いタイプのコンピュータウィルスにしか対応していないのに「最新のウィルスにも対応」と表示すること
などがあります。
4 有利誤認表示

(1)有利誤認表示とは
「有利誤認表示」とは、商品やサービスの値段やその他の取引条件を著しく有利にみせかける表示のことをいいます。
簡単に言うと、消費者に「これはとってもお得だ!」と思わせておきながら、ユーザーからみて、実際にはまったくお得ではない場合です。
例えば、「閉店セールで今だけ100円!」と言いながら、何年間も閉店セールをしているケースや昨今話題となっているアディーレによる「今だけ無料!」広告などです。
※なお、アディーレの「今だけ無料!」広告の景表法上の問題を詳しく知りたい方は、「アディーレ業務停止の理由とは?景表法3つのポイントを弁護士が解説」をご覧ください。
取引条件には、値段だけでなく、数量やアフターサービス、保証期間、支払い条件などが含まれます。
そして、有利誤認はさらに2つの類型に分かれています。
- 自社商品の値段それ自体を安く見せるような表示
- 他社商品との比較して、自社商品の方を安く見せる(比較広告)ような表示
前者が、これまで説明してきたもので、有利誤認の典型例です。たとえば、アディーレ法律事務所がしたように、「今だけ着手金は無料!」といいつつ、実際は、数年間にわたり無料キャンペーンを行っていたケースなです。
後者は、比較広告といって、例えば、「macはクソです!windowsの方がはるかに安くて・はるかにいい製品です!」のような広告をいいます。
(2)具体例
有利誤認表示の具体例としては、アディーレの「今だけ無料広告」のほか、以下のようなものがあります。
- 「有料課金アイテムを今だけ無料プレゼント!」と言ってアプリのダウンロードをさせつつ、実際は、無料じゃなく、有料の場合
- ソフトウェアやアプリの販売において、「新バージョン 特別価格5,000円」と表示されていたが、これが適用されるのは旧バージョンのソフトを持っている人に限定される場合
- ショッピングサイトなどにおいて、「セール期間(2週間)中につき、通常価格10,000円のところ6,000円で販売!」と表示していたが、10,000円で表示していたのは最初の一週間のみで、その他の期間は6,000円で販売していた場合
5 内閣総理大臣が指定する表示

(1)内閣総理大臣が指定する表示とは
景表法では、上の2つの類型以外にも、消費者が誤認してしまう可能性の高いケースを特に指定して禁止しています。これを「内閣総理大臣が指定する表示」といいます。
これは、優良誤認表示や有利誤認表示だけでは、複雑な社会の中で消費者の選択を邪魔するような表示に十分に対応することができない、と考えられているためです。
景表法上、個別の不当表示を指定する権限は内閣総理大臣が持っており、現在6つのケースが不当な表示として定められています。
(2)具体例
現在定められているのは、以下の6つのケースです。
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- おとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
6 景表法のポイント

ここまで読むと、「こんなにガチガチにルールで縛られていたら、消費者に“刺さる”広告なんて打てないんじゃないか?」「さすが役人!ビジネスのことなんて何も分かっていないな!」と思われた方もいるかもしれません。
実は、景表法もその点には配慮していて、ビジネスに完全にブレーキをかけるようなことまではしていません。
内容を盛りすぎる「優良誤認表示」であろうと、価格などの取引条件を盛りすぎる「有利誤認表示」だろうと、不当表示のルールのポイントは、「著しく」有利な表示のみを禁止している点にあります。
反対に、「単なる」有利な表示については、ビジネスとして当然にOKとされているのです。
これは、ビジネスの世界においては、消費者の購買意欲をそそるようなセールストークが行われるのは当たり前であって、消費者の側も、通常はそれを分かった上で商品を買うのであって、特段、消費者の利益を害することもないと考えられているからです。
簡単にいえば、多少盛ることはOKですが、ウソやオーバーな表示は、消費者による「安くてよいものを買いたい」という判断を誤らせてしまうおそれが高いことから、「著しく」有利な表示に限定して、これを禁止することにしたのです。
※具体の表示が有利誤認になるかどうかは、消費者庁が出している各種「景表法ガイドライン」を参照してください。
7 ペナルティ~課徴金・刑事罰~

では、景表法に違反した場合、業者にはどのようなペナルティが課されるのでしょうか?
景表法のルールを管轄・運営しているのは、消費者庁というお役所ですが、彼らが自ら違法なことをしている業者をリサーチして処罰する、ということは通常はありません。
普通は、ネット(web)の広告を見た一般消費者からのタレこみや通報をきっかけに、消費者庁が重い腰を上げ、景表法違反のリサーチ(調査)を開始します。
パズドラの件でも、ユーザーらが消費者庁への通報を多数行ったことがきっかけで実際にお役所が動く事態になりました。
そして、調査の結果違反行為が認められた事業者には、
①まず、言い訳をするチャンス(=弁明の機会)が与えられます。
ここでうまく言い訳をして、それが認められれば、無罪放免となります。
②反対に、言い訳をしてみたものの結局、景表法違反と認定されてしまった場合、
「措置命令」(問題とされる表示の撤回、再発の防止を命じる行政処分)という処分を受けることになります。
③不合理にもお役所とガチガチに争って、この措置命令に従わない場合には、事業者の代表者等に対し、
- 最大2年の懲役
- 最大300万円の罰金
のどちらか、または両方が科せられる
というリスクがあります。
とはいえ、措置命令には限界があります。
というのも、措置命令は、
- 業者が不当な表示によって得た利益返還させることはできない
- 罰金の上限が300万円にすぎない
ことから、「懲役をくらわない程度に過激な広告をバンバン打って、罰金の上限の300万以上の儲けを出せば痛くもかゆくもないじゃないか!」という打算的な行動に出る事業者も多いため、ペナルティとして有効に機能しない面があるからです。
そこで、このような悪知恵を働かせる事業者に対しては、「課徴金」というとても重いペナルティが用意されています。
「課徴金」とは、裁判所ではなく行政当局が、景表法に違反してお金を稼いだ法人・個人から、その利益を没収する行政処分のことです。
罰金などの刑事罰とは異なり行政当局が主体となっているため、いちいち裁判所の手続きを経ることなくスピーディーにお金を取り上げることができます。
一方、裁判所を通さないため、事業者側の言い分はきちんと聞いてもらえず、行政当局の都合のいいように運用される可能性があります。
加えて、行政上の処分(刑事罰とは違い、処分が下されても前科にはならない)といっても、世間では、刑罰と同じように考えられているため、企業のレピュテーションリスクは計り知れず、大幅なイメージダウンによって売り上げも激減してしまう可能性があります。
ちなみに、企業の違法行為が認められた場合の課徴金の金額は、違反商品やサービスの売上額の3%(過去5年までさかのぼる)とされています。
ただ、違反企業が被害者に自主返金した場合には課徴金処分が減免され、また違法行為を自主申告した場合には、課徴金を減額するという、刑事事件でいうところの自首のような仕組みも用意されています(これを「リーニエンシー」といいます。)。恩恵を与えることで、企業からの自首を促し、被害者が出るのを未然に防ごうという趣旨です。
8 モデル別の景表法の問題点

近年、アプリやwebサービス上の取引において、新しいサービスモデルがたくさん登場しています。
以下では、各モデルごとに、景表法上どのような問題点や注意点があるのかを解説していきます。
(1)フリーミアムモデル
「フリーミアム」とは、Free(フリー:無料)とPremium(プレミアム:上質)を組み合わせた造語で、基本的なサービスを無料で提供し、追加のサービスを有料で提供して利益を得るモデルのことをいいます。
例えば、音楽の配信アプリにおいて、基本利用料金は無料ですが、月額料金を払えば自分が聴きたいアルバムを指定して聴くことができたり、オフラインで聴くことができたりする場合がこれにあたります。
昨今、世には何十万個ものアプリが販売されているため、ユーザーは目が肥えており、使ってみて「すごい面白い」と感じたサービスでない限り、課金してくれません。
ましてやいきなり有料のアプリなんて、ダウンロードすらしません。
反対に、「楽しい・面白い」と感じたアプリであれば、いくらでも課金してくれます。
フリーミアムモデルはこういったユーザー特性や心理を踏まえたうえで、まずは無料の基本サービスを提供して大量の顧客を確保しようというモデルです。
フリーミアムモデルでよく問題となるのは、サービスが「無料」であることを大げさに強調し、本当はアイテム課金などがあるのに、あたかも全てが無料であるかのようなた広告(表示)をするケースです。
このような広告(表示)によって、例えば、実際には追加サービスを利用するには別途利用料金がかかるのに、追加サービスも含めたすべてのサービスがが無料で利用できるとの誤解をユーザーに与えてしまった場合には、景表法上の「不当表示」として違法になりえます。
これを避けるためには、事業者は、無料で利用できるサービスの具体的な内容や範囲を正確かつ分かりやすく表示する必要があります。
(2)二重価格表示
「二重価格表示」とは、商品やサービスについて実際の販売価格とは別に、比較対象として、より高い参考価格を一緒に表示することです。
この参考価格のことを「比較対象価格」といいます。
二重価格表示は、ユーザーの購買意欲の向上にとても効果的ですが、一方、その表示内容が不当である場合にはユーザーに与える損害が大きくなってしまいます。
不当な二重価格表示は、景表法上の「有利誤認表示」として問題になります。
そして、具体的には次のような場合に二重価格表示にあたる可能性があります。
- 同一ではない商品の価格を比較対象価格に用いて表示を行う場合
- 比較対象価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合
例えば、ソフトウェアの販売において、競合店の平均価格から値引きすると表示をしながら、その平均価格を実際よりも高い価格に設定し、そこから値引きを行っていたような場合です。よく見かけるのは、市場価格が実際には5万円なのですが、「通常価格10万円のところを・・・・うちなら50パーセント割引して、5万円!」と偽りのお得感を演出して売り出すようなケースです。
これを避けるためには、ユーザーに誤解を与えないよう、消費者庁が発表している「二重価格表示に関するガイドライン」を参考にしながら、適正な価格表示をすることが重要です。
(3)打消し表示(後出し表示)
「打消し表示(後出し表示)」とは、はじめに価格の安さを強調しておきながら、実はその価格で購入するには別途「条件」があるような販売形態のことをいいます。
条件は、ユーザーが通常は予想できないこと(例外条件、制約条件、追加費用の必要性など)であって、その商品やサービスを選ぶ上でとても重要な要素になるものです。
具体的には、例えば通販などでパソコンを購入しようとした際、とても安い価格に飛びつくとその下に小さく「※ただし、別途回線の契約が必要です」などと書いてあるような場合をいいます。
実際に買い物などをする際に注意書きや注釈をきちんと見ないユーザーも多く、ユーザー側の認識とズレが生じてしまうことも少なくありません。
この場合は景表法上の「優良誤認」や「有利誤認」にあたる可能性があります。
これを避けるためにも、事業者はまず「打消し表示」をしなくてもすむような表現をするのが大前提として、やむを得ず打消し表示をする場合には、「打消し表示に関するガイドライン」を参考にしながら、ユーザーの目にとまりやすく分かりやすい表示をすることが必要です。
(4)ネイティブ広告
「ネイティブ広告」とは、簡単に言うと、広告っぽさのない自然な広告のことをいいます。
一般的な広告は一目見ただけですぐに広告だと分かりますが、ネイティブ広告の場合は文章や画像、動画などの中に表示されるため、パっと見は広告だと気づきません。
例えば、FacebookやTwitterなどで、通常の投稿の中に「PR」と表示された企業の広告があるのを見たことはないでしょうか?
この広告の見た目は他の一般投稿と変わらず、うっかりして間違ってクリックしてしまうことも少なくないですよね。
このネイティブ広告は、コンテンツとの一体感があることからユーザーに受け入れられやすいというメリットもありますが、一方、ユーザーが「騙された!」と感じてしまう可能性も高いものとなっています。
ネイティブ広告の問題点は、広告について、まるで広告でないかのようにユーザーに誤解させてしまう点にありますが、商品やサービスの内容・取引条件について不当な表示がなされているわけではないため、直接的に景表法で規制されるわけではありません。
この問題について、規制のあり方やその内容についてはまだ議論が錯綜しており、現段階では法規制ではなく自主規制にとどまっています。
いずれにせよ、ネイティブ広告をする場合には、広告主体の表記や広告であることの表記をきちんとし、ユーザーの誤解を招かないようにすることが大切です。
9 まとめ
これまで解説してきたことをまとめると、以下の点になります。
- 「景表法」では、大げさな表現やウソによってユーザーが損をすることが無いように「不当な表示」を禁止している。
- 不当表示規制は3つあり、①優良誤認、②有利誤認、③内閣総理大臣が指定する表示
- 不当表示規制では、「著しく」有利な表示のみを規制しており、「単なる」有利な表示については禁止されていない
- 近年注目されている①フリーミアムモデル、②二重価格表示、③打消し表示と景表法との関係についても注意
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。