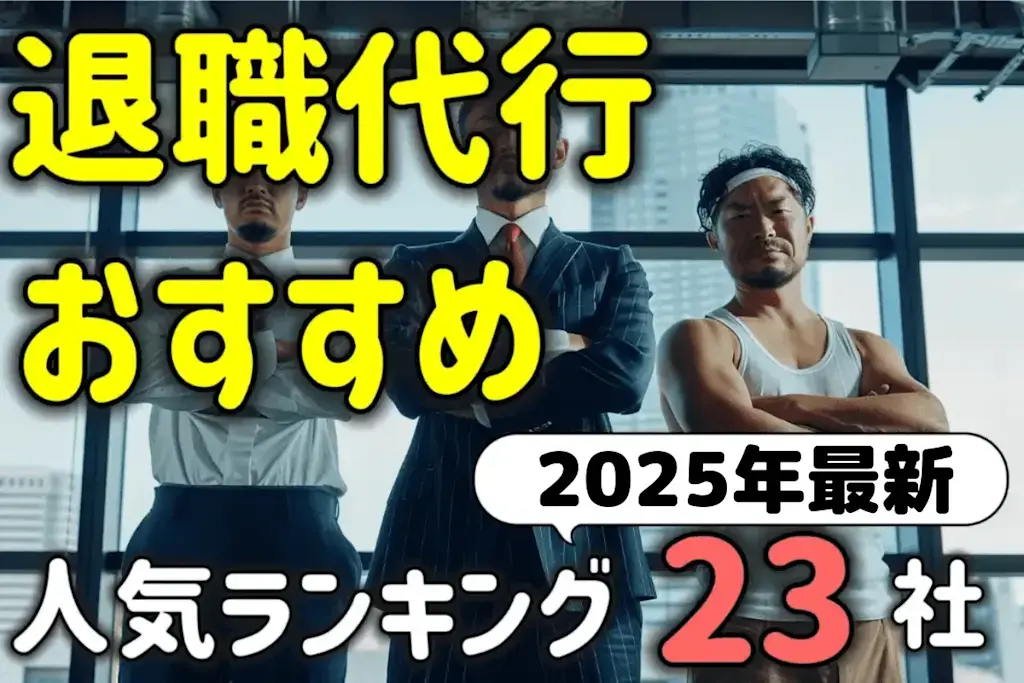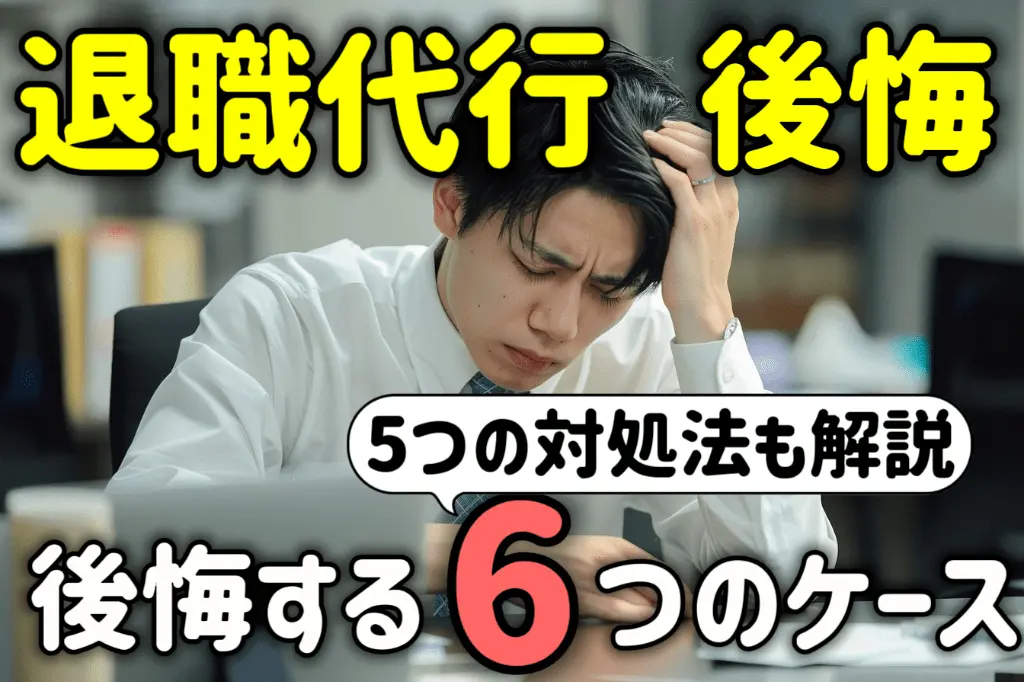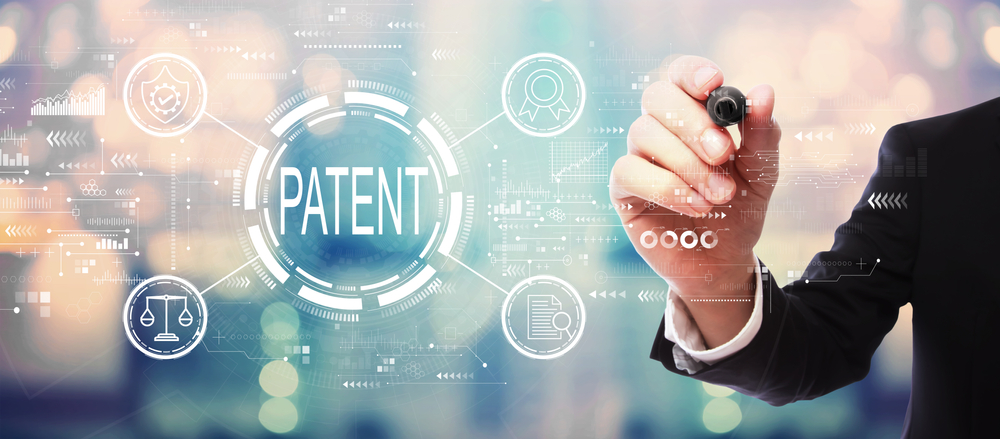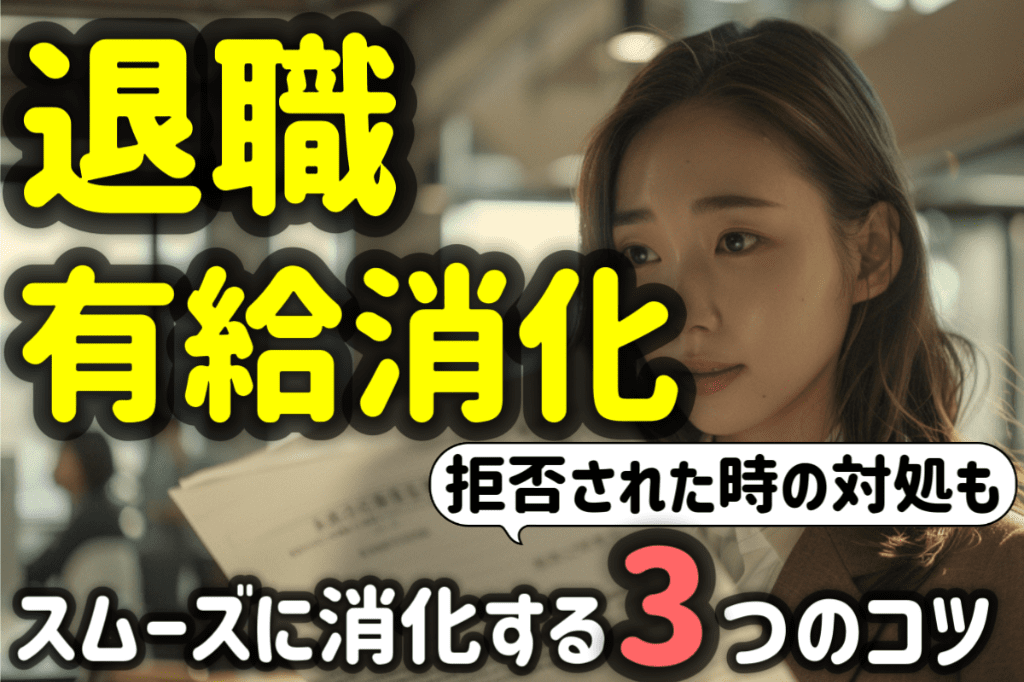景表法に違反した事例と罰則とは?3つのポイントをIT弁護士が解説

はじめに
広告の内容やその出し方などは、「景表法」という法律により規制されていますが、仮に自社が打った広告が景表法に違反する場合、どのような罰則やペナルティが科されるのかよくわからないという方が多いのではないでしょうか。
軽い気持ちで広告を出してしまうと、場合によってはペナルティを科され、事業に重大な影響を与えかねません。
そこで今回は、広告が景表法に違反した場合に科せられるペナルティの内容、また、景表法に違反しないためのポイントなどについて、弁護士が詳しく説明していきます。
1 景表法とは

(1)定義
「景表法」とは、企業が商品やサービスについて広告をする際のルールを定めることにより、ユーザーを守ることを目的とした法律です。
私たちは商品を買う時に、必ずといっていいほど、商品に表示されている商品の内容や価格を見ます。仮に、商品に表示されている内容や価格がウソだったり、オーバーな内容になっていたりしたらどうでしょうか。ユーザーは、その商品の本当の価値を正しく判断することができなくなってしまいます。
このようなことがないように、広告について企業が守るべきルールを定めたものが「景表法」です。
では、景表法は、具体的にどのようなことを対象に規制して、ユーザーを守っているのでしょうか。次の項目で確認しましょう。
(2)分類
景表法による規制は、以下の2つに整理することができます。
- 表示規制
- 景品規制
各規制について、簡単に見ていきましょう。
①表示規制
「表示規制」は、商品やサービスの内容、価格などについて行う広告の「表示」を規制対象としています。たとえば、スーパーで買ったお肉に表示されている「〇〇産」「〇〇円」などの表示がこれにあたります。
②景品規制
「景品規制」は、商品やサービスの提供に付随して与えられる「経済的な利益」を規制対象としています。たとえば、電化製品を買った際に、特典として付いてきた賞品や商品券などがこれにあたります。
このように、景表法は規制対象を2つのパターンに分けています。では、仮に自社の広告が景表法に違反した場合、どのようなペナルティを科されることになるのでしょうか。
次の項目で、詳しく見ていきましょう。
※なお、景表法について詳しく知りたい方は、「盛りすぎ広告に注意!5分でわかる景表法に違反しないためのポイント」をご覧ください。
2 景表法に違反した場合にどうなるのか?(罰則)

景表法に違反した場合に科されるペナルティは、大きく分けて以下の5種類あります。
景表法に違反した事業者には、一口に「罰則」といっても、最大5つのペナルティがあるということが大事です。
- 景表法のルールを管轄する消費者庁が行う「行政処分」
- 刑事罰
- 警告
- 損害賠償請求
- 差止請求
それぞれのペナルティについて、以下で詳しく見てみましょう。
(1)景表法のルールを管轄する消費者庁が行う「行政処分」
消費者庁による「行政処分」には、さらに次の2種類があります。
- 措置命令
- 課徴金の納付命令
以下で、順番に見ていきましょう。
①措置命令
商品やサービスに表示されている内容が景表法に違反するのではないか、という通報などにより、消費者庁は、必要があれば、事業者から事情聴取などを行います。事業者は、そこで自分の言い分を主張することになり、その言い分が認められれば、一件落着ということになります。
ですが、言い分が認められず、景表法に違反していると判断された場合、消費者庁は、事業者に対し、違反している表示を正しく表示し直すこと、今後同じ過ちを犯さないための策を講ずることを命じることになります。これを「措置命令」といいます。
②課徴金の納付命令
「措置命令」は、事業者に対して、一定の措置を講ずるように命じるものでした。
それでは、措置命令によって命じられた措置をとりさえすれば、それまでに、違法広告によって荒稼ぎしたお金を事業者は返さなくていいのでしょうか。
この点、景表法には、違反者に対し、措置命令とは別に「課徴金の納付」を命じなければならないというルールがあります。ペナルティが措置命令だけだとすると、「消費者庁から言われたことにいったん従って、ほとぼりがさめたら、またウソの広告を打って、荒稼ぎしよう。」なんて考える人もいるかもしれません。
このようなことを防止するために、景表法に違反して稼いだお金を取り上げようというのが「課徴金の納付命令」です。
この場合、事業者には、事前に弁明の機会が与えられ、事業者は「自分が出した広告の表示が景表法に違反しているとは知らなかった」ということを言い分として主張していくことになります。この言い分が認められれば、課徴金の納付命令を受けることはありません。
このように、景表法に違反した事業者に対しては、措置命令とは別に課徴金の納付命令が命じられることになります。
では、課徴金の金額は具体的にどのように決められるのでしょうか。この点、課徴金の金額は以下のように定められています。
- 稼いだ利益の3%に相当する金額
- 過去5年まで遡る
かつ
たとえば、景表法に違反する表示によって稼いだお金が直近1年で1000万円であったとしましょう。これだけだと、1000万円の3%に相当する30万円が課徴金の金額になりますが、その表示を10年間使い続けて、毎年1000万円を稼いでいた場合、過去5年まで遡ることになりますので、30万円×5年=150万円が課徴金の金額になるわけです。
もっとも、次の場合には、課徴金は減額・免除(リーニエンシー制度)されます。
- 調査が入る前に、景表法に違反していることを申告する
- 稼いだ利益を、所定の手続にしたがってユーザーに返金する
or
以上のように、景表法違反に対するペナルティとしての行政処分は、表示行為はもちろんのこと、経済的にも制裁を課せられることになるため、事業者にとっては、大変大きい痛手となります。
(2)刑事罰
消費者庁から措置命令を受けた場合に、その表示を直さなかったり、無視してその表示を使い続けたりすると、
- 最大2年の懲役
- 最大300万円の罰金
のどちらか、または両方を科せられる可能性があります。
(3)警告
事業者が正当な理由がないにもかかわらず、必要な措置をとらないことにより、景表法に違反する疑いがあると認めるときは、消費者庁は必要な措置をとるよう勧告をすることができます。
たとえば、携帯の料金システムの表示がわかりにくく、「有利誤認表示」にあたるおそれがあるとして、警告をする場合がこれにあたります。「有利誤認表示」については、後で詳しく説明します。
警告自体は、「行政指導」にあたりますので、従わなくてもそのことを理由に不利益な扱いを受けたりすることはありません。
ですが、警告に従わないと、消費者庁はその旨を公表することができることになっていますので、事業者のイメージダウンにつながる可能性があります。
(4)損害賠償請求
景表法にわざと違反したり、うっかり違反してしまったことによって、第三者に損害を与えてしまった場合、不法行為にあたる可能性があります。不法行為にあたる場合、事業者は損害を与えた第三者に対し、損害を賠償しなければなりません。
(5)差止請求
「消費者契約法」には、事業者が景表法に違反する行為をしていたり、また、違反するおそれがある場合、適格消費者団体は、その行為の停止や予防に必要な措置をとるように請求することができる、というルールがあります。
「適格消費者団体」とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体のことで、消費者契約法による差止請求はこの団体が行うことになります。
以上が、景表法に違反した場合に受ける可能性のあるペナルティです。
ここで重要なのは、ペナルティを受けたという事実は、一般消費者によりマイナスのレッテルを貼られることになり、その結果、信用を大きく失い、売り上げを大きく下げることにもなりかねないということです。
いったん失った信用を回復するのは、非常に難しいことですので、ペナルティの内容をしっかり理解して、景表法に違反しないように事業を展開していくことが大切です。
以下の項目から、景表法に違反しないためのポイントについて、過去の違反事例を参考にしながら見ていきたいと思います。
3 景表法に違反しないためのポイント~違反事例を参考に~

ペナルティを受けないためにも、景表法に違反しないためのポイントをしっかりと理解しておくことは大事です。
まずは前提として、景表法で禁じられている「表示」について見ていきたいと思います。
景表法で禁じられている表示は、以下の3つです。
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示
- その他誤認されやすい表示
以下で、簡単に見ていきましょう。
(1)優良誤認表示
「優良誤認表示」とは、商品やサービスの品質や内容などについて、
- 実際の品質や内容などよりも、著しく優良である
- 商品やサービスが競合している事業者よりも著しく優良である
or
と一般消費者に誤認させる表示のことをいいます。
「著しく優良である」かどうかは、オーバーに表示されている商品を見た一般消費者がその商品を買おうと考えるかどうかによって決まってきます。
たとえば、実際はタイ産のお米であるにもかかわらず「国産米」と表示する場合や「A社よりも持続力2倍!」と表示する場合がこれにあたります。
(2)有利誤認表示
「有利誤認表示」とは、商品やサービスの価格や取引条件などについて、
- 実際の価格などよりも、著しく有利である
- 商品やサービスが競合している事業者よりも著しく有利である
or
と一般消費者に誤認させる表示のことをいいます。
「著しく有利である」かどうかは、優良誤認表示と同様に、オーバーに表示されている商品を見た一般消費者がその商品を買おうと考えるかどうかによって決まります。
たとえば、実際は誰に対しても常時売っている商品を「先着〇〇名にかぎり」と表示する場合や「A社よりも〇〇円お得!」と表示する場合がこれにあたります。
(3)その他誤認されやすい表示
その他に、商品やサービスの提供に関して、一般消費者に誤認されるおそれがあるものとしては、内閣総理大臣が特に指定して禁止している表示があります。
具体的には、以下の6つの表示が内閣総理大臣により指定・禁止されています。
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- おとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
景表法により禁じられている表示は、以上のとおりです。
もっとも、「何となくイメージはつかめたけど、結局のところ、景表法に違反しないためにはどこに注意すればいいの?」という方もいらっしゃると思います。
次の項目で、過去の事例をまじえながら、景表法に違反しないためのポイントについて見ていきましょう。
4 優良誤認表示の事例

まずは、「優良誤認表示」と判断された過去の事例から見ていきましょう。
(1)事例
-
【事例①】
ファミリーマートが商品として提供していた「カリーチキン南蛮(おにぎり)」に使用していた鶏肉につき「国産鶏肉使用」と表示して、実際には国産鶏肉を使用していないのにあたかも使用しているかのように見せかけた事例
この事例では、実際に使用していた鶏肉は「ブラジル産」であって国産鶏肉ではないにもかかわらず、「国産鶏肉使用」とウソの表示をしています。
これは、鶏肉の品質につき、実際の品質(ブラジル産)よりも著しく品質の良い「日本産」であるかのように虚偽の表示をしているため、「著しく優良であると誤認させる」表示にあたり、景表法に違反します。
-
【事例②】
農協が販売していた特別栽培米の米袋に「化学肥料栽培期間中不使用」と表示して、実際には、化学肥料を使用していたのに、あたかも使用していないように見せかけた事例
この事例では、実際には化学肥料を使用していたにもかかわらず、「化学肥料栽培期間中不使用」とウソの表示をしています。
これは、化学肥料が使用されている米よりも著しく品質の良い米であるかのように虚偽の表示をしているため、「著しく優良であると誤認させる」表示にあたります。
このケースで、消費者庁は農協に対し、「措置命令」を発令しました。
-
【事例③】
販売用LED電球につき、「電球60形相当の明るさ」と表示して、実際には、使い方次第では、電球60ワット形と同等の明るさが出ないのに、あたかも同等の明るさが出るように見せかけた事例
使い方次第では電球60ワット形と同等の明るさが出ないにもかかわらず、使い方に関係なく電球60ワット形と同等の明るさが出るような表示をしているため、「著しく優良であると誤認させる」表示にあたります。
このケースも事例②と同様、消費者庁は事業者に対し、「措置命令」を発令しました。
その他にも、表示が優良誤認表示であると判断された事例に、以下のようなものがあります。
-
【事例④】
分譲マンションのパンフレットに、マンション全ての開口部の角部分にひび割れを防止するための補強筋を施しているかのような表示をして、実際には、その一部にしか補強筋を施していなかった事例
-
【事例⑤】
鉄道車両内に掲示されたモバイルデータ通信サービスの広告に、最大通信速度が某都市における人口のカバー率99%になるように開設する計画があるかのように表示して、実際には、そのような計画がなかった事例
-
【事例⑥】
移動体通信サービスを案内するカタログに、対応機種を使用した場合に、ほとんどの地域において、最大通信速度が75Mbpsとなるサービスを受けられるかのように表示して、実際は、そのサービスを受けられる地域が極めて限られていた事例
-
【事例⑦】
携帯電話用ソーラー式充電器のパッケージに、太陽光に当てることにより、最速約6~10時間で充電が完了するかのように表示して、実際は、充電を完了するには表示されている時間を大きく上回る時間が必要であった事例
-
【事例⑧】
粉末タイプのお茶を紹介するパンフレットに、国民生活センターが実施した試験により、ポリフェノール含有量日本一のお茶であるという結果が出たかのように表示して、実際は、国民生活センターが試験をした事実がなかった事例
(2)優良誤認表示に違反しないためのポイント
このように過去の事例を見てくると、優良誤認表示に違反しないためには、以下の点に注意することがポイントになってきます。
- 表示が虚偽(ウソ)でないこと
- 表示にきちんとした根拠があること
ここでいう「根拠」とは、テレビや新聞などで取り上げられていたり、他者から聞き及んだというだけでは足りず、適切な機関などによる適正な試験や検証などに基づいた客観性のあるものでなければならないということに注意が必要です。
5 有利誤認表示

次に、「有利誤認表示」と判断された過去の事例を見ていきましょう。
(1)事例
-
【事例①】
ウェブサイトにおけるモバイルデータ通信サービスに係る広告に、パケット通信などに関し、「「●●年間パスポート」なら、月額3,591円」と表示して、実際は、月額3,591円は、インターネット接続サービスを併用した場合の金額で、インターネット接続サービスを併用しない場合の金額は、3,591円より上回るものであった事例
この事例では、実際に表示されている金額はインターネット接続サービスを併用した場合の金額であるにもかかわらず、あたかもインターネット接続を併用しない場合の金額であるように表示をしています。
これは、サービスの価格について、実際の価格(インターネット接続サービスを併用しない場合の金額)よりも「著しく有利であると誤認させる」表示であるといえ、景表法に違反します。
-
【事例②】
振袖に袋帯や長襦袢等を組み合わせたセット商品のレンタルを案内するカタログに、「レンタルセット価格」として表示された金額を支払えば、写真に掲載されているセット商品と同等の商品をレンタルできるかのように表示して、実際は、セット商品をレンタルするためには、カタログに表示されている金額とは別に費用が必要であった事例
この事例では、実際には、セット商品をレンタルするためにはカタログに表示されている金額とは別に費用がかかるにもかかわらず、あたかもセット商品をレンタルするためには「レンタルセット価格」として表示された金額で足りるような表示をしています。
これは、セット商品のレンタルについて、実際の価格(表示されている金額と別の費用を合わせた金額)よりも「著しく有利であると誤認させる」表示にあたり、景表法に違反します。
-
【事例③】
ウェブサイトにおける歯列矯正に係る料金の表示に、9歳以下の患者が、歯列矯正の施術を受ける場合の料金はウェブサイトに記載されている金額で足りるかのように表示して、実際は、9歳以下の患者が歯列矯正の施術を受ける場合の料金はウェブサイトに記載されている金額とは別に器具に係る費用が必要であった事例
この事例では、実際には、9歳以下の患者が歯列矯正の施術を受けるためにはウェブサイトに記載されている金額とは別に器具に係る費用がかかるにもかかわらず、あたかもウェブサイトに記載されている金額で足りるような表示をしています。
これは、9歳以下の患者に対する歯列矯正の施術料金について、実際の価格(ウェブサイトに記載されている金額と器具の費用を合わせた金額)よりも「著しく有利であると誤認させる」表示にあたり、景表法に違反します。
その他にも、表示が有利誤認表示であると判断された事例に、以下のようなものがあります。
-
【事例④】
ウェブサイトにおける家庭教師派遣に係る費用の表示に、指導料金として掲載されている金額を支払うことで、役務の提供を受けることができるかのように表示して、実際は、指導料金とは別に入会金が必要であった事例
-
【事例⑤】
テレビCMで「毎月29日は肉の日!!」「牛肉が半額!当日表示価格より」と打たれた広告が、毎月29日は、牛肉が当日の表示価格より半額になるかのような表示であったが、実際は、対象となる商品についての表示価格が通常時より引き上げられた金額であり、当日の表示価格の半額ではなかった事例
(2)有利誤認表示に違反しないためのポイント
このように過去の事例を見てくると、有利誤認表示に違反しないためのポイントも、基本的には「優良誤認表示」の場合と同じであるということが言えます。
もっとも、有利誤認表示の場合には、さらにもう1つのポイントがあることに注意が必要です。
- 表示が虚偽(ウソ)でないこと
- 表示にきちんとした根拠があること
- ユーザーが、支払うべき金額やその内訳などを明確に知ることができること
事業者は、少しでもユーザーに誤認されるおそれがあると疑われるような表示をする場合には、慎重に検討することが必要です。
6 その他誤認されやすい表示

最後に、「その他誤認されやすい表示」にあたると判断された事例について、見ていきましょう。
(1)事例
-
【事例①】
商品(ハチミツ)を封するためのシールに「品質保証 いわて・もりおか〇〇養蜂場」という表示をして、実際には、日本以外の国で採蜜されたはちみつが混入していた事例
この商品を見た一般消費者の大半は、原産国=日本と考えると思います。
ですが、実際は、日本以外の国で採蜜されたはちみつが混入していたわけですから、「商品の原産地に関する不当な表示」にあたり、景表法に違反します。
-
【事例②】
1.阪神ホテルシステムズが経営するレストランが、メニューに「車エビのチリソース煮」と表示して、実際は車エビより安い「ブラックタイガー」を使用していた
2.阪神ホテルシステムズを含む3社が「三笠では『大和肉鳥鍋』や『つみれ鍋』としてお召し上がり頂いています。」と広告サイトに表示して、実際には、三笠で『大和地鶏』は限られた期間しか使用されていないにもかかわらず、そのことを表示しなかった
この事例は、1について「優良誤認表示」、2については「その他誤認されやすい表示(おとり広告に関する表示)」にあたるとされました。
1は、「車エビのチリソース煮」と表示しながら、実際は、車エビより安い「ブラックタイガー」を使用していたため、「実際の品質(ブラックタイガー)よりも優良であると誤認するおそれのある表示」にあたります。
2は、「おとり広告に関する表示」にあたるとされています。
ここでいう「おとり広告」とは、
- 提供する準備が間に合っていないなどの事情により、取引に応じることができないのに、商品やサービスの表示をすること
- そもそも商品やその提供期間などに限りがあるのに、その旨を表示していないこと
により、一般消費者に誤認させるおそれのある広告のことをいいます。
たとえば、商品の在庫が切れており、次に入荷できる見通しが立っていないにもかかわらず商品の広告を出している場合が前者にあたり、商品の在庫が残り10個しかないにもかかわらず、そのことを表示せずに商品の広告を出している場合が後者にあたります。
事例に戻りますが、三笠において、『大和地鶏』は限られた期間しか使用されていないにもかかわらず、そのことを表示しなかったわけですから、一般消費者からすれば、大和地鶏が使用されているものと思ってしまいます。以上から、「おとり広告に関する表示」にあたるとされたわけです。
-
【事例③】
ウェブサイトにおいて、本体価格等と併せて中古自動車の写真を掲載して、実際は、掲載前に売買契約が成立していた事例
掲載された中古自動車については、掲載前に売買契約が成立しているわけですから、取引に応じることは不可能です。
このケースも事例②と同様に「おとり広告に関する表示」にあたるとされました。
(2)「その他誤認されやすい表示」に違反しないためのポイント
この場合のポイントも、基本的には「優良誤認表示」や「有利誤認表示」の場合と同じであるということがいえます。これに加え、一般消費者が適切に判断するために必要な情報を表示することもポイントであるといえます。
- 表示が虚偽(ウソ)でないこと
- 表示にきちんとした根拠があること
- 一般消費者が適切に判断するために必要な情報を表示すること
※なお、「表示」について詳しく知りたい方は、消費者庁が出している「表示規制の概要」をご覧ください。
7 小括

今回は、景表法が規制する「表示」について、景表法違反に対して科されるペナルティにも触れながら解説してきました。
表示に関するルールは、非常に細かく決められていますので、軽い気持ちで広告を出してしまうと、場合によっては、ペナルティの対象にもなり、企業の信用を落としてしまうことにもなりかねません。
広告を打つ際には、その表示を規制する景表法について十分に理解していることが前提になってきます。また、万一、景表法に違反すると判断された場合も、その後の手続の流れをしっかりと理解したうえで、冷静に対応するようにしましょう。
8 まとめ
これまで解説してきたことをまとめると、以下のようになります。
- 「景表法」は、ウソの表示やオーバーな表示をすることを禁止して、ユーザーの利益を守ることを目的とした法律である
- 景表法による規制は、大きく分けて、「表示規制」と「景品規制」の2つがある
- 景表法に違反した場合に科される主なペナルティとして、「行政処分」と「刑事罰」がある。
- 「行政処分」には、さらに「措置命令」と「課徴金の納付命令」がある。
- 「行政処分」や「刑事罰」のほかにも、「警告」「損害賠償請求」「差止請求」といったペナルティがある。
- 不当表示には、「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されやすい表示」の3つがある
- 不当表示に違反しないための主なポイントは、①表示がウソでないこと、②表示にきちんとした根拠があること、③ユーザーにおいて、支払うべき金額やその内訳などを明確に知ることができること、④ユーザーが適切に判断するために必要な情報を表示すること、である
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。