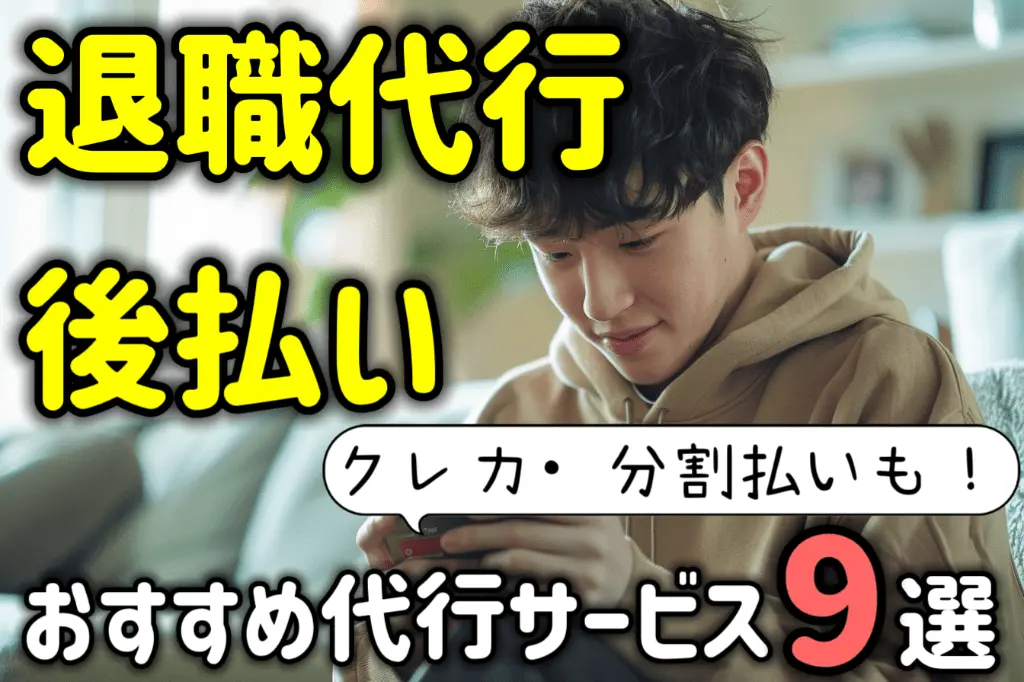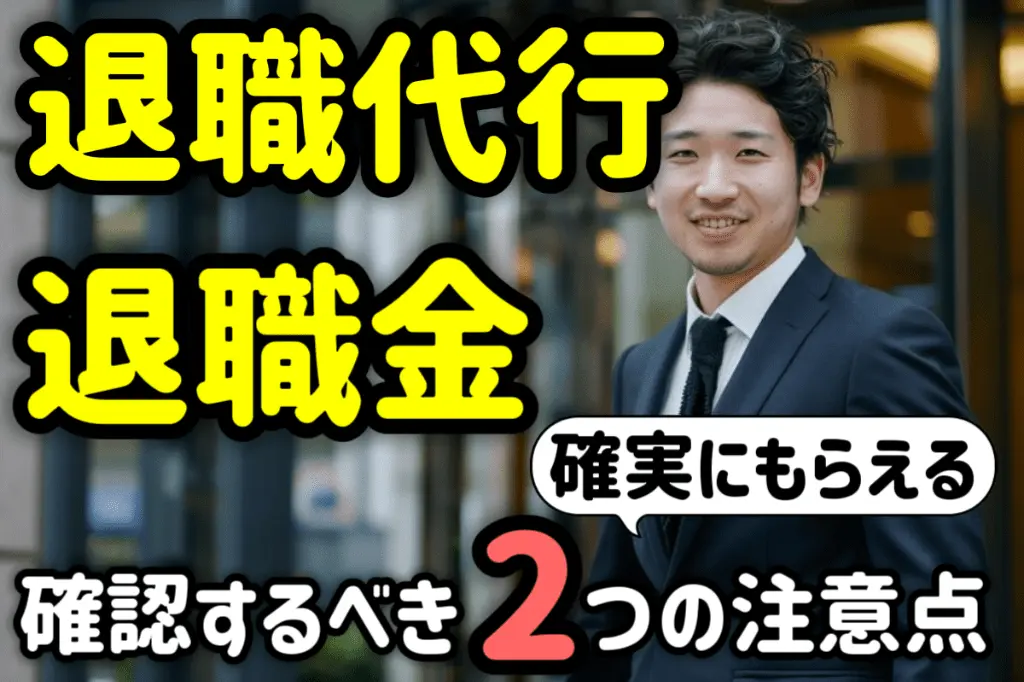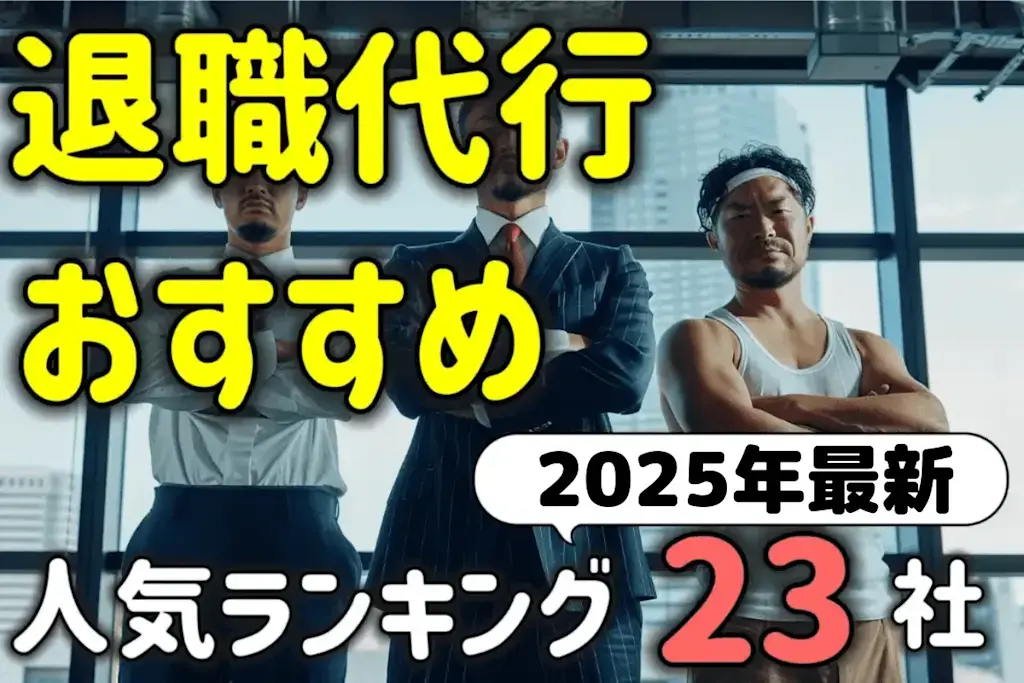内部統制とは?4つの目的を達成するために必要な要素を弁護士が解説

はじめに
「内部統制」という言葉をご存知でしょうか?
会社法や金融商品取引法では、一定の場合に内部統制の整備を義務付けています。
もっとも、その目的や内容を理解していない人は意外に多いのではないでしょうか。
事業を運営していくにあたり、内部統制の整備は極めて重要な意味合いをもっています。
そこで今回は、「内部統制」について、その目的や内容を弁護士がわかりやすく解説します。
1 内部統制とは
「内部統制」とは、企業において、事業活動を適切・適法に遂行するために設けられる仕組みのことをいいます。
事業を運営する過程では、従業員が法令に違反する行為をしたり、不適切な会計処理を行ったりして、不祥事を引き起こすリスクがあります。
事業者にとって、このような不祥事が起きると、さまざまな損失に繋がることになります。
とはいえ、従業員が不祥事を起こさないように常時監督することは現実的ではありません。
そこで、従業員が不祥事を起こす前兆を早期に発見・是正でき、常時従業員を監視しなくても事業活動を適切・適法に遂行できるような仕組みを作ることが必要になります。
これが「内部統制」です。
内部統制の仕組みを作ることにより、さまざまなリスクを管理することも可能になります。
2 内部統制の目的
内部統制の目的は、主に以下の4点を確保することにあります。
- 業務の有効性・効率性
- 財務報告の信頼性
- 法令遵守
- 資産の保全
(1)業務の有効性・効率性
業務の効率が悪いと、余計なコストがかかり、経営状況に悪影響を及ぼす要因になります。
業務の達成度や資源の合理的な利用度を正確に把握・評価し、必要に応じて適切な対応を図ることができるような体制を作ることにより、業務の有効性・効率性が向上し、事業活動の目的を達成できるようになります。
(2)財務報告の信頼性
財務報告は、事業活動を確認するために重要な情報であり、その信頼性を確保することにより、企業に対する社会的な信用を維持・向上することができます。
財務報告に誤りがあると、取引先等の利害関係者に不測の損害を与え、企業に対する信頼を低下させることに繋がります。
そのため、財務報告に誤りが生じることのないよう必要な体制を整備・運用することにより、企業に係る財務報告への信頼性を確保することができます。
(3)法令遵守
企業やその従業員が法令に違反した行動に出てしまうと、批判を受けるだけでなく刑事罰の対象にもなります。
このような事態は、企業の存続を危うくしかねません。
企業やその従業員において、法令遵守を徹底することは、社会的信用の向上、ひいては、業績や株価などの向上にも資することになります。
このように、法令遵守の下で事業活動を遂行していく体制を整備・運用することにより、企業の存続・発展を図ることができます。
(4)資産の保全
企業の資産が不正に取得・使用されていると、企業の資産や社会的信用に悪影響を及ぼします。
また、出資者などから財産の拠出を受けて事業活動を行っている場合、事業者は、これを適切に保全すべき義務を負っています。
そのため、事業者は、自社の資産について、不正な取得や使用、処分などが行われないように体制を整備・運用することが必要です。
3 内部統制の目的を達成するための要素
内部統制の目的を達成するためには、以下の6つの要素を適切に整備・運用することが必要です。
- 統制環境
- リスクの評価・対応
- 統制活動
- 情報と伝達
- モニタリング
- ITへの対応
(1)統制環境
「統制環境」とは、企業がもつ価値基準や組織の人事、職務の制度などを総称する概念です。
企業がもつ価値基準や制度は、従業員など企業内部の者が有する内部統制への考え方に大きく影響を与えるため、他の要素の前提ともなる要素であり、最も重要な要素です。
たとえば、企業がもつ誠実性や倫理観、経営者の意向や姿勢、経営方針などは、統制環境に含まれる事項とされています。
(2)リスクの評価・対応
事業目的を達成する過程では、多くの場合、さまざまな障害が生じます。
そのような障害をクリアしていくためには、その障害をリスクとして識別したうえで、分析・評価することが必要になってきます。
また、リスクを評価するだけでなく、その評価を受けて、適切な対応を選択することも必要です。
(3)統制活動
事業者は、不正行為などが発生しないように、各担当者の権限や職責を明確にし、その範囲において適切に業務を遂行していく体制を整備することが必要です。
この際に重要となるのは、職務を適切に分掌させるということです。
業務が特定の者に専属的に属すると、継続的な対応が困難になるケースがありますが、職務を分掌させることにより、このような弊害を解消することができます。
また、各担当者の権限や職責を明確にすることで、内部統制を可視化することができ、不正などが起きにくくなるという効果を期待することができます。
(4)情報と伝達
職務の遂行にあたり必要な情報は、適切に伝達されなければなりません。
また、伝達されるだけでなく、それが受け手において正確に理解され、その情報を必要とする他の従業員にきちんと共有されることが必要です。
(5)モニタリング
「モニタリング」とは、有効に内部統制が機能しているかどうかを継続的に評価することをいいます。
モニタリングを実施することにより、内部統制の現状を監視・評価でき、必要に応じて、是正することが可能になります。
(6)ITへの対応
事業内容がITに大きく依存している場合などは、ITの利用や統制について適切に対応する必要があります。
ITには、情報処理の有効性や効率性などを高める効果があるため、これを内部統制に活用することで、より効率的な内部統制を構築することが可能になります。
4 まとめ
内部統制を実施することにより、企業価値を高めるだけでなく、社会的信用や企業イメージを向上させることが可能になります。
自社にとって適切な内部統制を構築することが、企業を成長させるためには必要不可欠だといえます。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。