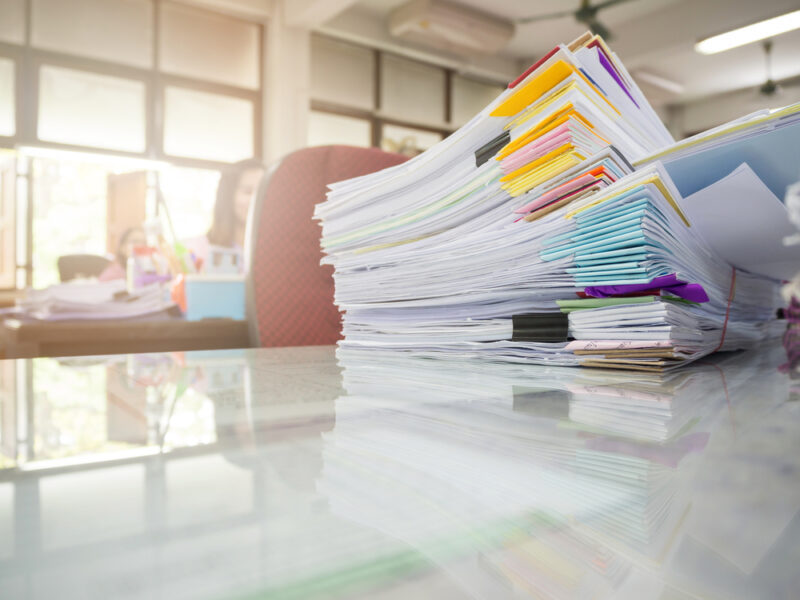定款とは?3つの記載事項と定款変更について弁護士が解説

はじめに
株式会社を設立するためには「定款」を作成することが必要になります。
定款には、記載することが必須とされている事項や、必須ではないものの記載していないと効力が生じない事項などがあります。
会社のルールともいえる定款ですが、そもそも定款を作成する目的はどのような点にあるのでしょうか。
今回は、「定款」について、その全体像をわかりやすく解説します。
1 定款とは|必要な理由

「定款」とは、会社を運営していくうえで必要とされる基本的なルールを定めたものです。
株式会社を設立する場合、以下のとおり、定款の作成が義務付けられています。
-
【会社法26条1項】
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
株式会社を設立すると、株主をはじめ、取引先や債権者など多くの利害関係者と関わりをもつことになります。
そのため、運営上のルールを定めていないと、さまざまな形でトラブルを招く可能性が高くなります。
また、トラブルになった場合にも、一定のルールを定めておくことで、解決を図ることが可能になるのです。
このように、定款は、会社という一つの組織において、規範的な役割を果たす大変重要なものなのです。
2 定款の記載事項

定款では、会社におけるさまざまなルールを定めることになりますが、定款における記載事項は以下の3つに分類されています。
(1)絶対的記載事項
「絶対的記載事項」とは、言葉のとおり、必ず定款に記載しなければならない事項のことをいいます。定款において絶対的記載事項が欠けている場合、定款全体が無効なものとして扱われるため注意が必要です。
絶対的記載事項は、以下の5つです。
- 事業の目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立時に出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名(名称)および住所
ここでいう「事業の目的」には、営利性があること、違法性がないこと、そして、明確であることが求められます。
設立しようとする会社に応じて事業目的もさまざまですが、記載内容があまりに広範囲にわたっていると、かえって取引先などに不信感をもたれるおそれもあるため注意するようにしましょう。
(2)相対的記載事項
「相対的記載事項」とは、定款に定めておくことで初めて効力が生じるとされている事項のことをいいます。
相対的記載事項には、以下のようなものがあります。
- 現物出資に関する事項
- 財産引受に関する事項
- 発起人の報酬に関する事項
- 設立費用に関する事項
①現物出資に関する事項
「現物出資」とは、金銭以外の財産をもって出資することをいいます。
会社を設立する場合、発起人にかぎって現物出資をすることが許されているため、発起人において現物出資をすることが予定されている場合には、その者の氏名や現物出資に係る財産とその価額、その者に割り当てる設立時発行株式の数などを記載する必要があります。
②財産引受に関する事項
「財産引受」とは、発起人が、会社成立後に財産を譲り受けることを約した契約のことをいいます。
財産引受をする場合、譲り受ける財産とその価額、譲渡人の氏名を定款に記載しなければなりません。
③発起人の報酬に関する事項
株式会社の設立に関し、発起人が提供した労務に対して対価を支払う場合には、発起人の氏名や報酬額を定款に記載する必要があります。
④設立費用に関する事項
株式会社を設立するためには、定款の認証手数料や設立登記費用などが必要になります。
成立後の会社が当然に負担すべき設立費用を除き、発起人は、定款に記載した設立費用の額を上限として、成立後の会社に請求することができます。
(3)任意的記載事項
「任意的記載事項」とは、会社法の規定などに反しない範囲で定款に定めることができる事項です。
もっとも、相対的記載事項とは異なり、定款に記載していない場合であってもその効力が否定されるわけではありません。
任意的記載事項としては、たとえば、役員の数や株主総会の招集時期などに関する定めが挙げられます。
このように、定款には絶対的記載事項を必ず記載したうえで、必要に応じて、相対的記載事項や任意的記載事項を記載することになります。
作成した定款は、最終的に公証人の認証を受けることによって効力を生じることになります。
3 定款の変更

定款は、後になって内容を変更することも可能です。
もっとも、一般的に「変更」と聞くと、いったん認証を受けた定款について、その内容を書き替えるようなイメージが強いかもしれませんが、そうではありません。
会社を設立する際に必要となる定款のことを「原始定款」ともいいますが、原始定款そのものが変更されることは未来永劫ありません。
自由に原始定款を書き換えることができてしまうと、勝手に自分の都合にいいように何者かに書き換えられる可能性があり、そうすると、もはや会社のルールとしての意義を失うことになってしまいます。
以上のような理由で、定款を変更する場合には、原始定款を変更することはせずに、変更点をまとめた議事録などを新たに提出することによって、定款変更が行われることになっています。
また、定款を変更する場合には、株主総会の特別決議を経る必要があり、手続面においても厳しいルールが存在します。
ここでいう「特別決議」とは、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議方法です。
このように、変更が生じたからといって定款を簡単に変更することはできず、定款を変更するためには、株主の判断を仰ぐことが必要なのです。
4 まとめ
定款は、会社のルールを細かく定めたもので「会社の憲法」と呼ばれるほど、会社にとっては重要なものです。
定款を作成する際には、大きく3つの記載事項があることを押さえたうえで、必要に応じた規定を盛り込むことが必要になってきます。
不備があれば、その都度定款を変更すればいいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、定款を変更するためには一定のコストがかかるうえ、変更の頻度が上がると、取引先等に不信感を抱かせる要因にもなります。
定款の変更を極力減らすためには、将来をも見据えたうえで、その内容を定款に盛り込んでおくことが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。