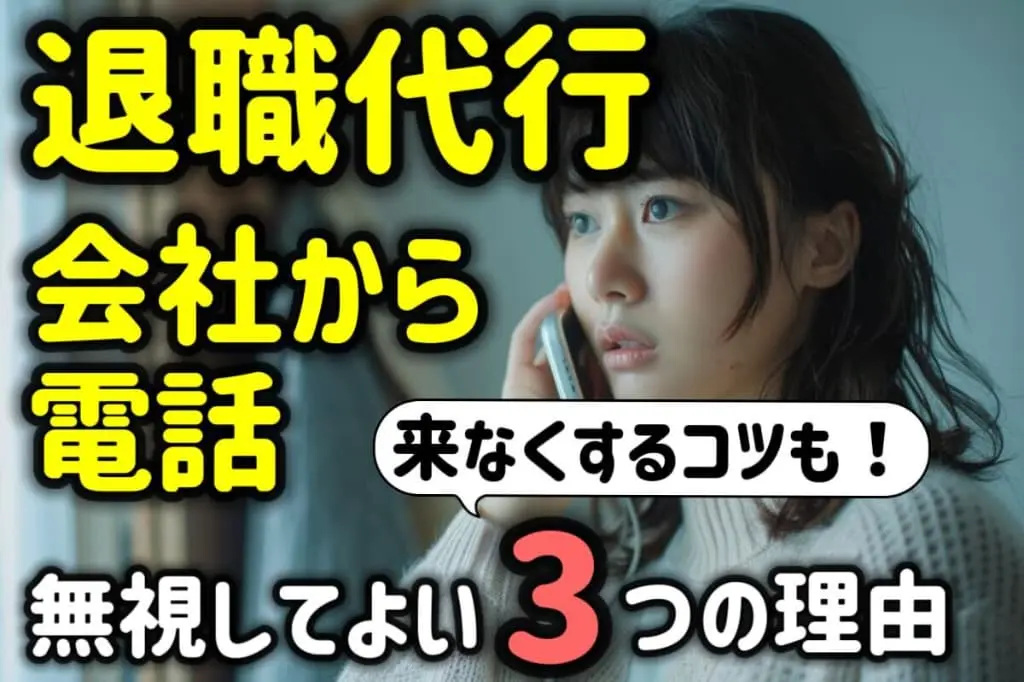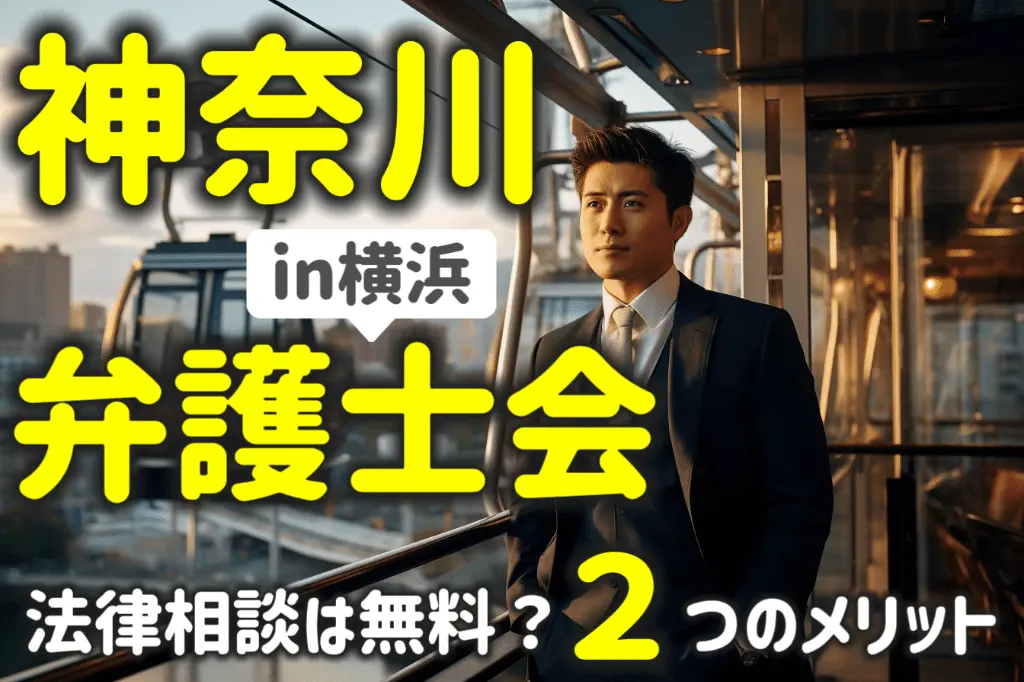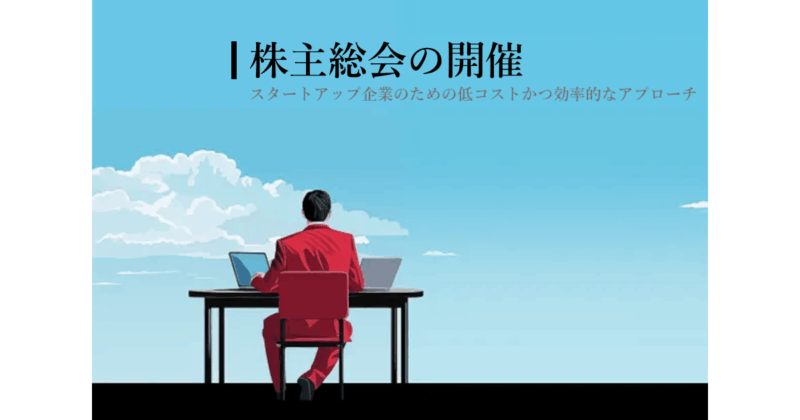営業秘密とは?テレワーク時における情報管理のポイントなどを解説

はじめに
2021年3月25日、昨年1年間に不正競争防止法違反で警察が検挙した件数が過去最多となったことが、警察庁のまとめで分かりました。
この中には、企業の営業秘密を不正に取得するといった事件も含まれています。
営業秘密取得、検挙最多38人 人材流動化一因か 警察庁(Yahoo!ニュース)
記事の中でも触れられていますが、最近は企業側の営業秘密に対する意識が非常に高くなっていることを肌で感じます。
ひと昔前は、辞めた従業員の知識などたかが知れており、情報窃盗のような悪質な持ち出し行為でもない限りは気にする必要はないという状況でしたが、現在はノウハウさえあればサービスを実装するための予算はそれほどかからず、後発のサービスでも数年でメジャーになるというケースも珍しくありません。
創業期のベンチャーにとって、同業大手の退職者が持つ情報は喉から手が出るほど魅力的である場合もあり、そこに誘惑が生まれます。
個人がどの会社で勤務するかは職業選択の自由から当然認められるべきことですが、一線を超えると取り返しのつかないことになります。
また、リモートワークの増加に伴い、営業秘密の漏洩や不正流出が起きやすい状況になっているとも言えます。
今回は、「営業秘密」について、わかりやすく解説します。
1 営業秘密とは

「営業秘密」は、不正競争防止法で次のように定義されています。
-
【不正競争防止法2条6項】
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう
このように、営業秘密にあたるといえるためには、以下の3つの要件を満たしていることが必要になります。
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 有用な情報であること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
2 「営業秘密」の3要件
(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
営業秘密に「秘密管理性」を求める趣旨は、事業者が秘密として管理しようとする対象を従業員などに周知し、従業員に予見可能性をもたせる点にあります。
そうすることにより、事業者は経済活動の安定性を確保することができます。
これは、内部の従業員のみを対象としているわけではなく、取引先についても同様に対象になります。
このように、秘密管理性の要件を満たすためには、秘密として管理しているだけでは足りず、秘密の情報であるということを従業員や取引先に明確にしておくことが必要になります。
たとえば、秘密保持契約書(NDA)を締結する方法、情報が紙媒体で保管されている場合には「マル秘」と記載する方法、情報がデータで保管されている場合には電子ファイルに「マル秘」と入力する方法などにより、従業員や取引先に対して秘密の情報であるということを明確にすることができます。
(2)有用な情報であること(有用性)
情報に「有用性」があるといえるためには、客観的に見てその情報が事業との関係で有用であると認められることが必要です。
そのため、ありふれたノウハウなどは事業との関係で有用性があるとはいえず、営業秘密にはあたりません。
もっとも、情報が「秘密管理性」や次で見る「非公知性」を満たす場合、その多くが有用性も満たしていることが通常です。
(3)公然と知られていないこと(非公知性)
情報に「非公知性」があるといえるためには、その秘密が一般的には知られていない、もしくは簡単に知ることができない状態にあることが必要です。
公開情報や入手可能な商品などからは簡単に推測できないことが必要であり、情報の保有者の管理下以外で入手することができないような状態にあることが求められます。
たとえば、すでにインターネットで公開されている情報やノウハウなどは、非公知性があるとはいえないため、営業秘密にあたりません。
※各要件の考え方については、経産省が公開している「営業秘密管理指針」が参考になります。
3 テレワークにおける営業秘密の管理

コロナ禍により、多くの企業でテレワークが実施されています。
その結果、これまでは社内で厳重に管理されていた秘密情報を紙媒体で持ち帰ったり、自宅などから共有ドライブにアクセスしたりするなどして作業を行うことも生じます。
そのため、従来とくらべ秘密情報の漏えいリスクが高くなると考えられます。
事業者などは、テレワークに応じた適切な情報管理を行っていくことが重要になってきます。
この点は、経産省が公表している「テレワーク時における秘密情報管理のポイント」が参考になります。
以下で、ポイントの一部をご紹介したいと思います。
(1)必要に応じた見直し
社内規程がテレワークに即した内容になっているかを確認したうえで、必要に応じて改訂することが必要です。
諸規程については、従業員などに周知徹底することが求められます。
また、必要に応じて秘密情報を社外に持ち出すことを認めつつ、持ち出す場合のルールを明確に定めておくことも必要になるでしょう。
さらに、事業者は、テレワーク時に困難となりやすい情報の「秘密管理性」を確保するために必要な措置を講ずることも必要です。
たとえば、秘密情報へのアクセス権限を一部の者に与えたり、「マル秘」などの表示を徹底したりすることが挙げられます。
(2)万一に備えた対策を立てる
事業者が適切に情報管理を行っていても、不正に情報を取得されたり持ち出されたりする可能性はゼロではありません。
不測の事態に備えて、あらかじめ対策を立てておくことは有益です。
たとえば、秘密情報へのアクセス権者をいまいちど確認したうえで、アクセス権者以外の者が秘密情報にアクセスできないようにしたり、社内教育などによる周知を通じて、秘密情報漏えいに対する従業員の危機意識を高めたりすることが挙げられます。
4 まとめ
「営業秘密」は、長年の経験から生み出したノウハウや顧客情報など、事業者が事業を行っていくうえでなくてはならない貴重な情報です。
営業秘密が外部に漏えいしたり、不正なことに使用されたりすると、事業者にとっては多大な損失となり、事業の継続が困難になるおそれもあります。
テレワークの導入が増えてきているなかで、事業者は情報管理についても柔軟に対応する必要があります。
いまいちど、情報管理の態様や諸規定の整備状況などを確認したうえで、状況に即した見直しをすることが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。