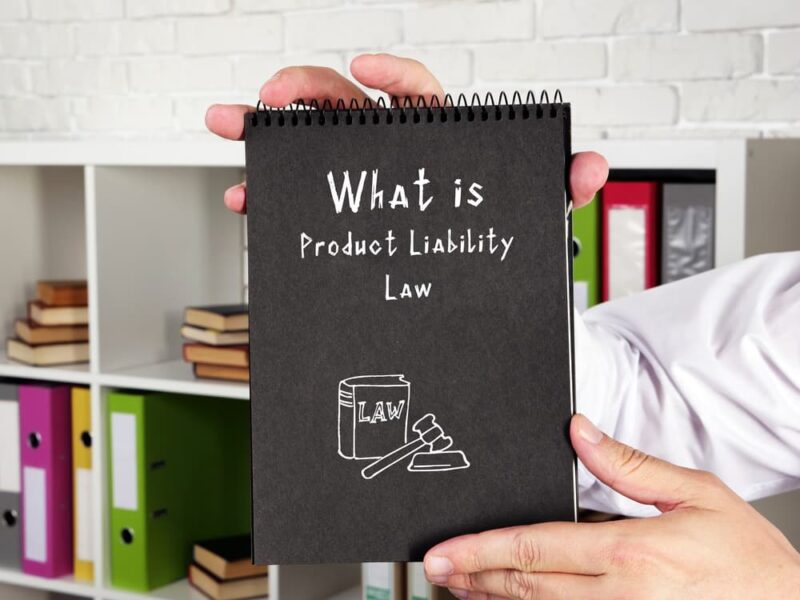不正競争防止法とは?事業者が注意すべき4つのルールを弁護士が解説

はじめに
新商品を考案する際には、独自の発想をフル回転させることはもちろんのこと、消費者のニーズや他社の商品など、さまざまな要素を参考にすることが多いです。
ですが、いざ販売に踏み切ろうとしたときに、「他社の商品に似ていて誤解を与えるんじゃないだろうか」などと心配になる時はありませんか。
このような場合、事業者は「不正競争防止法」という法律をきちんと確認しておく必要があります。
今回は、事業者が注意すべき不正競争防止法について、その全体像をわかりやすく解説します。
1 不正競争防止法とは
「不正競争防止法」とは、公正な市場を確保するために、事業者間の公正な競争を阻害する一定の行為を禁止する法律です。
同法は、事業者間の公正な競争を阻害する一定の行為を「不正競争」として規制しています。
不正競争を行った事業者は、民事上の請求を受けたり、刑事罰を科されたりする可能性があります。
そのため、事業者にとって、不正競争防止法は見過ごすことのできない法律なのです。
2 不正競争防止法による禁止事項
不正競争防止法が「不正競争」と定義している行為は多数ありますが、今回は、そのなかでも特に商品等を販売する際に注意しなければならない規制について見ていきたいと思います。
具体的には、以下の4つです。
- 混同を惹起する行為
- 商品表示を冒用する行為
- 形態を模倣した商品を提供する行為
- 誤認を惹起する行為
(1)混同を惹起する行為
「混同を惹起する行為」とは、他社の商品や営業の表示として既に広く知られているものと同一または類似の表示を用いて、他社の商品や営業と混同を生じさせる行為のことをいいます。
たとえば、有名な「かに料理屋」が使用する「動くかに看板」に類似した「かに看板」を使用する行為は、消費者において有名な「かに料理屋」による営業と混同を生じさせるため、ここでいう「混同を惹起させる行為」にあたります。
もっとも、他社の商品や営業の表示として広く知られる前から不正な目的をもたずに使用している場合には、「混同を惹起させる行為」にあたりません。
(2)商品表示を冒用する行為
「商品表示を冒用する行為」とは、他社の商品や営業の表示として全国的に知られている著名なものを、自社の商品や営業の表示として使用する行為のことをいいます。
取り扱っている分野が異なれば、商品表示を冒用しても、消費者において混同を生じることはありません。
ですが、これを許してしまうと、他社が積み上げてきた顧客吸引力を不当に利用されたり、ブランドイメージにキズがつく可能性があるため、不正競争行為として禁止されているのです。
たとえば、ご存知の方も多いと思いますが、任天堂の「MARIO KART」や「マリオ」などの表示と類似する「MariCar」「MARICAR」「maricar」といった表示を営業で使用する行為は、ここでいう「商品表示を冒用する行為」にあたります。
もっとも、他社の商品や営業の表示として著名となる前から不正な目的をもたずに使用している場合には、「商品表示を冒用する行為」にあたりません。
(3)形態を模倣した商品を提供する行為
「形態を模倣した商品を提供する行為」とは、他社の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為のことをいいます。
ここでいう「形態」とは、消費者が通常の用法に従って使用する場合に知覚によって認識できる、商品の外部や内部の形状、形状に結合している模様や色彩、質感などをいうとされています。
もっとも、商品の機能を確保するために必要とされる形態やありふれた形態は、ここでいう「形態」にはあたりません。
また、日本で最初に販売された日から3年を経過した商品の形態を模倣した商品を提供する場合には、規制の適用が除外されるため、不正競争行為にはあたりません。
(4)誤認を惹起する行為
「誤認を惹起する行為」とは、商品やその広告等に、品質や原産地などについて誤認を与えるような表示をする行為のことをいいます。
たとえば、商品に表示されている地域では、同商品が製造・産出されているという事実がないにもかかわらず、商品にその地域名を表示する行為は、ここでいう「誤認を惹起する行為」にあたります。
3 不正競争防止法に違反した場合の罰則
不正競争法に違反した場合、事業者は、
- 最大5年の懲役
- 最大500万円の罰金
のいずれか、または両方を科される可能性があります。
事業者が法人である場合には、行為者とは別に、法人に対して最大3億円の罰金が科される可能性があります。
また、刑事罰に加えて、以下のように、民事上の請求を受ける可能性もあります。
- 差止請求
- 損害賠償請求
- 信用回復措置請求
不正競争行為によって、他社の営業上の利益を侵害した場合、または侵害するおそれがある場合、他社から侵害の停止や予防を内容とする「差止請求」を受ける可能性があります。
また、事業者の故意または過失による不正競争行為が原因となって、他社に損害を与えた場合には、他社から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
この場合、事業者が不正競争行為によって得た利益が、そのまま他社の損害額として推定されるため、事業者は推定を覆すために反証することが必要になってきます。
さらに、事業者の不正競争行為により、他社に係る営業上の信用を侵害した場合には、他社から信用回復のために必要な措置をとるよう請求される可能性もあります。
請求が認められると、事業者は、たとえば、自社サイトや新聞などにおいて、謝罪広告を掲載することが必要です。
4 まとめ
不正競争防止法は、市場の健全性を確保するために、一定の行為を不正競争行為として禁止しています。
見落としがちな法律かもしれませんが、同法に違反してしまうと重いペナルティを科されるだけでなく、その後の事業活動にも大きく影響します。
そのような事態を招かないためにも、今回見てきた4つのルールをしっかりと押さえたうえで、不正競争行為にあたらないように事業を展開していくことが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。