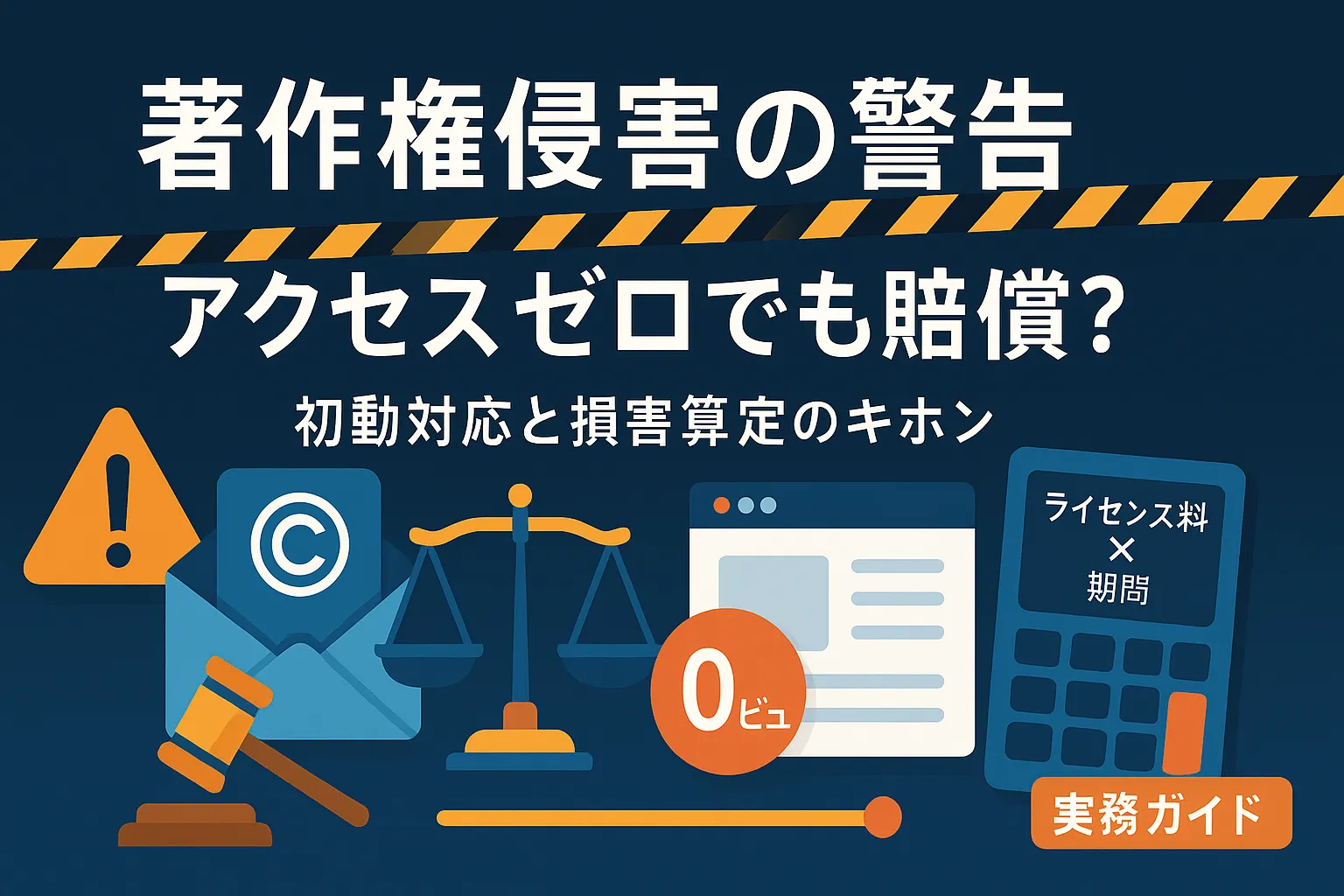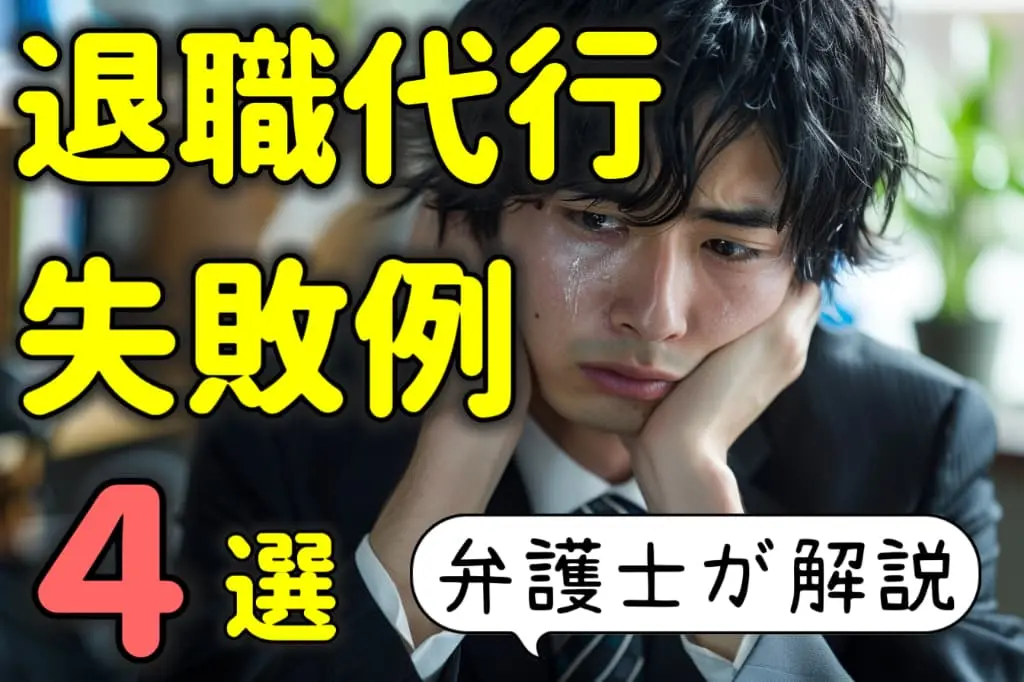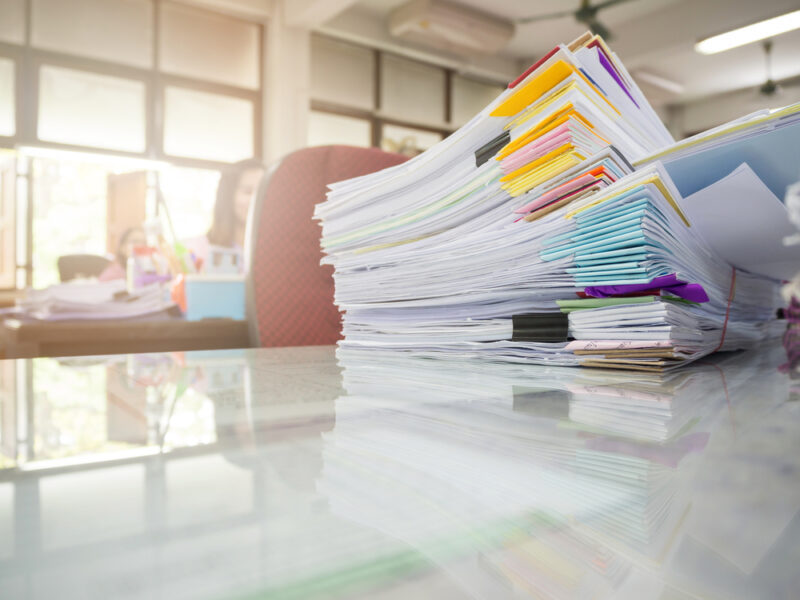競業避止義務とは?有効性を判断する6つのポイントを弁護士が解説!

はじめに
従業員を雇用する場合には、誓約書や就業規則によって「競業避止義務」を負わせることが一般的です。
ところで、競業避止義務がいったいどのような義務なのか、ご存知でしょうか。
競業行為は、事業者にとって自社の不利益に繋がるおそれのある行為です。
そのため、従業員に競業避止義務を課すかどうかは、大変重要な問題なのです。
今回は、「競業避止義務」について、その概要を弁護士がわかりやすく解説します。
1 競業避止義務とは
「競業避止義務」とは、企業と競合関係にある他社に転職したり、そのような会社を自分で起業したりすることを禁止することをいいます。
入社時に交わす誓約書や就業規則によって定めることが一般的であり、競業行為の対象は「在職中の違反行為」と「退職後の競業行為」の2つに分かれます。
(1)在職中の違反行為
労働契約法では、「在職中の労働者は、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」と定められています。
在職中については、誓約書や就業規則において競業避止義務を負う旨の定めがある場合はもちろんのこと、仮にそのような定めがなくても、労働者は信義則上競業避止義務を負うと解されています。
(2)退職後の競業行為
競業避止義務は労働契約に基づいて発生する義務であるため、退職すれば競業避止義務も消滅するのが原則です。
もっとも、労働契約とは別に、退職後も競業行為を行わないという合意が双方に成立していれば、退職後も引き続き競業避止義務を負うことになります。
とはいえ、退職後について競業避止義務を課すことは、「職業選択の自由」を侵害するおそれもあるため、制限的に解されています。
この点は、後ほど詳しく解説します。
企業にとって重要な情報・ノウハウなどが勝手に利用されてしまうと、多大な損失を受けるおそれがあります。
また、秘匿性の高い情報には、顧客情報が含まれていることが多いため、プライバシーを保護する観点からも競業避止義務を課すことが必要になります。
このように、競業避止義務は、近年重要視されるコンプライアンスやガバナンスを強化することにもつながると考えられています。
2 退職後の競業避止義務契約が有効となるためのポイント
退職後について競業避止義務を課す場合には、就業規則や誓約書などにより、退職後も競業行為を行わないという合意が成立していなければなりません。
そのうえで、以下の6つの要件をすべて満たしていることが必要になります。
- 守るべき企業の利益があること
- 従業員の地位
- 地域的な限定
- 競業避止義務の存続期間
- 禁止される競業行為の範囲
- 代償措置
(1)守るべき企業の利益があること
「守るべき企業の利益」とは、営業秘密や企業独自のノウハウなど、企業にとって財産ともなる利益のことをいいます。
「営業秘密」については、不正競争防止法が法的保護の対象としていることからも、企業側の利益であることは明らかです。
また、企業独自のノウハウなどについても、退職した従業員が競合他社に持ち込んだりしてしまうと、企業の利益を害するおそれがあるため、一般的には企業側の利益として認められています。
(2)従業員の地位
「従業員の地位」とは、形式的な職位を指すのではなく、守るべき企業の利益との関係で競業避止義務を課すことが必要であったかどうかにより判断されます。
そのため、すべての従業員を対象としていたり、特定の職位にあるすべての従業員を対象としていたりする場合には、その有効性が否定される可能性が高いといえるでしょう。
(3)地域的な限定
地域的限定については、企業の事業内容や職業選択の自由に対する制約の程度などから、その有効性が判断されます。
また、地域的限定がない場合であっても、企業の事業内容や職業選択の自由に対する制約の程度などを総合的に考慮して、その有効性が肯定されたケースもあるため、地域的限定がないことのみをもって競業避止義務契約の有効性が否定されるというわけではありません。
(4)競業避止義務の存続期間
退職後に課される競業避止義務の存続期間は、労働者の不利益の程度などを考慮した上で、守るべき企業の利益を保護する手段として合理的といえるかどうかによって、その有効性が判断されます。
存続期間を「1年以内の期間」としている場合には、肯定的に捉えられることが多いといえますが、これが「2年」になると、否定的に捉えられる可能性もあります。
(5)禁止される競業行為の範囲
「禁止される競業行為の範囲」と「守るべき企業の利益」の整合性がとれていなければなりません。
たとえば、競合他社への転職を一般的・抽象的に禁止するだけでは、有効性が否定される可能性が高いです。
一方で、禁止される活動内容などが限定されている場合には、有効性が肯定される可能性が高くなります。
(6)代償措置
代償措置の有無のみをもって、その有効性が判断されるわけではありませんが、代償措置と呼べるものが存在しない場合には、有効性が否定される可能性が高いといえます。
一方で、代償措置以外の点で、その有効性を肯定する方向で考慮される要素が多い場合には、有効性が肯定される可能性もあります。
3 まとめ
退職後について競業避止義務を課す場合は、憲法上の権利である「職業選択の自由」を十分に考慮する必要があります。
この場合、事業者は、守るべき自社の利益が現に存在していることをきちんと確認したうえで、競業避止義務の範囲を必要最小限にとどめることが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。