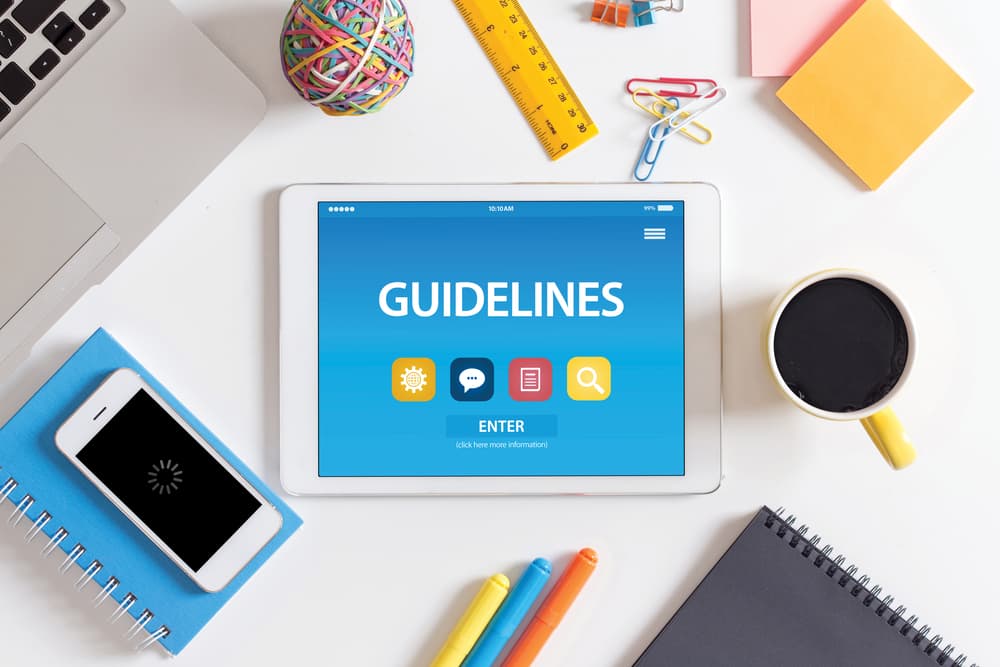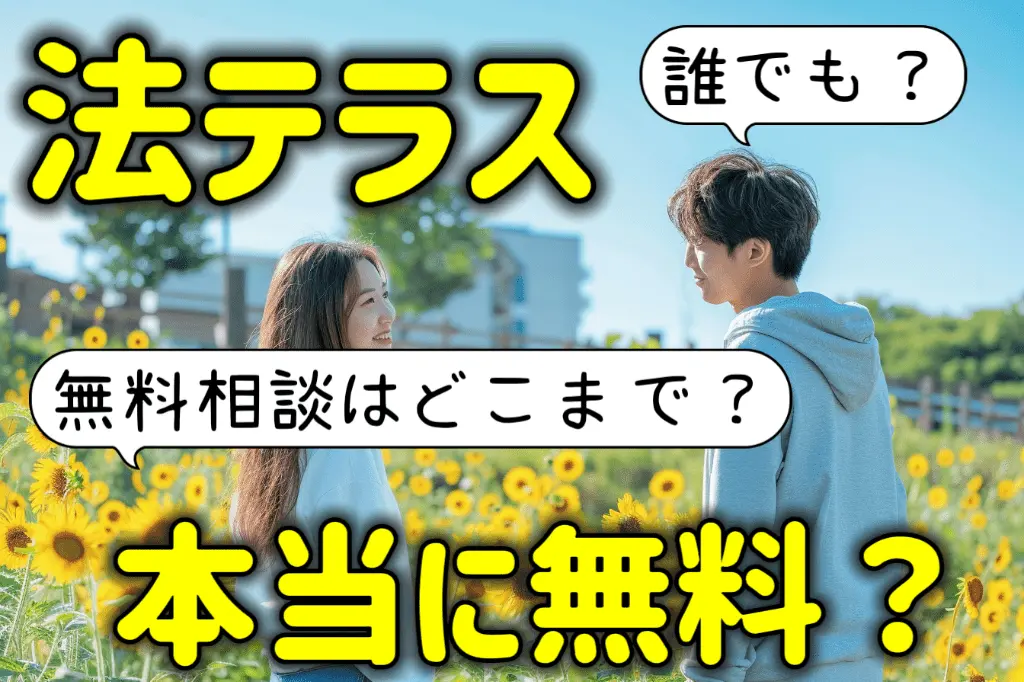ドローンで空撮をする場合に注意すべき人の映り込みと3つの法律規制

はじめに
昨今、ドローンを使った空撮が流行っていますが、空撮の際にどのような法律によって規制され、どういった点に気を付けるべきかきちんと把握している事業者は少ないのではないでしょうか?
ドローンを使った空撮では、被写体として予定していなかった「人」が映り込む可能性があるため、人のプライバシー、肖像権や個人情報保護の法律などが問題となります。
そこで今回は、ドローンでの撮影はプライバシー侵害となるのか?を中心に、ITに強い弁護士が解説していきます。
1 ドローンの撮影によるトラブル事例

ドローンの登場により、歩行者では撮影できないような場所も、撮影することが可能になりました。また、近年のSNS等の普及に伴い、簡単に映像や写真をアップロードして公開することが可能になりました。
現在では、撮影された映像・写真などが投稿サイトなどを通して頻繁に公開されるようになりました。そのため、写真などに人が映り込んでいるような場合、プライバシー権侵害を始めとした、以下のような法律問題が生じます。
- プライバシー権侵害
- 肖像権侵害
- 個人情報保護法
次の項目から順に見ていきましょう。
2 プライバシー権侵害

(1)プライバシー権とは
「プライバシー権」とは、私生活に関する情報を何の理由もなく公開されることのない権利のことをいいます。
ドローンで空撮した画像や動画の中に「人」が映り込むことはよくありますが、こういった場合にプライバシー権侵害が問題となります。
もっとも、時代の進化に伴いプライバシー権の中身は多様化しており、「自己情報コントロール権」として捉える考え方も有力になっています。これは、単にプライバシー権を「公開されない権利」という消極的な権利ではなく、「自己の情報をコントロールする権利」という積極的な権利として捉える考え方です。
具体的には、
- 自己の情報を勝手に収集・公開されない権利
- 自己の情報について閲覧・訂正・削除を求める権利
として、プライバシー権を捉える考え方です。
その結果、ドローン事業者が万が一プライバシー権を侵害するような画像・映像を撮影して公開してしまった場合、権利者の方から削除や、損害賠償請求といった請求を受けるリスクが高まっているのです。
この点、ドローンによる空撮では、予定していない被写体が映り込む可能性があります。しかもSNSなどを使って、簡単に映像などをアップロードすることが可能なため、被写体のプライバシー権との関係が問題となります
それでは、ドローンによって撮影をする場合に、プライバシー権が侵害されたといえるのはどのような場合なのでしょうか。
以下で、その判断基準について、見ていきましょう。
(2)プライバシー権侵害の判断基準
ドローンで撮影をする場合において、プライバシー権を侵害したといえるためには、被写体が単に映り込んでいたというだけでは足りません。
公開された事実について、以下の4つの条件をみたしていることが必要です。
- 私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれがあること
- 一般人がその人の立場に立った場合に公開されたくないと考えること
- 一般にまだ知られていないこと
- 公開されたことによって本人が不快・不安になったこと
これらの条件を簡単に言い換えると、「知られていない私生活上の事実を公開されたことによって、不快を覚えた」といえる場合には、プライバシー権侵害が成立することになります。
とはいえ、この判断基準では不明確な部分もあるため、実務では、総務省が作成した「ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取り扱いにかかるガイドライン」に基づいた運用がなされています。
そのため、ドローン事業者としては、空撮をする際には、上記のガイドラインを読み、プライバシー侵害にならないような形で取り組む必要があります。
以上のように、ドローンによって撮影をする場合には、第三者のプライバシーに配慮する必要があります。
ここで、まさしくこの点が問題となった事例を1つご紹介しましょう。みなさんもよくご存知の「グーグルストリートビュー」が問題となった事例です。
以下で、具体的に見てみましょう。
(3)グーグルストリートビューとの比較
「グーグルストリートビュー」は、自分が知りたい場所であったり、その周辺の風景を写真で表示させることができるサービスです。
もっとも、このサービスでは、あらゆる場所が写真で公開されているため、時に想定していないものが映り込むことがあります。
実際に、ベランダに干していた洗濯物を撮影・公開された人が、その撮影行為と公開行為に対して、プライバシー権が侵害されたなどとして、グーグルを相手に裁判を起こした事例もあります。
このケースでは、
①「たまたま」ベランダの様子が映り込んだに過ぎず、また、②画像全体に占めるベランダの画像の割合が小さかったことなどから、プライバシー権の侵害は認められませんでした。
「ストリートビュー」は、使ったことがある人であればわかると思いますが、自分が行きたい場所やその周辺を写真で確認することができますので、ユーザーにとっては大変便利なものです。
ですが、たとえ、多数のユーザーにとって有益性のあるサービス提供が目的であっても、そのための撮影によりたまたま第三者の住居などが映り込んでしまったというだけで、プライバシー権侵害が問題になるのです。
ドローンでの撮影は、一般的な撮影に比べ、想定していないものが映り込む可能性が高いといえるため、プライバシー権侵害の可能性も高まります。
仮に、想定していないものが映り込んでしまった場合であっても、ストリートビューの事例で示されたように、
- たまたま映り込んでしまった
- 映り込んだ画像の割合も小さい
場合には、プライバシー権の侵害が認められる可能性は低いということがいえます。
反対に、第三者の住居などに狙いを定めて、その内部を撮影したような場合には、プライバシー権の侵害となる可能性が高いです。
いずれにしても、撮影行為や公開行為がプライバシー権を侵害するかどうかは、具体的なケースで個別に判断されることになります。
ここで、ドローンで撮影した映像などをSNSなどインターネット上で公開する場合の基準については、先ほど触れたように総務省が「ガイドライン」を公表していますので、以下で見てみましょう。
(4)ドローン撮影ガイドラインの運用基準
このガイドラインでは、主に以下の2つの点について、総務省の見解が示されています。
- 撮影自体の違法性
- 撮影にあたって配慮すべき点
以下で、詳しく見ていきましょう。
①撮影自体の違法性
いつでも自由に撮影することが許されているわけではありません。撮影により、予定していない被写体が映り込む可能性があるため、プライバシー権を侵害するおそれがあります。
そこで、撮影自体の違法性については、
-
(ⅰ)撮影する目的
(ⅱ)撮影方法・手段の相当性
(ⅲ)撮影の対象(性質)
という3つの点を考慮したうえで、総合的・個別的に判断されるものとされています。
そのため、以上に挙げた3つの条件を念頭に置いて、撮影することは大変重要ではありますが、加えて、撮影者には撮影時に第三者などのプライバシー権を侵害することのないよう配慮することが求められます。
②撮影にあたって配慮すべき点
撮影者は撮影にあたって、以下の2つの点に配慮すべきとされています。
-
(ⅰ)住宅地は、なるべく距離を置いた場所から撮影し、カメラの向きにも配慮する
(ⅱ)なるべく人の顔が写らないように配慮し、写った場合はボカシを入れるなどする
ドローンが空を飛ぶ機体である以上、住宅地では、住民が見られたくないと思うものが映り込む可能性があります。
そのため、ドローンの高度やカメラの向きを調整するといった配慮が求められます。
また、人の顔が映り込んでしまうような撮影方法はなるべく控え、仮に、人が映り込んでしまった場合には、ボカシを入れるなどして、被写体を判別できないようにするといった配慮も求められます。
以上のように、ドローンで撮影をする場合、その撮影方法や対象を誤ると、プライバシー権を侵害することにもなりかねません。
そのため、適切な方法などによる配慮ある撮影が求められます。
さて、ドローンで空撮する際に人が映り込んだ場合、プライバシー権侵害のほか、次の項目で説明する「肖像権」という権利を侵害していないか?が問題となります。
3 肖像権侵害

(1)肖像権とは
「肖像権」とは、承諾なしに人の容ぼう・姿態を撮影されたり、撮影された写真などを公表されることのない権利をいいます。
肖像権を認めますよ!とはっきりと書かれている法律は存在しませんが、判例上も「肖像権」は一つの権利として認められています。
もっとも、プライバシー権と同様に、ドローンによる撮影は、予定されていない被写体の容ぼう・姿態を映し込む可能性があり、また、そのような映像などがインターネット上で公開される可能性もあります。
そのため、ドローンでの空撮が「肖像権」との関係で問題となるのです。
それでは、どのような場合に肖像権が侵害されたといえるのでしょうか。
その判断基準について、以下で見てみましょう。
(2)肖像権侵害の判断基準
肖像権侵害にあたるかどうかは、判例上、以下のことを総合的に考慮したうえで、その制限が社会生活上の程度を超えるものかどうかによって判断されるとされています。
- 被写体の社会的地位、活動内容
- 撮影場所、撮影目的、撮影態様、撮影の必要性
とはいえ、これだけでは抽象的過ぎてよくわからない方もいると思います。
そこで、以下の3つの視点から、解説していきたいと思います。
①承諾のない第三者の撮影
たとえば、公共の場(撮影場所)において、ドローンで風景を撮影した結果(撮影目的)、承諾を得ていない想定外の第三者が映り込んでいたとしましょう。
この場合は、風景を撮影した際に、偶然にも想定外の第三者が映り込んでしまったといえるため、特定の個人を狙い撃ちしたわけではないことや、公共の場で撮影されたことなどが考慮され、肖像権侵害が否定される可能性が高いです。
もっとも、たとえば、被写体の承諾がないにもかかわらず、住宅の塀の外から背伸びをして、ダイニングキッチンを撮影したような場合には、もはやこのような撮影は程度を超えており、肖像権侵害にあたるとされています。
ここで、実際に肖像権侵害が問題となった過去の事例について、具体的に見てみましょう。
②過去事例(裁判例)
ここでは、過去の裁判例を2件ご紹介します。
-
【事例①】
公共の場で、歩行者の全身を承諾なく大写しで撮影し、ファッション関係のウェブサイトに掲載した事例
この事例で、裁判所は、肖像権侵害を肯定しました。
-
【事例②】
週刊誌が病院内にいる人を撮影した事例
この事例は、肖像権に関するものではなく、プライバシー権が問題となった事例ですが、裁判所は、プライバシー権侵害を肯定しました。
このように、たとえ撮影された場所が「公共の場」であっても、特定の人を対象とした撮影や、一般人がその人の立場に立った場合に撮影されたなくないと思うような場所での撮影は、肖像権やプライバシー権の侵害となる可能性があります。
このことは、ドローンによる撮影の場合も同様にあてはまります。承諾のない人を対象とした撮影行為は肖像権やプライバシー権を侵害する可能性がありますので十分な注意が必要です。
③ドローン撮影の必要性・緊急性が高い場合
ドローンは警備や監視を目的として活用されることもあります。
たとえば、不審者を追跡し、人相を撮影する目的で使われることが想定されます。このような場合、不審者という特定の個人を対象とした撮影となりますが、そこには犯罪の予防や犯人の特定といった正当な目的があります。
また、その場で撮影をしなければ、不審者がわからなくなってしまう以上、そのような撮影には必要性が認められます。
このように、特定の個人を対象とした撮影であっても、撮影自体に正当な目的があり、必要性などが認められる場合には、その撮影のほとんどが適法になると考えられます。
以上のように見てくると、肖像権侵害はプライバシー権侵害と似た問題のようにも思えますが、細かい点で異なります。
撮影者は、この点をきちんと理解したうえで、プライバシー権・肖像権を侵害しないよう、撮影にあたっては十分に配慮することが重要です。
それでは、具体的にどのような点に注意すべきなのでしょうか。
次の項目で、詳しく見てみましょう。
4 プライバシー権・肖像権を侵害しないためのチェックポイント

ドローンによる撮影で、プライバシー権・肖像権を侵害しないためには、以下のフェーズに応じた配慮が必要です。
- 撮影開始前
- 撮影時
- 撮影した動画などの公開時
- 公開後
順に見ていきましょう。
①撮影開始前
撮影を行う場所が公共の場所なのか、そうでないのか、また、撮影しようとする対象が人なのか物なのかなどをきちんと特定する必要があります。
②撮影時
風景を撮影する場合には、できるだけ住宅地にカメラを向けないようにする必要があります。やむを得ずに、住宅地が写ってしまう場合は、ズームなどを行わず、また、人が写ってしまう場合には、その人から承諾がないかぎり、大写しにしないようにする必要があります。
③撮影動画の公開時
SNSを始めとしたインターネット上で撮影動画を公開する場合には、その動画にプライバシー権や肖像権などの権利を侵害する内容が含まれていないか、再度確認することが重要です。
また、仮に、人の顔などのように特定の個人が判別できるものが映り込んでいる場合には、ぼかし処理などを行ったうえで公開する必要があります。
④公開後
投稿者であれ、公開者であれ、第三者から権利侵害の申立てがなされたような場合には、対象となっている動画などを再度確認し、権利侵害があると判断した場合には直ちに削除することが必要です。
以上のように、それぞれのフェーズごとに配慮しなければならないポイントが違います。
もっとも、撮影動画の公開を予定している場合には、以上に挙げた①~④の点のすべてが関係してくることになるため、これらのポイントを総合的に理解していることが極めて重要になってきます。
最後に、ドローンで空撮をする際には、個人情報保護の法律との関係も検討する必要があります。
5 個人情報保護法

(1)個人情報とは?
「個人情報」とは、氏名など特定の個人を識別できるものをいいます。また、メールアドレス等それ単体では個人を特定できないものであっても、他の情報と簡単に照合ができそれにより合わせ技一本で個人を識別できるものも個人情報に含まれます。
例えば、メールアドレスが「yamada@●●●.com」だった場合、山田という氏の人はたくさんいることから、それ単体では「個人情報」にはなりません。ただし、このアドレスが「よしもとクリエイティブ・エージェンシーに所属する、お笑い芸人が使ってる」という情報を仮につかんでいる場合には、この情報と相まって、アドレスの保有者は「芸人の山田花子」という形で個人を特定できます。
このような場合におけるメールアドレスが「個人情報」になるのです。
ドローンでの空撮によって個人の容ぼう・姿態が映り込んだ場合、その画像によって被写体としての特定の個人を容易に識別できるため、その映り込み画像は「個人情報」に該当します。
もっとも、これだけでは、個人情報保護法の適用の対象にはなりません。個人情報が映り込んだからといって、何でもかんでも法律でガンジガラメにされたら事業者が大変すぎます。個人情報保護法では、規制されるケースを一定の範囲に制限しています。
(2)どのような場合に個人情報保護法で規制されるのか?
個人情報保護法が適用対象としているのは、「個人情報取扱事業者」です。
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報をエクセルで管理するなど、個人情報データベース等をビジネスに活用している事業者を指します。
ここでいう「個人情報データベース等」とは、以下のいずれかにあたるものをいいます。
- 特定の個人情報をコンピュータなどの電子計算機を使って検索できるように体系的に構成したもの
- 「①」のほか、特定の個人情報を簡単に検索できるように体系的に構成したもの
このいずれかにあたり、個人情報取扱事業者に該当すると、その事業者には個人情報保護法上の義務が課されます。
ポイントは、単に個人情報を持っているというだけでは個人情報保護法では規制されず、個人情報がデータベース化されている場合に適用されるということです。
もっとも今日では、事業で個人情報データベース等を使っている事業者が多いため、個人情報取扱事業者に該当する事業者が多いものと考えられます。
これはドローン事業者においても同様であり、たとえドローンで撮影した画像などをデータベース化していなくとも、それとは別の個人情報をデータベース化していれば、個人情報取扱事業者にあたることになりますので、その点は注意が必要です。
次の項目では、ドローン事業者が個情報取扱事業者にあたることを前提に、その事業者に課される個人情報保護法上の義務について、詳しく見ていきたいと思います。
※「個人情報データベース等」の定義については、個人情報保護委員会が出している「個人情報保護法ガイドライン」においても触れられています。
(3)個人情報取扱事業者に課される義務
個人情報取扱事業者には、個人情報保護法により以下の義務が課されます。
- 利用目的の通知・公表
- 目的外利用の禁止・安全管理措置など
- 不正な手段による取得禁止
順に見ていきましょう。
①利用目的の通知・公表
取扱事業者は、個人情報の利用目的をできる限り特定する必要があります。
ここでいう「できる限り」とは、利用目的を単に抽象的に特定するだけでは足りず、最終的にどのような事業に用いるのか、どういった目的で利用するのか、などを本人が一般的・合理的に特定できるようにしておくことが望ましいとされています。
このようにして特定された利用目的は、個人情報を取得した際に、本人に速やかに通知・公表する必要があります。
②目的外利用の禁止・安全管理措置など
利用目的が特定された個人情報について、事業者は、その特定された利用目的の達成に必要な範囲内でのみ、個人情報を利用することが認められています(目的外利用の禁止)。
また、取得した個人情報についてデータベースが構築される場合には、その個人情報について、漏えいや滅失、毀損の防止その他安全管理のために適切な措置を講じる必要があります(安全管理措置)。
さらに、本人の同意なく、第三者に個人情報を開示することができなくなります。
③不正な手段による取得禁止
取扱事業者は、ウソやその他の不正な手段で個人情報を取得してはいけません。
そのため、取扱事業者が後に不正に使用する意図をもって隠し撮りを行ったような場合には、個人情報保護法に抵触する可能性があります。
以上のように、ドローン事業者であっても、個人情報の保管方法次第では、個人情報保護法上の取扱事業者にあたる可能性があります。その場合は、個人情報の取扱いに関して守らなければならない一定のルールがありますので、まずは、自社が個人情報取扱事業者にあたるかどうかをきちんと確認することが重要です。
6 小括

ドローンによる撮影は、第三者のプライバシー権や肖像権を侵害するリスクがあります。そのため、ドローンで撮影をする場合には、撮影の前段階から公開後にいたるまで、フェーズに応じた十分な配慮が求められます。
また、場合によっては、撮影映像などが個人情報保護法上の「個人情報」にあたる可能性もありますので、その点も念頭に置いておかなければなりません。
これらのように、さまざまな法律規制があることをきちんと理解したうえで、適切に撮影するよう心掛けましょう。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- ドローンで撮影する場合、①撮影行為、②公開行為の2つの行為について、プライバシー権侵害が問題となる
- プライバシー権を侵害したといえるためには、①私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれがあること、②一般人がその人の立場に立った場合に公開されたくないと考えること、③一般にまだ知られていないこと、④公開されたことによって本人が不快・不安になったことの4つの条件をみたしていることが必要である
- 総務省ガイドラインでは、撮影自体の違法性は、①撮影目的、②撮影方法・手段の相当性、③撮影対象の3つを考慮したうえで、総合的・個別的に判断されるものとされている
- 撮影にあたっては、①住宅地は、なるべく距離を置いた場所から撮影し、カメラの向きにも配慮する、②なるべく人の顔が写らないように配慮し、写った場合はボカシを入れるといった点に配慮すべきである
- 肖像権侵害にあたるかどうかは、①被写体の社会的地位、活動内容、②撮影場所、撮影目的、撮影態様、撮影の必要性を総合的に考慮したうえで、侵害行為が社会生活上の程度を超えるものかどうかによって判断される
- ドローンによる撮影で、プライバシー権・肖像権を侵害しないためには、①撮影開始前、②撮影時、③撮影した動画などの公開時、④公開後に応じた配慮が必要である
- 個人情報保護法が適用対象としているのは、「個人情報取扱事業者」である
- 「個人情報データベース等」とは、①特定の個人情報をコンピュータなどを使って検索できるように体系的に構成したもの、②「①」のほか、特定の個人情報を簡単に検索できるように体系的に構成したもののいずれかにあたるものをいう
- 個人情報取扱事業者には、①利用目的の通知・公表、②目的外利用の禁止・安全管理措置など、③不正な手段による取得禁止、という3つの義務が課される
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。