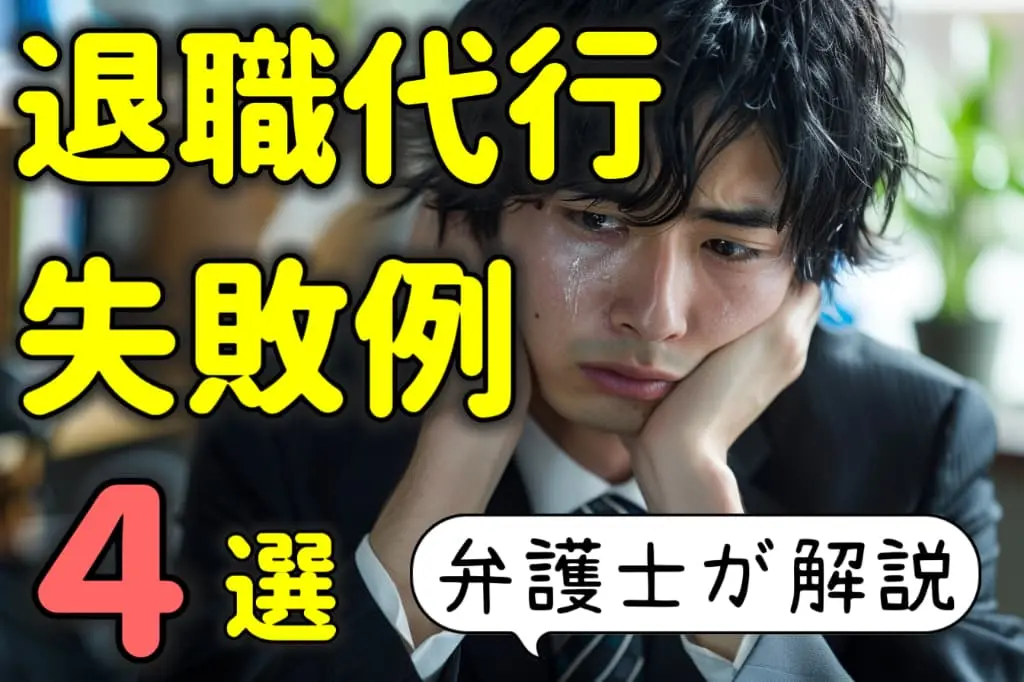ドローンで災害調査・捜索を行う際の2つの法律規制を弁護士が解説!

はじめに
災害現場では、地盤の崩落や土砂崩れなどにより「人」が入れないような危険区域があることが多いです。このような区域であっても、「ドローン」を使えば迅速な調査や捜索が可能になり、機動的に対応することができます。
ですが、たとえ災害などの緊急時であっても、ドローンを飛ばすには、航空法という法律のルールを守らなければなりません。
そこで今回は、災害時にドローンを飛ばす際に知っておくべき航空法のルールについて、ITに強い弁護士が詳しく解説します。
1 災害時におけるドローンの活用

近年、災害などが起きた場所でドローンが活用され始めています。 安全性の確保が難しい危険な場所や人が入れないような狭い場所、道路が寸断されて孤立してしまった場所などにおいても、ドローンであれば捜索をしたり撮影をしたりすることが可能です。
また、ドローンはヘリコプターよりも地上に接近した高度で飛行することができるため、災害によって生じた道路などの亀裂状況などを撮影することも可能です。
災害時にドローンを活用することによって、災害地の状況をいちはやく正確に把握することができるようになるため、復旧活動のあり方を考えるうえでも、大変有益なのです。
現に、2015年の口永良部島の火山活動の確認、2016年4月14日に発生した熊本地震での被災状況の確認にもドローンが使われています。
もっとも、ドローンを飛ばすためには、「航空法」という法律規制が存在します。いつでも自由に飛ばせるわけではありません。
まずは、航空法による一般的な法律規制について、次の項目で見てみましょう。
2 航空法による法律規制

「航空法」は、航空機が安全に飛べるように、さまざまなルールを定めています。
仮に、誰もが自由にドローンを飛ばすことができたら大変危険です。
そのため、ドローンの飛行について規制する法律が必要であり、それが「航空法」なのです。
航空法は、ドローンの飛行について、主に次の2つのルールを設けています。
- 飛行「場所」の規制
- 飛行「方法」の規制
それぞれについて、以下で詳しく見てみましょう。
(1)飛行「場所」の規制
ドローンは空を飛ぶ機体であるため、他の航空機などと接触するおそれがあります。
また、万一ドローンが落下した場合、地上にいる人や建物に危害を及ぼす可能性もあります。
そのため、航空法はある一定の区域でのドローンの飛行を禁じています。
飛行禁止区域は大きく次の2つです。
- 航空機の安全に影響する可能性のある場所
- 人や家屋が密集している場所
以下で、簡単に見ていきましょう。
①航空機の安全に影響する可能性のある場所
「航空機の安全に影響する可能性のある場所」とは、具体的には、空港周辺の空域、高度150m以上の空域を指します。
これらの場所でドローンを飛ばしてしまうと、航空機と接触するおそれがありますので、いずれも飛行禁止区域とされているのです。
②人や家屋が密集している場所
「人や家屋が密集している場所」とは、人口が密集している地域(人口集中地区)のことをいいます。
たとえば、下の画像を見てみると、東京都には赤く色がついています。これは、東京都のほぼ全域が人口集中地区にあたることを示しています。

このような場所でドローンを飛ばすには、あらかじめ国から許可をもらっておくことが必要です。
(2)飛行「方法」の規制
ドローンをどこで飛ばすかに関係なく、飛行方法(飛ばし方)のルールは守らなければなりません。
飛行方法(飛ばし方)についての規則は次の6つです。
- ドローンから物を落とさないこと
- まつりや展示会など人が多く集まるところで飛ばさないこと
- ドローンを飛ばす時間は日の出から日没までの間にすること
- 爆発物など危険なものは搭載しないこと
- 飛ばす時は直接目で見てドローンとその周辺を常に確認すること
- 第三者と建物などとの間に30m以上の距離を保つこと
これらについても、以下で簡単に確認しておきましょう。
①ドローンから物を落とさないこと

ドローンから物を落とすと、地上にいる人・建物などに危害をあたえるおそれがあり、また、物を落とした拍子にバランスを崩してドローンを操作することが困難になるおそれがあります。
②祭りや展示会など人が多く集まるところで飛ばさないこと

祭りや展示会などは、その場に多くに人が集まります。このような場所で、万一ドローンが落下するようなことになると、祭りなどに来ている人がケガをするなど、大変危険です。
③ドローンを飛ばす時間は日の出から日没までの間にすること

視界が悪くなる夜にドローンを飛ばすと、ドローンの位置や状態だけでなく、周辺の状況を把握することさえ難しくなります。そうすると、ドローンが人や建物などに衝突する可能性が高くなります。
そのため、ドローンは日中のみにかぎってしか飛ばすことができません。
④ 爆発物など危険なものは搭載しないこと

危険物を輸送しているドローンが落下してしまったり、危険物が漏れてしまったりすると、地上にいる人・建物などに重大な危害をあたえるおそれがあります。
そのため、危険物をドローンで輸送することはできません。
⑤飛ばす時は直接目で見てドローンとその周辺を常に確認すること

ドローンを飛ばす人が直接自分の目でドローンや周辺の状況を把握できなければ、安全が確保されているとはいえません。
そのため、ドローンを飛ばす際には、直接自分の目でこれらの状況を確認することが必要です。
もっとも、たとえば、先日楽天が発表したドローンを使った配送サービスのように、ドローンを監視し続けることが想定されていないケースもあります。
そのため、一般に、ドローンによる配送サービスは「目視外飛行」にあたり、国の承認を受ける必要がありますが、この場合であっても、ドローンを飛ばす人は安全を確保するために「補助者」を配置しなければなりません。
もっとも、離島などに配送するような場合に、飛行ルートすべてに補助者を配置することは困難です。
そこで、航空局は、審査要領を改正し、指定された飛行場所で、かつ、緊急時に適切な対応が行えるように体制を整備したうえでドローンを飛ばすのであれば、補助者を配置する必要がなくなりました。
※目視外飛行の改正について、詳しく知りたい方は、「ドローンによる配送ビジネスをする際の3つの法律規制を弁護士が解説」をご覧ください。
⑥第三者と建物などとの間に30m以上の距離を保つこと

人や建物に接近した場所でドローンを飛ばすと、衝突の可能性が高くなります。
そのため、ドローンを飛ばす際には、人や建物などとの間に30m以上の距離を保たなければなりません。
これらのルールに反する方法でドローンを飛ばすにはあらかじめ国の承認を受けていなければなりません。
以上のように、ドローンを飛ばす際には、航空法がいくつかのルールを設けていますので、そのルールをきちんと理解していることが前提となります。
もっとも、災害時など緊急性の高い場合にまで、これらのルールを徹底してしまうと、迅速に対応することができなくなり、場合によっては、ドローンを飛ばすことすらできなくなることも考えられます。
そこで、航空法は、災害や事故が発生した場合に、捜索活動・救助活動などを迅速に行えるようにするために、特例を設けています。
次の項目で、その特例について詳しく見ていきましょう。
3 災害時の特例

(1)災害時の特例とは?
「災害時の特例」とは、本来であれば、ドローンを飛ばすための許可・承認を受ける必要があるところを、災害などが発生した場合には、許可・承認を受けることなくドローンを飛ばすことができるとするものです。
もっとも、災害時であれば、常に国の許可・承認が不要になるわけではありません。
災害時の特例は、以下の2つの要件をみたしている場合にはじめて適用されます。
- 国・地方公共団体から依頼を受けた者
- 飛行機事故などの事故に際し、捜索・救助などを目的としてドローンを飛ばす場合
以下で、簡単に見てみましょう。
①国・地方公共団体から依頼を受けた者
「災害時の特例」は、国・地方公共団体から救助活動などの依頼を受けていなければ、適用されません。そのため、国・地方公共団体から依頼を受けていない事業者が、災害時にドローンを飛ばすには、従来通り、航空法により飛行場所や飛行方法の規制を受けることになります。
②飛行機事故などの事故に際し、捜索・救助などを目的としてドローンを飛ばす場合
ここでいう「捜索・救助などを目的として」とは、災害が起きた時などに人の生命や財産に対して、危害が及ぶことが切迫しているような場合において、そのような事態を避けることを目的としている場合を意味します。
そのため、災害により行方不明になった人を捜索することだけでなく、その被害状況を調査することを目的としている場合も含まれます。
このように見てくると、「災害時の特例」は、災害時に常に適用されるわけではなく、国などから依頼を受けていない事業者は、実際に災害などが起きたことを確認して、それから国の許可・承認を受けなければならないということになります。
迅速な対応が求められる災害時などに、このような対応をしていると、十分な救助活動は期待できません。
そこで、実務において広く行われているのが、地方公共団体との間で事前に協定などを結んでおくというやり方です。
以下で見てみましょう。
(2)協定などの締結
近時、災害が起きた時に迅速にドローンを活用するために、地方公共団体との間であらかじめ「災害協定」を結んでおくという動きが広まっています。
「災害協定」とは、自治体などが事業者やドローン協会などの一般社団法人と結ぶものです。
このような協定の締結は、
- 地方公共団体:災害時における捜索・被害状況確認などについて、ドローンの飛行に慣れている事業者に任すことができる
- 事業者:国の許可・承認を受けることなく、災害時にドローンを飛ばすことができる
といったように、双方にとってメリットがあります。
もっとも、このような協定を結び、国の許可・承認を受ける必要がない場合であっても、ドローンを飛ばす事業者は、さまざまなルールを守る必要があります。
以下で見てみましょう。
(3)事業者に求められることは?
「災害時の特例」が適用され、国による許可・承認を受ける必要のない場合であっても、事業者には、ドローンの飛行につき、以下の4点が求められます。
- 航空情報の発行
- 航空機の航行の安全確保
- 飛行マニュアルの作成
- 大規模災害時の対応
以下で、具体的に見てみましょう。
①航空情報の発行
事業者は、以下のいずれかでドローンを飛ばす場合には、飛行範囲や飛行日時、飛行の主体者の連絡先などといった情報をその空域を管轄する空港事務所に通知しなければなりません。
- 空港などの周辺
- 地上などから150m以上の高度
この通知を基に、航空局は航空情報を作成し、空港などの管理者に発行します。発行された航空情報に基づいて、空港などの管理者は、航空機の航行について安全を確保するための措置を講じることになります。
②航空機の航行の安全確保
災害時には、救助などを目的とした複数の航空機が災害地周辺を飛び交うことが想定されます。ドローンを飛ばす人は、これらの航空機について航行の安全を害するような飛行はしてはなりません。
③飛行マニュアルの作成
災害時の捜索や救助などの目的に沿ったドローンの運用方法をマニュアルに定めて、そのマニュアルに則った安全な飛行を行うことが期待されています。
※飛行マニュアルを作成する際には、航空局が出している「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」が参考になります。
④大規模災害時の対応
大規模な災害が起きた場合、通常の災害よりもさらに多くの航空機が捜索・救助などを目的として災害地周辺を飛ぶことになりますので、ドローンとの衝突などの可能性も高くなります。
そのため、災害対策本部などを介してドローンの飛行情報(日時や場所など)を共有・調整することが望ましいとされており、現に、大規模災害時には国土交通省のウェブサイトにおいて、ドローンを飛ばす旨の事前連絡を要請されることもあります。
このように、「災害時の特例」の適用を受けた事業者であっても、災害に特有のルールを守る必要があります。捜索・救助などを目的としてドローンを飛ばしたのに、同じ目的で飛んでいる航空機などと衝突事故などを引き起こしてしまっては、目もあてられませんね。
以上に見てきたように、「災害時の特例」の適用を受けるためには、そのための要件をみたしている必要があり、要件をみたしていない事業者は、「災害協定」を結ぶことで災害時における迅速な対応が可能になるわけです。
それでは、要件をみたしていないうえ、災害協定も結んでいない事業者は、災害時には何もできないのでしょうか。
次の項目で見てみましょう。
※「災害時の特例」の適用を受けた事業者が遵守を求められるルールについて、詳しく知りたい方は、「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」をご覧ください。
4 緊急に飛行を行う必要がある場合の対応

災害時における捜索や救助などといった活動には、機動性が求められます。
そのため、特例の適用を受けられず、災害協定も結んでいない事業者は本来であれば、先にも見たように、災害が起きたことを確認した後に、許可・承認のための申請手続を踏むことになります。
もっとも、これでは機動性は確保できません。
そこで、このような事業者においては、以下のような方法で対応することが考えられます。
- 包括的な許可・承認の事前取得
- 電子メール・電話などによる許可・承認の申請
以下で、簡単に見てみましょう。
(1)包括的な許可・承認の事前取得
災害を具体的に予測することは不可能です。
そのため、災害に「備える」という観点から、事前に包括的な許可・承認を得ておくことが考えられます。
具体的には、ドローンの飛行日時や場所に一定の幅を持たせて包括的に承認を得ておくということになります。
もっとも、許可・承認の期間は「1年間」が最長となりますので、1年ごとの更新が必要となることに注意が必要です。
(2)電子メール・電話などによる許可・承認の申請
災害など緊急に救助活動などをする必要がある場合には、電子メールやファクシミリといった方法で許可・承認を申請することが可能です。
また、地震や津波、爆発事故などといったように大規模な事故が起きた場合には、電話で許可・承認を申請することが可能です。
これらの方法で申請を行うことにより、許可・承認を得るまでの時間を少しでも短縮することが可能となります。
以上に見てきたように、航空法はドローンの飛行についていくつもの規制を設けていますが、災害など特別な状況においては、一定の場合に、国の許可・承認を求めないこととするなどといった例外的なルールを設けています。
それでは、以上に見てきた航空法以外に留意すべき規制はあるのでしょうか。
次の項目で見てみましょう。
※「許可・承認の申請」について詳しく知りたい方は、「ドローンの飛行許可申請のやり方は?5つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。
5 航空法以外の留意点

災害地などでは消防機関やボランティア団体などによる救助活動が連日にわたり行われます。こういった救助活動では、航空機が使われることもありますし、報道機関などが災害地周辺で航空機を飛ばすことも少なくありません。
そのような状況で、自由にドローンを飛ばしてしまうと、航空機と接触するおそれがあります。そのため、ドローンを飛ばす際の自主的な関係当局への連絡を求められる場合があります。
このような情報は、国土交通省のウェブサイトで確認できますので、災害地などでドローンを飛ばす際には、事前に国土交通省のウェブサイトを確認することを忘れないようにしましょう。
6 航空法に違反した場合の罰則(ペナルティ)

以上に見てきた「飛行禁止区域」や「飛行方法」でドローンを飛ばすと、航空法違反となり、
- 最大50万円の罰金
が科せられる可能性があります。
また、法人の従業員などがその業務に関して航空法に違反したような場合には、その従業員とは別に法人に対しても、
- 最大50万円の罰金
が科せられる可能性があります。
このように、航空法に違反した場合には罰金刑を科せられる可能性があります。
そのため、ドローンを飛ばす際には航空法のルールを事前にきちんと確認することが大切です。
7 航空法上の許可・承認申請のやり方

最後に、許可・承認の申請手続について見ていきましょう。
航空法上の許可を取るには、まず、そのための申請をする必要があります。
(1)申請の種類
ドローンの飛行許可申請には、以下の2つの方法が用意されています。
- 個別申請
- 包括申請
①個別申請
「個別申請」は最も一般的な申請方法です。
あらかじめ飛行日と飛行場所が分かっている場合は個別申請をすることになります。
②包括申請
事前に飛行日や飛行場所が決まっていたとしても、当日の天候などによってドローンを飛ばすことができなくなる場合があります。このような事態に備えて、「包括申請」を行うこともできます。
包括申請にはドローンを飛ばす日に期間を設ける「期間包括申請」と飛行場所に範囲を設ける「飛行経路包括申請」があります。
このように、申請にはいくつかのパターンがあるため、ドローンを飛ばす日程や場所に応じて適切な申請方法を選んで申請する必要があります。
(2)申請先
記入を終えた申請書の提出先は、以下の2つに分かれます。
- 空港事務所
- 航空局
順に見ていきましょう。
①空港事務所
ドローンを飛ばす空域を管轄する空港事務所が申請先となるのは、以下の場合です。
- 空港周辺の空域における飛行
- 150m以上の空域における飛行
②航空局
以下の場合には、東京航空局または大阪航空局が申請先となります。
- 物の投下
- イベント会場上空での飛行
- 夜間飛行
- 危険物の輸送
- 目視外飛行
- 人・建物との距離が30m未満の飛行
どちらの航空局に申請書を提出するかは飛行を予定している地域によって以下のように分かれています。
- 新潟県・長野県・静岡県より東の場合:東京航空局
- 富山県・岐阜県・愛知県より西の場合:大阪航空局
(3)申請方法
飛行許可の申請方法は、以下の4通りあります。
- 郵送
- 窓口に持参
- オンライン申請
- 電話、電子メールまたはファクシミリ
もっとも、電話、電子メールまたはファクシミリでの申請は、事故や災害といった緊急時でなければ認められていません。
以上のように、飛行許可の申請は種類や申請先などが細かく決められています。
申請する際には、飛行場所や飛行日時などをあらかじめ特定したうえで、適切に申請を行うようにしましょう。
※「許可・承認の申請」について詳しく知りたい方は、「ドローンの飛行許可申請のやり方は?5つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。
8 小括

近年、災害の現場でドローンが活用される場面が多くなっています。ドローンを飛ばすには原則として航空法のルールを守らなくてはいけませんが、災害時などは迅速な対応が求められるため、「災害時の特例」が存在します。
原則的なルールの理解はもちろんのこと、災害時には特例の適用を受けられる場合があることをその要件とともに覚えておきましょう。
災害などの緊急事態時であっても、これらのルールを理解していないままドローンを飛ばしてしまうと、場合によっては、罰金刑が科される可能性もありますので、注意が必要です。
9 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。
- 航空法は、ドローンの飛行「場所」と飛行「方法」を規制している
- 災害時の特例は、①国などから依頼を受けていること、②事故などに際し、捜索・救助などを目的としている、という2つの要件をみたしている場合に適用される
- 災害時に迅速に対応するために地方公共団体との間であらかじめ災害協定を結ぶ動きが広まってきている
- 災害時の特例が適用される事業者は、①航空情報の発行、②航空機の航行の安全確保、③飛行マニュアルの作成、④大規模災害時の対応の4点を求められる
- 特定の適用を受けられず、協定も締結していない事業者においては、①包括的な許可・承認の事前取得、②電子メール・電話などによる許可・承認の申請という方法で対応することができる
- 災害地などでドローンを飛ばす際に、自主的な関係当局への連絡を求められる場合がある
- 航空法に違反した場合、最大で50万円の罰金を科される可能性がある
- 従業員などが業務に関して航空法に違反した場合には、従業員が所属する法人に対しても最大50万円の罰金を科される可能性がある
- 飛行許可申請は、①個別申請、②包括申請の2つに分かれる
- 申請書の提出先は、①空港事務所、または、②航空局である
- 申請方法は、①郵送、②窓口持参、③オンライン申請、④電話、電子メールまたはファクシミリの4通りある
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。