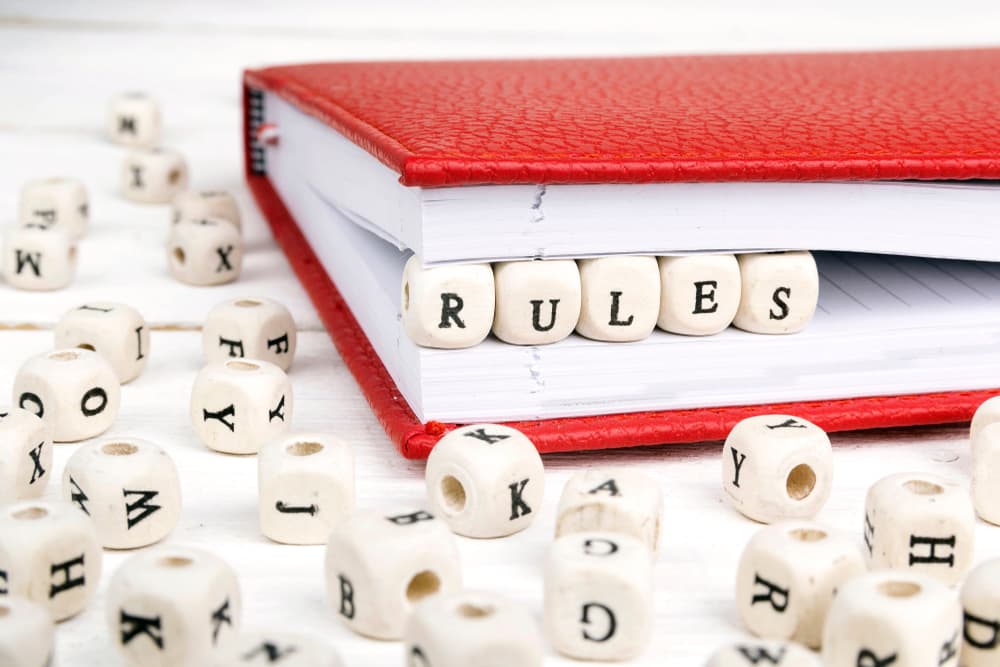金融サービス仲介業者が遵守すべき3つの法規制を弁護士が解説!

はじめに
近年、金融サービスをオンラインで提供する事業者が増えてきました。
日常生活における金融取引ニーズに応えるべく、今後もさまざまなサービスが展開されることが予想されます。
そのようななか、「金融サービス法(正式名称:金融サービスの提供に関する法律)」が2021年11月に施行されました。
金融サービス法は、銀行や証券会社、保険会社が提供する多種多様なサービスを一つの登録によりワンストップで提供できる「金融サービス仲介業」を創設しました。
これまでは、それぞれについて個別に許可・登録を受ける必要があったため、横断的なサービスを提供しようとする事業者の障害にもなっていました。
ですが、今後は一つの登録で横断的なサービスを展開することが可能になります。
そこで今回は、金融サービス仲介業者が遵守すべきルールについて、弁護士がわかりやすく解説します。
1 利用者保護のための規制
従来の金融サービス仲介業者は、特定の金融機関に所属していることが必要でした。
ですが、今後は、さまざまなサービスを取り扱うことができるよう、特定の金融機関に所属する必要はなくなります。
その代わりに、利用者保護を目的として、金融サービス仲介業者は以下の規制を課されることになります。
- 取り扱うことのできるサービスの制限
- 供託義務
- 利用者財産の受入禁止
(1)取り扱うことのできるサービスの制限
従来とは異なり、金融サービス仲介業者は特定の金融機関に所属する必要がなくなりました。
そのため、金融機関による指導・監督がなくなり、利用者保護を十分に図ることができない可能性があります。
そこで、利用者を保護するために、金融サービス仲介業者は、利用者に対し高度な説明を要するサービスについては取扱いができないという制限が設けられました。
-
【銀行分野】
- 預金関係(デリバティブ預金や譲渡性預金等)
- 貸付関係
- 特定保険契約(外貨建て保険や変額保険等)
- 団体保険に係る保険契約
- 有価証券の売買の媒介
【保険分野】
【証券分野】
なお、保険分野については、上記に挙げた契約以外にも取り扱うことが禁止されているものがあります。
また、証券分野については、有価証券の売買の媒介が全面的に禁止されているわけではなく、取り扱うことが可能なものも多数あります。
(2)供託義務
特定の金融機関に所属する必要がなくなったことにより、金融サービス仲介業者が提供したサービスにおいてトラブルが生じ、金融サービス仲介業者が損害賠償責任を負うこととなる場面が想定されます。
この場合、金融サービス仲介業者の資力が乏しいと、利用者に対して賠償金を支払うことができないということにもなりかねません。
このようなことがないように、金融サービス仲介業者は、保証金の供託が義務付けられます。
具体的な金額は、施行令(案)が以下のように定めています。
- 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後3か月を経過する日まで
- 各事業年度の開始の日以後3か月を経過した日から当該各事業年度終了の日後3か月を経過する日まで
→ 1000万円
→ 1000万円に当該各事業年度の前事業年度の年間受領手数料に100分の5を乗じた
額を加えた額
このように、事業者が金融サービス仲介業を始めるにあたっては、1000万円を供託することが義務付けられます。
(3)利用者財産の受入禁止
金融サービス仲介業者による仲介行為は「媒介」に限定されているなど、業務の性質からして、利用者の財産を預かるという必要性はさほど高くありません。
そのため、金融サービス仲介業者は、原則として、利用者から金銭やその他の財産を預かることは禁止されています。
2 その他の規制
金融サービス仲介業者は、以上のほかにも、遵守しなければならないルールがあります。
(1)利用者に対する情報提供
利用者が自身のニーズに合った金融商品やサービスを選択するためには、それに見合った情報が必要になります。
そのため、金融サービス仲介業者は、利用者に対して重要事項に係る情報を提供しなければなりません。
(2)利用者情報の適正な取扱い
金融サービス仲介業者は、業務の性質上、資産状況をはじめとした利用者に係るさまざまな情報を取得します。
そのため、金融サービス仲介業者は、利用者に係る情報を適切に取扱うことが求められます。
利用者から同意を得ていないにもかかわらず、利用者情報を他社に提供するようなことはしてはなりません。
(3)金融機関から受け取る手数料等の開示
金融サービス仲介業者は、利用者から求められた場合、金融サービス仲介業者が受け取る手数料や報酬等を開示しなければなりません。
金融サービス仲介業者の中には、仲介手数料の多寡によって、利用者に勧めるサービス等を変えてくる事業者もいるかもしれません。
手数料等を開示することにより、サービスの透明性を確保することができ、ひいては、利用者の信頼確保にも繋がります。
以上に挙げた規制のほか、分野ごとに個別に課されるルールもあるため、注意が必要です。
※分野ごとに個別に課されるルールについて詳しく知りたい方は、「金融サービス仲介業とは?法律案を基に3つのポイントを弁護士が解説」をご覧ください。
3 まとめ
金融サービス仲介業は、一つの登録で横断的にサービスを展開することが可能な事業です。
もっとも、特定の金融機関に所属することが必須ではなくなったため、利用者保護の観点から一定の規制を課されることになります。
また、利用者財産を預かることができないため、金融事業者と連携しながら事業を展開していくことが必要になってくるでしょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。