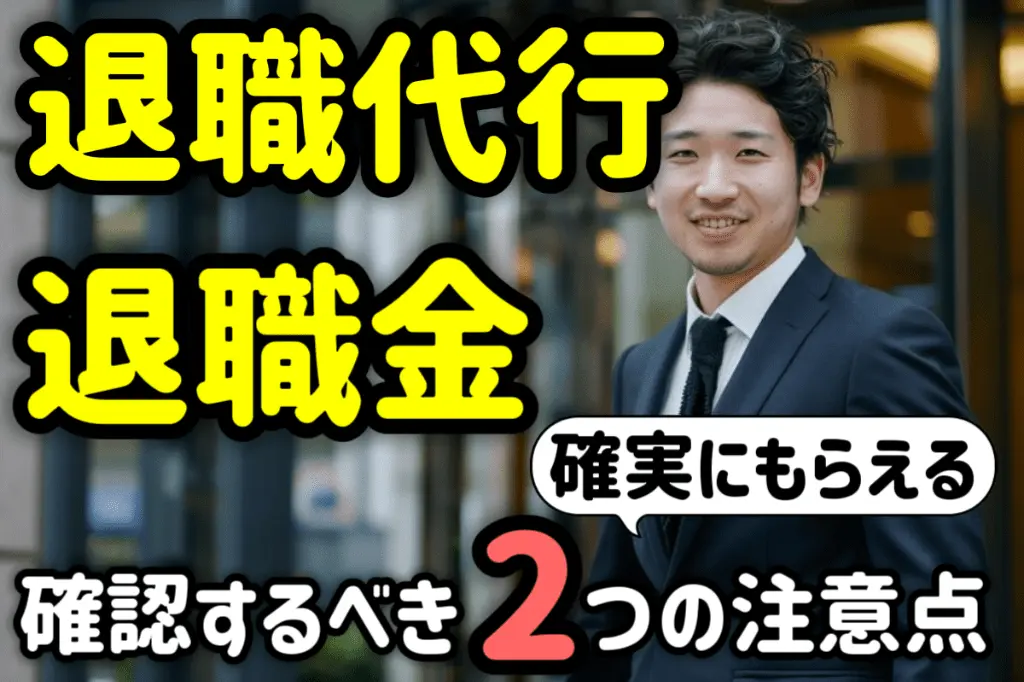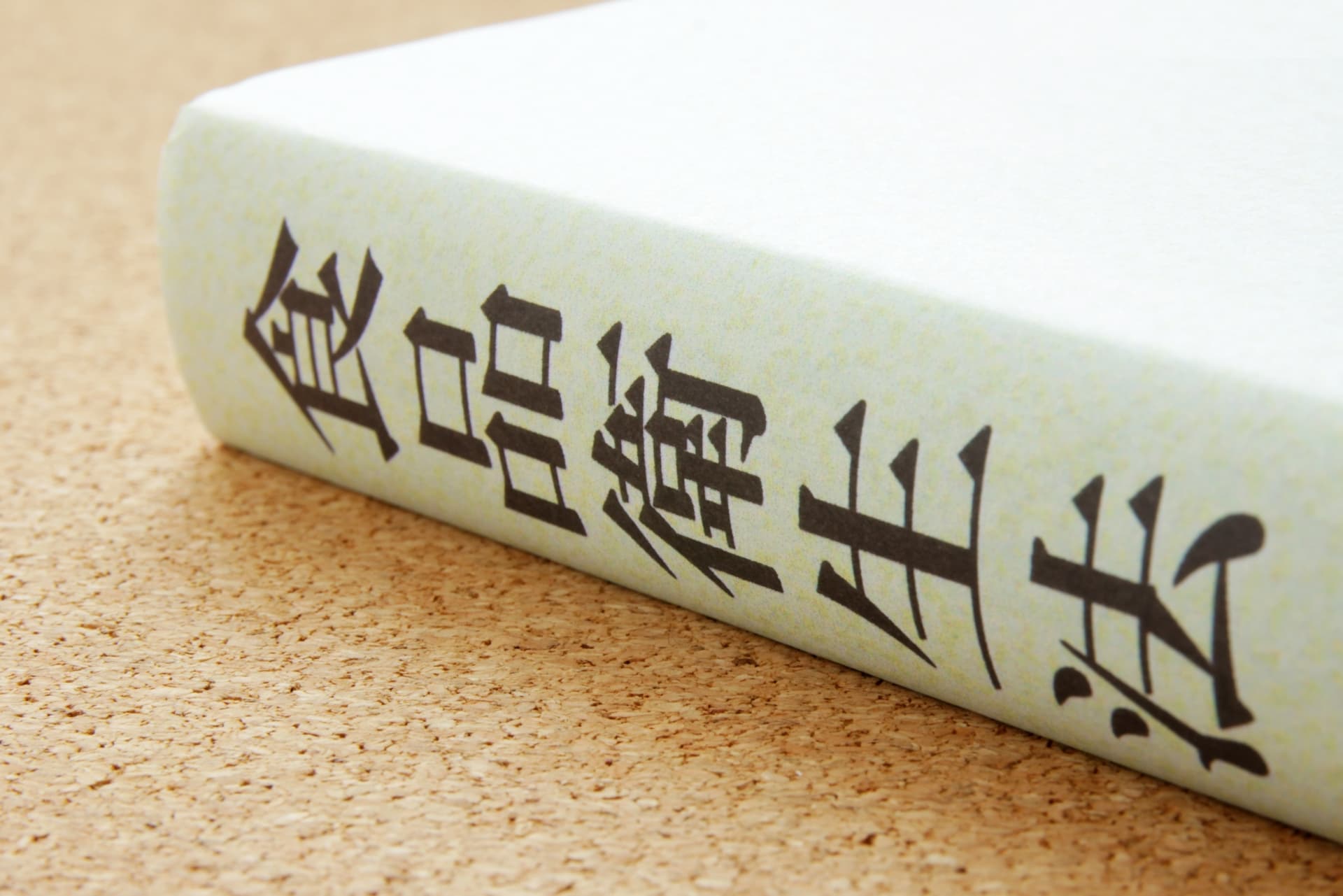資金決済法の供託金とは?支払義務の回避方法2つを弁護士が徹底解説

はじめに
アプリケーションを開発したとき、お金を稼ぐために「課金」のシステムを設けることがほとんどですよね。
お金が関係しているので、もちろん「課金」にも法律が絡んできます。
特に注意が必要なのが「資金決済法」と「供託金」。しっかり理解しておかないと、後から莫大なお金を支払わなくてはならなくなるケースもあるのです。
この記事では、資金決済法と供託金の詳細やそのルール、供託金の支払いを免れる方法などについて解説していきます。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 課金アプリのリリース前に!「資金決済法」の規定に注目
(1)資金決済法とは?
「資金決済法」は、お金の支払い・決済や移動についてルールを定めた法律です。
ビットコインなどが代表的な「暗号資産」(仮想通貨)に対して規制を設けているのもこの法律です。
「アプリ内課金の話で、資金決済法がどのように関わるのか?」と思う人もいるかもしれませんが、それは、課金によって生じるコインやポイントの定義が関係しています。
①アプリ内コインは「暗号資産」ではない
資金決済法は、「暗号資産」を以下のように明確に定義しています。
- インターネット上でやりとりできる財産的価値であること
- 不特定の物に対して代金の支払いに利用でき、かつ、円などの法定通貨と交換できること
- 電子的に記録され、移転できる
- 法定通貨やプリペイドカードではない
この定義を見ると、アプリ内コインは、暗号資産の定義から外れていることがわかります。
そのため、アプリ内コインは「暗号資産だから資金決済法が適用される」というわけではありません。
②アプリ内コインは「前払式支払手段」
アプリ内課金で入手するコインやポイントは、そのアプリにある様々なアイテムを購入するために使用するものであり、「お金を一度、コインやポイントに変換してアイテムを購入している」ということになりますよね。
このように、アプリ内でアイテムを入手するために、事前にお金を支払って変換したコインやポイントは、資金決済法において、「前払式支払手段」として定義されています。
たとえば、「Pokemon GO」の「ポケコイン」や「ドラクエウォーク」の「ジェム」などが前払式支払手段に該当します。
前払式支払手段は、資金決済法の規制対象であるため、アプリ内のコイン・ポイントには資金決済法の規制が適用されるのです。
(2)もしも違反したら…科される罰則
資金決済法が適用された場合、事業者には、さまざまな義務が発生します。
もしも、その義務を無視したり、資金決済法のルールに違反してしまったりした場合、もっとも重い罰則だと、以下のようなものが科されてしまいます。
- 最大3年の拘禁刑
- 最大300万円の罰金
のいずれか、または、両方を科される可能性があります。
このような罰則を受けることがないよう、資金決済法のルールをしっかりと把握し、正しい方法でビジネス・サービスに取り入れることが大切です。
資金決済法違反に対する罰則についてより詳しく知りたい方は、「資金決済法に違反するとどうなる?3つの事業に応じた罰則などを解説」もご参照ください。
2 アプリ内コイン・ポイントは「前払式支払手段」
先ほどご紹介した通り、アプリ内コイン・ポイントは、「前払支払手段」というものに分類されます。
いったい、どのようなものなのか、詳しく解説していきましょう。
(1)前払式支払手段とは?
「前払式支払手段」とは、ユーザーがお金を支払って購入し、それを用いて商品などを購入できるもののことです。
たとえば、LINEコインの場合、先にLINEコインを購入し、そのコインを使ってスタンプなどを入手する流れになっています。このような流れで商品を入手するコインやポイントが「前払式支払手段」であり、SuicaやPASMOなどが有名です。
具体的には、以下の3点すべてに合致しているものを「前払式支払手段」といいます。
- 金額等の財産的価値が記載・記録されること(価値の保存)
- 対価を得て発行されること(対価発行)
- 代価の支払いなどに使用できること(権利行使)
たとえば、あらかじめ現金を支払っておき、後から商品の支払いに使用する商品券やカタログギフト券、インターネットで利用できるプリペイドカードなどがこの条件に該当し、アプリ内のコインやポイントも、この前払式支払手段となります。
(2)「自家型前払式支払手段」と「第三者型前払式支払手段」
「前払式支払手段」は、利用方法によって以下の2つに分けられます。
- 自家型前払式支払手段
- 第三者型前払式支払手段
①自家型前払式支払手段
「自家型前払式支払手段」とは、そのコイン等を発行している事業者との関係でのみ使用できるものをいいます。
アプリ内課金によるコインやポイントは、一般的には、そのアプリ内でしか使用できないため、自家型前払式支払手段に該当します。
「自家型」の場合、毎年3月末か9月末に、発行している通貨の未使用残高が1,000万円を超えない限り、資金決済法の規制対象にはなりません。
1,000万円を超えると、管轄する財務(支)局長等に対して、自家型前払式支払手段発行者として届出をする義務が発生します。
②第三者型前払式支払手段
「第三者型前払式支払手段」とは、発行している事業者以外との関係でも、コインやポイントを利用できるものをいいます。
たとえば、交通系電子マネーの「Suica」は、電車だけでなくコンビニや自動販売機での支払いに利用できるため、「第三者型前払式支払手段」に分類されます。
なお、「第三者型」は、財務局長等へ登録した法人のみが発行できるものであり、誰でも気軽に発行できるものではありません。
(3)前払式支払手段発行者に課される義務
前払式支払手段の発行者には、いくつかの義務が課されます。主に以下の2つです。
- 情報の提供義務
- 発行保証金の供託等
①情報の提供義務
1つ目の義務が、情報の提供義務です。
前払式支払手段を発行する場合、発行した券の裏面や公式Webサイトなどで、さまざまな情報を掲載する義務があります。
掲載する情報は、発行者の氏名・商号・名称や利用者からの苦情相談窓口の連絡先・所在地など、もしもトラブルが起こったときに消費者にとって必要となる情報がほとんどです。
②発行保証金(供託金)の供託義務
「発行保証金(供託金)の供託義務」とは、万が一、サービス終了などで前払式支払手段が利用できなくなったときに備えて、ユーザーへの保証とするため、国家機関である供託所(法務局や地方法務局など)にお金(発行保証金・供託金)を預けておく義務のことです。
2016年にLINEが関東財務局から立ち入り検査を受けたことが話題になりましたが、その争点になったのが、この供託義務についてでした。
このことから、発行保証金(供託金)の供託義務は、LINEのような大手企業・サービスでもトラブルが起こりえるような、解釈が難しい義務だといえます。
いったいどのようなものなのか、次の項目で詳しく解説していきます。
3 前払式支払手段発行者が支払うべき「供託金」とは?
(1)供託金とは?
先ほど解説した通り、「供託金」は、会社の倒産やサービスの提供終了などの事態に備えて、供託所に預けておくお金のことです。「自家型」「第三者型」に関わらず、一定以上の基準を超えた場合、必ず供託する必要があります。
前払式支払手段は、実物の商品を購入する前に、現金を商品券やゲームコインなどに変換しておく方法ですが、会社の倒産などで商品券やゲームコインなどが使える場所・機会がなくなると、消費者はあらかじめ変換しておいた現金分の商品を手に入れられなくなってしまいます。
そうしたリスクから消費者を保護するために、前払式支払手段の発行者には供託金を支払う義務が設けられており、もしものときは、この供託金から消費者に対してお金が戻されることになります。
(2)供託金を支払わなければならないケースは?
それでは、供託金を支払う「一定の基準」とはどのようなものなのでしょうか。
- 残高の目安
- 有効期限の目安
2つの目安を解説していきます。
①残高の目安
3月末か9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その半額に相当する額を最寄りの供託所に供託する必要があります。
未使用残高とは、現金からゲーム内コインなどに変換した後、まだ利用されていないゲーム内コインのこと。
たとえば、1コイン100円という料金設定だとすると、3月末(または9月末)の時点で、購入後に使用されていないコインが10万コイン(1000万円分)あると、供託義務が発生することになります。
それでは、なぜ供託義務に、このような残高の目安があるのでしょうか。
考えられる理由の1つとして、多くの消費者に影響を与えることで起こりうる社会的混乱をある程度防ぐことが挙げられます。
多額の未使用残高がある前払式支払手段は、当然利用者も多く、もし倒産やサービス終了などで利用できなくなった場合、保証や払い戻しなどで社会的な混乱が生じるかもしれません。
このことから、多くの消費者の利益を保護するために、1,000万円をボーダーとして供託金を供託するよう定められていると考えられるでしょう。
さて、ここで注意が必要なのが、有料コインと無料配布コインの管理・扱いです。
ゲームアプリなどの場合、「新規登録者にプレゼント」などとしてゲーム内コインを無料配布することがあります。
供託義務の対象となるのは、前払式支払手段に該当するコイン(有料コイン)であり、無料配布コインは対象となりません。
しかし、有料コインと無料配布コインを分けずにまとめて管理していた場合、未使用で残っているコインが無料か有料か判断できないため、すべて有料コインとして換算されてしまいます。
たとえば、3月末に有料コインが800万円分で無料配布コインが200万円分、未使用残高として残っていたケースを考えてみましょう。
有料・無料それぞれ分けて管理していれば供託義務は発生しませんが、まとめて管理していた場合、トータルで1,000万円となるため、供託金を支払う必要があります。
そのため、無料配布コインと有料コインは分けて管理し、ユーザーにもそれぞれがいくら残っているのか表示できるよう、システムを組んでおいてください。
②有効期限の目安
前払式支払手段には、有効期限が設けられていることがほとんどです。
「2019年12月31日まで有効」などと書いてある商品券を思い浮かべていただければわかりやすいかもしれません。
供託義務が発生するのは有効期限が6ヶ月を超えているものと定められています。
有効期限が6ヶ月前を超えていないものは、前払式支払手段にあたるものの、供託義務の適用は除外されます。
つまり、前払式支払手段の有効期限が6ヶ月を超えていなければ、供託義務は発生しません。
4 供託金の支払を回避する方法
それでは、供託金の支払を回避する方法は、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。
(1)利用規約に、コイン・ポイントの有効期限を書いておく
先ほど解説した通り、前払式支払手段の有効期限を6ヶ月以内と定義しておけば、供託義務は発生しません。
アプリ内のコインやポイントに有効期限を設けるときは、利用規約に「コインの利用可能期間は、発行してから180日以内とする」などと書いておけば問題ないでしょう。
また、ユーザーのマイページなどで、コインやポイントがいつ失効するのか表示しておけば、ユーザーは有効期限が切れる前にコインを使い切るために、アプリを積極的に利用するはずです。
ユーザーが積極的にアプリを利用すれば、追加で課金することも考えられ、ひいてはアプリそのものの活性化にもつながると期待できます。
【法命題:前払式支払手段の有効期限・消費順序(有償優先)・失効の取扱いは約款等で明確に定め、利用者へ周知すべきである。/根拠条文:資金決済法(business-legal.csv)】
(2)ポイント消費を促すイベントを開催する
これは確実な方法ではありませんが、ポイント消費を促すイベントを開催することもひとつの手です。もしも、何らかの理由で有効期限を設けることが難しい場合は、この方法を取ってみましょう。 供託義務が発生するか否かを判断される3月末か9月末(基準日)の前に、未使用残高が1,000万円を下回るよう、イベントを開催してみましょう。 ただし、この方法を取るときは、有料ポイントと無料ポイントを分けて管理しておく必要があります。 実は、有料ポイントと無料ポイントを分けずに管理していた場合、その全額が「未使用残高」として換算されてしまいます。 本来であれば、発行保証金を支払わなくてもよいケースであっても、無料ポイント分が上乗せされ、支払わざるを得なくなってしまうこともあるのです。
詳しくは弊所記事の「資金決済法にいう「6ヶ月」とは?前払式支払手段の有効期限を解説!」も御覧ください。
5 アプリのリリース先のルールに注意
先ほど、アプリのコインに6ヶ月以内の有効期限を設ければ供託金を支払う必要はない、と解説しましたが、実はアプリのリリース先によっては、有効期限をそもそも設けられない場合があるので注意が必要です。
アプリをリリースするときは、以下の2つが主なリリース先の候補となります。
- App store
- Google play
このうち、「App Store」の「App Store Reviewガイドライン」には、以下のような規定があります。
App内課金で購入されたクレジットやゲーム内通貨に有効期限を設定することはできません。
(出典:2019年9月12日『App Store Reviewガイドライン』)
一方、Google Playの「Google Play デベロッパー販売 / 配布契約」(2019年11月5日発効)には、そのような規定がありません。
つまり、App Storeにアプリをリリースする場合、コインに有効期限を設けることができないため、3月末か9月末の時点で未使用残高が1,000万円を超えると、確実に供託金を支払う必要があります。
もちろん、アプリのリリース先をGoogle playのみとすることも可能ですが、将来的にApp Storeにもアプリをリリースしたい場合は、以下のような流れでリリースを行う方法が考えられます。
- 最初は6ヶ月有効期限つきでコインを発行できるGoogle playにアプリをリリースし、お金を貯める
- お金がある程度貯まってきたタイミングで、App Storeにもアプリをリリースする
- Google play版とApp Store版でルールが異なる問題があるため、ルールを統一し、コインの有効期限を撤廃する
このように、供託金の支払いを回避、もしくは支払っても問題のない体制にしておくためには、あらかじめ様々な方法・スケジュールを検討しておく必要があるのです。
とはいえ、マーケティング等の観点から、優先してApp Storeにアプリをリリースしたいケースも考えられます。
そのような場合は、アプリのリリース前から、コイン消費を促すイベントをいくつか考えておいてください。
先ほど解説したように、有料コインが優先的に消費されるシステムを構築するとともに、コイン消費が期待できるイベントを積極的に開催することで、供託義務が回避できる可能性があります。
ただ、このような対策を講じても、供託義務を回避しきれなかった場合は、必ず供託金を支払いましょう。
それでは、供託金を支払う場合、具体的にはどのような流れで行うのでしょうか。
6 供託金の納付手順
供託金は、支払義務が発生した翌日(4月1日か10月1日)から2ヶ月以内に供託する必要があります。
なお、初めて供託義務が発生したときは、同時に「前払式支払手段の発行届出書」等を届出る必要があるので、注意しておきましょう。
供託金を納付する基本的な流れは以下の通りです。
- 窓口か郵送、オンラインで供託の申請を行う
- 納付情報を取得する
- 各納付手段を用いて納付する
- 供託書正本が交付(郵送)される
詳しく解説していきます。
(1)窓口か郵送、オンラインで供託の申請を行う
まずは、供託を行うことを、供託所などに申請する必要があります。
申請方法は、
- 窓口
- 郵送
- オンライン
の3種類です。
①窓口
最寄りの供託所(法務局)に直接訪問し、窓口で申請する方法です。
供託申請をするときには、主に以下のようなものが必要になります。
- OCR用供託書
- 資格証明書(または登記事項証明書、作成日から3ヶ月以内)
なお、供託書を記入するときは、法務省の見本を参考にしてください。
②郵送
納付方法の希望を記載した紙とともに、以下の書類等を供託所に郵送してください。
-
- OCR用供託書(折り曲げると使用できません)
- 資格証明書(登記事項証明書など、作成日から3ヶ月以内)
- 返信用封筒(定形外、A4判が入る大きさ)と郵券
※供託書正本などを郵送するため
-
- 返信用封筒(定形)と郵券
※供託受理決定通知書(振込方式や電子納付の場合)や振込依頼書(振込方式の場合)など、供託金を納付するために必要な書類を郵送するため
- 送付先や電話番号、納付方法を記載したメモ
③オンライン
PCを用いて、申請を行う方法です。
方法としては、
の2種類がありますが、どちらでも供託申請を行うことができます。
ただし、オンライン申請の場合、供託金の納付方法は電子納付のみとなります。
電子納付はATMやインターネットバンキングを利用して納付する方法です。発行保証金を供託する場合、最低でも500万円を供託するため、100万円までの取引額上限が設けられていることが多いATMでは振り込むことができません。
インターネットバンキングで取引額の上限を高く設けている場合は電子納付を利用できる場合もありますが、オンライン申請を行う前に、自社の供託金の額を計算し、インターネットバンキングで納付できるか確認しておいてください。
オンライン申請を利用する際は、登記・供託オンライン申請システムの申請者情報の登録をして、申請者IDとパスワードを設定する必要があります。
すでに登記手続きのオンライン申請や登記事項証明書の請求を利用している場合は、同じID・パスワードを利用できるため、改めて申請者情報の登録をする必要はありません。
(2)納付情報を取得する
①窓口で申請した場合
申請したその場で、「供託受理決定通知書」(振込方式や電子納付の場合)や「振込依頼書」(振込方式の場合)など、納付するために必要な情報が記された書類が交付されます。そのため、そのまま窓口でお金を納付することもできます。
②郵送で申請した場合
希望した納付手段に必要な情報が記された、「供託受理決定通知書」(振込方式や電子納付の場合)や「振込依頼書」(振込方式の場合)などの書類が送付されます。
③オンラインで申請した場合
「電子納付情報表示」画面で電子納付に必要な情報を確認できます。
(3)各納付手段を用いて納付する
交付(送付)された情報を用いて、供託金を納付しましょう。
納付手段は以下の4つです。
- 供託所窓口での納付
- 日本銀行本支店・代理店での納付
- 電子納付
- 振込方式
なお、供託の申請時にはすでに、供託金の納付方法について決めておく必要があります。それぞれの特徴について、把握しておいてください、
①供託所窓口での納付
供託所窓口に供託書を提出する際、現金も併せて納付する方法です。
現金の受入事務を行っている供託所であれば、窓口で供託申請するとともに、供託金をそのまま支払うことができます。なお、希望すればその他の振込方法を利用することも可能です。
現金の受入事務を行っている供託所は以下の通りです。
- 法務局・地方法務局の各本局
- 東京法務局八王子支局および福岡法務局北九州支局
上記以外の供託所では、窓口での納付ができません。そのため、それ以外の方法で納付する必要があります。
②日本銀行本支店・代理店での納付
供託所窓口に供託書を提出した後、日本銀行本支店・代理店に納付する方法です。現金の受入事務を行っていない供託所の場合、この方法を提示されます。
③電子納付
国庫金などを取り扱う金融機関のATM(ペイジー対応)やインターネットバンキングなどを利用して納付する方法です。
ただし、ATMは100万円の取引額上限が設けられていることが多いため、資金決済法で課される供託金の納付では、利用できないことがほとんどです。
供託申請を行う前に、契約しているインターネットバンキングの取引額上限の設定と、納付する供託金の額を調べ、電子納付を利用できるかどうか確認しておきましょう。
④振込方式
供託書を供託所窓口に提出(もしくは郵送)した後、供託官の指定する金融機関の口座に、供託金を納付する方法です。
金融機関の窓口で振込を行えば、取引額の上限規制などには引っ掛かりません。
(4)供託書正本が郵送される
供託所で入金が確認された後、供託書正本が交付または郵送されるので、受け取ってください。なお、申請用のソフトウェアの場合は、PCで確認できる「電子正本」も送信されます。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- 課金アプリで発行されるコインやポイントには、資金決済法が適用される
- 課金アプリのコインやポイントは、「前払式支払手段」に該当する
- 前払式支払手段は、毎年3月末か9月末の時点で、未使用残高が1,000万円を超えていた場合、その半額を「発行保証金(供託金)」として、供託所に供託する必要がある
- 「供託金」の支払いを回避したいときは、発行したコイン・ポイントに6ヶ月の有効期限を設ける
- App Storeにリリースするアプリの場合、コイン・ポイントに有効期限を設けることができない
- 供託金を納付するときは、窓口か郵送、オンラインで申請を行う
- 供託金の納付は「供託所窓口納付」「日本銀行本支店・代理店納付」「電子納付」「振込方式」の4パターンがある
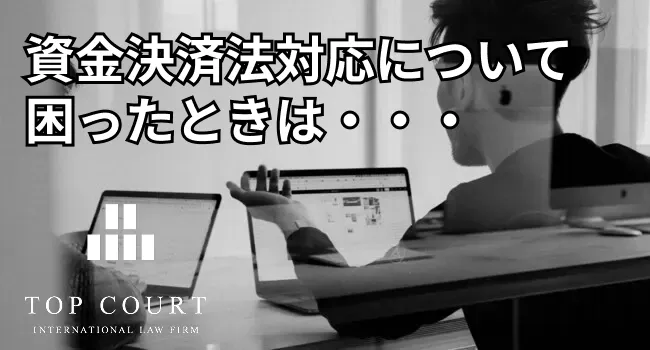
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。