ロボアドバイザーを提供する際に必要な2つの登録制度や規制を解説!

はじめに
従来、投資サービスは、銀行や証券会社などにおいて「人」が提供するサービスでした。それが現在では、通信技術やAIの発達により、「人」を介さずに、投資サービスを提供することが可能になりました。これが「ロボアドバイザー」と呼ばれるサービスです。
ロボアドバイザーを提供するためには、登録を受ける必要がありますが、そのための条件は非常に厳しいものになっています。
また、登録後においても、投資家保護の観点から、さまざまな規制が課されます。
そこで今回は、「ロボアドバイザー」と呼ばれる、自動化された投資サービスを提供する場合の法律上の規制を中心に、弁護士が詳しく解説します。
1 ロボアドバイザーとは
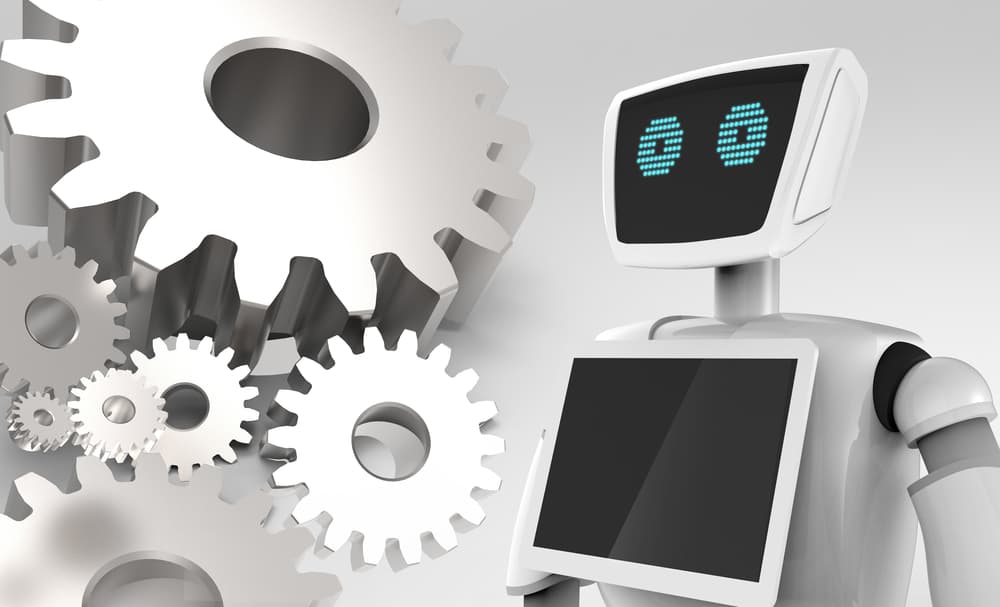
「ロボアドバイザー」とは、資産運用を自動化して行ったり、投資のアドバイスをしたりする、新しい形の投資サービスのことをいいます。
従来、投資に対するアドバイスや資産運用そのものを行う主体は「人」でした。
ロボアドバイザーは、従来の「人」ではなく、AIなどを活用した「ロボット」が資産運用などを行う主体となる点に大きな特徴があります。
ロボアドバイザーを導入する事業者からすれば、人件費などのコストが削減できるため、従来の「人」による同等のサービスよりも低価格でサービスを提供することも可能になります。
ロボアドバイザーには、大別して以下の2つのタイプがあります。
- アドバイス型
- 投資一任型
(1)アドバイス型
「アドバイス型」は、ユーザーにおいてどの程度のリスクを許容できるかをロボアドバイザーが診断し、ユーザーにとって最適となる資産運用の配分についてアドバイスを行います。ユーザーは、ロボアドバイザーによるアドバイスに従って、投資の発注や運用を行います。
また、運用中に資産の配分を変更する必要が生じた場合には、自身で資産の再配分を行います。
例えば、Webサイト上で投資に関する質問(年齢、収入、保有資産の有無など)に回答すると、AIがその回答を基に、その人に合った運用スタイルやポートフォリオの提案などを行ってくれます。
アドバイス型は、その多くが無料で利用できるため、投資に関し初心者であっても気軽に投資を始めることができます。
(2)投資一任型
「投資一任型」は、ユーザーのリスク許容度を診断したロボアドバイザーが、その結果を踏まえて、投資の発注や運用まで行ってくれるものです、
また、運用中の資産配分を最適な状態に維持するための調整(リバランス)なども自動で行ってくれます。
投資一任型は、アドバイス型とは異なり、利用するためには手数料を負担しなければなりませんが、投資の発注から運用、資産配分の変更まですべてロボアドバイザーが対応してくれるという点に特徴があります。
以上のように、ロボアドバイザーには主に2つのタイプがあり、両者の違いは、主に投資の発注や運用をユーザー自身が行うか、ロボアドバイザーが行うかという点にあります。
2 ロボアドバイザーと金融商品取引法

ロボアドバイザーには、アドバイス型と投資一任型の2つのタイプがあることは既に見たとおりですが、これらのサービスには以下のように金融商品取引法が関係してきます。
(1)アドバイス型
アドバイス型は、ユーザーの資産運用について事業者が助言するなどして、その対価を支払ってもらうことを内容としています。
アドバイス型のサービスを利用する場合には、ユーザーの投資判断に事業者が助言をすること、それに対しユーザーは事業者に報酬を支払うこと、を内容とした契約(投資顧問契約)を締結します。
このように、投資顧問契約に基づいて助言を行うことは、金融商品取引法上の投資助言・代理業にあたり、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
(2)投資一任型
投資一任型は、投資判断の全部・一部の一任に加え、投資判断に基づき投資を行うために必要とされる権限を委任されることを内容としています。
投資一任型のサービスを利用する場合には、これらの事項を定めた契約(投資一任契約)を締結します。
このように、投資一任契約に基づいて投資判断を行い、その判断に基づき有価証券やデリバティブ取引に関する権利に投資するために、金銭などの財産を運用することは、金融商品取引法上の投資運用業にあたり、アドバイス型と同様に、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
以上のように、ロボアドバイザーを提供する場合には、そのタイプに応じて、投資助言・代理業もしくは投資運用業の登録を受ける必要があるのです。
3 投資助言・代理業とは

アドバイス型ロボアドバイザーを提供する事業者は、ユーザーと投資顧問契約を結んで、その契約に基づいて投資助言サービスを提供します。
この場合、既に見たとおり、投資助言・代理業の登録が必要になるのが一般的です。
(1)業務の範囲
「投資助言」とは、投資家に対し、投資に関するアドバイスをすることをいいます。
たとえば、投資家が抱える悩みを聞いて解消してあげたり、オススメの商品を紹介したりすることが投資助言にあたります。
事業者は、アドバイスの対価として投資家から報酬の支払いを受けます。
投資助言は、あくまで「助言」をすることにとどまるため、投資家の資産を運用することはできず、最終的な投資判断は投資家に委ねられます。
また、事業者による「助言」は、成果を保証するものではないため、投資家は自らの責任で投資を行うことになります。
これに対し「代理業」とは、代理・媒介業を意味し、具体的には、投資家と他の投資顧問会社を繋げることを目的とした業務です。
そのため、投資家に対し、投資助言をすることもなければ、直接資産を運用するといったこともありません。
代理業を行う事業者は、投資家と他の投資顧問会社の間に契約が成立することにより、投資家から一定の報酬を支払ってもらえます。
このように、アドバイス型ロボアドバイザーができることは、投資助言・代理業に限られています。
(2)登録の条件
投資助言・代理業者は、投資家の資産を直接運用することはできないため、登録を受けるための条件は、投資運用業に比べると緩和されています。
具体的な条件は、主に、以下の2つです。
①財産の条件
登録を受けるためには、営業保証金として500万円を供託所(法務局)に供託しなければなりません。
「営業保証金」とは、投資家が事業者との取引で損害を被った場合の弁済原資となるものです。
営業保証金を準備できないと、登録を受けることはできないため、投資助言・代理業を行う予定の事業者は、最低でも初期費用として500万円を用意する必要があります。
②人的構成
投資助言・代理業において、備えなければならない人的構成はかなり細かく定められています。
たとえば、経営者や役員は、投資助言・代理業者として業務を公正かつ的確に遂行できるだけの十分な資質があることが必要です。
また、実際に投資判断の助言を行う者についても、金融商品の価値などに関する知識や経験を有することが求められます。
さらには、コンプライアンス担当者を設置し、同担当者にもコンプライアンス担当者としての知識や経験があることが必要です。
③体制整備
投資助言・代理業を的確に遂行するために必要とされる体制が整備されている必要があります。
たとえば、帳簿や報告書といった書類の作成・管理、リスク管理、苦情・トラブル処理といったように、各種業務に関する体制整備が可能な人員が確保されていなければなりません。
このように、投資助言・代理業の登録を受けるためには、資金面から人的構成、体制整備にわたり条件が細かく定められており、決して簡単なものではありません。
※投資助言・代理業の登録要件について詳しく知りたい方は、金融庁が出している「投資運用業等 登録手続ガイドブック 令和2年1月」をご覧ください。
(3)新たに創設される「金融サービス仲介業」との関係
令和2年(2020年)3月、金融サービスの改正に関する法律案が国会に提出されました。この法律案が施行されると、これまで銀行・証券・保険などにおいてバラバラだった仲介業を横断的にまとめた「金融サービス仲介業」という事業が創設されることになります。
金融サービス仲介業の登録を受けると、銀行や証券会社、保険会社のサービスを仲介することが可能になります。
もっとも、アドバイス型ロボアドバイザーとは異なり、金融サービス仲介業では、投資家を代理することはできず、取引を行うのはあくまで投資家本人です。
アドバイス型ロボアドバイザーの提供を予定している事業者は、自社が取り扱うサービスの範囲や業務範囲などによっては、金融サービス仲介業の登録を検討することが必要になってくるものと考えられます。
※金融サービス仲介業について詳しく知りたい方は、「金融サービス仲介業とは?法律案を基に3つのポイントを弁護士が解説」をご覧ください。
4 投資運用業とは

投資一任型ロボアドバイザーを提供する事業者は、ユーザーと投資一任契約を結び、ユーザーから資産運用に必要な権限を委任されます。
事業者は、この権限に基づいて有価証券やデリバティブ取引に投資をして、ユーザーの金銭その他の財産の運用を行います。
この場合、既に見たとおり、事業者は、投資運用業の登録を受ける必要があります。
(1)業務の範囲
投資運用業の業務の内容は、主に、以下の4つに分けられます。
- 投資法人資産運用業
- 投資一任業
- 投資信託委託業
- ファンド運用業
①投資法人資産運用業
「投資法人資産運用業」とは、登録を受けた投資法人との間で委託契約を交わし、有価証券やデリバティブ取引に投資し、資産運用を行うことをいいます。
ここでいう「投資法人」とは、資産を特定の資産に投資して運用することを目的として設立された社団法人のことをいいます。
②投資一任業
「投資一任業」とは、投資家と投資一任契約を交わし、有価証券やデリバティブ取引に投資し、資産運用を行うことをいいます。
③投資信託委託業
「投資信託委託業」とは、投資信託に係る信託財産を運用することを目的として、有価証券やデリバティブ取引に投資し、資産運用を行うことをいいます。
④ファンド運用業
「ファンド運用業」とは、集団投資スキーム持分などの権利保有者から出資などを受けた財産について、主に、有価証券やデリバティブ取引に投資し、資産運用を行うことをいいます。
投資運用業は、投資助言・代理業とは異なり、投資判断から実際の運用までを投資運用業者が行います。
そのため、投資助言・代理業に比べると、以下で見るように登録を受けるための条件も厳しくなっています。
(2)登録の条件
投資運用業の登録を受けるためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
なお、これらの条件は、登録申請時だけでなくその後も満たし続ける必要があります。
①会社・事務所の条件
投資運用業を営む会社は、以下の3点を満たしていなければなりません。
- 株式会社であること
- 取締役会設置会社であること
- 定款において「投資運用業」等が目的として記載されていること
このように、投資運用業を始めるためには、株式会社であり取締役会設置会社であることが必要です。
ここでいう「取締役会設置会社」は、3名の取締役に加え、監査役1名が必要となります。
②財産の条件
投資運用業を営む事業者は、以下の3点を満たしていなければなりません。
- 資本金が5000万円以上であること
- 純資産額が5000万円以上であること
- 決算内容、決算見込みが良好であること
資本金については、申請時に会社謄本で確認されることになります。
また、登録を受けた後に、純資産額が5000万円を下回ることとなった場合には、監督上の処分の対象となるため、注意が必要です。
決算内容や決算見込みが良好であるかどうかは、申請時に提出する直近1年間の決算書と登録後3年間の収支計画によって判断されます。
③主要株主規制
「主要株主」とは、総議決権の20%以上の議決権を保有している株主のことをいいます。主要株主において、成年被後見人などの欠格事由が認められる場合には、登録を受けることはできません。
また、主要株主になった場合や、その反対に主要株主でなくなった場合は、その旨を届出なければなりません。
④金融ADR制度への対応
「金融ADR制度」とは、投資運用業者と投資家との間に紛争が生じた場合に、裁判外で解決を図る制度です。
投資運用業者は、金融ADR制度への対応として、一般社団法人日本投資顧問業協会に入会しなければなりません。
協会への入会に伴い、事業者は入会金として100万円、会費として40万円(下限)~800万円(上限)を支払う必要があります。
なお、会費の金額に幅があるのは、投資運用業による営業収益によって、金額が異なるためです。
⑤人的構成
人的構成については、投資助言・代理業の場合と、ほぼ同じ内容になっています。
たとえば、経営者においては、投資運用業者として業務を公正かつ的確に遂行できるだけの十分な資質があることが必要になります。
また、役員においては、金融商品取引法などの規制内容を十分に理解し、それを実行に移せるだけの知識や経験、コンプライアンスやリスク管理に関する十分な知識などを有していることが求められます。
加えて、実際に資産運用を行う者についても、運用する資産に関する知識や経験を有することが必要です。
コンプライアンス担当者を設置し、同担当者にもコンプライアンス担当者としての知識や経験があることが必要であるという点も、投資助言・代理業の場合と同様です。
⑥体制整備
投資運用業を営むにあたって、一定の体制整備が可能となる人員が確保されていることが必要です。
たとえば、帳簿や報告書といった書類の作成・管理、運用資産の分別管理やリスク管理、苦情・トラブル処理や内部監査などの体制整備が可能となる人員が確保されていなければなりません。
このように、投資運用業の登録を受けるには、数多くの厳しい条件をクリアする必要があります。
(3)その他の規制
投資運用業者は、登録を受けた後も、さまざまな義務を負うことになります。
登録後に投資運用業者に課される義務としては、たとえば、以下のようなものがあります。
- 善管注意義務
- 分別管理義務
- 預託の受入れの禁止
- 報告書の交付義務
①善管注意義務
「善管注意義務」とは、職業や専門家としての地位や能力などから通常期待される注意義務のことをいいます。
投資運用業者は、投資運用業者として通常期待される注意義務をもって投資運用業を行う必要があります。
投資家から一任される内容が「投資判断」や「資産運用そのもの」であることを考えると、ここでいう「注意義務」は高度なものと考えられます。
②分別管理義務
「分別管理」とは、投資家の運用財産と自社の財産を分けて管理することをいいます。
投資運用業者は、運用財産と自社の財産が混同することがないように、分別して管理することが義務付けられています。
③預託の受入れの禁止
投資運用業者は、原則として、投資家から金銭や有価証券の預託を受けてはなりません。
もっとも、投資運用業者が投資家のために行う有価証券の売買やデリバティブ取引の決済に必要な場合は、預託を受け入れることが可能です。
④報告書の交付義務
投資運用業者は、原則として、定期的に運用報告書を作成し、運用財産に関する権利者に交付しなければなりません。
また、運用報告書を作成した場合には、内閣総理大臣に届け出る必要があります。
このように、投資運用業者は登録を受けた後も、投資家を保護する必要性から、さまざまな義務を課されることになります。
また、業態によっては、金融商品販売業者等や第一種金融商品取引業にあたる可能性があるため、その場合には、上記に加え、金融商品販売業者等や第一種金融商品取引業に課される義務を負うことになります。
5 登録を回避することは可能か

これまで見てきたように、ロボアドバイザーを提供する際に必要となる登録条件は、決して緩いものではありません。
登録を回避する形でロボアドバイザーを提供できないだろうか、と考える事業者の方もいらっしゃるかもしれません。
以下では、登録を回避するための3つのスキームについて見ていきます。
(1)無償での投資助言業務
登録が必要となる投資助言業務(アドバイス型ロボアドバイザー)は、有償であることが前提になっています。
そうすると、仮に投資助言業務が無償で行われる場合には、登録を受ける必要がなくなります。
証券会社や金融機関の中には、多種多様なサービスの1つとしてロボアドバイザーを導入して、無償で最適のポートフォリオを提案しているところもあります。
このような形で、付随的にアドバイス型ロボアドバイザーを無償で提供することも可能になると考えられます。
もっとも、受け取る対価の名目を変えるなどしても、実質において投資助言業務への対価とみなされる場合には、登録を求められる可能性が高いため、注意が必要です。
(2)不特定多数の者を対象として投資判断を提供する
不特定多数の人が、随時購入可能な文書により助言をすることは、投資助言業にあたらないとされています。
たとえば、週刊誌や新聞、コンピュータソフトウェアといった媒体を使って助言をすることが挙げられます。
もっとも、投資分析ツールなどのコンピューターソフトであっても、登録を受けた会員のみが購入できるようになっていたり、利用に際し継続的に投資情報に関するデータやその他のサポートなどを受ける必要があるときには、登録が必要と判断される可能性があります。
(3)有価証券以外の金融商品について助言する
有価証券以外の金融商品を対象として、その価値や金融指標の動向などを助言するにとどまる場合は、投資助言業務にあたらないと考えられます。
もっとも、助言の範囲が投資判断にまで及ぶと、投資助言・代理業の登録が必要になるため、注意が必要です。
たとえば、FX取引の対象になる「通貨」は、有価証券以外の金融商品にあたります。
この場合、「米ドルが上昇するでしょう」「ユーロが下落するでしょう」といった助言にとどまるかぎり、投資助言業務にあたらないと考えられます。
ですが、「米ドルが上昇しそうなので、今が買いどきです」といったように助言の内容が投資判断にまで及ぶ場合には、投資助言・代理業の登録が必要になります。
このように、登録を回避するための3つのスキームを見てきましたが、ロボアドバイザーを提供するサービスにおいては、あまり現実的ではないかもしれません。
とはいえ、他のサービスに付随してロボアドバイザーを提供するような場合には検討の余地があるといえるでしょう。
6 小括

ロボアドバイザーを提供する事業者は、業態に応じて、投資助言・代理業や投資運用業の登録を受ける必要があります。
アドバイス型と投資一任型とでは、登録を受けるための条件や登録後に課される規制に違いがあるうえ、条件や規制もかなり細かく定められています。
適切にサービスを展開していくためには、専門家に相談することも選択肢の一つとして検討すべき分野であるといえます。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 「ロボアドバイザー」とは、投資家に合わせて自動で資産運用を行ったり、投資のアドバイスをしたりする投資サービスのことをいう
- ロボアドバイザーには、主に、①アドバイス型、②投資一任型の2種類がある
- アドバイス型ロボアドバイザーを提供するためには、投資助言・代理業の登録が必要である
- 投資一任型ロボアドバイザーを提供するためには、投資運用業の登録が必要である
- 投資運用業の登録条件は、①会社・事務所の条件、②財産の条件、③主要株主規制、④金融ADR制度への対応、⑤人的構成、⑥体制整備に分類される
- 投資助言・代理業、投資運用業の登録を回避するスキームとして、①無償での投資助言業務、②不特定多数の者を対象とする投資判断の提供、③有価証券以外の金融商品を対象とした助言が考えられる




