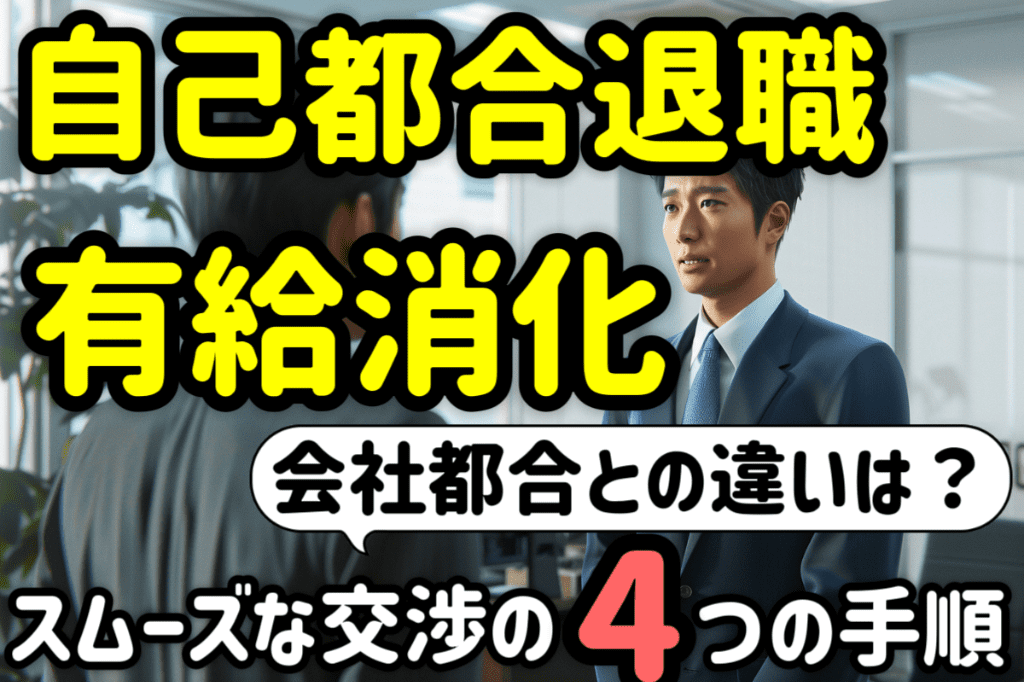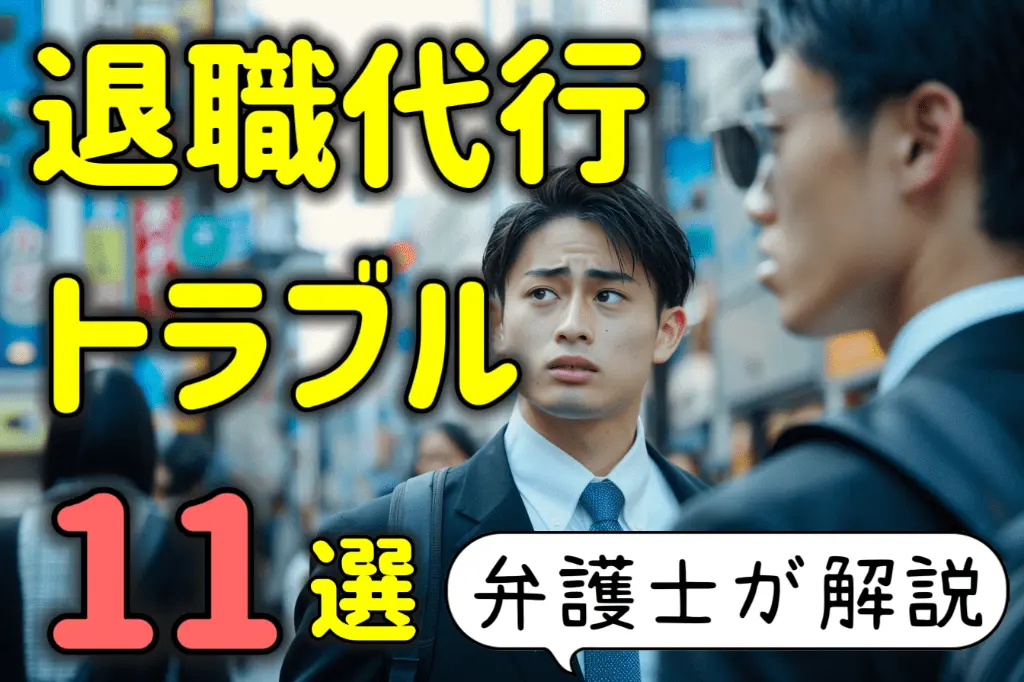資金決済法が規制する「前払式支払手段」とは?2つの規制などを解説

はじめに
ここ数年の間に、ポイントサービス国内市場の規模は大きく拡大しました。現在では、さまざまなサービスにポイントサービスが付いていることも多く、ポイントを目的としてサービスを利用する消費者も増えています。
もっとも、一定の条件を満たしたポイントなどは、資金決済法にいう「前払式支払手段」にあたり、同法の規制対象になるため、注意が必要です。
自社のサービスにポイントサービスなどを導入しようと検討している事業者は、発行しようとするポイントなどが「前払式支払手段」にあたるかどうか、あたる場合にどのような規制を課されるのか、などをきちんと確認する必要があるのです。
この記事では、資金決済法にいう「前払式支払手段」について、関係する規制にも触れながら、弁護士が詳しく解説します。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 前払式支払手段の種類

前払式支払手段にあたるといえるためには、一定の条件を満たしていることが必要であり、また、発行形態の違いにより、前払式支払手段には2つの種類があります。
(1)前払式支払手段にあたるための条件
前払式支払手段にあたるといえるためには、以下の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。
- 金額やサービスの数量が記載、記録されている
- 記載されている金額やサービスの数量に応ずる対価が支払われている
- 代価の支払いなどに使用できる
たとえば、SuicaやPasmoといった交通系電子マネー、ゲーム内で使うポイントやコイン、商品券などは前払式支払手段にあたります。
(2)前払式支払手段の2つの種類
前払式支払手段は、発行形態に応じて、以下の2つの種類があります。
- 自家型
- 第三者型
①自家型
「自家型」とは、前払式支払手段を発行している事業者が提供するサービスの中でしか利用できないものをいいます。
たとえば、ゲーム内でしか利用できないポイントやコイン、発行事業者との関係でのみ利用できる商品券などは、自家型前払式支払手段です。
②第三者型
「第三者型」とは、前払式支払手段を発行している事業者に限られず、他の事業者との間でも利用できるものをいいます。
たとえば、先に見た交通系電子マネー、加盟店の全店舗で使用できる商品券などは、第三者型前払式支払手段です。
このように、前払式支払手段は利用可能な範囲によって、自家型と第三者型とに分かれています。
2 前払式支払手段に関係する規制

資金決済法は、利用者保護、決済システムの安全性の向上などを目的として、前払式支払手段を発行する事業者に対し、さまざまな規制を課しています。
(1)自家型前払式支払手段の発行者に課される規制
自家型の前払式支払手段を発行する場合、基準時(毎年3月末もしくは9月末)において、前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えているときは、財務局長などに届出をしなければなりません。
ここでいう「未使用残高」とは、対価を支払って得た前払式支払手段のうち、まだ使用されていないものをいいます。
届出書には、事業者の名称や住所、資本金、そして、基準日における未使用残高など、多くの事項を記載する必要があります。
※自家型前払式支払手段の発行届出書の書式は、金融庁の「前払式発行手段に関する内閣府令別紙様式01」からダウンロードできます。
(2)第三者型前払式支払手段の発行者に課される規制
第三者型の前払式支払手段を発行する場合、事業者は、未使用残高に関わらず、財務局長から登録を受けなければ、前払式支払手段を発行することはできません。
登録申請書には、自家型における届出書と同様、事業者の名称や住所、資本金などを記載しなければならず、そのほかにも、役員の氏名や前払式支払手段の支払可能金額などを記載する必要があります。
※第三者型前払式支払手段発行者としての登録申請書の書式は、金融庁の「前払式支払手段に関する内閣府令別紙様式03」からダウンロードできます。
(3)種類を問わず前払式支払手段の発行者に課される規制
自家型であると第三者型であるとを問わず、前払式支払手段を発行する事業者に共通して課される規制もあります。
代表的な規制は、以下の2つの規制です。
- 発行保証金の供託
- 払い戻し義務
このほかにも、たとえば、事業者の名称、前払式支払手段の支払可能金額などの情報をユーザーに提供することや、基準日ごとに一定の事項を記載した報告書を内閣総理大臣に提出することが義務付けられています。
以下では、代表的な規制である2つの規制について、見ていきましょう。
3 発行保証金の供託

前払式支払手段を発行する事業者は、自家型か第三者型かに関係なく、一定の条件を満たすと、発行保証金を供託しなければなりません。
(1)発行保証金の供託義務が発生する条件
発行した前払式支払手段について、基準日(毎年3月末もしくは9月末)における未使用残高が1,000万円を超えるときは、未使用残高の2分の1以上にあたる額の発行保証金を最寄りの法務局に供託しなければなりません。
つまり、事業者は、最低でも500万円を発行保証金として供託しなければならないのです。
たとえば、前払式支払手段を発行した事業者が経営不振で倒産してしまった場合、サービスが終了し、未使用となっている前払式支払手段を使うことができなくなることが想定されます。
事業者に発行保証金を供託させることで、このような事態が生じた場合も、供託金からユーザーに対して未使用分を返金することが可能になるわけです。
もっとも、銀行などとの間で発行保証金保全契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出た場合、または、信託会社などとの間で発行保証金信託契約を締結し、内閣総理大臣から承認を得た場合には、供託に代えることができます。
(2)供託義務を回避するために、前払式支払手段に6ヵ月以内の有効期限を設ける
スタートアップなど、一般的に経済的基盤が強くない事業者にとって、発行保証金を準備することは簡単なことではありません。
できることなら、供託義務を回避したいと考えるのが自然でしょう。
前払式支払手段には、有効期限が付されることが少なくありませんが、資金決済法は、有効期限が6ヵ月を超えていないものについては、供託義務を課さないこととしています。
このように、前払式支払手段に6ヵ月を超えない有効期限を設けることで、事業者は供託義務を回避することが可能です。
※供託義務やその回避方法について、詳しく知りたい方は、「資金決済法の供託金とは?支払義務の回避方法2つを弁護士が徹底解説」をご覧ください。
4 前払式支払手段の払い戻し(返金)

前払式支払手段を発行する以上、ユーザーから未使用分について返金を求められた場合の対応について、きちんを整理しておく必要があります。
資金決済法は、前払式支払手段を払い戻すことができる3つのケースを挙げており、これ以外のケースでは前払式支払手段を払い戻すことはできません。
(1)払い戻すことができるケース
前払式支払手段を払い戻すことができるケースは、以下の3つのケースです。
- 前払式支払手段の発行業務を廃止した場合
- 払い戻す金額が少額である場合
- ユーザーのやむを得ない事情による場合
①前払式支払手段の発行業務を廃止した場合
事業者が、前払式支払手段の発行を廃止すると、前払式支払手段を使用できなくなります。
このような場合に、未使用となっている前払式支払手段の払い戻しをユーザーが請求できないのは、不合理です。
そのため、事業者が前払式支払手段の発行業務を廃止した場合には、ユーザーに対し払い戻すことができます。
②払い戻す金額が少額である場合
払い戻す金額が少額である場合には、事業者の判断で前払式支払手段を払い戻すことができます。
払い戻す金額が少額といえるかどうかは、
- 基準期間における払い戻しの総額が、直前の基準期間の発行額の100分の20を超えない
- 基準期間における払い戻しの総額が、直前の基準日未使用残高の100分の5を超えない
という2つの基準によって判断されます。
③ユーザーのやむを得ない事情による場合
「やむを得ない事情」といえるかどうかは、事業者が個別のケースで具体的に判断することになるため、ハッキリとした基準のようなものはありません。
(2)払い戻すときの注意点
上に見た3つのケースにあてはまらない場合に、払い戻しをすると、以下の2つの法律に違反する可能性があるため、注意が必要です。
- 出資法
- 銀行法
①出資法
「出資法」とは、業者がお金を貸し付ける際の利息やお金を預かる業務などを規制する法律です。
この点、預貯金などのためにお金を預かる業務は、銀行など法律で認められた一定の者にしかできないこととされています。
仮に、前払式支払手段を自由に払い戻すことができると、ユーザーが購入した前払式支払手段をそのまま払い戻すことが可能となり、元本保証と見られる可能性が出てくるのです。
そうすると、出資法上の「預り金」にあたり、出資法に違反する可能性があります。
②銀行法
「銀行法」とは、銀行業を行う事業者を対象に、さまざまな規制を設けている法律です。銀行法は、現金以外の方法で決済する「為替取引」について、免許制を採っています。
前払式支払手段について自由に払い戻すことができてしまうと、送金手段に前払式支払手段が使われる可能性があり、その場合、銀行法上の「為替取引」にあたる可能性があるのです。
以上のように、前払式支払手段の払い戻しは、無制限にできるものではありません。
そのため、払い戻しができるケースにあたるかどうかをきちんと確認することが大切です。
※前払式支払手段の払い戻しについて、詳しく知りたい方は、「前払式支払手段で払い戻しはできる?資金決済法の3つのルールを解説」をご覧ください。
5 ポイントサービスと前払式支払手段

ポイントサービスを導入しているサービスが増えてきており、これからの導入を検討している事業者の方もいらっしゃると思います。
ポイントサービスを導入する場合には、まず始めに、発行を予定しているポイントが前払式支払手段にあたるかどうかをきちんと確認することが大切です。
いまいちど、前払式支払手段にあたるための条件について、見ておきましょう。
前払式支払手段にあたるための条件は、以下の3つです。
- 金額やサービスの数量が記載、記録されている
- 記載されている金額やサービスの数量に応ずる対価が支払われている
- 代価の支払いなどに使用できる
これらの条件をすべて満たす場合、発行を予定しているポイントは前払式支払手段にあたります。
発行予定のポイントが前払式支払手段にあたる場合には、先に見たように、発行形態に応じて課される規制をきちんと遵守することが必要です。
6 小括
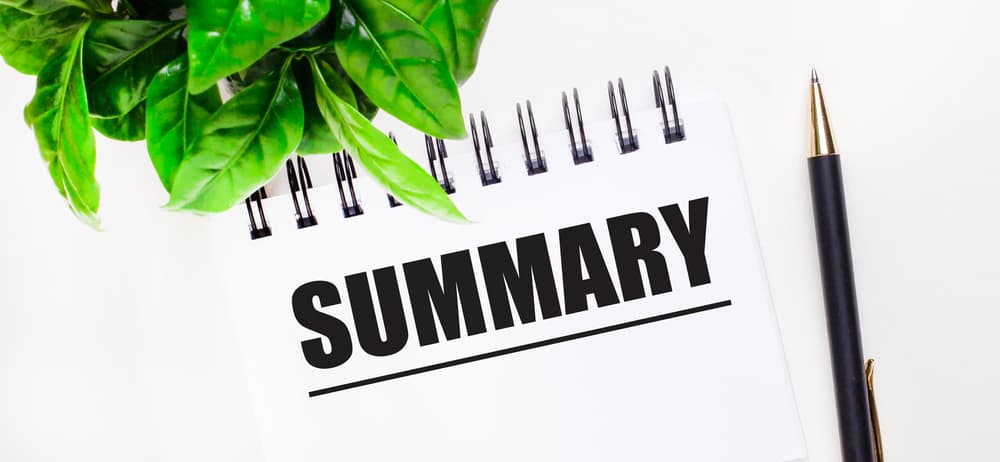
あらゆるサービスにおいて、ポイントサービスが導入されている昨今ですが、ポイントが前払式支払手段にあたる場合には、資金決済法による規制を受けることになります。
これからポイントサービスを導入しようと検討している事業者の方は、自社が発行するポイントが前払式支払手段にあたるかどうか、自社に課される規制はどのような内容の規制か、などをきちんと理解したうえで、進めていくようにしましょう。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 前払式支払手段にあたるといえるためには、①金額やサービスの数量が記録されている、②対価が支払われている、③代価の支払いに使用できる、という3つの条件を満たしていることが必要である
- 前払式支払手段には、①自家型、②第三者型の2つの種類がある
- 自家型を発行する場合、基準時における未使用残高が1,000万円を超えるときは、財務局長などに届け出なければならない
- 第三者型は、財務局長から登録を受けなければ、発行することはできない
- 前払式支払手段発行者に対しては、①発行保証金の供託義務、②払い戻し義務が課される
- 供託義務を回避する方法として、前払式支払手段に6ヵ月以内の有効期限を設けることが挙げられる
- 前払式支払手段は、①事業者が発行業務を廃止した場合、②払い戻す金額が少額である場合、③ユーザーのやむを得ない事情による場合には払い戻すことができる
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。