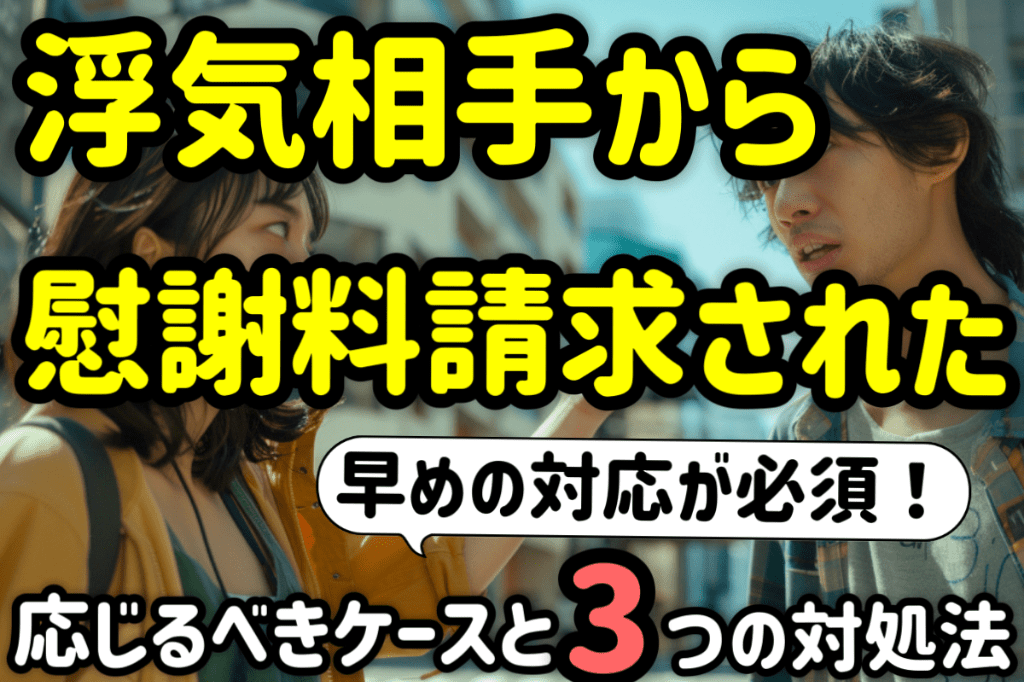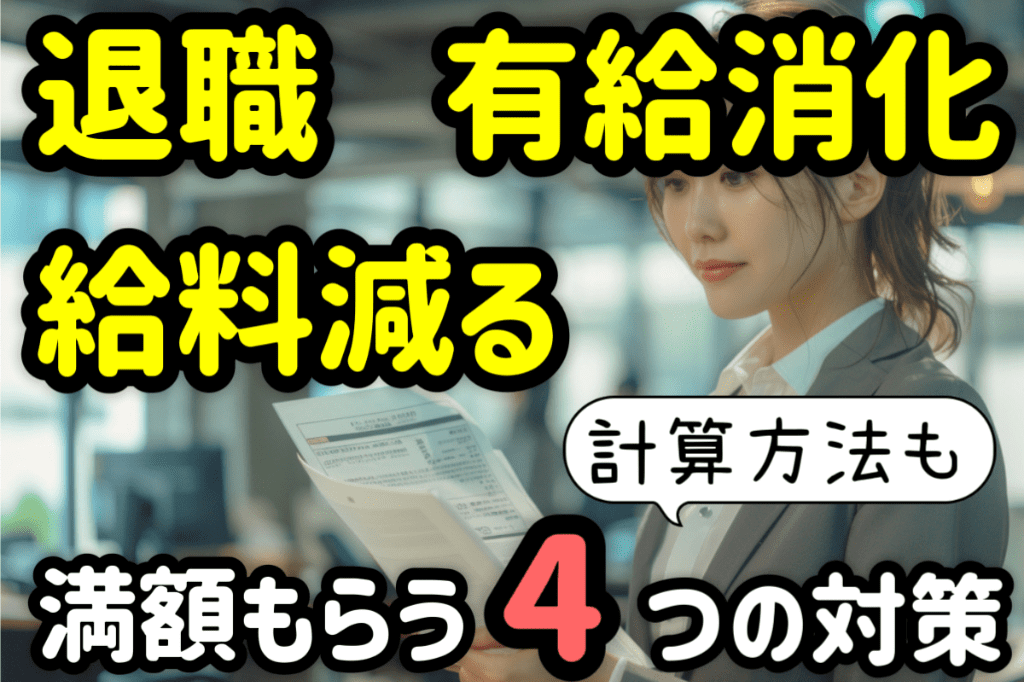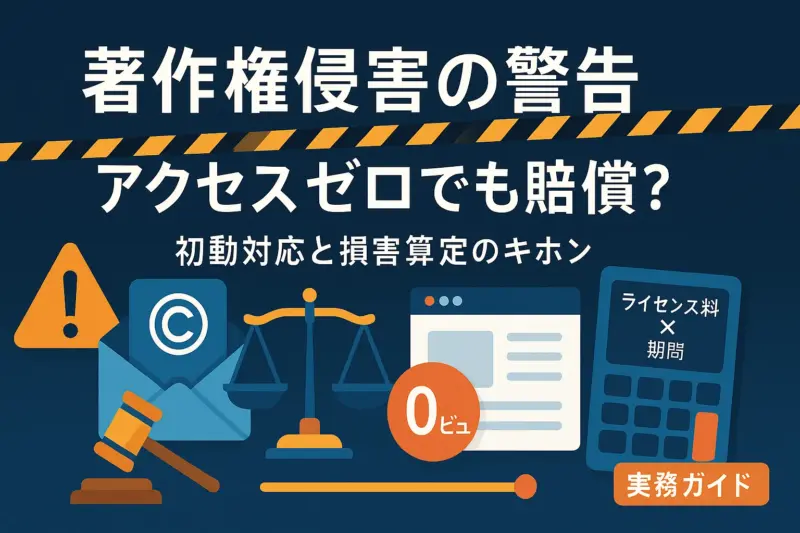著作者人格権とは?4つの権利内容を弁護士がわかりやすく解説!
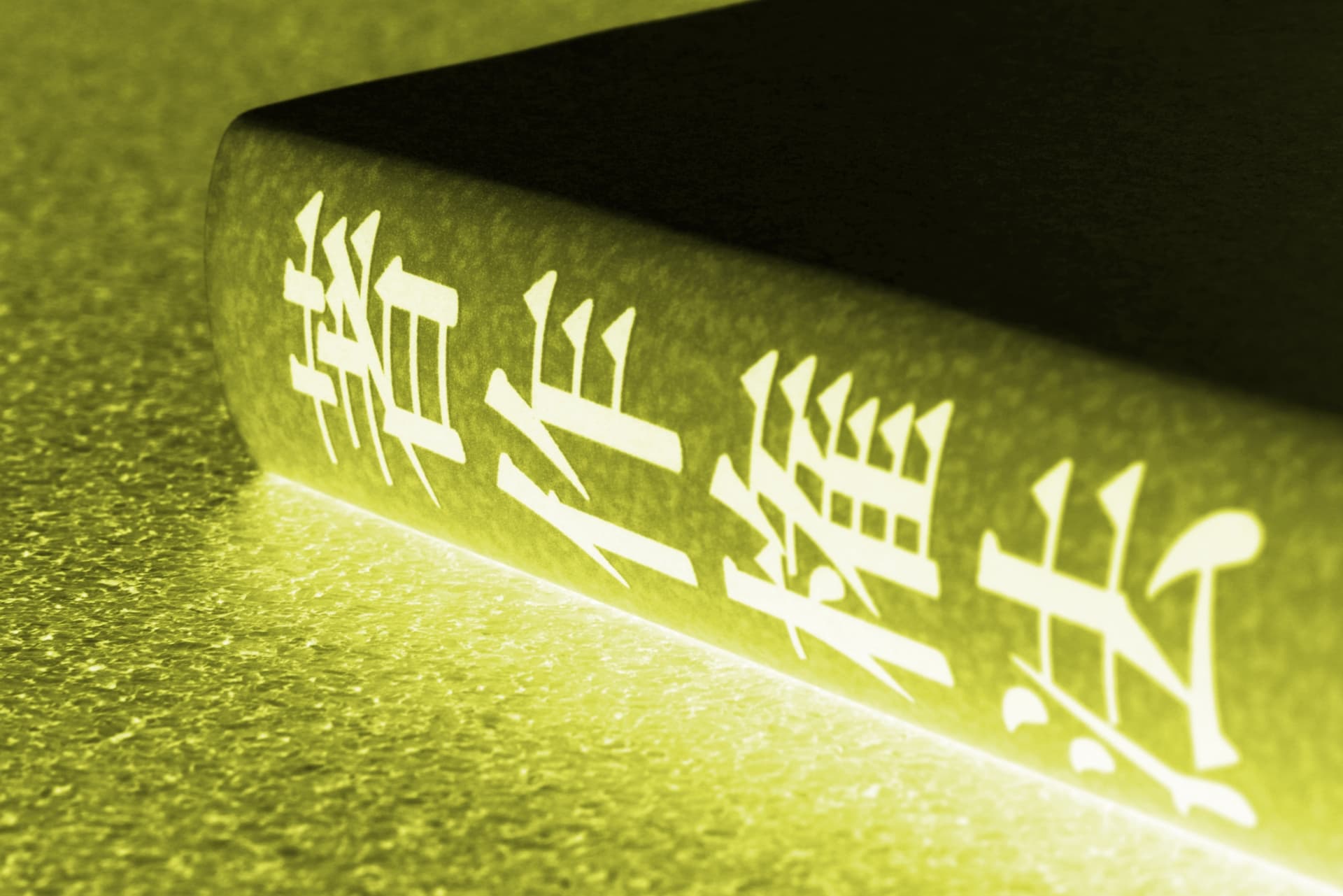
はじめに
著作物を利用する際には、さまざまなルールに従う必要があり、その一つとして「著作者人格権」があります。
著作物に係る契約書で「著作者人格権を行使しない」といった条項を見たことがあるという人は多いのではないでしょうか。
「著作者人格権」は著作権とは別の権利であるため、著作物に関する契約書を締結する際には、著作者人格権がどのような権利かをきちんと理解していることが必要です。
そこで今回は、「著作者人格権」について、その権利内容を中心に弁護士がわかりやすく解説します。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 著作者人格権とは
「著作者人格権」とは、著作者が有する人格的・精神的利益を保護するための権利のことをいいます。
簡単に言い換えると、著作者が著作物に対して有する思い入れや著作者の名誉を守るのが「著作者人格権」です。
著作者人格権は、原則として、著作物を創作した「著作者」に認められる権利ですが、事業者がその業務の一環として創作した著作物については、「職務著作」として、事業者が著作者となります。
この場合は、事業者が著作者人格権を有することになり、著作物を直接創作した従業員などに著作者人格権は認められません。
また、著作者人格権は著作者本人が有する思い入れなどを保護するための権利であることから、譲渡や相続の対象にはなりません。
そのため、著作権が第三者に譲渡された場合であっても、著作者人格権は著作者に残ることになります。
2 著作者人格権の内容
著作者人格権の具体的内容は以下の4つです。
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
- 名誉声望保持権
(1)公表権
「公表権」とは、公表されていない著作物について、公表するかどうか、公表する場合はいつ、どのような方法・条件で公表するかを決定できる権利のことをいいます。
著作物が既に公表されている場合であっても、それが著作者の同意を得ずに公表されている場合には、公表されていないものとして扱われます。
また、著作物を元に創作された二次的著作物についても、その元となっている著作物が公表されていない場合には、著作者に公表権が認められます。
そのため、公表されていない小説を原作として制作された映画を、作家の同意を得ずに放映するような行為は公表権侵害にあたります。
もっとも、公表されていない著作物について、著作権を第三者に譲渡したような場合は、著作物を公表することに著作者が同意したものと推定されるため、特段の事情がないかぎり、著作権の譲受人は著作者の同意を得ることなく著作物を公表することが可能です。
(2)氏名表示権
「氏名表示権」とは、著作物を公表する場合に、著作者名を表示するかどうか、表示する場合に実名で表示するか、または、ペンネーム等で表示するかを決定できる権利のことをいいます。
たとえば、著作者がペンネームで表示することを望んでいたにもかかわらず実名で表示するような行為は氏名表示権侵害にあたります。
一方で、著作者において特に意向が示されていない場合において、既に特定の著作者名が表示されているような場合は、その著作者名を表示したとしても氏名表示権侵害にはあたりません。
また、次の2つの要件をいずれも満たす場合は、著作者名の表示を省略することも可能です。
- 著作物の利用目的などから著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれのないこと
- 公正な慣行に反しないこと
たとえば、テレビやカフェなどで流れるBGMは、その利用目的などから字幕などで著作者名を表示しなくても、氏名表示権侵害にはあたりません。
(3)同一性保持権
「同一性保持権」とは、著作物の題号や内容を勝手に改変させない権利のことをいいます。
同一性保持権は、著作物を勝手に改変されたことにより精神的苦痛を受けた著作者を救済する趣旨で設けられた権利です。
そのため、著作者の思い入れやこだわりといった主観的な意図に反する形で行われた改変を対象に同一性保持権は及びます。
たとえば、一般的にはプラスと評価される改変であっても、その改変が著作者の主観的な意図に反するものであれば、同一性保持権の侵害にあたる可能性があります。
なお、ここでいう「改変」とは、著作物における表現形式上の本質的な特徴を維持しつつ、その外面的な表現形式に改変を加える行為をいうとされていますが、誤字や脱字を修正する程度であれば、改変にはあたらないと考えられています。
(4)名誉声望保持権
「名誉声望保持権」とは、著作者の名誉や声望を害する方法により著作物を利用することを禁止できる権利のことをいいます。
ここでいう「名誉・声望」とは、主観的な名誉感情ではなく、客観的な名誉・声望(社会的評価)を指すとされています。
たとえば、芸術性の高い音楽を性風俗店のBGMとして使用する行為は、名誉声望保持権の侵害にあたる可能性があります。
3 著作者人格権が保護される期間
最後に著作者人格権が保護される期間について見ていきましょう。
著作者人格権が一個人に帰属する場合、その権利は永久的に保護されます。
正確には、著作者が死亡すると著作者人格権は消滅することになりますが、著作者が死亡した後も著作者人格権を侵害するような行為は著作権法で禁止されています。
一方で、著作者人格権が職務著作として事業者(法人)に帰属する場合は、事業者が解散・破産するなどして法人格を失うまでの間、著作者人格権により保護されることになります。
4 まとめ
著作物を利用する場合、著作権にだけ注意すれば大丈夫だろうと考えがちですが、著作者人格権についてもきちんと理解していないとトラブルになる可能性があります。
実務では、こういったトラブルを避けるために、著作権を譲渡する際の契約には「著作者人格権を行使しない」旨の条項を設けることが多いです。
著作権だけに気をとられるのでなく、著作者人格権に関する理解も深めておくことが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。