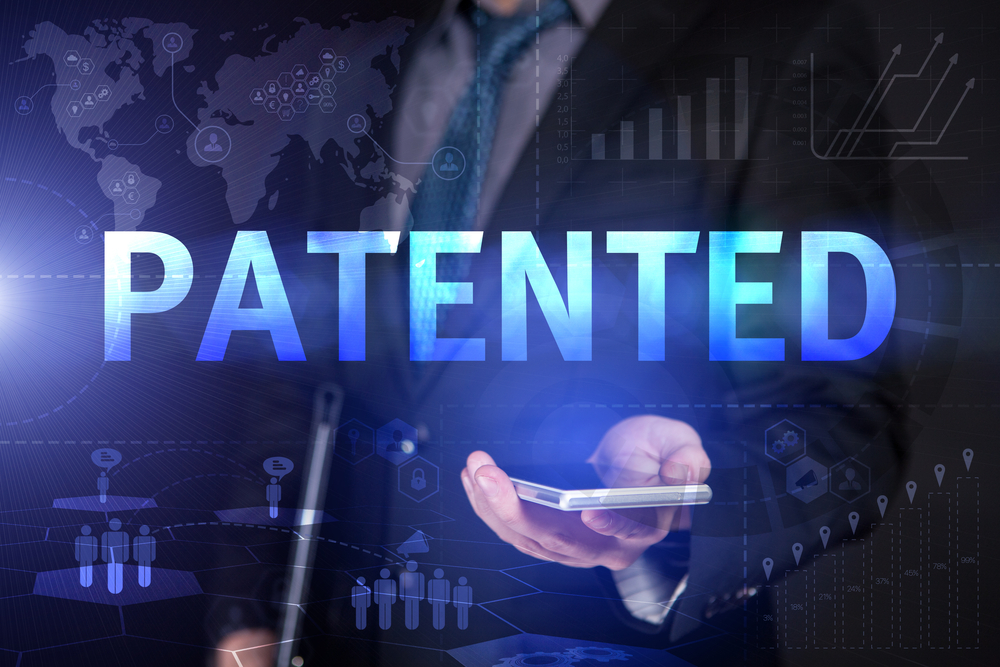特許法改正(2021年5月公布)の3つのポイントを弁護士が解説!

はじめに
令和3年5月14日に可決・成立した改正特許法が、同月21日に公布されました。
新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけとして、テレワークや非接触、デジタル化などが推奨され、経済活動のあり方が大きく変化しています。
今回は、このような変化に対応すべく、デジタル化の手続やデジタル化の進展に伴う権利保護の見直しなどを柱として改正されました。
1 改正特許法のポイント
改正特許法のポイントは、以下の3点です。
- デジタル化等の手続きの整備
- 権利保護の見直し
- 知的財産制度の強化
2 デジタル化等の手続きの整備
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、さまざまな分野においてデジタル化が進んでいます。
改正特許法では、このような情勢に対応するために、デジタル化等の手続が整備されました。
具体的な改正点は、以下の4点です。
- 審判における口頭審理のオンライン化
- 印紙予納の廃止と支払方法の拡充
- 意匠・商標国際出願手続のデジタル化
- 災害等による手続期間徒過後の割増料金免除
(1)審判における口頭審理のオンライン化
従来、特許の無効審判などは、当事者が審判廷に出頭して対面で口頭審理することとされていました。
ですが、今回の改正により、ウェブ会議システムで審理することが可能になりました。
今後は、当事者の申立て又は審判官の職権により、審判廷に出向くことなく、リモートで口頭審理手続きを行うことができるようになります。
(2)印紙予納の廃止と支払方法の拡充
特許料の納付方法には、予納制度や現金納付制度、口座振替制度などのように、いくつかの制度があり、当事者は自由に選ぶことができます。
改正特許法により、このうち予納制度が廃止されることになりました。
また、これまではオンラインでのみクレジットカード支払いに対応していましたが、今後は、窓口でのクレジットカード支払いが可能となります。
(3)意匠・商標国際出願手続のデジタル化
意匠・商標国際出願の登録査定の通知などについて、国際機関を経由した電子送付での対応が可能になりました。
新型コロナウイルス感染症拡大により、郵送手続きが停止することを想定した改正だといえます。
手続きをデジタル化することにより、今後は、手続が簡素化されます。
(4)災害等による手続期間徒過後の割増料金免除
特許料の納付期間を徒過した場合、期間経過後6ヶ月以内であれば特許料を追納することができますが、これまでは、その際に特許料と同額の割増特許料を納付することが必要でした。
ですが、今般のコロナ禍において、やむを得ない理由により期間を徒過した場合にも割増特許料を納付しなければならないとするのは不合理であるとの意見が多数ありました。
このような意見を受けて、感染症の拡大や災害など、やむを得ない理由によって特許料の納付期間を徒過した場合には、割増特許料の納付が免除されることになりました。
3 権利保護の見直し
デジタル化が進むなかで、事業者はその変化に適応していかなければなりません。
その表れとして、事業者の活動にも一定の変化が起きています。
このような変化に対応するために、改正特許法では、権利保護のあり方が見直されました。
具体的なポイントは、以下の3点です。
- 国外からの模倣品流入に対する規制強化
- 訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し
- 特許権等の権利回復要件の緩和
(1)国外からの模倣品流入に対する規制強化
国外から個人使用目的で模倣品を輸入するケースが増えています。
模倣品の越境取引に関して、現行では、国内の事業者が模倣品を輸入した場合には商標権侵害にあたるとされていますが、国内の個人が模倣品を輸入した場合には商標権侵害にあたらないとされています。
ですが、改正特許法は、増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応するため、国外事業者が模倣品を郵送などで国内に持ち込む行為について、相手方が事業者であると個人であるとを問わず、商標権侵害にあたる行為として位置付けました。
(2)訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し
従来、特許権者が、訂正審判や訂正の請求をする場合には、通常実施権者(ラインセンスを受けた者)の承諾を得ることが必要でした。
ですが、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス態様は複雑化してきており、訂正等についてすべての通常実施権者から承諾を得ることが困難なケースが増えています。
このような状況に対応するために、特許権の訂正等において、通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾を不要とすることにしました。
(3)特許権等の権利回復要件の緩和
現行において、手続期間の徒過により特許権が消滅した場合には、一定の基準を満たすことにより、その権利を回復することができます。
具体的には、状況に応じて必要とされる「相当な注意」を払っていたにもかかわらず、期間を遵守できなかったといえることが判断基準となります。
ですが、ここでいう「相当な注意」という判断基準は、他の主要国と比べて厳格に過ぎるとの指摘がありました。
そこで、今回の改正により、権利回復要件が緩和されました。
4 知的財産制度の強化
訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度が強化されました。
具体的なポイントは、主に以下の2点です。
- 第三者意見募集制度の導入
- 特許料などの料金体系見直し
(1)第三者意見募集制度の導入
AIやIoT技術などの進展に伴い、特許権に関する訴訟は、いっそう高度化・複雑化することが想定されます。
そのため、特許権に関する訴訟においては、裁判官がさまざまな意見を参考にしながら判断できるような環境を整備することが必要になってきます。
そこで、裁判所が広く第三者から意見を募集できる「第三者意見募集制度」が導入されることとなりました。
(2)特許料などの料金体系見直し
特許の高度化・複雑化に伴う審査負担の増大や手続のデジタル化に応じて、収支のバランスを確保するために、特許料などの料金体系が見直されました。
今秋にも政令を改正し、特許料などの料金が全体的に引き上げられる予定です。
5 まとめ
改正特許法は、一部を除き、公布の日(2021年5月21日)から起算して1年を超えない範囲内で施行されることになります。
今回の改正は、新型コロナウイルス感染症拡大を契機としており、非接触化やデジタル化に適応していくための改正であるといえます。
改正内容は、さほど難しい内容にはなっていないため、関係する事業者は簡単にでも目を通しておくことをおすすめします。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。