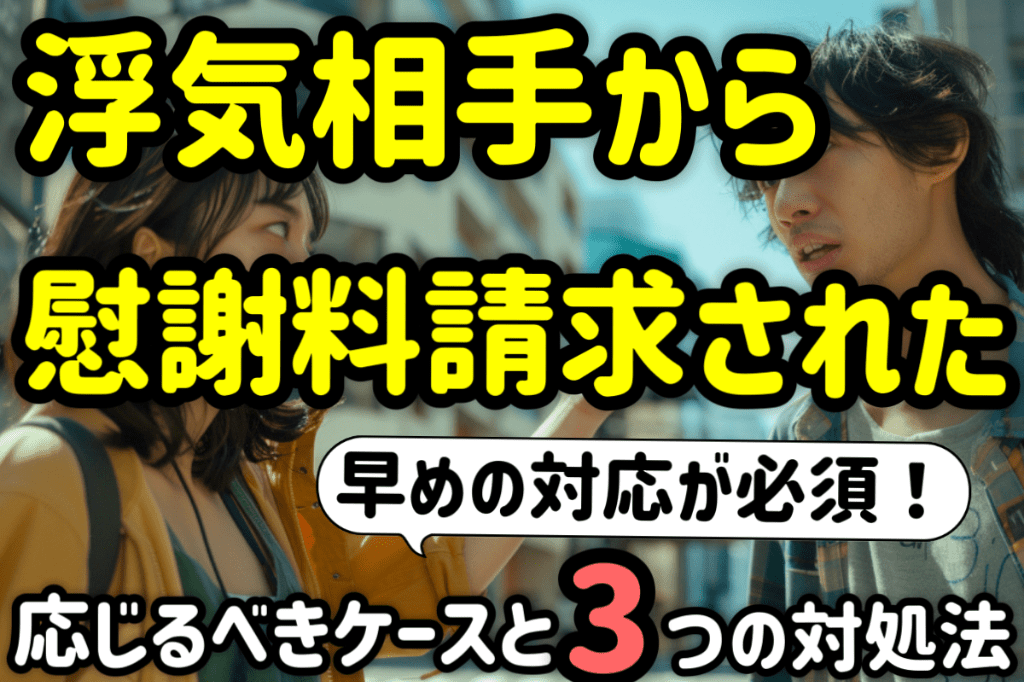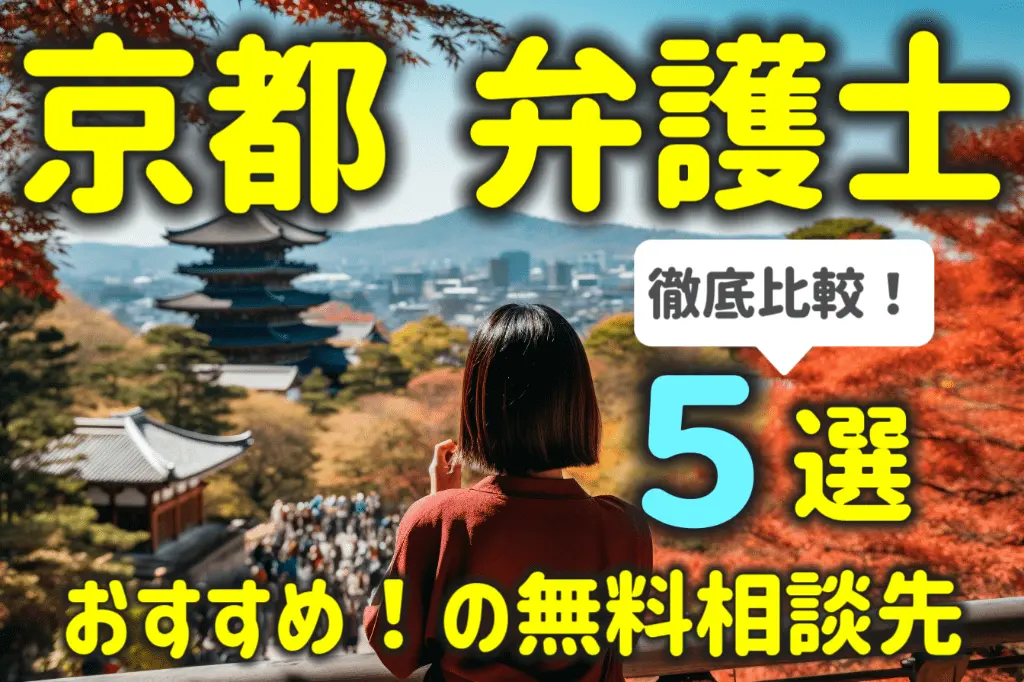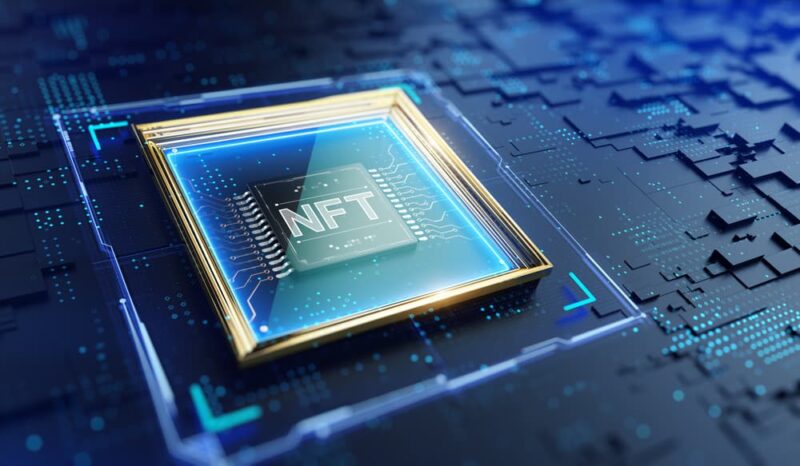【単なるツイートが3億円!】NFTの本質を法的に分析します(2)

0 はじめに
弁護士の勝部です。
前回に引き続き2回目です。
【前回の記事】
【単なるツイートが3億円!】NFTの本質を法的に分析します(1)
前回は、主にNFTの中身がどのような法的権利なのか、ということの前提として、どのようなシチュエーションでNFTに値段がついているのか、というご説明をしました。
ポイントは以下の通りです。
- 所有権は実体のある物に対する権利であり、デジタルやインターネットなど、実体のない物の価値を把握することは想定されていない
- NFTは代替できない(Non Fungible)という特質によって従来可視化できなかった価値に取扱い可能としているが、その価値は、人為的に供給数量を減らすという意味の希少性とはやや異なる
今回は、前回に引き続きNFTの価値についてもう少し考察した上で、その性質を法的に分析していきたいと思います。
1 NFTの価値~続き
実は、このトピックを取り扱うにあたって、色々な情報や見解を参考にしたのですが、その中でも特に参考にしたものの一つが、以下の動画です。
NFTs, Explained(youtube)
この動画の中に、以下のコメントがありました。
-
As soon as humans have enough abundance to have their basic needs met, food, shelter, warmth, etc., the next frontier is to create value in things that have no inherent value.
(訳)人々が食料、居住環境、暖かさなど、(生存のための)基本的なニーズを満たすに足りる豊かさを手にしてすぐに、彼らが次に目指すべきものは「本来的価値を持たない物の中に価値を創造すること」となった。
生存に必要な食糧や居住空間には本来的な価値があります。
ですから、こういったものに貨幣的な価値がつけられ、取引されていくということは誰もが納得しうるところです。
また、人が生存に必要な最低限度のリソースを確保した後であっても、更なる豊かさを求めるのであれば、商品やサービスを求めるという経済活動は続くでしょう。
しかし、それにも限界はあります。
そうすると、人間は「本来は価値のないものに価値を創り出す」ことに興味を持ちます。
このような価値創造は極めて心理的なものですし、その価値に対する主観的な思い入れや、共感に支えられていることになります。
動画の中で、ある試合のレブロンジェームスのプレーがNFT化されて価値がつけられているということが紹介されていました。
NBA top shotとは、NBAの試合でのプレーハイライトをNFTとして取引することができるサービスです。
【参考】
【人気NFT】NBA Top Shotとは?仕組みや買い方・始め方を徹底解説
おそらく、NFTというツールがなければこのような価値を取引の対象とするのは困難であったと思います。
しかし、NFTを使うことによって、試合ごとのハイライトを取引の対象とするようなことが可能になってきます。
「NBA Top Shot」のNFTを売り買いしている人は、その動画を閲覧したいから売り買いしているわけではなく、そのハイライトに価値を感じるコミュニティの中で価値のやり取りをしているということになります。
あるNFTを100ドルで買う人は、「将来150ドルに値上がりしそうだから買っておこう」という期待で買っているのではなく(そういう人もいるでしょうが)、本来的には、自分が100ドルの価値を感じたから100ドルを払えるということになります。
将来高値で転売できそう、とか、その動画の権利でビジネスをして儲けよう、とか、そういう考え方はあくまで経済的な考え方です。
そうではなく、そういった実利的な価値観のレイヤーとは異なるレイヤーで生み出された価値を直接取引の対象としていると説明することができます。
従来の価値観でも、有名選手が引退試合に着ていたユニフォームやホームランボールに高値が付くことがあります。
こういった価格は、ユニフォームやボールという物質に価値があるというよりも、そのような物質に紐づいた付加価値が価値を生み出しているということになるかと思います。
NFTは、このような世界観を超えて、より直接的に、物質的な意味を捨象した価値のみを取引の対象としている、ということになります。
2 NFTは株式会社が発行する株式に対する権利と似ている
このような権利は、物質の使用・収益・処分をする所有権という権利や、著作物の複製権を独占できるという著作権とはかなり性質が異なります。
NFTの発行や譲渡にまつわる法律関係は、あえて言えば、株式会社を設立して株式を発行し、この株式を取引の対象とするという法律関係に似ているのではないかと思います。
(1)株式会社の株式発行プロセス
-
株式会社は、定款作成などを経た後に設立登記をして、株式の引受をして株式を入手します。
株券不発行会社においては、株式を入手しても株券は発行されないので、自分が株主であることを確認するためには、会社の株主名簿を確認するしかありません。
会社の株主名簿に株主として記載されていれば、会社はその人を株主と認めて取扱います。
ある人が株式を譲渡すれば、名義書換によって株主が変わり、以降は株式を譲り受けた人が株主として扱われることになります。
(2)ブロックチェーン上のトークン発行のプロセス
-
トークン発行者は、ブロックチェーンのスマートコントラクトコードを作成し、必要な手数料(GAS代)と一緒にブロックチェーンに送信することにより、トークンを入手します。
自分がトークンの所有者であることは、ブロックチェーンに記録されているので、ブロックチェーンを見れば自分がトークン保有者であることが確認できます。
トークン発行者が誰かにトークンを譲渡する場合は、必要な手数料(GAS代)とともにトランザクションを送信することにより、ブロックチェーンに取引内容が追記されます。
トークン発行者や、このトークンに興味を持っている人は、ブロックチェーンを確認することによって、誰がトークンの保有者であるかを確認することができます。
つまり、トークンを株式とをアナロジカルに考察すると、ブロックチェーンは株主名簿であり、誰がトークンの保有者かは株主名簿に相当するブロックチェーンを介してのみ確認できるということです。
株式は、私法上、「社員権」の一種であると考えられています。
社員権は、会社という社団の構成員である社員が、社員としての地位に基づいて社団に対して有する権利義務の総体であると理解されます。
ここにいう権利義務には、株主総会での議決権や、会社に対する利益配当請求権などが含まれてきます。
NFTを始めとするトークンの内容には、議決権も利益配当請求権も含まれていないのが通常です(仮に含まれていれば、それはファンド持分やセキュリティトークンという、金融商品に分類されることになります)から、その意味で、トークンは株式などの社員権とはまるで異なります。
しかし、団体の中で自分が株式やトークンなどの保有者であることを認めてもらう権利である、という側面においては、NFTは社員権に似ているということになります。
例えば、ジャック・ドーシー氏の最初のツイートのNFT保有者は、ツイートの所有者でもなければ、著作権者でもなく、その権利によって利益配当や何らかの請求ができるわけではありません。
しかし、トークンを発行したジャック・ドーシー氏や、その他このトークンに価値を見出している人々に対し、自分がトークンの保有者であるということを、ブロックチェーンの記録を通じて認識してもらうことができます。
トークンを持っていることを自慢したい、とか、ジャック・ドーシーとお近づきになりたい、アピールしたい、ということとも少し異なると思います。
トークンを取引するということは、経済的な価値観とは別個のレイヤー内の価値のみを対象にしているので、対象に価値を感じたから対価を払っているだけ、ということになります。
それを買って●●したい、という用途が購入動機にはなっているとは限らないということです。
一見、理解できない経済行動であるようにも見えます。
しかし、世の中にはすでに物があふれ切っており、既に「死にたくないから働かなければいけない」「大きなお金を稼いで贅沢をしたい」という行動原理や価値観から解放されている方々が少なからずいます。
そういった方には、お金を節約して食べ物を確保しよう、とか、もっとたくさん稼ごう、という動機はありません。
ですから、より直接的に価値のやり取りをすることに興味を持つのだと思います。
そして、そういった価値観の人は今はまだ少数ですが、少しずつそのような考え方が広がってくるものと予想されます。
なお、ドーシー氏はこのオークションで得たお金を、@giveDirectlyという慈善団体に寄付したと発言しています。
経済的に豊かな人々が価値の取引をし、それを自分のためだけに使うのではなくソーシャルグッドな対象に使う、という緩い信頼感も、こういった取引の背景にあるのかも知れません。
3 NFTはブロックチェーン上、どのように見えているのか?
ちなみに、NFTが購入され、譲渡されると、ブロックチェーン上どのように見えるのかについて簡単に説明しておきます。
以下のサイトは、ジャック・ドーシー氏の最初のツイートがオークションされた、Valuables By Centの当該ツイートの画面です。

リンク元:https://v.cent.co/tweet/20
このサイトからNFTプラットフォームであるOpenseaのページを経由して、ブロックチェーン上の記録を閲覧するサイト(このNFTはPolygonというEthereumのセカンドレイヤー上で発行されています)を閲覧すると、以下の表示が確認できます。

リンク元:https://polygonscan.com/tx/0x8ad39b10f26e2da972a833edbb1cdb25af476fefaaa77e4ceda033e4c9ddf264
このトランザクションは、ジャック・ドーシー氏の最初のツイートのNFTをmint(鋳造)したものです。
NFTはブロックチェーン上のスマートコントラクトによって発行されるので、当該トランザクションによって発行され、その後複数回移転(transfer)していることが確認できます。
4 NFTは実利用途においても有用である
もちろん、NFTはこういった抽象度の高い価値を扱うためだけのものではありません。
例えば、NFTをログイントークンのように用いて、トークンの保有者だけに情報を見せたり、特別扱いをしたり、ということも可能です。
例えば、以下の記事は、フォーブスが、広告を非表示にするためのNFTトークンを発売したという記事です。
【参考】
フォーブスが「広告非表示権」を発売、イーサで購入可──ブロックチェーンでNFT活用
例えばchromeなどのインターネットブラウザのアドオンウォレットにNFTを送信することにより、サーバーはNFT保有者と非保有者を区別して情報を出しわけることが可能です。
似たような仕組みを応用すれば、例えばゴールドカード保有者のような特典を乗せたNFTや、サロンやスタジアムの入場券、ファンクラブの会員権などとして使えるNFTを発行することも可能です。
また、NFTプラットフォームの中には、著作権ライセンスなど、法的な権利を付与することを条件に取引するものもあります。
こういったプラットフォームで取引したNFTには、著作権に関する許諾などの法的権利が付与されたのと同じ効果を持つものもあり得ます。
もちろん、これらもNFTの重要な実用例と言えます。
以上に述べたような様々な可能性を秘めているのがNFTである、ということができるかと思います。
まとめ
今回は若干長くなってしまいましたが、NFTにまつわる権利関係が私法上の財産権のうち、社員権に近いという考え方の説明と、それがある種の団体(株式会社などの法令上認められた社団よりも緩やかなコミュニティ)の中で認識されうるものであるというご説明をしました。
次回は、NFTの実装や、ゲーム等での実例についてご説明をしたいと思います。
何度か述べたように、NFTの中身はスマートコントラクトであり、Solidityなどのプログラミング言語で記述されたコードであると説明できます。
ERC-721などの規格は、共通規格で発行したトークンであれば同じウォレットで管理できるなどのメリットを享受できるという意味はありますが、必ずしもこういった規格に準拠する必要はありません。
スマートコントラクトのイメージがわくと、ブロックチェーン上でどのようなことが行われているのかが分かり、NFTの理解も進むのではないかと思います。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。