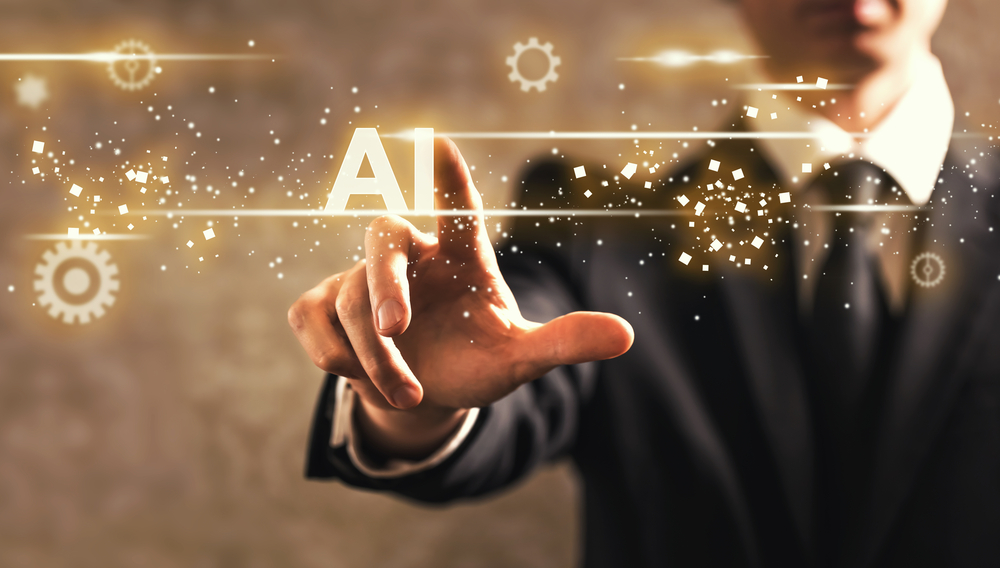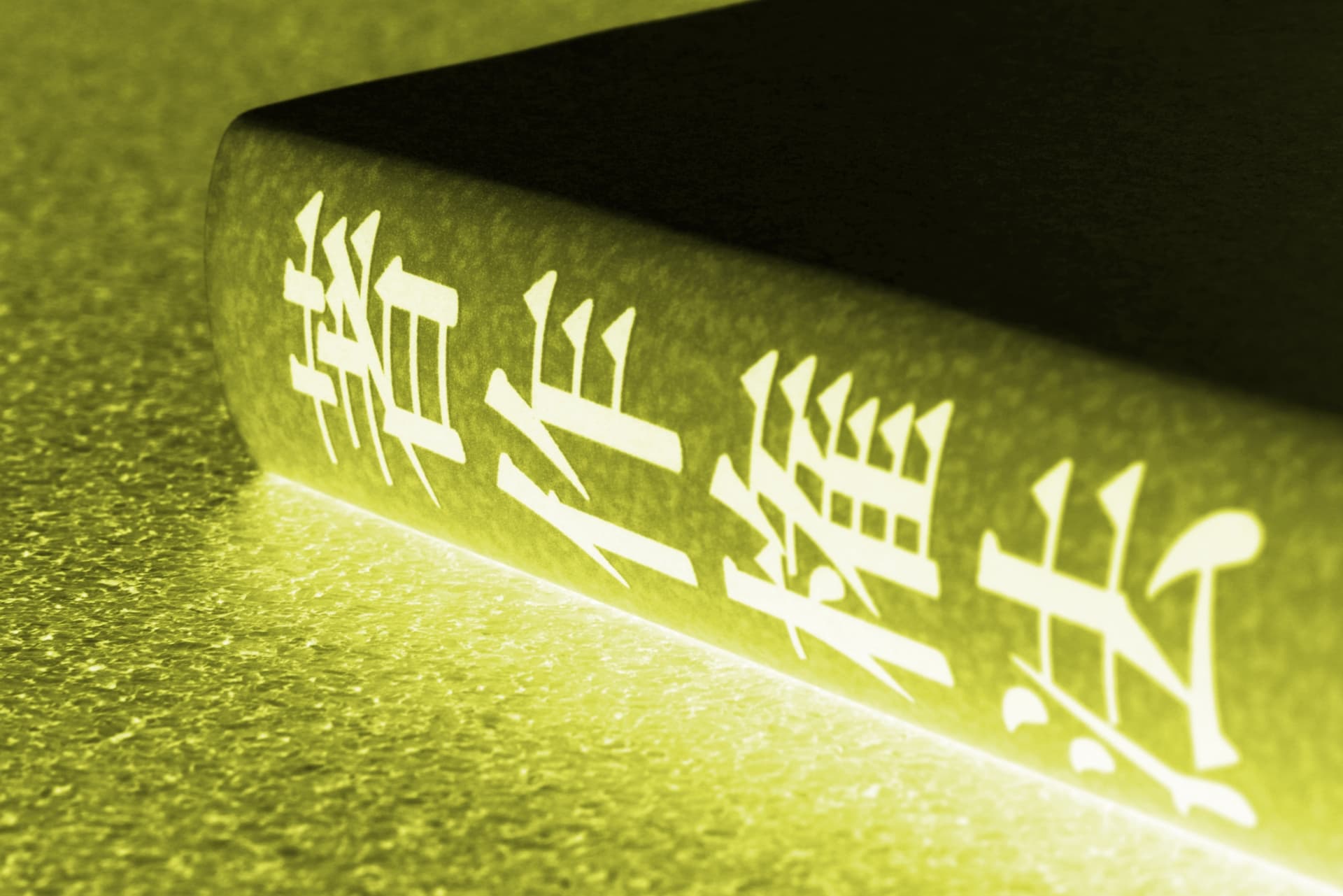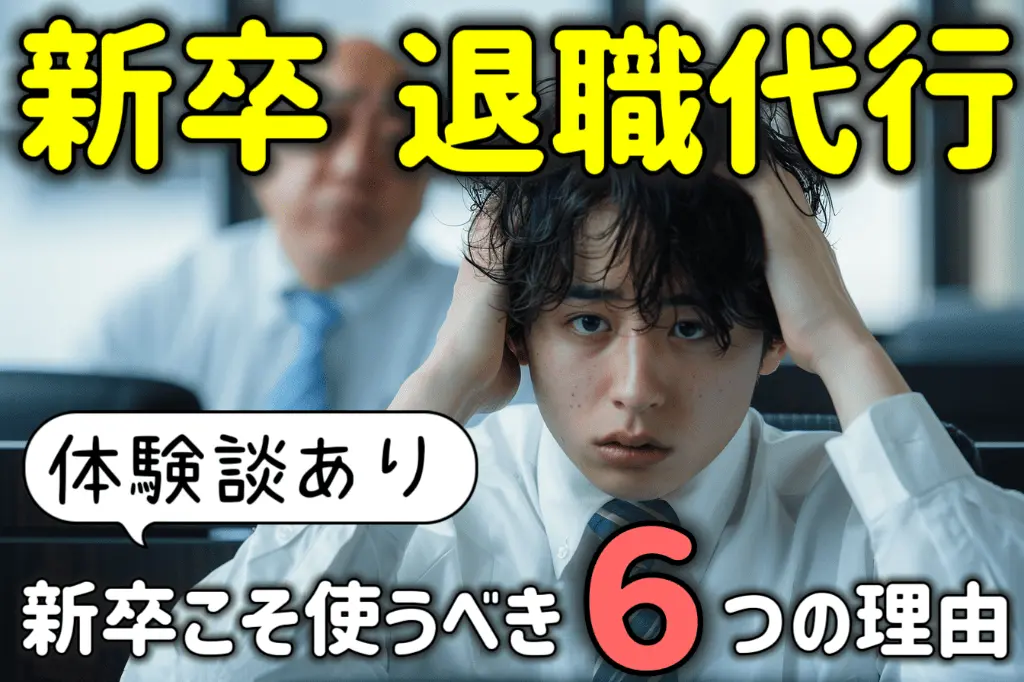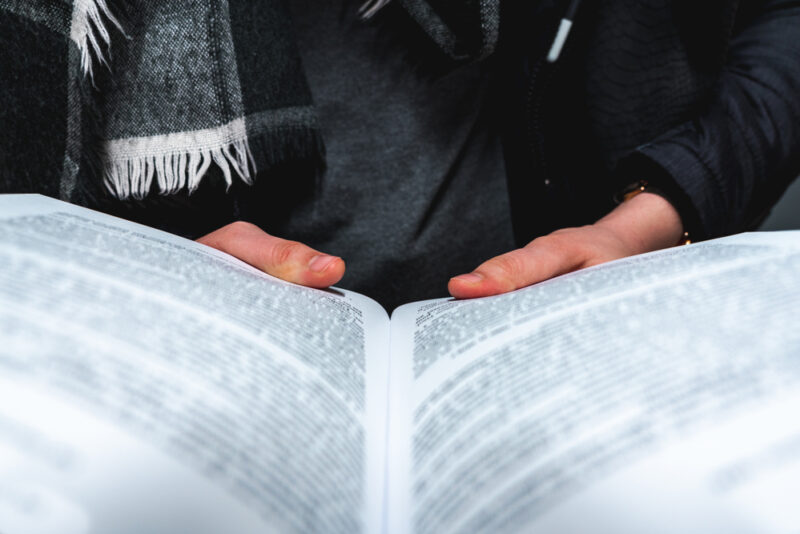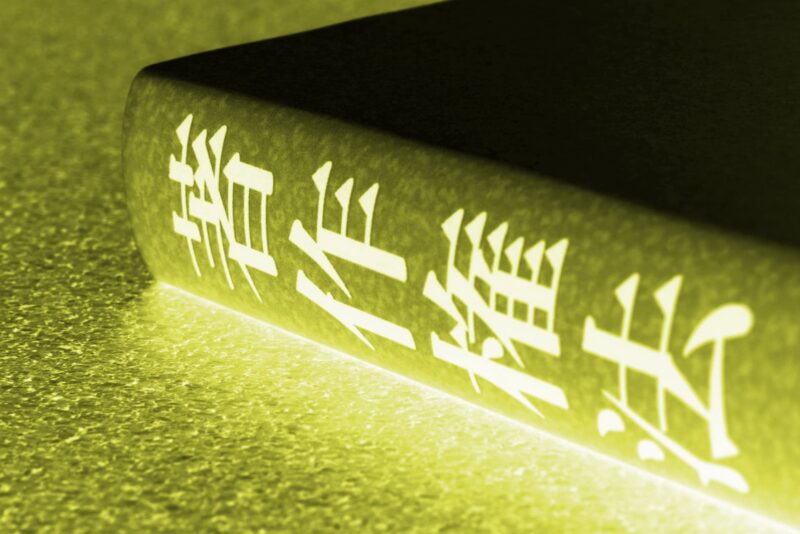【雛形付き】著作権譲渡契約書の作成で気を付けたい11のポイント!

はじめに
近年、インターネット上などで個人や企業が著作物を発表できる場が増えたことなどから、著作権への意識が社会の中で高まっています。これにより、
「他人の著作物を利用するにはどうすればいいのか」
「クリエイター(著作者)として不利な契約とならないためにはどこに気を付ければいいのか」
が考えられるようになってきました。
この点は著作者でも著作物の利用者であっても、対応を誤ったケースがSNSを中心に「炎上」したりすることも珍しくありません。
こういった事態を防ぐために、著作者とその著作物の利用者は、お互い事前に決めたルールを書面化し、それに従って利用をすることが重要になっています。
中でも、著作者が著作物の権利を他者に引き渡すときの「著作権譲渡契約書」は、著作者にとっては自分が創作したものが他人の手に移って利用され、譲受人にとっては他人の権利を新たに取得していくことになるため、気を遣います。
この記事では、
- 「なぜ著作権譲渡の際には契約書を取り交わす必要があるのか」
- 「契約書に入れるべき項目はどのようなものがあるのか」
について、弁護士が詳しく説明をしていきます。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 なぜ著作権譲渡契約が必要なのか
著作者にとって著作物は創作の成果物であり、その価値に対しては正当な対価が発生すべきものです。
これにより著作者は継続して創作活動を続けることができ、社会全体のクリエイティブ環境の保護にもつながっていきます。ひいては文化発展に貢献するものとなるため、著作物を正しく使うことができるよう、「著作権」という権利が定められています。
この著作権を得るのに特別な資格や手続は必要なく、著作物を創作した時点で自動的に著作者に付与されます。
(1)著作権の譲渡とは
他人の著作物を利用する際には、用途に合わせて、著作者と譲受人(利用者)が契約を結ぶ必要があります。一部の例外を除いて著作物は著作権者の承諾がないと、勝手に使うことはできないからです。
このうち、譲渡は著作者が著作物に関する権利の全部または一部を、他人に引き渡すことを意味します。
そのため、著作権を譲渡した場合は、元の著作権者は、権利者でなくなります。
(2)著作権譲渡の対象
著作者が譲渡できるのはあくまでも「著作権」のみで、ここに含まれるのは、複製権(コピーをすることができる)、譲渡権、翻訳権、翻案権(加工や変更をすることができる)、二次著作物の利用に関する現著作者の権利(二次著作物についても、元の著作者が権利を主張できる)、など11の権利があります。
一方、著作者だけに認められる「著作者人格権」は、他者に譲渡することができず、本人に残り続けます。文字通り著作者の人格や作品の名誉などを保護する権利だからです。
(3)著作権譲渡契約とトラブルの可能性
そうはいっても、そこまで複雑なことを求めるわけではないなら、口頭での約束では不足なのでしょうか。
たとえば、「記録が残るから」といって、メールやメッセージツールで数行のやり取りだけで取り決めをしてしまうこともあるかもしれません。しかし、メールなどは改ざんや偽造が可能で、記録として不確定なこともあります。
また、後に細かい利用のルールや金額、その他のトラブルが発生した場合、双方にとって不利益が発生したり、片方が一方的に利益を得たりすることにもなりかねません。
権利関係の不備が社会的に明らかになった際には、企業や著作者自身が受けるイメージダウンも大きくなります。
そのため、事前に権利関係の範囲やその内容を契約書として書面化しておくことは取引の安全を保証することにもつながります。
書面で譲渡契約を交わさなかったり、内容が不十分な状態で著作物を利用することになったりしたら、どのようなトラブルが予見されるでしょうか。譲渡人・譲受人双方の立場からみてみましょう。
①著作者(譲渡人)にとってのトラブル
自分が作成した著作物を譲渡したのに譲受人が対価を支払ってくれない、勝手にキャラクターの色を変えられた、勝手に尻尾を付け足されたなどといったトラブルになることが考えられます。
②譲受人にとってのトラブル
一方、著作物を利用する側(譲受人)にとっては、著作者から加工や変更の都度、法外な使用料などを請求されたり、利用範囲などについて全く自由度のない利用条件で譲渡を受けても、著作物を利用する価値を見出せません。
このように、譲渡契約を締結する際は、双方の主張がより良い条件で合意できるよう、落としどころを探るようにしたいものです。
2 著作権譲渡契約とライセンス契約(著作権利用許諾)の違い
「著作権利用許諾契約(ライセンス契約)」とは、著作者(ライセンサー)が著作物の権利を譲渡することなく、ライセンス契約に定められた範囲内で利用者(ライセンシー)に著作物の利用を許可する形式です。
こちらははあくまでも「許諾」を求めるのみなので、著作権が他人に移るわけではなく、著作者に残ったままになります。
例えば、食品やアパレル商品などにキャラクターがついているものは、キャラクターの原作者(個人のほか団体・企業を含む)がライセンサーとなり、食品メーカーなどのライセンシーに図柄の使用を許可するものです。
譲渡とは異なり、ライセンサーは著作物の利用を複数人に許諾することができます。利用を許諾したライセンシーが増えるほどロイヤリティー収入が上がるため、権利を保有しているだけで大きな資産となります。
3 著作権譲渡契約書の「雛形」のダウンロード
以下の項目からは、この雛形を使って、著作物譲渡契約書に定めるべき一般的な事項について見ていきたいと思います。
4 著作権譲渡契約書に定めるべき一般的な事項(雛形解説)
著作権譲渡契約書に定めるべき一般的な事項は以下の通りです。
- 目的
- 本件著作物
- 保証
- 対価
- 秘密情報の取扱い
- 損害賠償
- 権利義務譲渡の禁止
- 反社会的勢力の排除
- 解除
- 管轄裁判所
- 協議
(1)目的
-
- 第1条(目的)
- 本契約は、譲渡人が保有する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)を譲受人に譲渡することに関して、必要な契約事項を定めることを目的とする。
最初に、著作権譲渡を内容とする契約を交わす「目的」をはっきり記載しておきましょう。
ここでのポイントは、譲渡する著作権の範囲を明確にすることです。
繰り返しとなりますが、著作権は、その中に11もの細かい権利があり、その全てを譲渡することもできますし、一部の権利に絞って譲渡することもできます。
そのため、譲渡する著作権の範囲がどこまでなのかを明確にする必要があるのです。雛形では全ての著作権を譲渡することとしています。
なお、全ての著作権を譲渡する際には「著作権法第27条と第28条」にも注意しなければいけません。
「著作権法第27条」とは、著作物を翻訳・編曲するなど、著作物に関し加工・変更する権利が著作者にあることを定めた規定です。
「著作権法第28条」とは、二次的著作物(ある著作物を翻訳・変形するなどしてできた新しい著作物)の利用に関して、原著作物(元の著作物)の著作者に二次的著作物の著作者と同じ権利があることを認めるとする規定です。
これらの権利は、譲渡する対象に含まれていることを明記しなければ、譲渡の対象にならず、元の著作者に権利が残る(留保する)ことが法律上決まっています。
そのため、著作権に含まれる全ての権利を譲渡する場合、「著作権全てを譲渡する」と契約書に書くだけでは不十分であり、著作権法第27条と第28条の権利も含めて譲渡することを明確にしなければいけないのです。
(2)本件著作物
-
- 第2条(本件著作物)
- 本件著作物は、●●とする。
この契約書における譲渡の対象となる著作物を特定する条項です。
ここには、
- 著作物のタイトル
- 様式
など、著作物を特定する情報を記載します。
言葉で特定することが難しい場合などは、譲渡の対象となるキャラクターのイラストなどを別紙に添付するという方法で特定するのもありです。
なお、当然ではありますが、契約書に特定された著作物以外には契約の効力は及ばず譲渡の対象とはなりません。
例えば、ある著作者が作成したキャラクターのイラストAを譲渡の対象とした場合、同一の著作者が作成した同一のキャラクターの別ポーズのイラストBは対象外となってしまいます。イラストBについても譲渡を受けたい場合は、譲渡の対象として含める必要があります。
(3)保証
-
- 第3条(保証)
-
- 1.譲渡人は、本件著作物について、譲受人および譲受人が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないことを約す。
2.譲渡人は、本件著作物が第三者の知的財産権を侵害していないことを譲受人に保証する。
保証条項では、主に、著作者(権利を譲渡する譲渡人)は次の2点を保証することとなります。
- 著作者人格権を行使しないこと
- 第三者の知的財産権を侵害していないこと
①著作者人格権を行使しないこと
「著作者人格権」とは、前述の通り著作物を作成した著作者だけが持つ権利です。この中には、以下の3つの権利が含まれます。
- 「公表権」:著作物を公表するかしないか、公表する場合はどのような手段で公表するかを決められる権利
- 「同一性保持権」:著作物を意に反して改変されたりしない権利
- 「氏名表示権」:著作物を公衆に向けて公開する際に、実名やペンネーム、ハンドルネームなどの変名を著作者として表示するかどうかを決めることのできる権利
これらの権利行使が可能な状態にしておくと、
著作物を譲渡された譲受人は、著作者から
- 著作物の公表タイミングは今じゃない
- 著作物に変更を加えるな
- 著作物に私の名前をつけろ
と主張される可能性があります。著作権の譲渡を受けたにもかかわらず、著作者(譲渡人)から常にこれらの権利を主張されると、譲受人にとっては不便が生じるため、行使しないようにすることを明記しておきましょう。
②第三者の知的財産権を侵害していないこと
第3条2項は、著作者(譲渡人)に他人の著作権などの知的財産権を侵害していないことを保証してもらい、安心して取引を行うための定めです。
なぜ著作者(譲渡人)にこんなことを保証してもらうかというと、知的財産権を侵害せずに著作物を生み出したことを確認できるのは、多くの場合、著作者のみだからです。
イラストなどの著作物の製作過程で他人の著作物を参考にし、似たような著作物を生み出した場合、その著作物は著作権侵害となる可能性があります。こうして生み出された著作物を譲受人が利用していると、著作権侵害の責任を追及されるのは、著作物を利用している譲受人です。
このようなトラブルを可能な限り予防するために、著作権などの知的財産権を侵害していないことを確認できる著作者に侵害していないことを保証してもらうのです。
(4)対価
-
- 第4条(対価)
-
- 1.譲受人は、譲渡人に対して、本件著作物の譲渡の対価として、金●●円(税込)を支払うものとする。
-
- 2.対価の支払は、納品後●日以内に支払うものとする。
- 3.対価の支払は、譲渡人が指定する銀行口座とし、振込手数料は譲受人が負担する。
著作物の金銭的対価について定めた項目です。
トラブルの原因になることが多い部分であるため、金額や支払期日は慎重に設定しましょう。
振込手数料についても、負担する側をあらかじめ決めておくべきです。金額も税込か税抜かは確認の手間を防ぐために明記しておきましょう。
(5)秘密情報の取扱い
-
- 第5条(秘密情報の取扱い)
- 譲渡人および譲受人は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、本契約の有効期間中および本契約の終了後、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用してはならず、第三者に開示または漏洩してはならない。
一般的な契約書における秘密情報の取り扱いと同様、契約関係に入った譲渡人と譲受人が契約に関連して知り得た相手方の秘密情報には、守秘義務が発生します。
これは契約書上の期限が終了したとしても継続する項目です。
(6)損害賠償
-
- 第6条(損害賠償)
- 譲渡人および譲受人は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
譲渡人と譲受人が、相手方に責任がある状態で損害を被った場合は、その相手方に損害賠償を請求できるというものです。
例えば、生み出された著作物が他人の著作物をパクっていた場合が典型例です。この場合、第3条2項でパクっていないことを保証していたにも関わらず、著作者(譲渡人)はその保証の約束を守っていなかったことになります。この場合、パクったことが原因で発生した損害をこの条項に基づいて譲受人は譲渡人に請求できることになります。
(7)権利義務譲渡の禁止
-
- 第7条(権利義務譲渡の禁止)
- 譲渡人および譲受人は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。
この条項は、予期せず取引の相手が変わってしまうことを防ぐことを目的としています。
(8)反社会的勢力の排除
-
- 第8条(反社会的勢力の排除)
-
- 1.譲渡人および譲受人は、相手方に対し、次の各号のいずれかにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
-
- ①自らまたは自らの役員もしくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
-
- ②反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
-
- ③反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
-
- ④自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
-
- ⑤反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
-
- ⑥の役員または自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
-
- 2.譲渡人および譲受人は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、または第三者を利用してかかる行為を行わせないことを表明し、保証する。
-
- ①暴力的または脅迫的な言動を用いる不当な要求行為。
-
- ②相手方の名誉や信用等を毀損する行為。
-
- ③偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害する行為。
-
- ④その他これらに準ずる行為。
-
- 3.譲渡人または譲受人は、相手方が前二項のいずれかに違反し、または虚偽の申告をしたことが判明した場合、契約解除の意思を書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)で通知の上、直ちに本契約を解除することができる。この場合において、前二項のいずれかに違反し、または虚偽の申告をした相手方は、解除権を行使した他方当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできない。
4.前項に定める解除は、解除権を行使した当事者による他方当事者に対する損害賠償の請求を妨げない。
いわゆる「反社条項」と呼ばれる条項で、反社会的勢力とつながりを一切持っていないことを表明するものです。
会社として暴力団、やくざなどの反社会的勢力とのつながりを絶たなければいけないことは理解していても、暴力団、やくざなどは反社会的勢力であることを巧妙に隠し、資金獲得活動を行っています。
そのため、この条項は、相手と初めて取引をする際には必須の条項になっています。
また、巧妙に隠している以上、反社会的勢力であることを知らずに、取引をしてしまうこともあり得ます。
そのため、反社条項を設ける際には、必ず
- 反社と繋がりがあることが発覚した場合には解除できること
- 損害賠償請求
をできることは明記しておくと安心です。
(9)解除
-
- 第9条(解除)
-
- 1.譲渡人または譲受人は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
-
- ①重大な過失または背信行為があった場合
-
- ②支払いの停止があった場合、または仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合
-
- ③手形交換所の取引停止処分を受けた場合
-
- ④公租公課の滞納処分を受けた場合
-
- ⑤その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2.譲渡人または譲受人は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。
3.譲渡人または譲受人は、第1項各号のいずれかに該当する場合または前項に定める解除がなされた場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。
双方が一定の場合に、契約をなかったことにできること(解除)について定めた条項です。
解除できる条件(解除事由)として、雛形では一般的な条件を定めていますが、これらの条件しか定められないわけではありません。それが守られなければ契約はなかったことにしたほうがいいといえるような条件があれば、それについても必ず解除事由として定めるようにしましょう。
(10)管轄裁判所
-
- 第10条(管轄裁判所)
- 本契約に関する一切の紛争については、●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとする。
万が一双方の間で紛争が発生した場合、どこで争うかを予め定めておく条項です。このように予め定めておくことで、いざ紛争に巻き込まれてもどこで争うか覚悟しておくことができます。
ここでのポイントは、場所をどこにするかです。
いざ裁判となれば、裁判所に出廷しないといけません。あまりに遠くの地域とされてしまうと、出廷するだけでも大変になってしまいますので、注意してください。
(11)協議
-
- 第11条(協議)
- 本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い譲渡人および譲受人が協議し、円満な解決を図る努力をするものとする。
契約書を交わしたとしても、実務上で契約書に定めていない事項が発生することは多々あります。そのような時にはどうするかを定めた項目です。
「契約になければ何をしてもいい」というわけではなく、この項目を設けることにより、未知の事態が発生した際、どちらかが勝手な判断で著作物を毀損するようなことがあったり、金銭的な対価をないがしろにしたりするような対応を防ぐことができます。
5 修正・追加について
これまでの項目はあくまでも一般的に著作権譲渡契約書に記載する事項にすぎません。
著作物もデザインなど有形のもののほか、音楽や講演なども含まれてきますので、ここに含まれない内容が必要になることもあります。
上記の契約書の内容を双方で確認し、個別のケースで必要な項目の追加・削除とその確認を行い、双方が合意できる契約書を目指しましょう。
6 小括
著作権譲渡契約書を交わす必要性と、主な項目について解説をしてきました。
著作権の譲渡は著作者にとって大きな決断が必要なこともあるでしょう。その際、譲り受ける側も誠意をもって契約をしたいものです。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- 他人の著作物を利用するときは、著作者から承認を得なければならない
- 他人の著作物を利用するには、利用許諾(借りる方法)と譲渡(権利を取得)の2つの方法がある
- 著作権譲渡で譲り受ける側が取得できるのはあくまでも「著作権」についてのみであって、著作者人格権は元の著作者に残り続け、譲渡はできない
- 著作権を譲渡する際には、必ず書面で契約書を交わすことにより、後に発生し得るトラブルを未然に防止することができる
- 「著作権を全て譲渡する」と記載したとしても、翻案権や二次的著作物にかんする部分(著作権法第27・28条)は別途表記をしないと、この部分の権利が著作者に留保されることになる
- ※【雛形の注意事項】
- 本記事にてダウンロード可能な各種ひな形の著作権その他の一切の権利については、弁護士伊澤文平に専属的に帰属しております。したがいまして、ひな形の利用許諾は、これら権利の移転を意味するものではありません。
- 各種ひな形をご利用いただけるのは、法人様又は法律家以外の個人の方のみに限り、弁護士・司法書士・行政書士などのいわゆる士業の方のご利用は一切禁止しておりますので予めご了承ください。
- 本ひな形は、自己又は自社内でのビジネスのためにのみ(以下、「本件利用目的」)ご利用いただけます。
- したがいまして、本件利用目的以外での利用並びに販売、転載、転送及びネット上にアップロード・投稿する行為その他一切の行為を禁止します。
- 各種ひな形の内容に関して、弁護士伊澤文平はいかなる保証も行わず、ひな形の利用等に関して一切の責任を負いませんので、予めご承知おきください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。