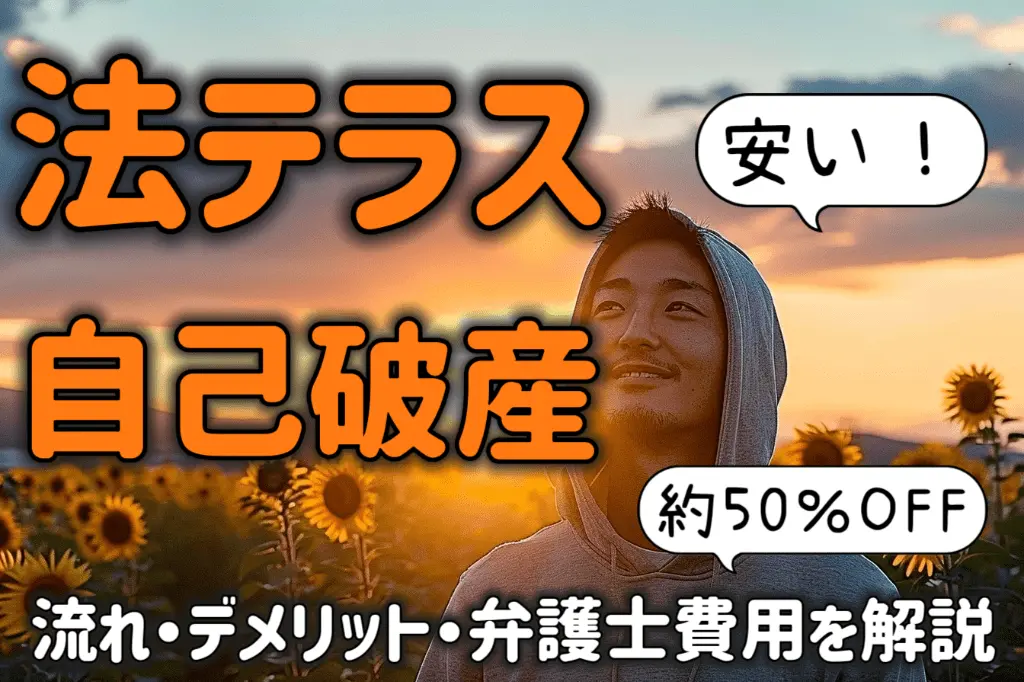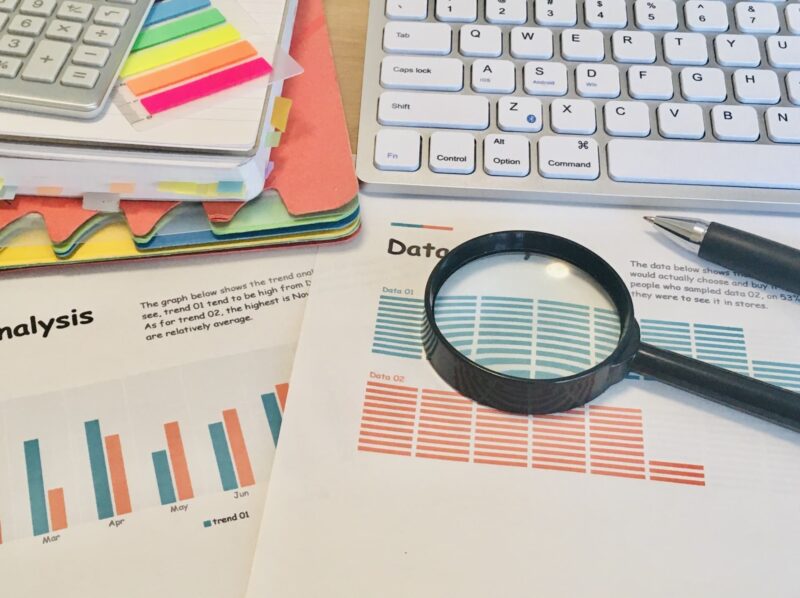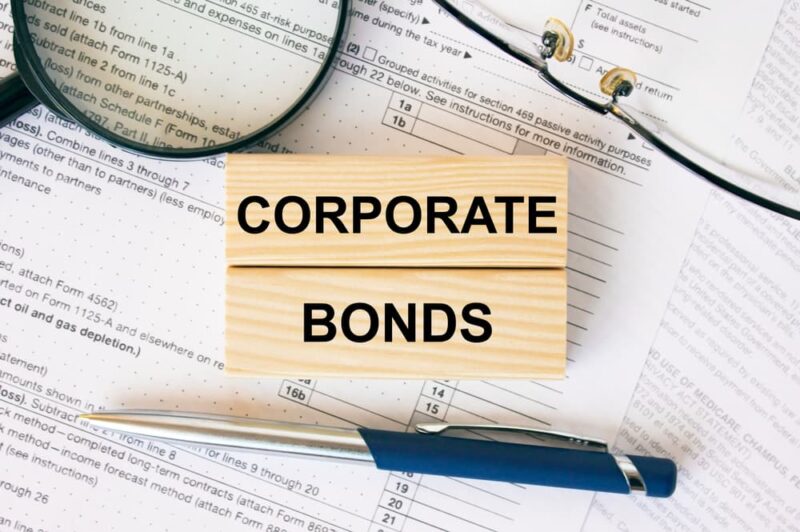表明保証条項を決定する際に注意すべき2つのポイントを弁護士が解説!

はじめに
事業者が投資を受ける場合、投資家との間で投資契約を締結することが一般的です。
多くの投資契約では、「表明保証」という条項が設けられますが、どのような意味をもつ条項かをご存知でしょうか。
表明保証条項は、投資を受ける事業者にとっては、大変重要な条項です。
深く考えずに契約に盛り込んでしまうと、後に大きな問題に発展する可能性があります。
そこで今回は、表明保証条項の注意点について弁護士がわかりやすく解説します。
1 表明保証条項とは
「表明保証条項」とは、投資を受ける事業者が投資家に対して、会社に関する一定の事項が真実かつ正確であることを表明・保証することを内容とする条項をいいます。
投資を受ける場合には、すぐに投資が実行されるわけでなく、投資が実行される前に投資家によるデューデリジェンスが実施されることが一般的です。
ここでいう「デューデリジェンス」とは、投資家が実施する調査のことをいい、投資家は、投資先の事業計画・財務状況などを調査し、投資の是非を判断します。
もっとも、デューデリジェンスには限界があります。
事業者から投資判断に必要な情報が全て開示されるとはかぎらず、また、開示された資料に誤りがある可能性があるからです。
そこで、投資家は、デューデリジェンスを補完するために、事業者に一定の事項を表明保証してもらうわけです。
一般的に、投資契約では、表明保証条項に違反した場合には、損害賠償を請求したり、投資を白紙に戻したりすることができるといった内容の条項が盛り込まれるため、これにより投資家はデューデリジェンスの不完全性を補完することができます。
なお、表明保証条項は、投資契約にかぎらず、M&Aの際に締結する契約でも設けられることが一般的です。
※デューデリジェンスについて詳しく知りたい方は、「デューデリジェンスとは?注意すべき5つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。
2 表明保証条項で盛り込まれる内容
表明保証条項で盛り込まれる内容は、投資規模や投資条件、事業者の事業内容や経営状況などによって異なるため、最終的には個別のケースごとに決定することになります。
以下は、表明保証条項に盛り込まれることが多い事項です。
-
【事業者に関する基本的事項】
- 事業者の権利能力・行為能力
- 株式の発行状況
- 株式の発行について適切な機関決定を経ていること
まずは、「事業者において投資契約を締結したり新株を発行したりするために必要な権利能力・行為能力があること」を表明保証の対象とすることが挙げられます。
また、株式が適法に発行されていること、また、その発行数などについても、表明保証の対象とされることが一般的です。
-
【事業に関する事項】
- 法令違反、訴訟が存在しないこと
- 許認可、知的財産権の取得がされていること
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 貸借対照表・損益計算書が適正であること
事業者に関する事項のほか、事業に関する事項も対象とされることが一般的です。
法令違反がないこと、必要となる許認可等が適切に取得されていること、また、貸借対照表等の内容が適正であることなどが対象となることが多いといえます。
表明保証条項に盛り込む内容は、事業者の事業内容や成長フェーズ、表明保証の必要性などを考慮したうえで、事業者にとって盛り込む内容が過剰なものとなっていないかをきちんと確認して決定する必要があります。
3 表明保証条項を決定する際の注意点
表明保証条項に対する考え方は、事業者と投資家ではまったくといっていいほど異なります。
事業者は、損害賠償や契約解除といったリスクを最小限にするために、表明保証条項に盛り込む内容は少なくしたいと考えるのが一般的です。
これに対し、投資家は投資リスクを最小限にするために、表明保証条項に盛り込む内容を多くしたいと考えるのが一般的です。
表明保証条項に盛り込む内容を決定する際には、このような考え方の違いも念頭に置いておく必要があります。
以下では、表明保証条項を決定する際に注意しなければならない基本的事項を2点ご紹介します。
(1)内容を明確にする
表明保証条項に盛り込まれる内容は、可能なかぎり明確にする必要があります。
内容が曖昧であったり、解釈に疑義が生じるような定め方をしていると、双方の認識に齟齬が生じ、トラブルに発展する可能性があります。
最悪の場合、損害賠償責任を負わされる可能性もあるため、双方において共通の認識をもつことができる程度に、内容を明確にすることが重要です。
(2)虚偽の申告をしない
ごく当然のことではありますが、虚偽の申告をしてはなりません。
事業者が、投資を受けたいがために、自社に不利な情報はできるだけ開示したくないと考えるのは自然なことです。
ですが、場合によっては、このような不利な情報を開示しなければならないケースもあります。
ここで、自社に不利な情報を改ざんしたり隠蔽したりした場合、後に表明保証条項違反を問われ損害賠償責任を負う可能性があります。
自社に不利な情報であっても、表明保証条項に盛り込む必要があれば、正確な内容を盛り込むことが必要です。
4 まとめ
投資契約では、表明保証条項を盛り込むことが一般的になっています。
近年では、この表明保証条項が問題となって、裁判にまで発展しているケースもあります。
表明保証条項に違反すると、投資家から契約を解除されたり、損害賠償請求をされたりする可能性があります。
事業者は、表明保証条項に盛り込まれる内容を一つ一つ確認し、自社にとって過剰な内容となっていないか丁寧に精査することが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。