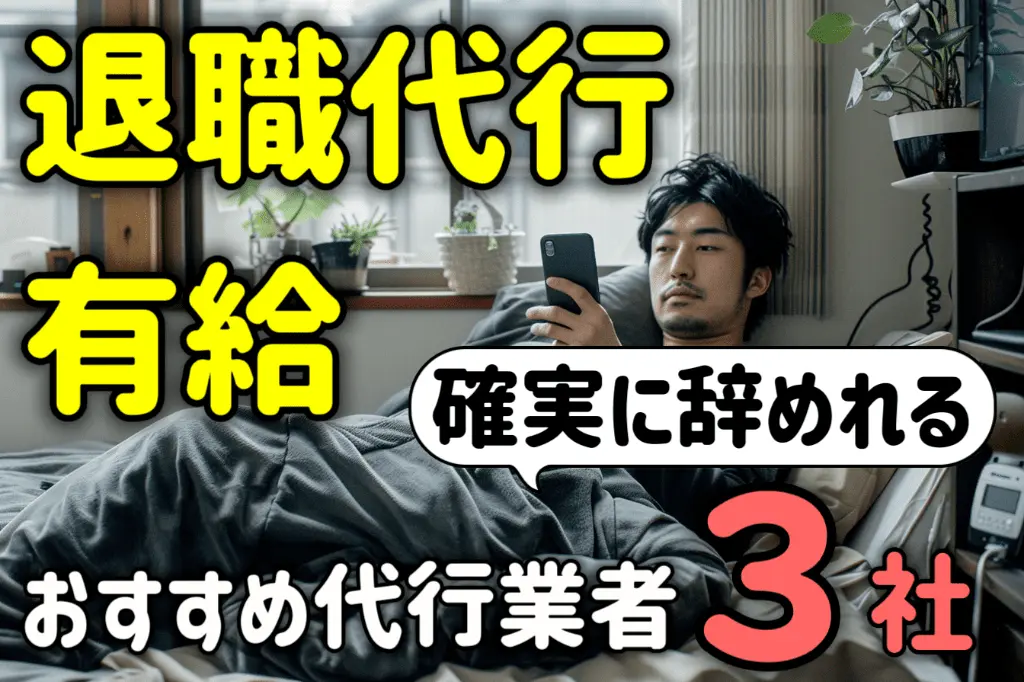【2024年WG検討スタート】暗号資産規制緩和でゲームやサービスに革命が!企業参入の鍵は?

1. はじめに:暗号資産規制緩和の背景と意義
2024年に入り、日本政府は暗号資産(仮想通貨)に関連する規制緩和に向けた議論を加速しています。
-
“金融庁は事業会社が暗号資産(仮想通貨)を扱いやすくする仕組みづくりの議論に着手する。弁済原資の確保といった負担が軽減され、海外のようにゲーム内で暗号資産を使ってアイテムなどを購入しやすくなる可能性がある。”
「ゲーム内の仮想通貨、事業会社が扱いやすく 金融庁」(日本経済新聞)2024年9月24日
記事の内容は、金融審議会のワーキンググループの内容を敷衍したものとなっています。
資金決済法の今後の改正が焦点となりますが、ポイントは以下のとおりです。
-
資金移動業について
資金移動業の利用者と送金額が大幅に増加
安全性の説明が必要
クロスボーダー収納代行について
昨今の決済代行業者トラブルを受け、資金移動業の登録と資産保全を義務付けるべき
暗号資産交換業者について
FTX事件の教訓から、資金決済法で国内保有資産命令を出せる措置を支持。
追加の審議事項
後払いサービスであるBNPL(Buy Now, Pay Later)を審議対象に追加すべき。
過剰与信や不正利用への対応が不十分であり、利用者保護を資金決済法等で検討すべき。
このような規制の穴となっている重要トピックの解決の他、企業がより柔軟に暗号資産を活用できるようにするための仕組み作りも検討されています。これまで、日本では暗号資産取引に関して厳しい規制が課されており、特に企業が暗号資産を活用する際の参入ハードルが高いという問題がありました。
現在の法律では、事業会社が暗号資産交換業を営むためには、厳しい暗号資産交換業者の登録を受ける必要があります。これは、特に中小企業や新規参入者にとって大きな障害となってきました。しかし、政府はこの状況を変えるために、企業向け仮想通貨規制緩和に向けた措置を検討しています。今回の規制緩和により、特にゲーム業界と仮想通貨の連携が進み、ブロックチェーンゲームやサービス内での仮想通貨利用が急速に広がる可能性があります。
ちなみに、暗号資産交換業登録をしようとする場合は、まず暗号資産交換業者の登録審査に係る「質問票」に回答することになりますが、この質問票も今年6月に改訂が入りました。
質問票の段階で多くの会社が対応困難となるのは以下のポイントです。
- 取引時確認やマネロン対策
- ウォレット管理、「履行保証暗号資産」の確保
- 分別管理監査のノウハウ不足
- ハッキングや漏洩への技術的対応
実施のためには金融機関でのAML、疑わしい取引審査の実務経験のある人材の配置が求められますが、そのような人材は希少かつ高単価なため、体制整備ができない
いわゆるホットウォレット維持のためには履行保証暗号資産を積む必要がありますが、この運営ノウハウがない
一般的な会計監査のほか、分別管理監査という特殊な監査を受けなければならないが、その内容がよく分かっていない
日本に限らず世界的にエンジニアやコンプライアンス人員が圧倒的に足りておらず、ハッキングにどう対応するかの説明ができない
暗号資産交換業は仮想通貨交換業の時代から考えるともうすぐ施行から8年が経過し、ある程度ノウハウも溜まっているはずなのですが、案件が少なかったり、廃業に至ってしまう理由は上記のような負担が重すぎるからであると感じています。
ただ、法施行当初から想定されていた通り、日本の暗号資産市場には潜在的な成長力があり、政府は市場拡大の機会を逃さず、グローバル競争力を高めるために法改正に踏み切ろうとしているのです。
2. 規制緩和がもたらすメリットとは?
規制緩和は、暗号資産の企業利用を容易にし、企業や消費者の双方にとって数多くのメリットをもたらします。
まず、暗号資産の活用は企業のビジネス活用に新たな道を開き、特にゲーム業界やエンターテインメント産業においては、新たな収益モデルが生まれる可能性があります。
たとえば、現在多くの企業が興味を持っているのが、暗号資産とゲーム内アイテム購入の統合です。ブロックチェーン技術を利用して、ゲーム内アイテムやNFT(非代替性トークン)を暗号資産で売買することができるようになれば、従来のゲーム経済が大きく変わります。
これにより、ゲーム内アイテムの取引が透明化され、プレイヤーにとっても資産価値が高まります。
また、ステーブルコイン導入も、企業にとっては大きなメリットです。
ステーブルコインは、法定通貨の価値に連動する暗号資産であり、価格変動のリスクを最小限に抑えることができます。これにより、企業はリスクを減らしながら、デジタル資産の利用を拡大することが可能になります。
3. ゲーム業界における暗号資産活用の可能性
特に注目すべきなのが、ゲーム業界における暗号資産の活用です。暗号資産の規制緩和により、ゲーム開発業者やゲーム配信業者(いわゆるパブリッシャー)は、より自由にブロックチェーン技術を取り入れ、ゲーム内での経済活動を暗号資産で支えることが可能になります。
これは単にゲーム内でアイテムを売買するだけでなく、プレイヤーが真の所有権を持つデジタルアイテムが登場し、取引可能な市場が形成されることを意味します。
例えば、ブロックチェーン技術を活用したゲームでは、NFTとゲーム業界の融合が進み、プレイヤーはゲーム内のアイテムやキャラクターを実際の資産として保有し、それを外部のマーケットで取引することができます。
これにより、プレイヤーが得る報酬や利益が現実世界での価値を持つことになり、ゲームの遊び方や経済圏が大きく変わるでしょう。
4. 規制緩和の方向性としてのブローカー業の新設
現行の規制では、事業会社が自社サービス内で暗号資産を扱う場合、非常に厳しい規制をクリアしなければなりません。
ただ、規制緩和といっても、暗号資産交換業者の障壁であった、マネロン対策や利用者の資産保全に関する規制が緩くなる可能性は極めて低いと考えられます。
そもそもそのような状況だったのが2017年4月の仮想通貨交換業新設当初で、その当時の規制対応では事故が頻発したからこそ今の厳しい対応があるからであり、規制を当時の緩い状況に巻き戻すというのはレギュレーション対応としてありえない話です。
ただ、ブローカー業という新たな業態が検討されています。
現在の法規制では、暗号資産取引の仲介・媒介業務も「暗号資産交換業」のカテゴリに入ってきます。
ということはブローカー業や暗号資産販売の営業をする場合もすべて交換業登録が必要ということになります。
しかし、交換業で重視されるべきマネロン対策や預かり資産保全という重点は必ずしもブローカー業務で求められるべきポイントではありません。
ブローカー業務はブローカー向けのコンプライアンス態勢が敷けていればあとは既に登録を持っている事業者と連携して業務をすれば十分なはずです。金融商品仲介業のように所属制にするかどうかも含めてこれからの議論が待たれますが、方向性としては非常に正しいと感じています。
実は私も、暗号資産の預かりを一切自社でやらないブローカー専業での登録ができないか模索したことがあったのですが、ブローカー専業は変な詐欺会社と同類に見られて印象が悪く、規制が過剰な点と収益性の折り合いがつかずに断念したことがあります。もうかなり昔の話ですが。
いずれにせよこのブローカー業が設立されることにより、企業はブローカーを介して暗号資産の取引を行うことが可能となり、顧客の利便性を向上し、参入ハードルを大きく下げることが期待されています。
この仕組みによって、特にスタートアップや中小企業が暗号資産市場に参加しやすくなり、従来の大手企業に対する競争力が強化される可能性があります。さらに、ブロックチェーンと連動したweb3技術の事案蓄積が、より多様なビジネスモデルを生み出すでしょう。
5. サービス産業における暗号資産利用の未来
ゲーム業界だけでなく、他のサービス産業においても暗号資産の利用が進むと考えられます。例えば、Eコマースやデジタルコンテンツの分野では、暗号資産を用いた支払いが広がることで、より自由度の高い取引がよりスムーズに行えるようになります。
また、エンタメ産業においても、アーティストやクリエイターが自身のコンテンツをブロックチェーン上で販売し、暗号資産で報酬を得る新しいビジネスモデルが生まれる可能性があります。これにより、従来の中央集権的なプラットフォームに依存せずに、直接的な取引が可能となり、クリエイターの収益性が向上するでしょう。
6. 暗号資産規制緩和がもたらすリスクと課題
一方で、規制緩和に伴うリスクも無視できません。特に暗号資産は、その性質上、価格変動が激しく、詐欺やサイバー攻撃のリスクも高いです。企業がこれらのリスクに対処するためには、適切なセキュリティ対策や資産保護の仕組みが必要となります。
また、法的整備も重要な課題です。暗号資産に関連するトランザクションが増えるとともに、詐欺や不正取引が発生するリスクも高まります。政府や規制当局は、企業や消費者が安心して取引できる環境を整えるため、適切な利用者保護を進める必要があります。
7. 海外事例:ゲームやサービスにおける暗号資産の活用事例
海外では、既に暗号資産を活用したゲームやサービスが広がっています。例えば、プレイヤーがゲーム内でキャラクターを購入・育成し、トークンを稼ぐことで現実の収入を得ることができます。これは、ゲーム業界における暗号資産の可能性を示す代表的な事例です。
さらに、アメリカやヨーロッパでは、ステーブルコインを活用して資金決済を行う事例も増えています。これにより、国際的な取引コストが削減され、暗号資産の利用が一層加速しています。
8. 企業が参入するためのステップとは?
規制緩和を見据えて、企業が暗号資産市場への参入を検討するためには、いくつかのステップが必要です。まず、企業は暗号資産のビジネス活用に対する理解を深め、どのように自社のビジネスに暗号資産を組み込むかを検討する必要があります。
次に、法的な要件を確認し、必要な認可やライセンスを取得します。規制が緩和されるとはいえ、なくなるわけではないので、想定するビジネスの規制を予測し、どのように対応するかを検討することが重要です。最後に、技術的な準備を進め、ブロックチェーン技術や暗号資産を扱うための技術蓄積、組織態勢を整えることが必要です。
9. まとめ:暗号資産規制緩和がもたらす革新と今後の展望
暗号資産規制緩和は、日本の企業や消費者にとって大きなチャンスをもたらします。
特に、ブロックチェーンゲームやサービス産業での利用拡大が期待されており、新しいビジネスモデルが次々と生まれるでしょう。
しかし、同時にリスクと課題にも目を向け、慎重なアプローチが求められます。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。