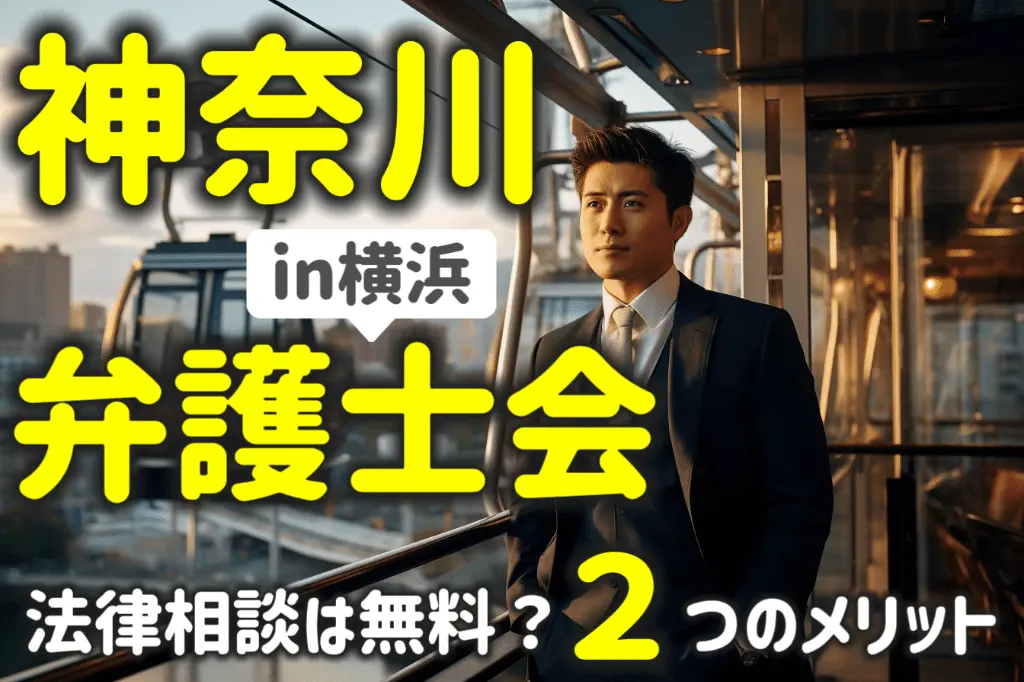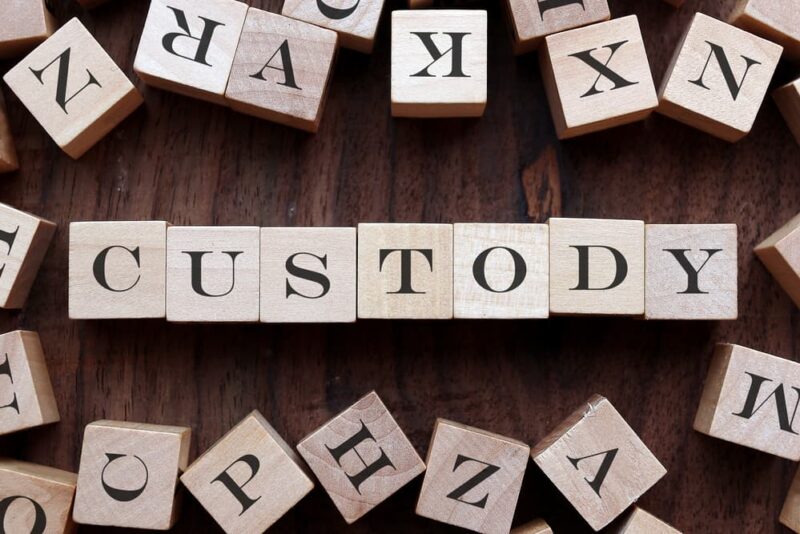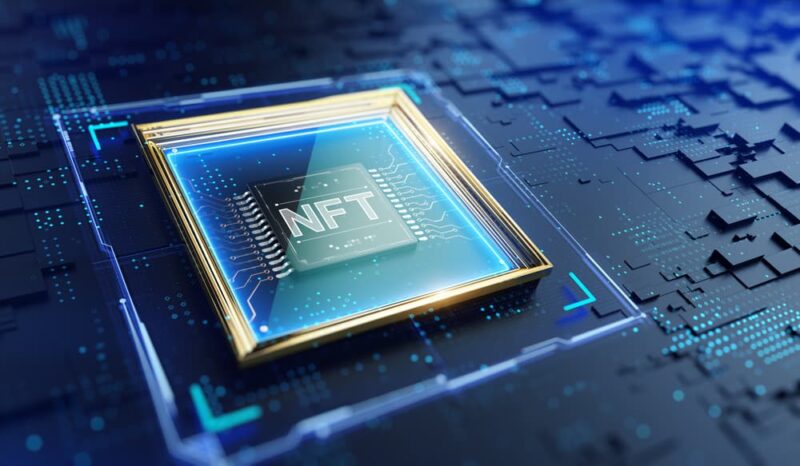【弁護士解説記事】「暗号資産」課税見直しへ…新興企業の成長に配慮、海外流出防ぐ

はじめに
弁護士の勝部です。
暗号資産(仮想通貨)を発行するスタートアップにとって足かせとなっていた、法人税法の規定が改正されます。
2023年度税制改正にて議論される予定で、具体的な施行時期は未定です。
今回は、この規制の概要と、なぜこの規制がスタートアップの足かせになっていたのかを解説いたします。
1 法人が暗号資産を保有している場合に生じる課税について
暗号資産の課税の基本となるのは、所得税(法人の場合は法人税)です。
暗号資産は、安く買って高く売った時点で収益が発生します。収益発生のために必要となる経費(取引手数料等)を控除した額が課税対象となり、このことは個人も法人も基本的には変わりありません。
したがって、暗号資産を買っただけで売却(他の暗号資産への交換も含みます)をしていない状態であれば、課税対象となる所得が発生しません。かつての仮想通貨バブルで、安価に購入した暗号資産が大幅に値上がりしたとき、賢い人は所得が発生する前に所得税が安い(若しくは発生しない)日本以外の国に居住地を変更しました。
個人の場合、売却して初めて所得が発生し、課税が発生するのです。
法人の場合、このルールが異なります。
法人の場合は、決算期末時に保有する暗号資産を時価評価して損益を計上する必要があり、含み益が課税対象になってしまうのです。
つまり、暗号資産を保有したまま決算期末を迎えると、売却していなくても法人税が発生してしまうのです。
-
法人が事業年度終了の時において有する暗号資産については、時価法により評価した金額(本問において「時価評価金額」といいます。)をもってその時における評価額とする必要があります。
なお、その市場暗号資産を自己の計算において有する場合には、その評価額と帳簿価額との差額(本問において「評価損益」といいます。)は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。
また、この評価損益は翌事業年度で洗替処理をすることになります。
「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」より
例えば、ある日本法人が主体となってブロックチェーントークン(日本の資金決済法上の「暗号資産」に該当するものと仮定)を発行したとします。
ブロックチェーントークン発行の方法には様々ありますが、発行したすべてのトークンを日本法人が管理するアドレスにて保管していると仮定します。
この日本法人がブロックチェーントークンを保有したまま決算期末を迎えてしまうと、全量のトークンについて法人税が発生してしまう可能性があるのです。
例えば、トークンのアマウント総量が20億で、1単位当たり0.1円と仮定すると2億円のトークンを保有していることになり、自社で発行したトークンであるため取得原価を0とすると、その年に2億円の売上があったとして課税をしなければいけない可能性が出てくるのです。
2 「市場暗号資産」に該当する場合に限る
ただし、このような決算期末処理が必要なのは、当該暗号資産が「市場暗号資産」に該当する場合に限ります。
市場暗号資産とは、活発な市場が存在する暗号資産のことで、その要件は以下の通りです。
-
「市場暗号資産」の要件
イ 継続的に売買価格等(売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
ロ 継続的に上記イの売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
ハ 次の要件のいずれかに該当すること。
(イ) 上記イの売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。
(ロ) 上記ロの取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。
【関連法令】
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)61条
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)118条の7
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)118条の8
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)118条の9
「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」より
つまり、自社が保有しているだけで市場性がない暗号資産の場合は、かかる課税の対象にはならないということです。
ただし、トークンは小規模であっても取引の対象となれば価格がつき、流動性が生まれます。
どの時点から市場暗号資産に該当するのかを正確に区別するのは困難です。
単に自社の小さなプロジェクトでトークン発行するだけであれば問題ないとしても、トークン発行と流通を事業スキームの中に組み込んでいるようなケースでは、この課税リスクを明確にできなければ事業を大きくしていくことはできません。
日本の法人がトークンを保有しているとそれだけで突然課税されるリスクがある、ということでは、安心してブロックチェーン事業を展開することは困難です。
このような判断から、有望なプロジェクトほど日本を避ける、というケースが存在していました。
今回の法人税法の改正はこのようなシチュエーションに対応するためのものということです。
【2022/8/30追記】
なお、日本暗号資産ビジネス協会は、法人にのみ課される期末時価評価課税について、自社発行トークンを対象から除くこと等を含む提言をしております。
-
(2)法人税
期末時価評価課税の対象を市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的(短期売買目的)で保有している市場暗号資産に限定し、それ以外のものを対象外とすることを要望する。少なくとも喫緊の課題への対応として、まず自社発行のトークンについて対象から除くことは必須である。
日本暗号資産ビジネス協会ウェブサイトより
3 まとめ
この取り組みは、岸田内閣の「新しい資本主義」の実行計画の中のスタートアップ育成という流れに沿ったものということです。
今後数年はスタートアップにとって追い風となりうるルール変更が複数なされる可能性もあり、関連業界にとっては追い風になりうるかも知れません。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。