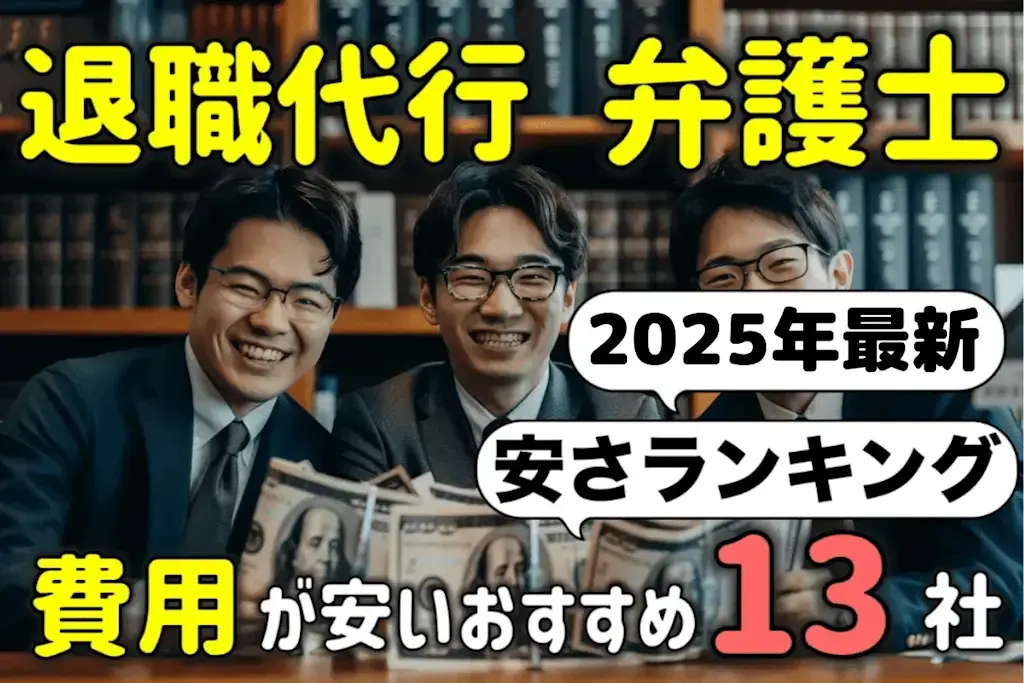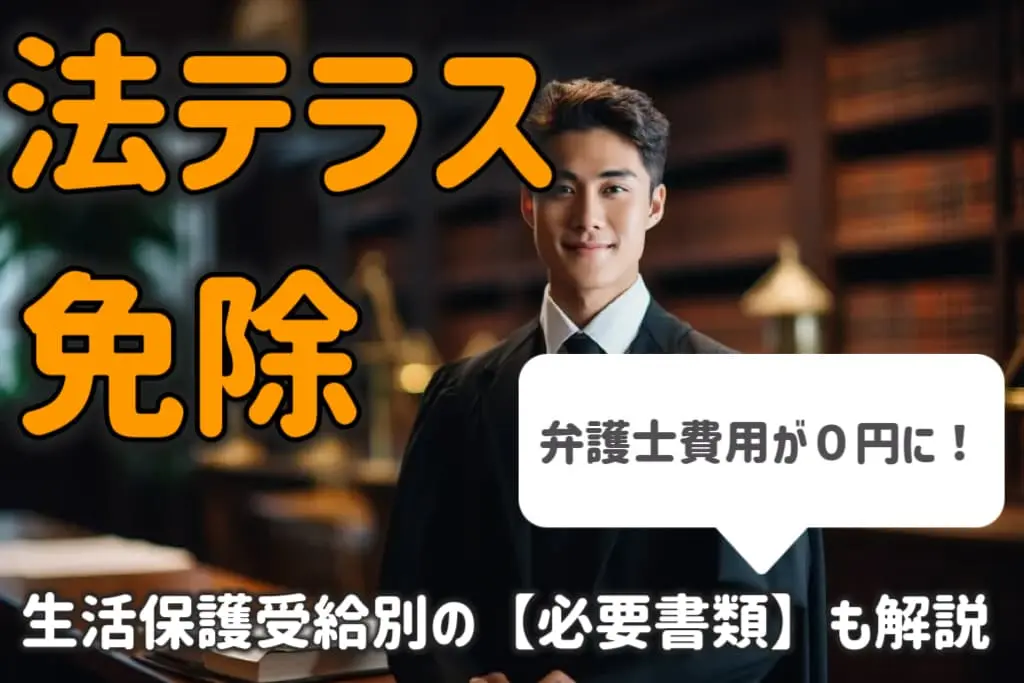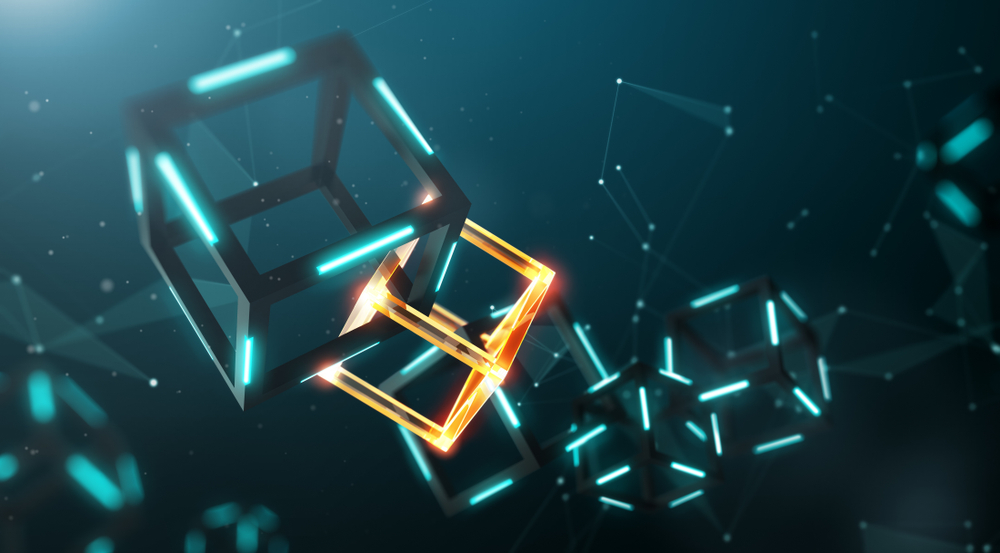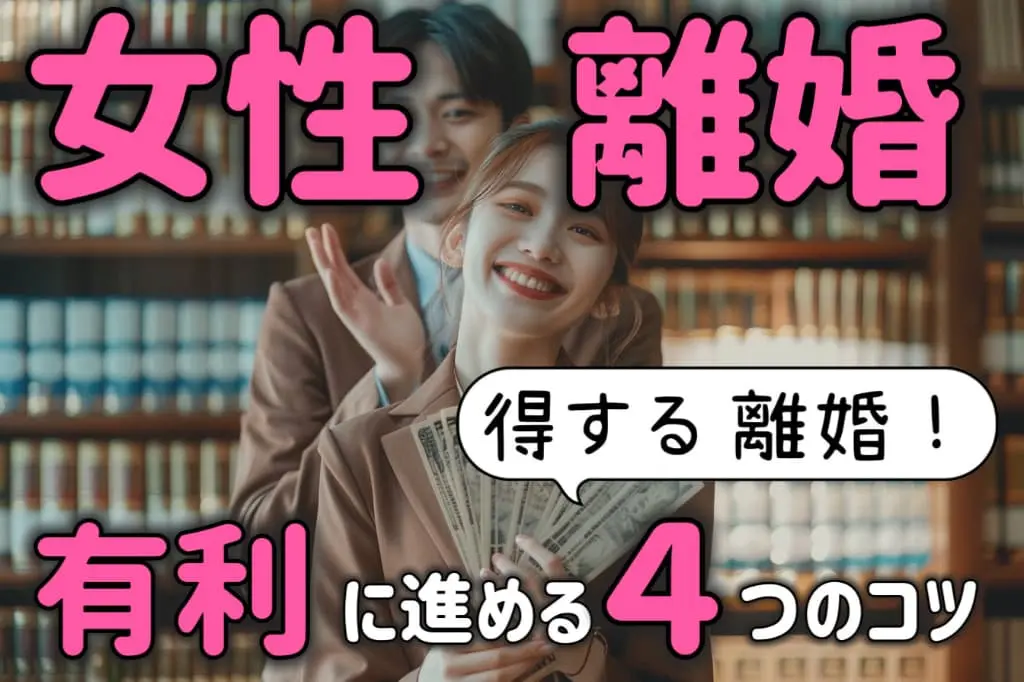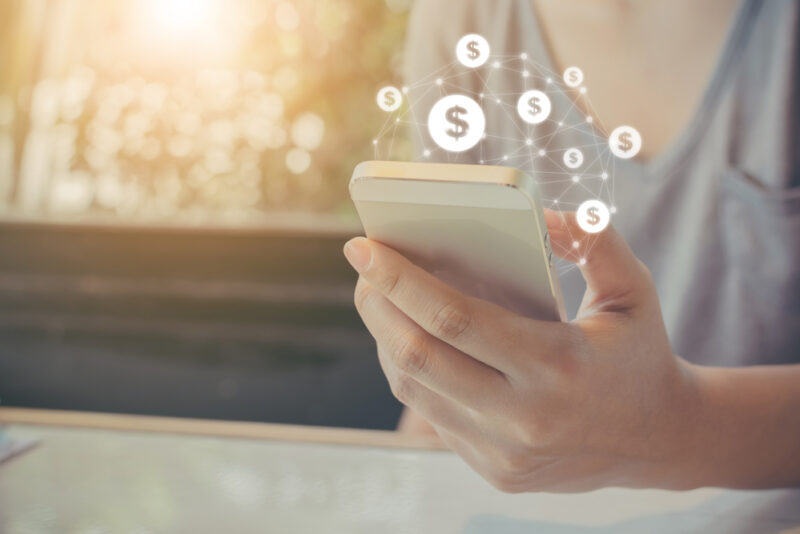ポイントサービスを始める方は必読!資金決済法3つのポイントを解説

はじめに
皆さん、お気に入りのポイントカードはありますか?
現在、数多くの企業がポイントサービスを導入しており、買い物の際に「ポイントカードはお持ちですか?」と声を掛けられることが多くなりましたね。
Tカードやポンタカードはご存知の方も多いのではないでしょうか。
また、ウェブサービス上においても、サービス内で使用できるポイントを導入する企業が増えてきました。
有名なものだとアメーバブログのアメゴールドやLINEのLINEコインなどがありますね。
さて、顧客にとってかなり身近な存在となったポイントサービスですが、企業が新たにこのポイントサービスを導入しようとした場合「資金決済法」という法律が関係してきます。
あまり馴染みのない法律なので、具体的な内容についてはさっぱり・・・という方も多いのではないでしょうか。
そこで、以下では、資金決済法とポイントサービスの関係について、適用の有無やペナルティなどをわかりやすく解説していきたいと思います。
1 ポイントサービスを利用するメリット

「ポイントサービス」とは、ある企業のサービスを利用する状況やステータスに応じて顧客にポイントが発行され、貯まったポイントは購入代金の一部に充てたり商品やアイテムと交換することができる仕組みです。
企業がこのポイントサービスを利用するメリットは、以下の点にあります。
- 顧客の囲い込みによる売り上げの向上
- 顧客データを分析しプロモーションや商品
- コンテンツ開発に活用
- 客単価の向上
- 顧客満足度の向上
- 競合他社との差別化
つまり、ポイントサービスは、顧客だけではなく企業にとってもメリットのあるシステムであるといえます。
2 資金決済法とは

さて、冒頭でも述べましたように、ポイントサービスを導入する場合、「資金決済法」という法律を知っておく必要があります。
「資金決済法」とは、簡単にいうと、お金の移動や支払いの決済に関するルールを定めたものになります。
正式名称を「資金決済に関する法律」といい、2010年4月1日に施行された比較的新しい法律です。
そして、「資金決済法」では導入しようとしているポイントサービスが「前払式支払手段」(まえばらいしき しはらいしゅだん)というものに当てはまる場合には、規制の対象となるとしています。
そのため、ポイントサービスが「前払式支払手段」に当てはまる場合には、一定のルールに従ってサービスを提供する必要があります。
それでは、「前払式支払手段」とは何か、どのような場合に当てはまるのかを次の項目から詳しくみていきましょう。
3 前払式支払手段とは

(1)意味
まず、以下の3つの要件を充たすものが「前払式支払手段」に該当します。
-
- ① 金額等の財産的価値が記載・記録されること(価値の保存)
-
- ② 対価を得て発行されること(対価性)
- ③ 代金の支払い等に使用されること(権利行使)
これだけではいまひとつよく分からないと思いますが、身近なところでみなさんがよく利用している前払式支払手段としては、商品券やギフトカード、SuicaやPASMO、また、スマートフォン上でのアプリ内課金などがあります。
2016年にはLINEが提供するスマートフォン向けアプリ内で販売されていたアイテムについて、「前払式支払手段」に当てはまるか否かが問題になりましたね。
報道もされていたので、ご存知の方もいるかと思います。
それでは以下で、「前払式支払手段」の3つの要件を具体的に説明していきます。
① 金額等の財産的価値が記載・記録されること(価値の保存)
「財産的価値の記載・記録」というのは、商品券やギフトカードを思い出してもらうと分かりやすいと思います。
券の表面に「1万円」など、その商品券にいくら分の価値があるのかが書かれていますよね。
この部分が「金額等の財産的価値の記載・記録」になります。
また近年、SuicaやnanacoのIC式プリペイドカードにお金をチャージして買い物などに利用するタイプのものが普及してきていますが、この場合にもカードに内蔵されたICチップなどに利用可能な金額情報が記録されているため、「金額等の財産的価値の記載・記録」にあたります。
② 対価を得て発行されること(対価性)
「対価性」についてはとても簡単です。
例えば商品券を購入するとき、代金を支払うことでその金額分の商品券を購入することができますよね。
この点が「(事業者が)対価を得て(商品券が)発行された」ということになります。
また、IC式プリペイドカードに関しては、チャージの際に実際に物が発行されるわけではなく、ICチップに金額情報が記録されるだけですが、これも「発行」に含まれます。
③ 代金の支払い等に使用されること(権利行使)
3つ目の要件である「権利行使」については、文字どおり、利用者が対価を支払って得た財産的価値を、現金の代わりに代金の支払いなどに使用することをいいます。
商品券やIC式プリペイドカードを実際に使用する場面を想定すると分かりやすいと思います。
以上の3つの要件のうち、ポイントになるのが2番目の対価性の部分です。この点については後程詳しく検討していきます。
(2)義務
以上の3つの要件をすべて充たす場合は「前払式支払手段」に該当し、発行者にはおおまかに以下のような義務が課せられます。
-
- ① 管轄する財務局長等への届出または登録
-
- ② 表示義務、情報提供義務
- ③ 発行保証金の供託
①は、行政庁への届出や登録です。
②は、一定の事項について必ず表示しなければならないというものです。
③は、発行している前払式支払手段の未使用残高が1000万円を超えた場合、その2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所に供託しなければならないというものです。
(3)ペナルティ
では、「前払式支払手段」に該当し「資金決済法」が適用されるにもかかわらず、これに違反した場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
基本的には懲役や罰金という処分が下されますが、重いものでは
-
- 最大で3年の懲役
あるいは
- 300万円以下の罰金
になる場合もあります。
資金決済法が利用者保護のために作られた経緯を考えると、当然の処分かもしれませんね。
4 ポイントサービスは「前払式支払手段」に当てはまる?

それでは、ポイントサービスが「資金決済法」に規定されている「前払式支払手段」に当てはまるのか、順番にみていきましょう。
まず、「前払式支払手段」に当てはまるには、繰り返しになりますが、3つの要件を充たす必要がありました。
-
- ① 価値の保存
-
- ② 対価性
- ③ 権利行使
ポイントサービスにおいては、ポイントという財産的価値が利用者のマイページやポイントカード、また、企業のサーバー上に記録されているため、①金額等の財産的価値が記載・記録されること(価値の保存)の要件を充たします。
また、利用者が貯めたポイントは、買い物の際に現金の代わりに使ったり、商品やアイテムと交換したりすることができるため、③代金の支払い等に使用されること(権利行使)の要件も充たします。
では、②対価を得て発行されること(対価性)の要件は充たすのでしょうか。
一般的に、「対価」には、現金だけではなく財産的価値のあるものはすべて含まれるとされています。
このように、「対価」の範囲は広くて曖昧であるため、ポイントが「対価」を得て発行されているかどうかは難しい判断になります。
そのため、最終的には常識に従って主観的に判断するほかないとされています。
つまり、利用者が「対価」を支払ったと認識したかどうか、が基準となるのです。
この点、ポイントサービスにおける「ポイント」は、単なるおまけや景品として無償で発行されるため、「対価」を得ているとはいえず、②の要件は充たしません。
利用者側から見ても、「対価」を支払ってポイントを得たという認識は基本的にないでしょう。
そのため、ポイントサービスのうち、ポイントを単なるおまけや景品として発行するものについては資金決済法の規制対象とはなりません。
つまり、発行者に対する前に説明したような義務はなく、ポイントの発行や廃止について企業が自由に決定することができます。
ただし、同じように「ポイント」という名称を使用している場合でも、利用者から「対価」を得て発行されるものに関しては、「前払式支払手段」に当てはまるため、資金決済法の規制対象となってしまうことには注意が必要です。
例えば、ウェブサービス上であらかじめポイントを購入し、そのポイントを使ってサービスを利用する、というような場合です。
要するに、資金決済法の規制の対象となる「ポイント」とは「購入型」のポイントを指すのであって、無償で発行される「付与型」の場合には資金決済法の問題を気にする必要はありません。
5 他の法規制もあることに注意!

仮に、導入しようとしているポイントサービスが資金決済法の規制を受けないとしても、企業との関係で弱い立場にある利用者を保護するため、景品表示法(景品規制)や消費者契約法などの利用者保護のルールが適用される可能性があります。
①景品表示法(景品規制)
「景品表示法」(景表法)とは、その名のとおり、不当な景品類と不当な表示を規制する法律です。
一般に、「景品」とはおまけや粗品などを指します。「おまけ」といっても、目に見える物(例:プロ野球チップスについてくる野球選手のカード)に限らず、ポイントなどの目に見えない物でも「景品」にあてはまることがあります。
そのため、企業の発行するポイントが「景品類」に当てはまる場合には、発行するポイントの最高額や総額について制限を受ける可能性があります。
②消費者契約法
「消費者契約法」とは、企業と比べて情報弱者で交渉力が弱い消費者を守ることを目的とした法律です。
ポイントサービスは、その有効期限や廃止に関して、原則的に企業が自由に設定することができます。
しかし、利用者がポイントを利用できないような短い期間を設定したり、悪意のある設定をしたような場合には消費者契約法によって無効になる可能性もあります。
また、経済産業省からもガイドラインが出されており、ポイントサービスを導入する企業は、以下のガイドラインも遵守する必要があります。
6 ポイントサービスを終了する場合

仮に、ポイントが前払式支払い手段に当てはまる場合には、合わせて、ポイントサービスを終了する場合の手続きについても知っておく必要があります。
前払式支払手段は、商品を買ったり、サービスの提供を受けるために発行されるものですから、その払戻しは、原則として禁止されています。
しかし、前払式支払手段の発行業務を廃止したときなどは、利用者を守るため、例外的に未使用分についての払戻しを義務付けています。
この場合、発行者は、発行業務の廃止と払戻しのスケジュールなどについて、まずは内閣総理大臣に届け出た後、利用者にも知ってもらうために、合わせて、新聞にも払戻しをすることやその手続きについて記載して公告します。
さらに、すべての営業所・利用店舗に払戻しについての手続きや払戻し期間(60日以上)の掲示を行います。
利用者は、この手続きに沿って払戻しの申請をし、発行者が払い戻しをするという流れになっています。
7 まとめ
これまでの解説をまとめますと、以下のようになります。
- ポイント①:ポイントサービスを導入するにあたっては、「資金決済法」の「前払式 支払手段」に当てはまるかどうかが重要。特に、「対価性」の有無がポイント
- ポイント②:資金決済法以外にも、(ⅰ)景表法や(ⅱ)消費者契約法といった弱者である利用者を守るためのルールがあることに注意
- ポイント③:仮にポイントサービスが「前払式支払手段」に当てはまる場合、サービス終了時には払戻し義務が生じる
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。