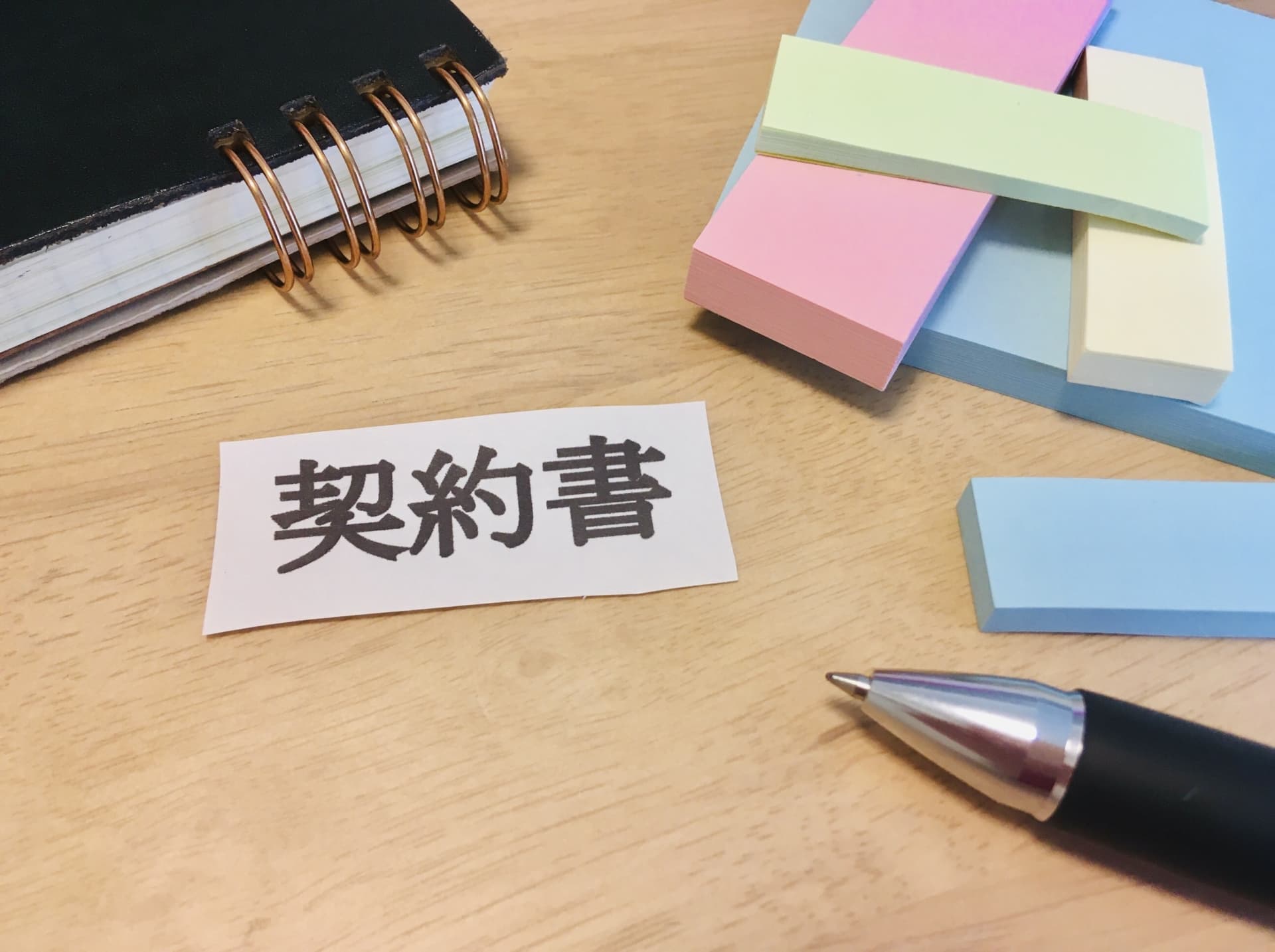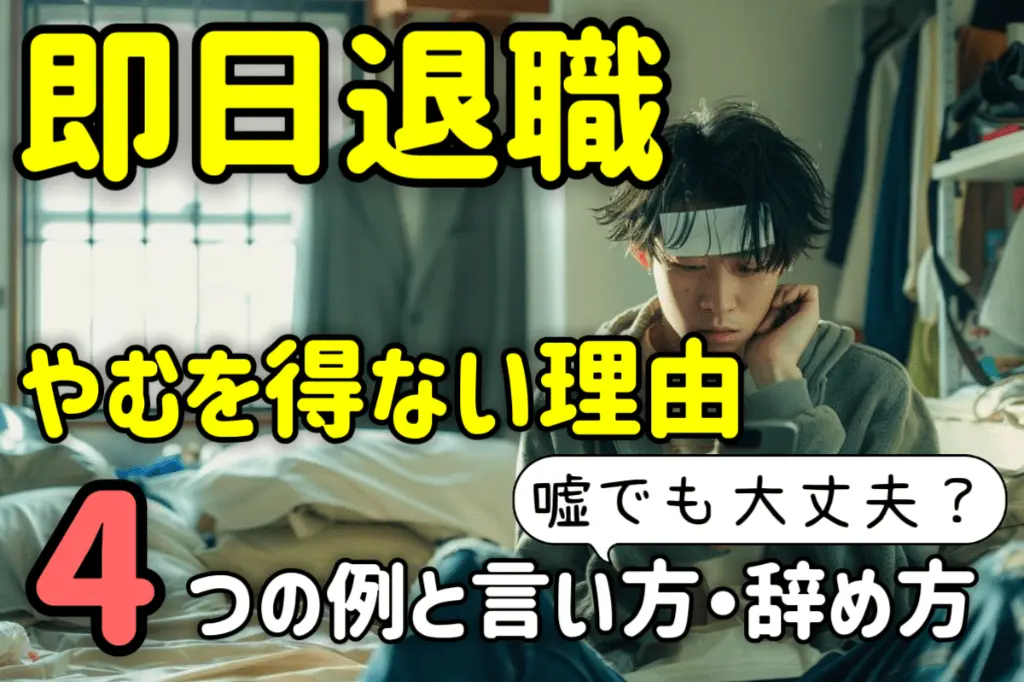不合格を糧に前に進む──弁護士が語る「中小企業診断士二次試験」合格への道

みなさん、こんにちは。弁護士の勝部です。
先日(2025/1/15)、令和6年度中小企業診断士第2次試験(筆記試験)の発表があり、無事に合格していました。
けれども私は、弁護士になるための司法試験の勉強過程で「不合格」の経験を何度か味わってきた人間でもあります。つまり、“試験で落ちる悔しさ”は身にしみてわかっているつもりです。
だからこそ、今このタイミングで残念な結果に直面してしまった方々――「不合格だった……」と落ち込み、勉強への意欲を失いそうな方々へ、何かお伝えできることがあるかもしれないと思い、この記事を書いています。
今回は、私が中小企業診断士試験に取り組んだ体験をもとに、「合格をつかむための心構え」や「試験との向き合い方」などを綴っていきたいと思います。
今回は法律トピックと関係ない内容ですが、どうぞ肩の力を抜いて読んでみてください。
1.不合格を経験したからこそわかること
まずはじめに、私自身、司法試験という大きな試験で不合格を経験しました。あのときの落ち込みは相当なものでした。「次は本当に受かるのかな」「自分のやり方ではダメなのかな」など、いろいろな不安が頭をめぐり、しばらくは勉強にも手がつかなくなったものです。
しかし振り返れば、この“どん底”を味わった経験こそが、合格を勝ち取るための大きな糧になったと思っています。
不合格という結果は、人によっては「自分はダメだ」と人格を否定されるかのように感じがちです。でも本当はそこまで重く考える必要はない。それにいかに早く気が付くかが勝負を分けるのではないかと思います。
試験はあくまでも「試験」――合格か不合格か。その日のコンディションや、どんな問題が出るかによっても結果は左右されます。もちろん勉強量や理解度、論述力など基本的な実力も重要ですが、ある程度は運の要素もあります。また、試験というのは出題する側が一定の基準を設けて受験者の能力の一部を部分的に判断しているだけのものです。不合格になってしまったことで、努力やその人の人格そのものが否定されるわけではない、ということをまずは胸に留めておいて欲しいところです。。
2.中小企業診断士を目指したきっかけ
私が中小企業診断士を目指そうと思ったのは、2023年5月に「飲食業界のDX化」や「地方創生」に取り組むコネクテッドコマース株式会社という会社の取締役に就任したことが大きなきっかけでした。こちらの会社です。
NTT東が新興と“売らない店舗”オープン 10年で2000店舗の勝算は
経営メンバーとして、事業を広く俯瞰し、改善策を提案していく――まして飲食業のオペレーション自体は専門外でもあります。そのような立ち位置で知見を深めたいと考えたとき、仕事でお世話になっている「中小企業診断士」の存在を思い出したのです。
中小企業診断士の学習範囲は、とにかく幅広い。経営戦略、会計、運営管理、情報システム、法務、経済学、中小企業政策など、経営に関わるエッセンスが網羅されています。
経営に関する知見を早急にインプットしてキャッチアップするために、この知識を体系的に身につけることは必ずプラスになるはずだと思い、本格的に勉強をスタートしました。
3.不合格にへこまないための「確率思考」
中小企業診断士試験には一次試験(択一)と二次試験(筆記+口述)がありますが、二次試験の合格率はざっくり言って20%弱、択一合格者の5人に4人が落ちる試験です。
そんなデータを見たとき、「なんて難関なんだ」と思うのが普通かもしれませんが、私の頭には別の考え方が浮かんでいました。それは「期待値20%のくじを引いているようなもの」という発想です。
つまり、合格率が20%ということは、端的に言えば「5回受ければ1回は当たるかも」という期待値の話です。もちろん受験勉強のレベルが一定以上あるという前提の上ですが、「今年だめでも、来年またやればいい。そのうち必ず合格できるだろう」というふうに捉えるのです(後で触れますが、私は一次試験についてはある程度安定的に合格できるだろうという見立てもあったので、二次試験については徐々に確率を上げていくようなアプローチで対応できそうという感覚を持っていました。)。
この「くじ引き理論」的思考は、実は私が司法試験に合格する前、営業の仕事をやっていたときに教わった考え方でもあります。100件アタックして1件取れれば上出来だよ、という世界です。つまり「ダメだったときの感情的ショックをいかに減らして、平常心を保つか」というのがポイントということです。試験も同じで、何回か挑むうちの「1回」で合格すればそれでいいんだ、と長期的に構えることで、目先の不合格に心が折れにくくなるのです。
4.日々の勉強への向き合い方
とはいえ、それは「勉強をいい加減にやってもよい」という話ではありません。やはり一定の質と量の学習は必要ですし、理解が浅いままでは確率自体が低いままです。
私が心がけていたのは、毎日少しでも勉強を進めるということでした。そして、自分のモチベーションが落ちないように、「今年絶対合格しなければいけない」という悲壮感で自分を追い詰めないようにしていました。一生懸命さは、モチベーションを高めるエンジンにもなりますが、ときに自分を傷つける刃にもなりかねないのです。
社会人になると、プライベートの時間をすべて勉強に割くのは現実的に困難です。仕事が忙しかったり、家族と旅行の予定が入ったり……。でもそういうときでも、スキマ時間の活用を徹底しました。ちょっとした移動の合間に録音したテキストを聴き、あるいは昼休みに数ページだけでもテキストを読み返す。こうやって、「継続して頭に入れ続ける」ことが大切だと考えたのです。
5.答案作成の基本方針:全知識&過去問重視
二次試験の筆記対策で、私がメインに据えたのは「全知識」と呼ばれる有名な基本書です。
2024年版 中小企業診断士二次試験 2次試験合格者の頭の中にあった全知識
これをまずは繰り返し読み込み、さらにそこに書かれている内容を「絶対に落とさない」という意識で、録音ファイルに吹き込みました。そして、2倍速や3倍速などで再生して耳からもインプット。いわゆる「一つの教材を完璧にする」というやり方です。
もちろん、それでカバーしきれない知識もあるかもしれませんが、皆が知っている知識を落とす方がよほど危険という、まあこれも確率論ですね。
あとは、過去問演習です。過去問を解いてみることで、どういう視点で問題文を読むべきかが体感できます。
私の場合、過去問を10回も20回も解くような「量」よりも、1回1回をしっかり吟味して、自分で採点してみるという「質」を重視しました。形を変えて何度も聞かれる知識もあれば、もう二度と聞かれないようなマイナーな知識もあります。後付けで満点を目指すのではなく、初見でどんな戦い方をするのか、というシミュレーションを繰り返していました。
6.試験に合格することの意義
「中小企業診断士は独占業務がないから資格としての価値は薄いのでは?」という声を耳にすることがあり、これがモチベーションの妨げになることもあります。確かに、弁護士や税理士、公認会計士のように、資格がないとできない“業務独占”という要素はありません。生成AIの進化もあり、コンサル業務そのものがどうなるかわからない、という見方もあるでしょう。
しかし、私自身は「資格を取るまでの学習プロセス」に大きな意味があると考えていました。中小企業診断士試験の一次・二次を通じて、経営に関わるあらゆる知識を体系的に一巡できます。しかも、ただ表面的に学ぶだけでなく、試験合格ラインを超えるまで突き詰める過程で、新たな気づきや発想も得られるわけです。
これは、弁護士をはじめとした他の士業の方々や、企業経営者の方々にも大いにプラスになるはずです。幅広い視点や、問題解決の思考プロセスを養う上で、私にとってはとても価値ある挑戦でした。
7.合格を目指す方へのエール
「今回ダメだった……」「あと一歩足りなかった……」という方に、私から伝えたいのは、「この結果に一喜一憂する時間をなるべく短くしてほしい」ということです。どうしても悔しさや落ち込みから立ち直れない時期はあると思います。しかし、あまりに長引かせてしまうと、次のステップへのエネルギーが削がれてしまいます。まして、一時的な感情でこれまでの積み重ねを放り出してしまったり、自暴自棄になってしまっては元も子もありません。
自分は野球が好きなので、ダルビッシュ有投手が今のように本気で野球に取り組むきっかけになったエピソードをご紹介します。
——————————————————————————
「20歳の時、東京ドームで5点ぐらい取ってもらったのに簡単に追いつかれた。なんでこうなるねんって……で、東京ドームホテルに泊まってたから、水道橋あたりやったと思うけど、40歳になった自分がホームレスになって、お金もない、ご飯も食べられへんっていう状況を1回、自分で想像してみたんです」
(中略)
「そんな時に神様がいきなり現れて『おい、お前、20歳の時のことを覚えてるか? あの頃に戻りたいか? 1回だけチャンスやる。その代わり、できること全部やらへんかったら、またここに戻すぞ』って言われたら、誰でも絶対戻るでしょう?
で、僕はパッと目を開けて、たった今、神様のお陰で20歳の自分に戻って来たっていう体(てい)にしたんです。そしたら、もう未来が見えてるし、当時の僕はプライドも高かったから、『このまま終わるのはどうしても嫌や、ホンマにちゃんとやらなアカン』と」
https://number.bunshun.jp/articles/-/840376?page=2
——————————————————————————
失敗に直面したときの受け止め方は人それぞれだと思いますが、自分はこの「失敗は神様からのメッセージ」というか、試されているという解釈が好きです。自分も去年の初回はダメだったのですが、そこでやめていたら今年にはつながらなかったとも思います。
ちなみにダルビッシュ投手はこれをきっかけに体づくりから食事まで徹底的にこだわり始めて、その後は多くの方が知る大投手になっています。
大事なのは、“合格まではプロセスの一部”として割り切り、失敗を“自分の伸びしろ”だと考えることなのかなと思います。そしてまた、毎日の生活の中に少しでも勉強を組み込み続けること。そうやって長期的に学習を積み重ねていけば、いつか必ず結果はついてくると思います。
8.おまけ:択一をこうして乗り切る
最後に、私が「一次試験はそう苦労しないだろう」と考えていた理由を共有しておきます。中小企業診断士試験では、一次試験が7科目ありますが、そのうちの経営法務は私にとって“法律ど真ん中”で、ほぼ無勉でも満点が狙えるカンスト状態でした。同様に、経営情報システムもエンジニア経験があったのでやはりカンストしていました。
つまり、私の場合、この2科目は勉強時間をショートカットできるだけでなく、+40~60点の“上澄み”がある程度見込めるボーナス科目だったわけです(さすがに2科目とも常時満点は無理そうでしたが、どの年の過去問を解いても両方80点以上ではあったので、2科目は足切りギリギリの40点でもよいという計算ができたということです。)。あとは残り5科目で大崩れさえしなければ一次試験はクリアできる。そう思うと、焦りがなくなり、「企業経営理論、運営管理、財務・会計はどうせ二次で問われるので、やるならここをしっかりやろう」と、二次試験重視の戦略が取りやすかったのです(ちなみに弁護士は一次の財務・会計も免除を受けられますが、せっかくの機会なので免除は受けずに受験していました)。
もちろん、人によって得意・不得意は違うので、私のケースがすべての方に当てはまるわけではありません。ただ、「自分なりにどこで点数を稼げるか」を見極めて択一の安心感を持つことはとても大事だと思います。一次科目は二次の合格に直結しませんが、ここでの安定感は二次にもそれなりに影響してくると思います。
9.さいごに
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
もし今、「不合格」の結果に直面してモチベーションが低下している方がいらっしゃったら、どうか今回の結果だけで自分を否定しないで欲しいと思います。
日々の学習を、自分を成長させるための“習慣”にしてみるのもいいでしょう。テキストや過去問を丁寧に復習しながら、新しい気づきを見つけていくことの楽しさを感じられるようになると、不思議とモチベーションは続きやすいものです。試験本番までの長い道のりを、ゲーム感覚で楽しんでしまうくらいの余裕を持つのも、ひとつの手かもしれません。
最後に、あなたが再チャレンジを決意したとき、この文章が少しでも励みになれば、書き手としてこんなに嬉しいことはありません。合格へ続く道は、必ずしも一直線ではないですが、試行錯誤を重ねていけばきっとたどり着けるはずです。諦めず、一緒に歩んでいきましょう。
自分もまだ口述が残っているのに仮にダメだったらと考えるとこういう記事を投稿するのも気が引けましたが、口述ダメで一次からやり直すことになったら、それはそれでまたチャレンジして合格したいと考えています。もちろんそうならないようにできることは全てやり、退路を断って準備したいと思いますが。
それでは、また。皆さんが、次こそ自分の目標を達成できることを、心から応援しています。きっとあなたなら大丈夫。焦らず一歩ずつ、一緒に前に進んでいきましょう!
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。