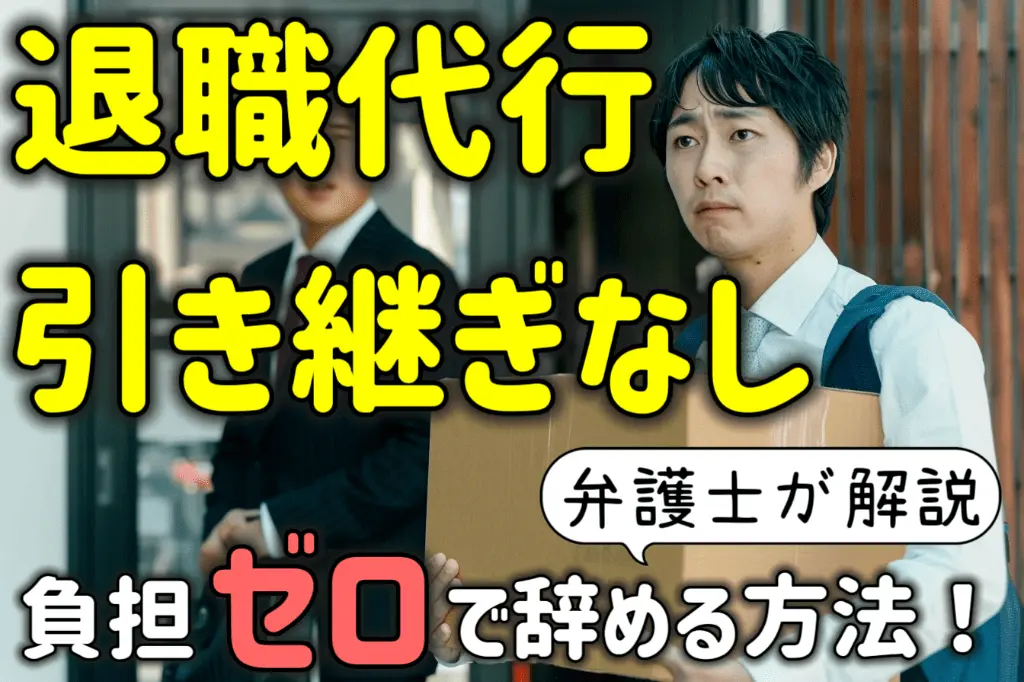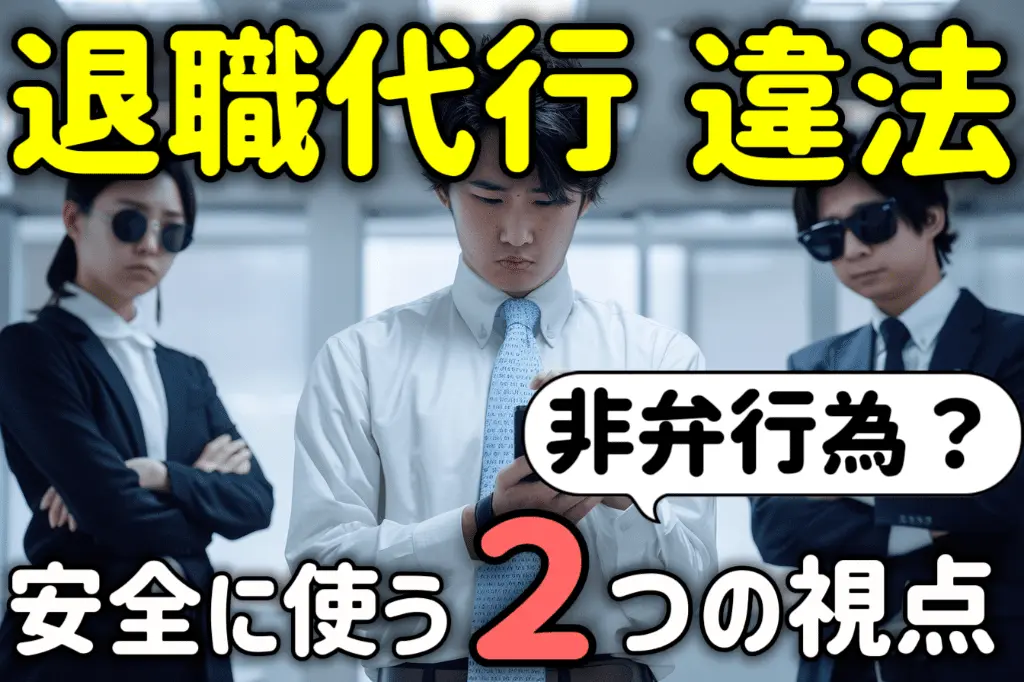【コンサル思考】トヨタ生産方式を弁護士業務に応用し、無料法律相談をやめた私の方法
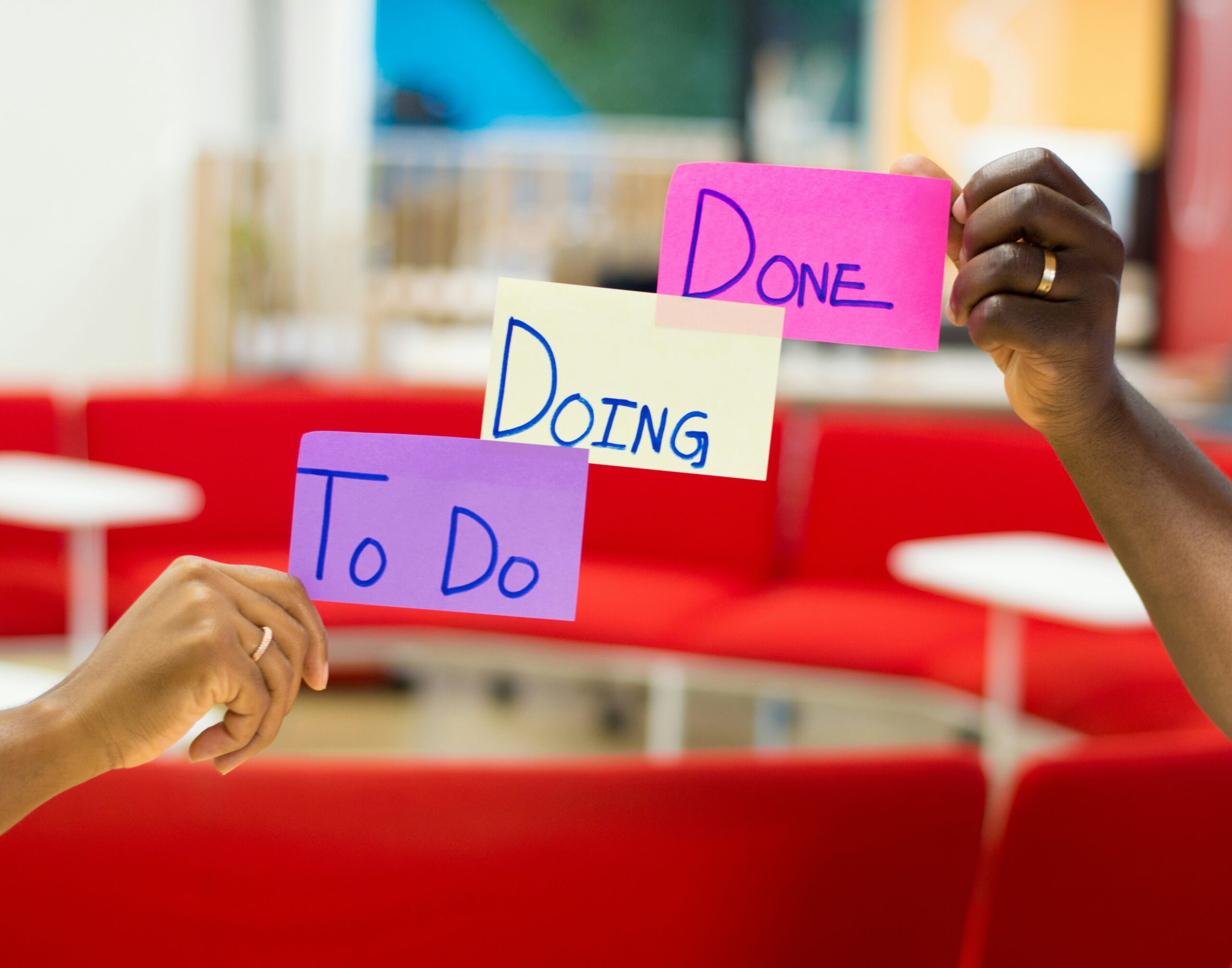
はじめに
弁護士の勝部です。
今回は、弁護士の生産性向上と無料法律相談の落とし穴について私が考えていたこと、そして自分がどういう思考で無料法律相談を止めたのかについてお話していきたいと思います。
弁護士としての生産性を高め、より多くの利益を上げることは、特に中小法律事務所や一般民事を扱う「町弁」にとって大きな課題です。この記事では、無料法律相談がどのようにして生産性を低下させ、収益に悪影響を及ぼしているか、そしてそれを改善する方法について解説します。
なお、今は企業法務をやっている私ですが、昔は一般民事事務所にいました。
その経験から比較すると、確かに企業法務の方が法律相談でお金をとりやすいという側面はあるのかなとは思います。
ただ、企業が弁護士費用を使って節税できると言っても、節税効果(タックスシールド)が働くのはせいぜい10~20%程度です。キャッシュが出て行かないように無駄な法律相談を回避しようというモチベーションは企業法務でも当然あります。
ですので、町弁だから、企業法務だから、というのはそれほど本質的な違いではないというのが私の考えです。
1 無料法律相談が生む生産性低下の問題
多くの弁護士が未だに無料法律相談を提供していますが、これが弁護士の労働生産性に与える悪影響は無視できません。
本来時間あたり単価が発生すべき弁護士の稼働を使って、その結果受任ができないということになると、無料での相談が事務所リソースを圧迫し、業務効率を損なうケースが多いです。
2 トヨタ方式に学ぶ業務効率化のヒント
生産性向上において、企業の中でも特に成功を収めた例として、トヨタ自動車のJIT(ジャストインタイム)、後工程引取方式、カンバン方式、という生産管理手法が挙げられます。
多くの方が耳にしたことがある概念かも知れませんが、弁護士業務の効率化にも応用できることがたくさんあります。
これらの手法は、ノウハウとしての表面的手法だけを見ても意図が分かりにくいですが、要するに、
売上につながらない所作は全て悪
という考え方です。
当たり前に感じられるかも知れませんが、全ての従業員が個々の作業についてどう売上につながっているのかは、意外と意識できていないと思います。
これらの生産の無駄をゼロに近づけることで生産性をマックスにする、という方法論がトヨタ方式に集約されています。
この考え方は、弁護士業界にも応用できると考えています。
弁護士はサービス業であるため、製品を作るわけではありませんが、売上に繋がらない法律相談や業務に時間を費やすことは「無駄な生産」です。
特に、無料相談が多い事務所では、このような無駄が業務効率を大きく低下させる原因になっています。
3 無料法律相談はすべて悪なのか?
トヨタ的考え方に従うと、「無料」だからと言って全ての無料相談が悪ということではありません。
なぜならば、結果的に受任につながった相談であれば、これは必要な生産と評価してよいことになるからです。
逆に対外的な相談チャネルを閉じてしまったことにより売上が低下してしまったら元も子もないわけです。
つまり、
-
結果的に受任につながる相談
: 売りにつながるから無料でもよいよね
結果的に受任につながらない相談
: そもそもお断りするか、原価分だけでも有料設定しましょうね
と整理できることになります。
至極当たり前といえば当たり前ですが、重要なことは、この精度をMAXにするためにPDCAを回しまくる、ということです。
4 無料法律相談は本当に顧客にとってよいことなのか?
顧客が無料法律相談を利用する理由は、法的トラブルや課題を解決したいという思いからです。
しかし、無料で相談できるからといって、それが最適な解決策を導くかどうかは別問題です。
無料相談が顧客にとって不利益になる大きな理由は、当該問題に対して専門外の弁護士に対して時間を割くことがあるからです。
相談後、弁護士がその案件に対して十分な経験や知識を持っていなかった場合、顧客にとっては時間の無駄になってしまいますね。
これは無料であっても顧客にとって価値のないサービスであり、弁護士の方の生産性も落ちることにつながります。
ですから、弁護士の側でまずこの点を先回りし、自身のサービスを分析し、適切な顧客層の設定とサービスの最適化をしておくことが重要になります。
5 トヨタ生産方式の応用
(1) 基本的な考え方
効率的な生産、という観点からは、売りにつながるというジャッジメントができてから、生産量が決まってくるということになります。
しかしながら、最終的に顧客が自分に依頼をするかどうかは、100%顧客が自由に判断すべきことであり、サービス提供者側からはコントロールが不可能です。
では、サービス提供側にできることは何か。
私は、自分が提供できるサービスの内容を明確にし、適切なプライシングをすることだと考えています。
予めサービス内容と価格が明らかであれば、「相談すべきでない弁護士に相談申込をしてしまう」という無駄の発生はかなり減らせるのではないかと思います。
(2) 一連のサービスとPDCAサイクル
また、自分が相談時においてする説明や、受任時において締結する契約書や請求書、最初に出す通知書や良く使う書式のひな形を用意しておけば、更なる短納期を実現することができ、顧客満足度が上がります。
そして、いったん収益につながるサービスが設計できたら、Q(quality:品質)、C(cost:コスト)、D(derivery:納期)を改善して更に顧客満足が上がらないか、様々な改善をしていくことになります。
PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回す、というやつですね。
これによって段々と顧客満足が上がって、差別化ができるようになってきます。
(3) 仕掛在庫の管理
また、自分が相談時においてする説明や、受任時において締結する契約書や請求書、最初に出す通知書や良く使う書式のひな形を用意しておけば、更なる短納期を実現することができ、顧客満足度が上がります。
6 サービスの質が上がると自然と無料相談はなくなっていく
実は、受任率が高くなってくれば、法律相談を無料にするか有料にするかは経営に与えるインパクトとしては軽微です。
正直、どっちでもよいというのが実感です。
なぜなら、相談をする前に請求書を出し、更に受任後に請求書をまた出すことになってしまい、二度手間ですし、これをまとめられるのであればまとめてもよいのかなとも思えるからです。
ただ、最終的には以下の2つのメリットが享受できるので、結果として有料にしているということですね。
- メリット1:決裁権の問題を回避できる。
無料相談を利用する顧客の中には、決裁権のない人が多いことがあります。たとえば、新規事業の担当者が情報を集めているが、決裁権がないため無料相談の方がやりやすい、というケースがあります。
仮に、こういった方が相談をしてきた場合、最終的な決裁権がないために、その相談が実際の依頼に繋がらないケースが多く見られます。
逆に有料の場合は既に社長や上司にも話が通っていることが多いので、このようなケースは少なくなってきます。
- メリット2:生産性が下がらない。
受任率を高めると言っても、100%にすることは不可能です。むしろ、無料で相談したから、何か居心地が悪い。断りにくいので今回の件はちゃんと費用を払っていったん清算した方が気分がよい、という方も少なからずいます。
こういった傾向の考え方は、お金の使い方が上手い人に多く見られます。お金の使い方が上手な人は、一時的な雰囲気で浪費をすることがなく、自由な意思決定をしたいと考える傾向にあります。そして、自由な意思決定の結果この支払をしようという考えをまとめてから消費行動に入ります。
短時間の相談であっても、大人と大人が互いの都合をつけてやり取りをしているわけですから、それを無料にすると言う方がむしろ不自然な発想とも言えます。
こう考えた結果、現在のやり方に落ち着いていますが、今後どのようなやり方がベストなのかは常に模索すべきだと考えています。
また、やり方はターゲット市場や地域特性によっても変わってくるのかなと思います。
まとめ
今回は、私がどういうプロセスを経て無料相談を止めて行ったのかをお話しましたが、これは意識的にやったことというより、生産管理の勉強をしていればまず真っ先に改善すべきところとして、自然に見えてきたように今では思います。
製造業の考え方がサービス業に応用できるの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、以下の本はとてもお勧めです。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。