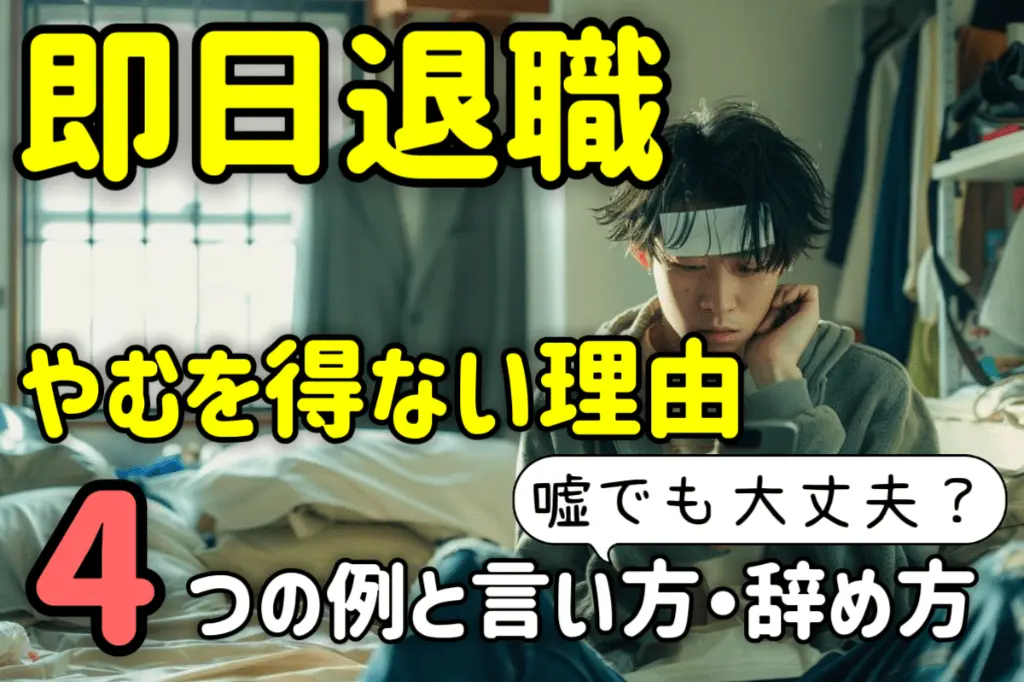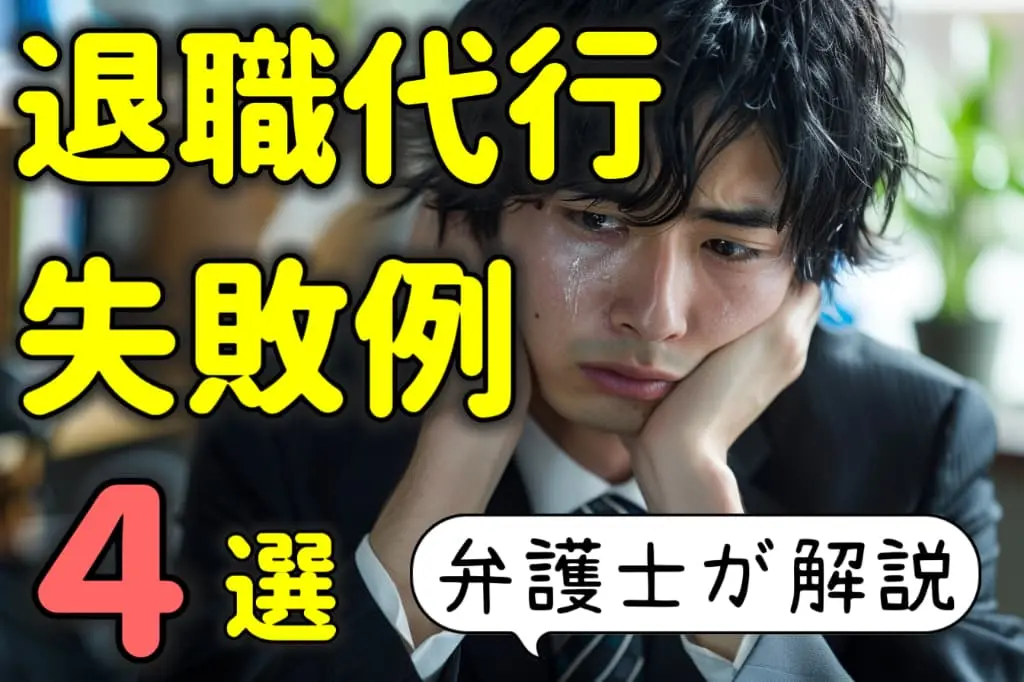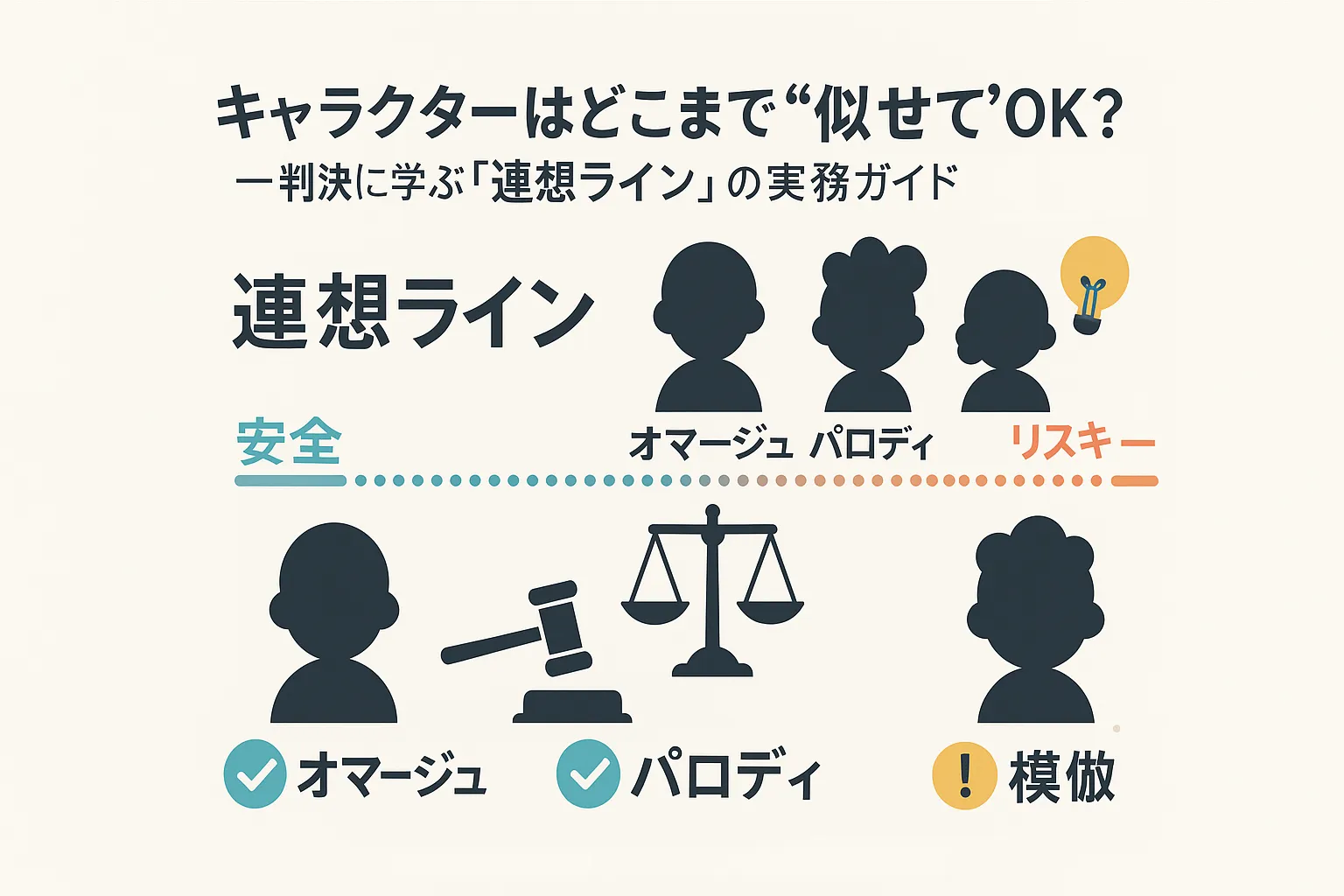弁護士の私が「中小企業診断士」の勉強を始めたワケ─AI時代の新たな価値を求めて

弁護士の勝部です。
従前からこのブログ等でお話していたように、私は2023年の5月から中小企業診断士の勉強を始め、今日(2025年2月5日)正式に合格しました。
いま仕事もかなり立て込んでいて、なかなかまとまった文章を書く余裕はないのですが、合格直後はXのインプレッションも増えるということもあり、また、すぐに実務従事や診断士プレ活動が始まることもあるので、このタイミングで、私がなぜコンサルティングや中小企業診断士の学習に踏み出したのか、そのきっかけをお話ししたいと思います。
飲食事業の取締役就任とChatGPTの衝撃
私が中小企業診断士の勉強を始めようと思った大きな理由の一つは、ある飲食事業の取締役を務めることになったことでした。経緯は以下のポストに書いています。
不合格を糧に前に進む──弁護士が語る「中小企業診断士二次試験」合格への道
経営に直接関わる立場になったことで、法的リスクをいかに回避しつつビジネスを成長させていくか、実践的な経営知識が必要だと強く感じたのです。
もう一つは、ちょうど2023年の2月頃から話題になり始めたChatGPTの登場でした。
登場当初の弁護士によるChatGPT評は、「プロレベルには到底至っていない」というものでしたが、自分は「これは近い将来、AIが本格的に弁護士の仕事を脅かしてくるかもしれない」と直感していました。
最初のChatGPTは、たとえば弁護士1年目のアソシエイトが書いたリサーチのように「形式はそれっぽいけど中身が全くダメ」という状態でした。しかし、他方で、パッと見の印象が「これ、しっかり知識を与えれば十分正確な回答を出せるのでは?」と思える完成度だった。これが脅威に感じた理由です。
なぜならば、人間のアソシエイト弁護士(勤務弁護士)もダメダメの状態からスタートして、その後知識を吸収して一気にできるようになっていくものであり、自分もそのような過程を何度も目にしていたからです。
そして実際、前提知識やプロンプトの工夫次第で、かなり正確な法的回答に近いものが生成されるようになってきています。今では、高度な有料版のGPT(o1 proなど)を使えば、既に法的な鑑定の領域までできてしまっています。これが鑑定であれば有料版の生成AIは非弁(弁護士法違反)ということになりますが、それで生成AIの法的な利用が何らかの形で規制されるようになる可能性はほぼゼロでしょう。
弁護士としては、正答率が100%でなければ基本仕事の競争相手として敵視すべき存在とは言えません。1%でも嘘が紛れていると専門知識のないクライアントはそのリスクを回避することが困難だからです。
ただ、もうこれは時間の問題だなと、それは直感しました。
AIに代替される時代に、弁護士はどう生きるか
AI技術の進歩は止められません。
では、人間の弁護士に何が求められるのか。単なる職人的スキルやニッチな裁判実務だけに頼っていると、その需要自体が将来ゴソッとなくなっても、誰も補償してくれません。
その危機感が私の中で一気に高まりました。
自分はAI以前から、リスクヘッジという名目で事業コンサルやエンジェル投資という活動を始めていました。ただ、この活動をするだけであれば中小企業診断士の資格は必須とまでは言えません。
自分が考えたのは、法律の専門家として、AI普及後に需要が出てくるビジネスは果たして何なんだろうか、ということです。
AIによるタスク処理が実用したら企業はどのような発想をするか?
当然、AIで代替可能な仕事はAIで代替し、不要な人材は解雇する(レイオフ)という行動に走るだろうと考えられます。
しかし、この動きは自分は全く逆だと思っていて、むしろAIを駆使して生産性を上げられる人材が一つの企業にしがみつく必然性がなくなるので、人の囲い込みに走るのではないか、ということになるのでは、と考えました。
自分が弁護士として独立した後に感じたのは、「一つの企業や事務所に所属しているというのはなんて時間効率が悪いんだろう」ということでした。本来、自分の手柄で上がった売上は、会社に所属していなければ自分が独占できますが、しかし、雇用という立場だと成果報酬はわずかですし、自分が働く場所、対象、時間帯は決められません。
一定の不自由がありながら組織に帰属する動機は様々です。リスクヘッジもあると思いますし、組織でなければ得られない大きな仕事へのコミット、優秀な上司、同僚とチームで働くこと自体の楽しさ等々、色々あると思います。
ただ、綺麗ごとは言ったとしても、つまるところ、今まで一番大きな理由となっていたのは、生活の安定や自分で仕事を取ってきて処理することへの不安ではないかと思います。つまり、自分一人で働いていると急に仕事が来なくなったりするので、会社に所属していた方がいい、ということです。
ところが、優秀な人材が副業で50万円、60万円と稼げるようになると、無理に会社に所属するモチベーションがなくなってきます。AIが優秀になって、コンテンツ制作、ウェブ運用、投資などの手法で優秀な人がさらに小銭を稼ぐのは難しくなくなるはずです。そうなると優秀な人からどんどんやめていってしまうというリスクがあります。
企業としては、ここに先手を打って、優秀な人が会社に残りたいという環境を作る、まさに人的資本経営の発展版ですが、大企業だからこそできる大きなプロジェクトや、成長できる環境の構築にお金を使う方向に行くのではないかと想像したのです。
組織に対する考え方の変容
この辺りは、中小企業診断士試験(2次)で言うところの事例1の発想ですね。企業が高いパフォーマンスを出すための人材育成、組織の在り方の追求という分野です。
私自身、「これは今後、企業が本気で取り組むことになる」と予測しました。AIが普及した未来では、人はより多面的な知識とスキルを駆使して生産性を何倍にも引き上げられるようになるからです。
こうしたニーズを取りにいくために、私が「中小企業診断士」の資格取得を目指したのは自然な流れでした。
思い返してみると、中小企業診断士の試験勉強を始めるまでは4事例の勉強はしたことがなかったのに、なぜそういう考え方ができたのか、あるいは勉強していく過程でそのような、当初は抽象的でラフな発想に過ぎなかったものが徐々に具体化していったのかも知れませんが、今考えるとスティーブ・ジョブスが言うところの「点が線でつながった(Connecting the dots)」ということなのかも知れません。
もちろん資格を取ること自体がゴールではありません。合格に向けて勉強する過程で経営視点や最新ビジネス動向を身につけ、実際に企業やクライアントに貢献できる弁護士・コンサルタントになりたいと思っています。
また、私も今年で50歳です。仕事や家庭がある中での学習はなかなか大変ですが、逆に「AIを活用して効率よく複数のスキルを身につける」という新しい学びのスタイルを実践し、それを普及させる活動は面白いかなと考えたのです。
自分で実際に試行錯誤しながら、このプロセスを企業や個人にも提案できるようにしていく。それが次の時代に必要な高度人材のあり方ではないかと考えています。
AIと人が協働する未来へ
AIがあれば、法律相談やドキュメント作成の多くが自動化されるかもしれません。では人は必要なくなるのか? そうではありません。AIを使いこなし、複数の分野を横断する知識を持つ「高度人材」こそが重宝される時代になると私は予想しています。
例えば、医師でありながら会計や内部統制、情報セキュリティにも詳しいという人材が複数人でチームを組んで、AIのパフォーマンスも駆使しながら日本国内での医療ミスをゼロに近づける、なんていう動きができたとしたら、これは社会全体にとって好ましいことです。
弁護士はどうしてもリスクが顕在化した後の責任の振り分けというフェーズでしか自分の能力を生かす場がありませんが、そもそも不幸な事故が起こらないようにするという仕事は、とても魅力的ですしやりがいがあります。様々な社会課題に対する新たなアプローチを考案する人も出てくるかもしれません。
そんな人材を活かすために、企業がもっと積極的に人的資本経営やリスキリングに投資する。
これによって組織の生産性は飛躍的に向上し、社会のさまざまな課題も解決に近づくはずです。私が想像したのは、まさにそんな「未来のしくみ」を作る一員として貢献していきたいという未来です。
合格後にやりたいこと
基本的にはこれまでと変わらず弁護士としての活動は維持しつつ、診断士活動もできる限り入れていきます。
これまで私に仕事を依頼して下さっているクライアントの方々には、より一層の還元ができるように精進していこうと考えています。
それに加えて、勉強法・キャリアアップ・リスキリングという新たな分野に本格的に時間を割いていきたいと考えています。
昨年からは、中小企業庁の研修講師や、大学の仕事(大学TLOでスタートアップに関する外部審査委員)の仕事も初めているのもその一環です。
自分の強みとして、司法試験、ロースクール留学(英語)、中小企業診断士という3つの異なる分野での試験経験があります。また、証券会社勤務、エンジニア経験という同業者の中では比較的珍しい職歴もあります。
この強みを生かして、自分の仕事ポートフォリオの最適解を今後も模索していきたいと考えています。
弁護士として、そして経営に携わる人間として、AI時代の新しい働き方を模索しながら、少しでも皆さんの参考になれる情報をお届けしていきます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。