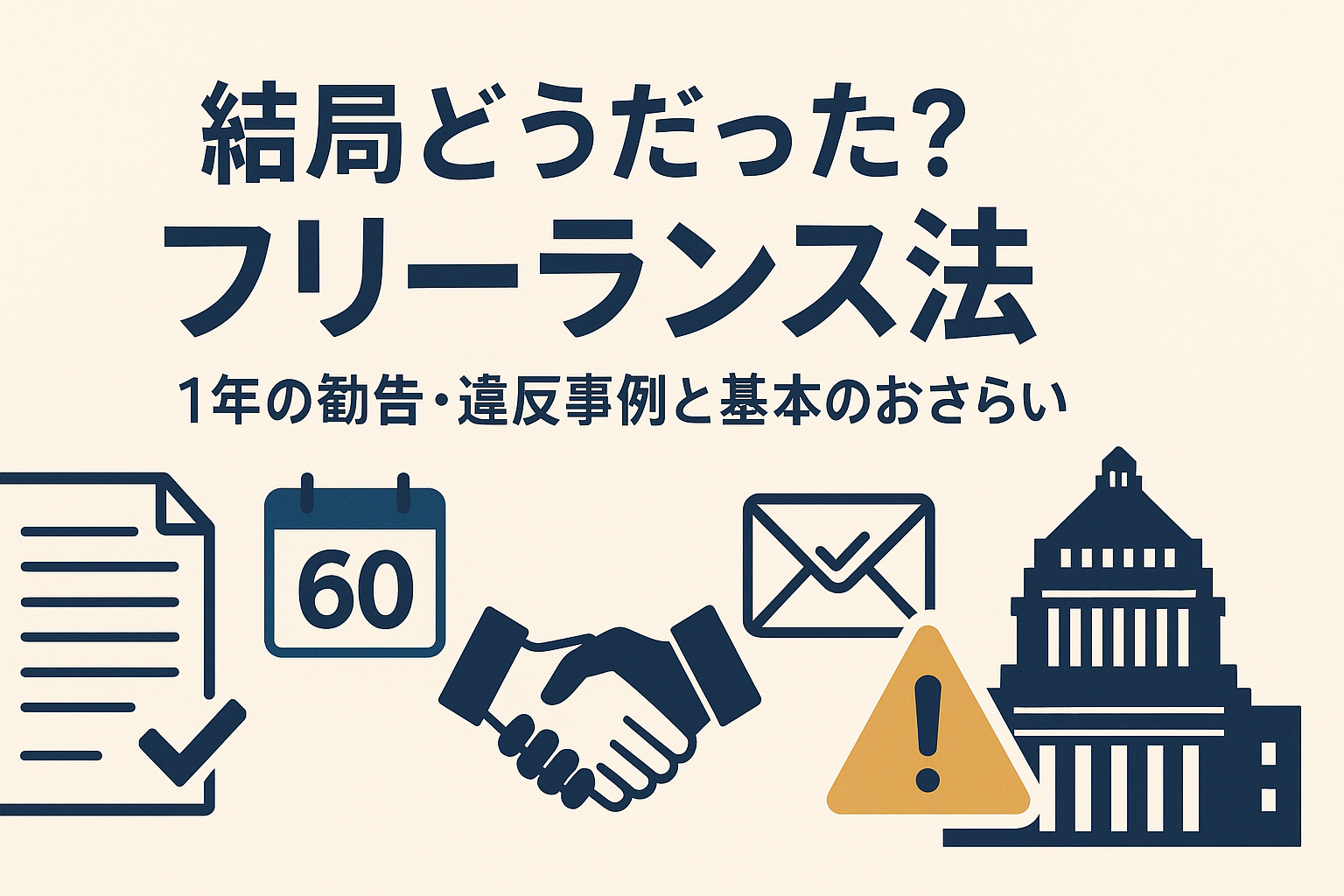【弁護士が本音で教える】未払金を効果的に防止する債権管理、回収フロー
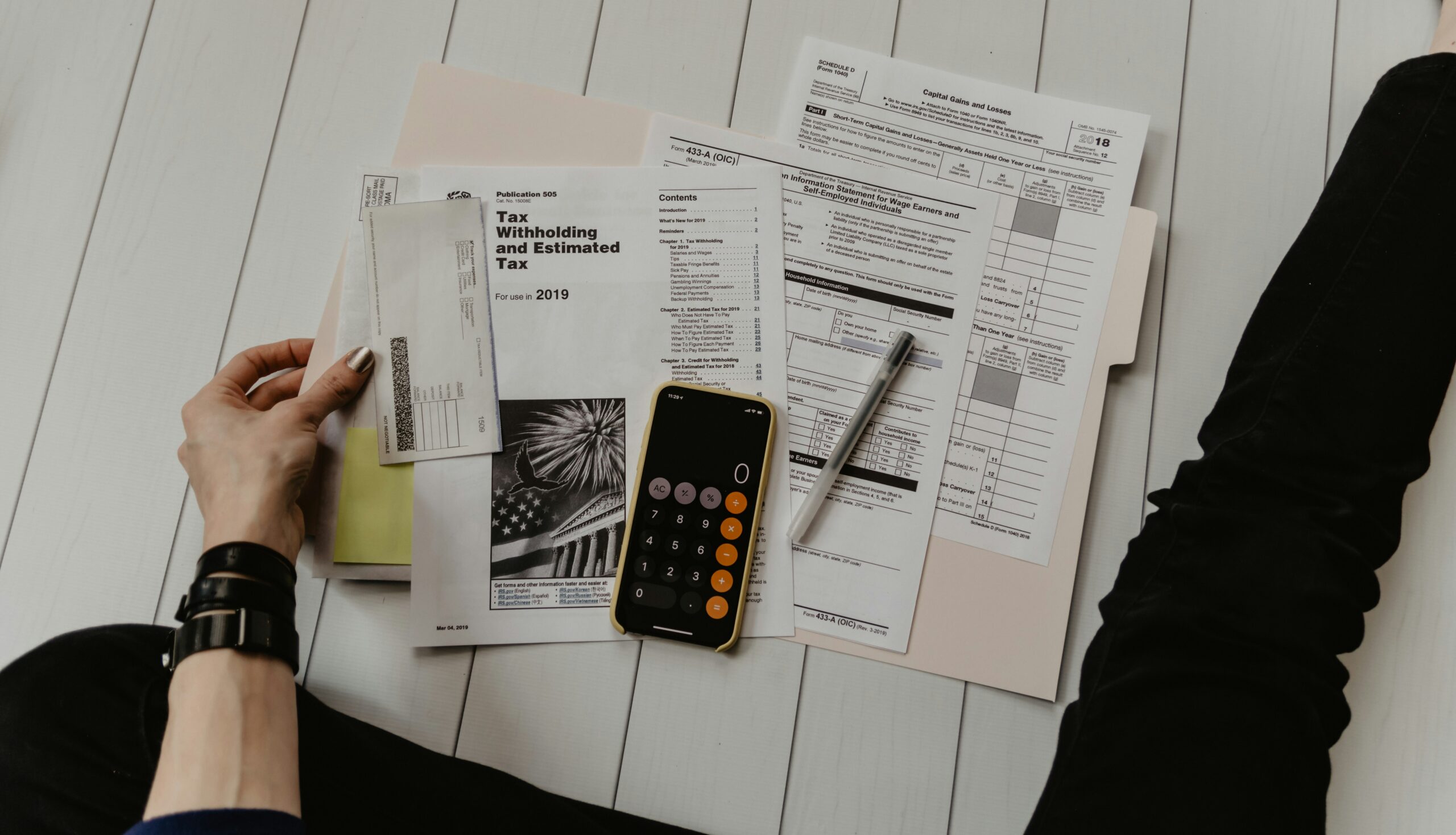
はじめに
弁護士の勝部です。
このブログ記事は、以下の方を対象に書いています
-
【この記事のメインターゲット】
請求書の期日に代金の支払がなされずに困っている
貸付金の分割払い、払ってはくるが遅れがち
債権の支払がないので法的手続きをしたい
債権管理は企業の生命線であるキャッシュフローに直結する業務です。
多くの企業が、債権回収を後回しにしてしまうことが少なくありませんが、債権管理の甘さは回り回って企業の存続を危うくしてしまうことがあります。
なぜか。
それは、企業体というのは、そもそも出来る限り早くキャッシュを回収し、それを投資に回して成長する存在だからです。
しかし、これは日本人の特性なのかも知れませんが、うるさく請求すると「金にがめつい」としてよくないことをしていると感じることもあります。
仕事は好きだけれど、お金に関することは苦手、という意識を持っている方は少なくありません。
そこで、本記事では、債権回収の基本的な流れと、具体的な対応策について、弁護士としての経験も交えて詳しく解説していきます。
1. 債権管理が企業経営に与える影響
債権回収は、会社のキャッシュフローに思い切り直結します。
売上がどれだけ高くても、未払金が多ければ資金繰りが悪化し、経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
特に中小企業では、キャッシュフローの悪化が再投資や仕入れに影響し、銀行からの評価値も下げてしまうことになります。
そのため、売上を上げることだけでなく、債権回収をいかに早く行うかが非常に重要です。債権回収が遅れると、会社全体の収益性や成長性に悪影響を与え、経営が滞る原因となります。
2. 債権回収の基本的な流れ
債権回収を成功させるためには、基本的な流れを理解しておくことが必要です。
-
(1) 契約書・請求書を正しく発行する
(2) 未収チェック
(3) 内容証明郵便送付
(4) 仮差押え・仮処分
(5) 支払督促
(6) 訴訟手続き
(1) 契約書・請求書を正しく発行する
債権回収の第一歩は、取引に関する契約書をキッチリと作成し、締結しておくことです。
契約書は、取引の内容や支払い期日を明確に記載するだけでなく、万が一支払いが遅れた場合の対応方法も漏れなく盛り込んでおくことが重要です。
具体的には、支払い遅延に伴う損害金や、支払いがない場合の契約解除条件なども記載しておくことで、債権回収がスムーズに進むようになります。
実際のところ、契約書には、取引類型によって非常に多くのチェックポイントがあります。
ただ、どの契約書についても共通して重要なのは、債務の内容(引き渡すべき物や金銭の具体的内容)と期限です。
金銭的請求をするのであれば、いつまでに、いくら払うべきなのかがきちんと読み取れるか、正しい言い回しが使えているか、十分注意する必要があります。
また、請求書についてはいつまでに発行しなければいけないというルールはないものの、期限の直前に送るのはマナー違反です。
基本的に、請求書は債権発生後速やかにというのがルールなので、例えば、物の引渡しや業務の履行が完了したら発行するイメージになります。
前払の場合は、期限の2週間から1ヶ月前くらいには発行するとよいかと思います。
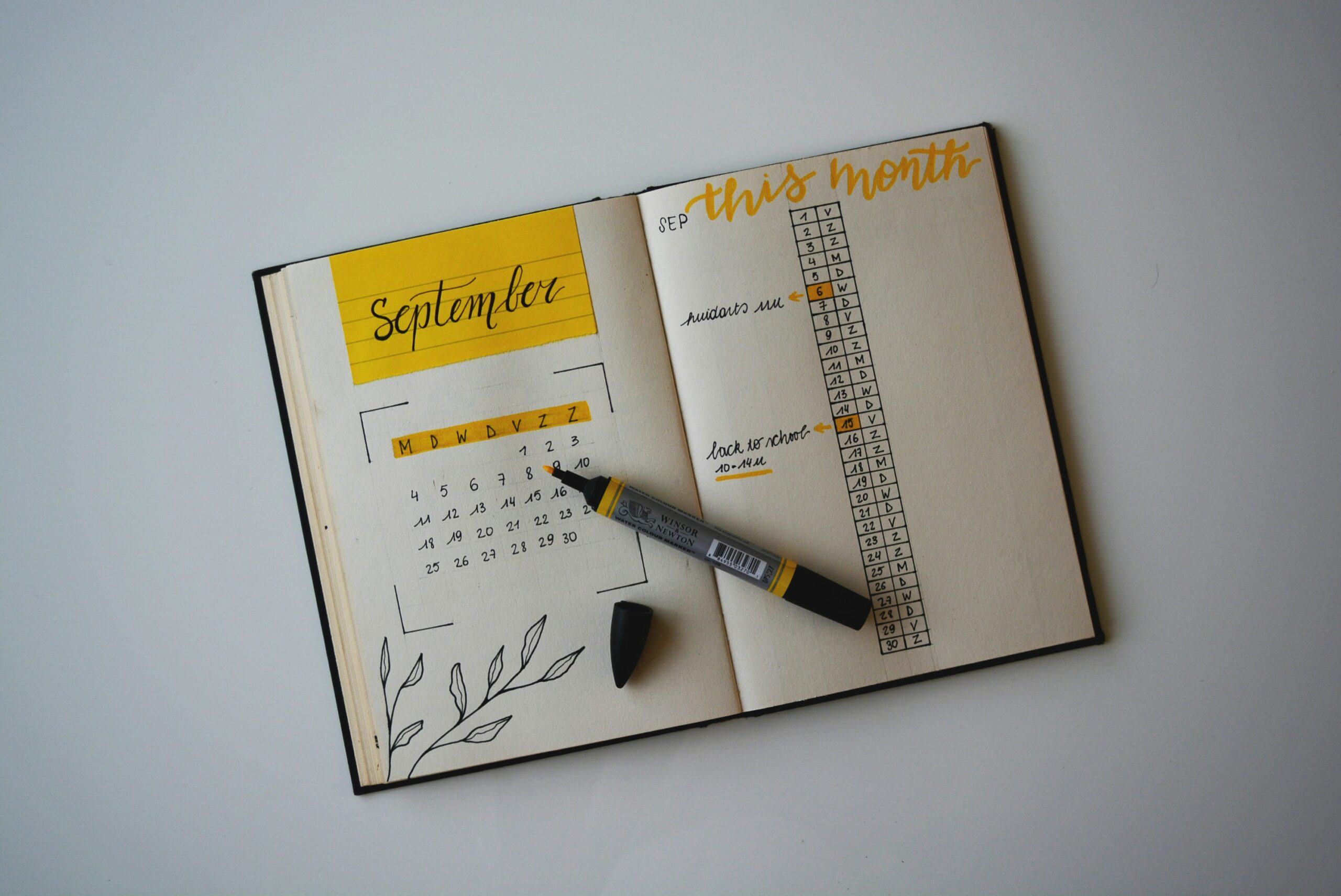
(2) 未収チェック~期限日の午前中に済ませる
次に、入金チェックをするタイミングですが、できるだけ早く、理想は期限日の午前中(朝イチ)にチェックするのがおすすめで、期限日の午前中に入金がない場合はすぐに電話で連絡を取ることが大切です。
しかし、意外とこれができていない企業が多いように思います。
日本では「お金に関してガツガツすることが恥ずかしい」という文化が根強くあるためかも知れませんし、わざわざ連絡するのが苦手、気が引けるということもあるのかも知れません。
ポイントは一切の感情を挟まず、あくまで冷静に「本日期日ですが、どうされましたか?」という確認のトーンで連絡をすることです。
もしうっかり忘れていたのであれば感謝されるかも知れませんし、これから入金するつもりだったのであればそのような回答があるだけです。
当日連絡をして「金にがめつい会社だ」「こんなに急いでいるということは資金繰りが危ない会社なのではないか」などと勘繰られることは通常ないので、粛々とやるだけのことかと思います。
むしろ、こういう管理をしないと、取引先の方も甘えが出てしまい、数日遅れるのが当たり前になり、徐々に未回収金が溜まってしまい、それから弁護士に相談、という状況になってしまうこともあります。
これは最悪の状態です。
この後言及しますが、金銭回収は、回収をされる側よりもする側が圧倒的に不利です。
そもそも、金銭回収のためのコストは全て債権者側が負担で、訴訟に勝っても弁護士費用の請求を相手にできるわけではありません(一定範囲でできないことはありませんが)。
そのため、債権管理のある意味での王道は、未収の可能性をとにかく極小にすることです。
延滞が発生すると、
①貸倒のリスクが上昇する、
②回収までのキャッシュフロー悪化は自社に帰属、
③回収コストも自社負担、回収できなければ無駄な出費、
となってしまうため、何一ついいことがありません。
最終的に貸倒になれば利益率も悪くなります。
未収が大きくなってくると、弁護士を入れても回収できない可能性もありますし、回収できてもコスト負担が大きくなります。
弁護士の私が言うのもアレですが、未収の発生を可能な限り回避し、危ない取引先とは早急に手を切るのが、ある意味で一番の債権管理方法であると言えます。
弁護士としては余り認めたくないですが、ある意味事実です。
(3) 内容証明郵便送付
法的手続きにはさまざまな方法がありますが、一般的なのが内容証明郵便の送付です。
内容証明郵便は、特定の内容を証明するための書類を相手に送る方法です。これにより、相手に対して請求額を明示して請求したことを証拠として残し、支払いを促すプレッシャーを与える効果が期待できます。
ただし、内容証明自体には法的拘束力はありません。
今時、内容証明自体は訴状などの強制力のある手続書面ではないことは調べればすぐに分かることですから、無視されることも少なくありません。
(4) 仮差押え・仮処分
仮差押えは、裁判を行わずに相手の銀行口座や資産を差し押さえる手続きです。これにより、相手が支払えない状況に陥る前に資産を確保することができます。
仮差押えは非常に強力な法的手段ですし、最短で2~3日で結果が出ます。
債務者が銀行口座に預金を残しているような場合には効果を発揮することもあります。
ただし、以下の点に注意です。
-
事前の供託が必要
裁判官の判断次第ですが、請求額の2割(1000万円であれば200万円)ほどの供託金を法務局に供託する必要があります。
それなりに厳格な手続き
契約書の内容が曖昧だったり、納品書など、反対給付を完了した書面などがそろっていないと裁判所から突っ込まれたり、認められないこともあります。
仮差押えした金銭をすぐに受け取れるわけではない
よく誤解されがちですが、仮差押えに成功したとしても、その金銭が得られるのは、本訴(仮処分に続く訴訟手続き)で勝訴判決を確定させた後です。
(5) 支払督促
支払督促は、未払いの金額に対して裁判所を通じて相手に支払いを促す手続きです。裁判所に納める費用は数万円ですし、裁判所が用意しているひな形を使えばある程度定型的に申立てをすることができる、シンプルな手続きとなります。
しかし、相手が督促に異議を申し立てると、裁判(簡易裁判所又は地方裁判所)に移送され、訴訟手続きに進むことになります。
(6) 訴訟手続き
一般的に「裁判をする」というのは、管轄のある裁判所に訴えを提起する(民事訴訟)ことを指し、おそらく多くの方が想像する裁判の手続きとなります。
訴訟の特徴は、とにかく非常に時間がかかることで、判決が出るまでに1年~2年かかることもザラですし、勝っても相手が控訴すれば上級審での手続きがまた進行するということになります。
ただ、契約書の内容がしっかりしていて特に争点となることがなければ半年ほどで審理が終了するケースも少なくないですし、途中で和解によって終わることもあります。
法的手続きについては、回収可能性やコストを十分に判断して進めることをお勧めします。
状況判断も重要です。
例えば、仮差押えをすれば回収可能であったにもかかわらず、内容証明を送ってしまったがゆえに相手が法的手続きの実行を予見し、銀行から金銭を抜いてしまい、結果仮差押えが空振りになることもあります。
他方で、高いコストを払えば回収可能性が高くなるわけではないので、どのような結果が得たいのかをよく考え、信頼できる専門家に相談しながら、手続きを進めていくことをお勧めします。
3. 法的手続きを取らないことのリスク
上記のように、支払いが遅れ、連絡を取っても対応がない場合は、法的手段を視野に入れることが必要です。
というよりも、何らかの方法で必ず決着させる必要があります。
一人代表の法人で株主も自分だけ、ということであればよいのかも知れませんが、外部から調達を受けているスタートアップの場合、親会社やステークホルダーがいる企業の場合、部署ごとに利益責任が明確にある場合などは、回収できないから放置するというのは、下手をすると社長や担当者の個人的な利益供与すら疑われかねない状況になります。
例えば、取引先の責任で支払いが滞り、訴訟をしたけれども相手先が破産したので回収ができなかった、ということであれば、やるべきことはやっているのである意味仕方がないよねという見られ方をします。
しかし、期限をとうに過ぎているのに内容証明すら送らず、法的手続きも何も取らないとしたらどうでしょうか?
明かに自然ではありませんね。
債権は消滅時効期間の経過によって消滅しますので、法的にはそこで損が確定することになりますが、あえて提訴もせず、時効が完成しないような手続きも取らなかったのはなぜですか、ということを説明するのが非常に難しくなります。
極端なことを言えば、取引先から提訴しないよう個人的にキックバックをされていたので強硬措置を取らなかったということにでもなれば、社長や担当者の背任行為になりかねない状況です。
ですので、万が一未回収が問題になったとしても、ステークホルダーに明確な説明ができるよう、法的手続きで案件を終結させるのが鉄則ということになります。
4. 未払金を防ぐための債権管理のポイント
まとめですが、債権回収を効率よく進めるためには、未払金を防ぐための事前対策も重要です。以下のポイントを押さえて、債権管理を徹底しましょう。
-
契約書の明確化: 支払い条件や遅延損害金、契約解除条件を明確に記載する。
定期的な債権の見直し: 定期的に未払い債権をチェックし、早めに対応する。
支払い期日前のリマインド: 支払い期日前にメールや電話でリマインドを行う。
取引先の信用調査: データバンクや同業者聞き取りなどによって取引先の信用状態を定期的に確認し、リスクを最小限にする。