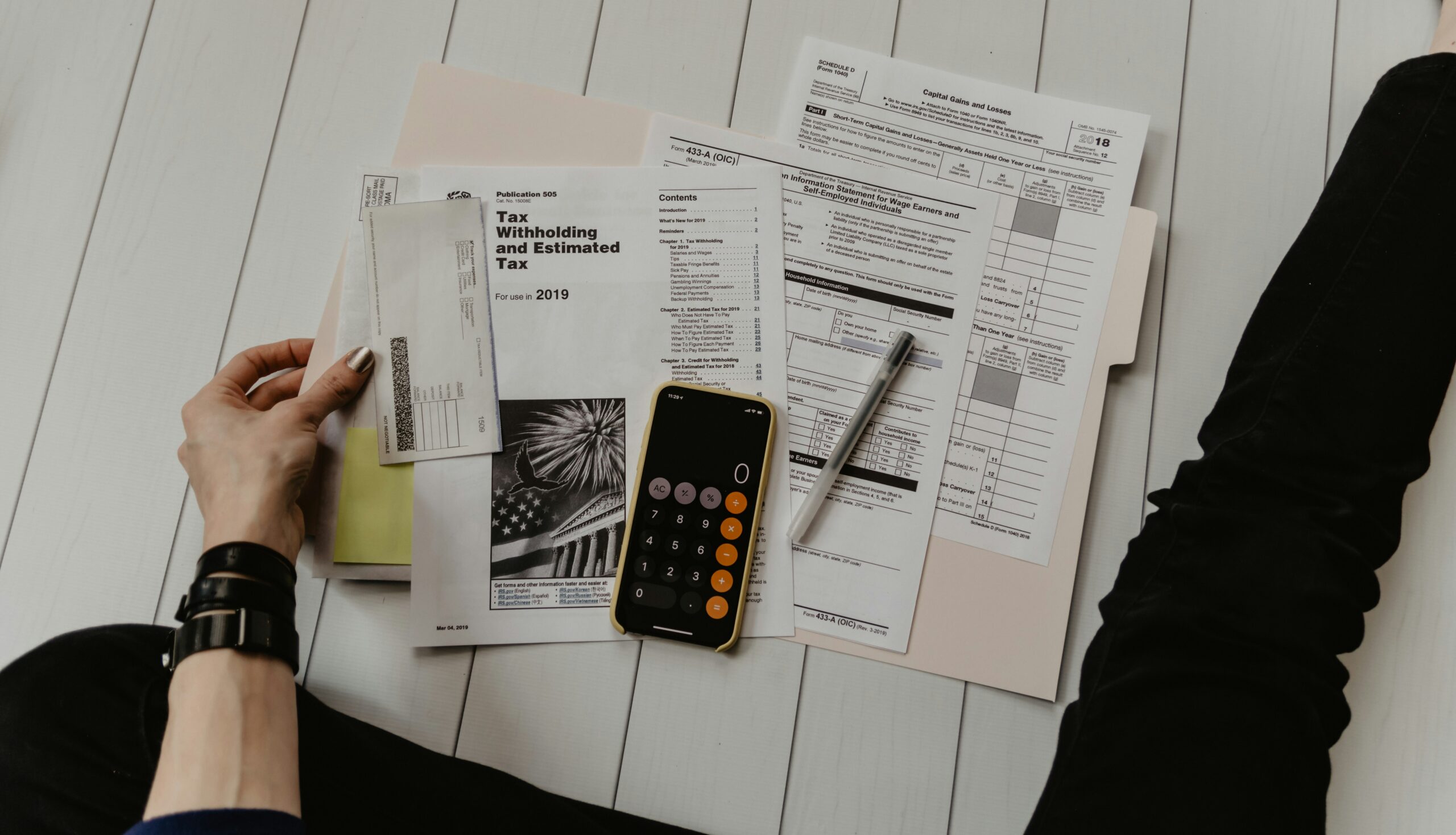秘密保持契約書を従業員と交わす理由は?2つの理由と締結時期を解説

はじめに
ニュースなどでよく目にする「情報漏えい問題」ですが、事業者にとっては、その後の事業活動に大きく影響を与える不祥事です。
事業者は、社会的信用性を低下させるだけでなく、多額の損害賠償責任を負う可能性すらあります。
いったん情報が外部に漏れてしまうと、元の状態に戻すことはほぼ不可能だといっていいでしょう。事業者は、このような事態を招かないように、十分な予防策を講じておくことが必要になります。
その予防策の一環として、多くの事業者は従業員との間で「秘密保持契約書」を締結します。
今回は、従業員と締結する秘密保持契約書について、その必要性や締結の時期をわかりやすく解説します。
1 秘密保持契約書とは
「秘密保持契約書」とは、業務上の情報について、持ち出しや不正利用を防ぐために、従業員との間で締結する契約書です。
秘密保持契約書を締結することにより、顧客情報を持ち出した従業員や退職時に営業秘密を持ち出した従業員に対して、法的手段を講じることが可能になります。
また、顧客情報が漏えいしたり、不正利用されたりした場合には、顧客から損害賠償を請求される可能性がありますが、秘密保持契約書を締結していないと、情報の管理方法に問題があったと判断される可能性が高いです。
このように、秘密保持契約書は、顧客から預かっている情報や事業に関する情報などを守るために、従業員との間で締結すべき契約書なのです。
2 秘密保持契約書を従業員と締結する2つの理由
従業員と秘密保持契約書を締結する理由は、主に以下の2点にあります。
(1)情報漏えいの予防策
従業員との間で秘密保持契約を締結する主な目的は、事業者が保有する重要情報の漏えいを予防することにあります。
この点、従業員は日々の業務において、事業者が独自に開発した技術やノウハウなどの情報、取引先などの顧客情報に接する機会が多いといえます。
仮に、従業員が自己の利益を図るために、業務上知り得た情報を不正に利用したり、顧客情報を競合他社に譲渡したりすると、事業者にとっては、多大な損失となります。
このような事態を招かないためには、あらかじめ、従業員との間で秘密保持契約を締結し、事業者が保有する情報等を不正に利用しないことや、外部に情報を持ち出さないことについて誓約させておくことが必要になります。
(2)退職時の競業避止
「競業避止(きょうぎょうひし)」とは、競合する企業への転職や競合する企業の設立などを禁止することをいいます。
従業員が在籍している間は、労働契約等において競業避止義務を負わせることができます。
ですが、退職後は、自由に転職できることが原則です。
退職した従業員が、それまでのキャリアを活かして、競合する他社に転職することは十分にありえることです。
そこで注意しなければならないのが、事業者が保有する情報を転職先で漏えいされたり利用されたりしてしまう可能性があるということです。
このようなことが起きないように、従業員が退職する際に、秘密保持契約を締結しておくことも大切なのです。
退職者による情報漏えいを完全に防ぐことは難しいですが、一定程度の抑止効果を期待することができます。
また、秘密保持契約を締結しているにもかかわらず、退職した従業員が情報を漏えい・不正利用し、その結果、事業者に損害を与えた場合には、退職した従業員に対し秘密保持契約違反を理由として損害賠償を請求することも可能になります。
3 秘密保持契約書を交わす時期
従業員と秘密保持契約書を交わす時期は、以下の3回に分けることができます。
(1)入社したとき
従業員と始めに秘密保持契約書を交わすことになるのは、従業員が入社したときです。
入社する際には、身元保証書や給与の振込先口座に関する届出書などを提出させることが多いですが、このときに秘密保持契約書も一緒に提出させる事業者が多いです。
実際に業務に就くようになると、多くの情報に接することになるため、入社時に秘密保持契約書を交わしておくことで、情報の漏えい・不正利用に対する抑止効果を期待することができます。
(2)異動・昇格するとき
従業員は、入社後に異動や昇格を経験することがほとんどです。
たとえば、社内で独自に開発したノウハウなどに関する情報を取り扱う部署に異動する場合、異動する従業員との間で秘密保持契約書を交わすことが一般的だといえます。
この場合、秘密保持契約書には、実際に取り扱うこととなる情報を明記しておくことが必要です。
また、昇格により、それまではアクセスできなかった事業者の情報にアクセスできるようになる場合があります。
このような場合も、昇格する時期に、取り扱う情報を明記した秘密保持契約を締結することが必要になります。
(3)退職するとき
退職した従業員が外部で営業秘密を漏えいするといったケースは少なくありません。
そのため、退職する従業員との間で秘密保持契約を締結しておくことも忘れてはなりません。
この場合、情報の漏えい・不正利用というリスクを踏まえ、在職中に従業員が保有していた情報を破棄・返還すること、転職後に自社の情報を漏えい・利用しないこと、などを秘密保持契約書に定めておく必要があります。
4 まとめ
社会問題にもなっている「情報漏えい問題」ですが、いったん情報が漏えい・不正利用されてしまうと、事業者の信用は一気に失墜することになります。
信用を回復することは容易ではないため、事業者は、情報の取り扱い等についてあらかじめ予防策を講じておくことが大切です。
従業員が入社した時をはじめ、従業員の業務内容や取り扱うこととなる情報内容などを考慮したうえで、適切な時期に秘密保持契約を締結することが必要です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。