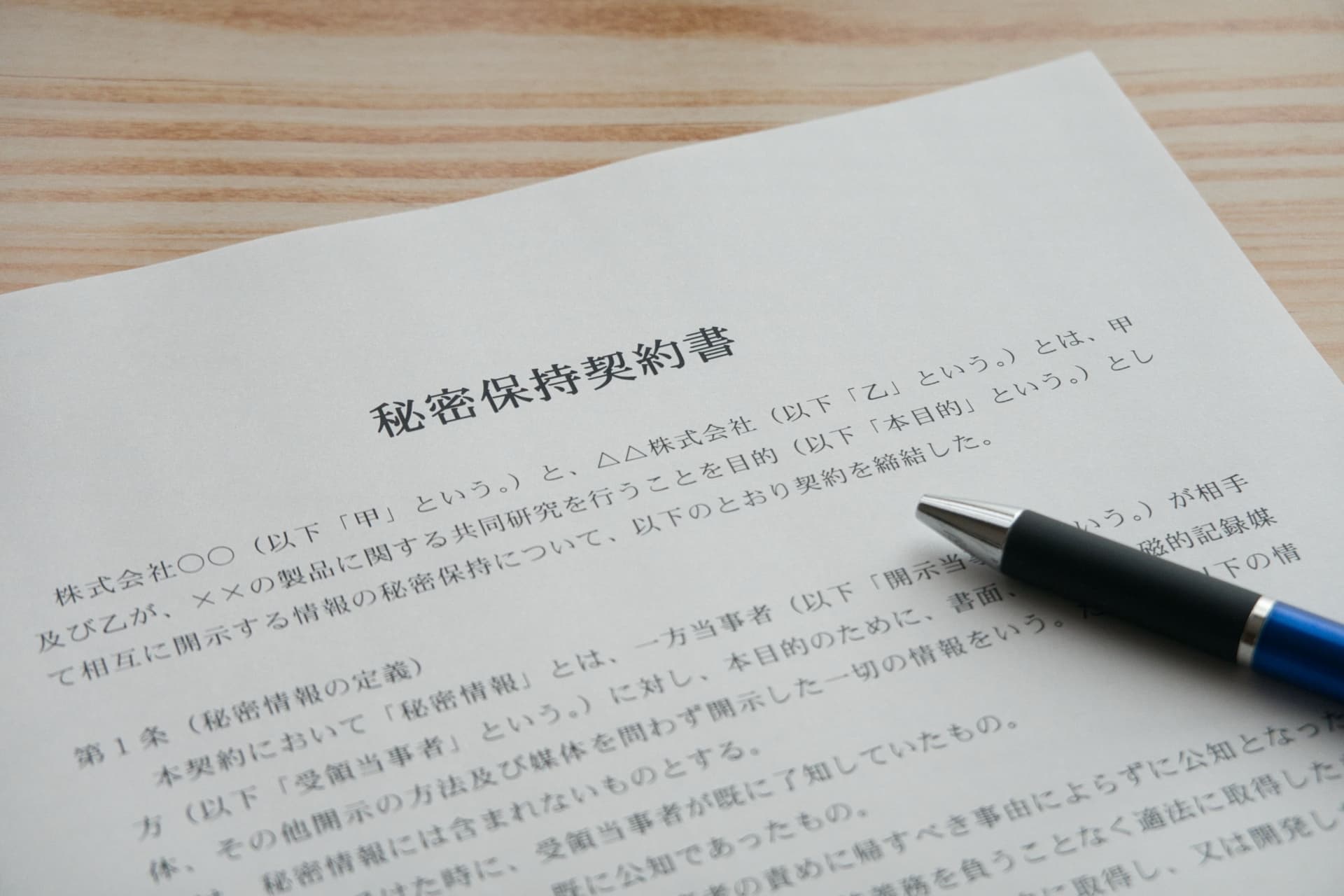秘密保持契約書に収入印紙は必要?作成時の5つのポイントを解説!

はじめに
事業者が他の事業者などと取引関係に入る際には、秘密保持契約を締結することが多いです。
秘密保持契約を締結することにより、自社の情報が取引先を通じて漏れることを防止することができます。
契約書にはさまざまな種類がありますが、契約書を交わす際に気になることの一つとして、「収入印紙を貼る必要があるのか」という問題があります。
今回は、秘密保持契約書に収入印紙は必要なのかという点を中心に、その書き方などについても解説します。
1 秘密保持契約とは

「秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)」とは、機密性のある情報を他の事業者に提供する場合に、他社がその情報を漏らしたり不正に利用したりすることを防止するために締結する契約のことをいいます。
他の事業者と取引関係に入ると、取引目的を遂行するためにさまざまな情報を他の事業者に提供する必要が出てきます。
ですが、提供する情報の中には、事業者にとって機密性の高い情報が含まれている場合もあるため、外部に漏れてしまったり、不正に利用されたりしてしまうと、多大な損害を被ることになります。
このようなことがないように、当事者間で締結されるのが秘密保持契約です。
秘密保持契約が締結される場面はさまざまであり、たとえば、他社と共同開発を実施する場合や一部の業務を外部に委託する場合などには、情報を開示する前に秘密保持契約を締結することが一般的になっています。
2 秘密保持契約書に収入印紙は必要?

秘密保持契約を締結する際には、対象となる情報などを定めた「秘密保持契約書」を当事者間で交わすことになります。
具体的には、それぞれが署名・押印などをする方法で契約書を交わすことになりますが、契約書の類はその性質によっては、収入印紙を貼る必要があります。
それでは、秘密保持契約書に収入印紙を貼る必要はあるのでしょうか。
結論から言うと、秘密保持契約書については基本的に収入印紙を貼る必要はありません。
一般的に、秘密保持契約は秘密保持に関する事項を取り決める契約であるため、この限りでは収入印紙は不要です。
ですが、秘密保持に関する事項のほかにも、別の取り決めが契約に含まれている場合には、収入印紙が必要となるケースもあります。
たとえば、継続的取引に関する事項や業務委託に関する事項が秘密保持契約の中に含まれている場合は、課税文書として収入印紙がかかる可能性があります。
また、契約書の名称には左右されませんので、その点にも注意する必要があります。
つまりは、契約書の名称が秘密保持契約書となっていても、その内容において継続的取引や業務委託に関する事項が含まれている場合には、課税文書にあたる可能性があるということです。
3 秘密保持契約書の書き方|作成時のポイント

秘密保持契約書を作成する際には、以下の点にポイントを置きながら進めていくことが大切です。
- 秘密情報の範囲
- 目的外利用の禁止
- 複製の可否
- 契約終了後の情報の取扱い
- 契約違反に対するペナルティ
(1)秘密情報の範囲
どのような情報を秘密情報とするか、その範囲をできるだけ明確に定めておくことがポイントになります。
秘密情報の範囲を漠然としか定めていない場合、仮に秘密情報を外部に漏らされた場合にも「この情報は契約書で定めた秘密情報に当たらない」といった主張を簡単に許すことになり、トラブルの元になります。
そのため、秘密保持契約では例外規定を設けるなどして、秘密情報に該当するものとそうでないものを明確にしておく必要があります。
「秘密情報の範囲」に関する条項は、秘密保持契約において核にもなる部分ですので、慎重に決定することが大切です。
(2)目的外利用の禁止
秘密情報は、何らかの目的をもって取引先に提供されることが一般的です。
そのため、情報の提供を受けた事業者は、原則として、その目的の範囲でしか情報を利用することはできません。
仮に、自社の秘密情報を他の事業者によって目的外利用されてしまうと、場合によっては、多大な損害に繋がる可能性もあります。
以上のような観点から、秘密保持契約ではこの点も定めておくことが必要です。
具体的には、情報提供者の承諾なしに秘密情報を目的外利用することを禁止する旨の条項を盛り込みます。
もっとも、目的外利用を禁止する以上、秘密保持契約書ではそもそもの「利用目的」について定義しておくことも必要です。
(3)複製の可否
秘密情報は、紙媒体で提供されることもあれば、データで提供されることもあります。
そのため、複製しようと思えば簡単に複製できてしまいます。
情報の複製について何の取り決めもしていないと、その情報を勝手に複製され利用されるおそれがあります。
以上のような観点から、秘密保持契約には、複製の可否についても定めておくことが望ましいといえるでしょう。
この場合、複製を一切認めないとする条項や、取引目的の遂行の範囲でのみ複製を許諾する旨の条項などを盛り込むことになります。
(4)契約終了後の情報の取扱い
秘密保持契約の終了後における秘密情報の取扱いについてもきちんと定めておくことが必要です。この点を定めていないと、契約終了後に目的外利用されるなどして、秘密情報が流出するおそれがあります。
具体的には、情報を含む記録媒体などの返還、相手方による廃棄などを内容とする条項を盛り込んでおくことが重要です。
特に、対象となる秘密情報が事業者独自のノウハウといった機密性の高い情報である場合には、その情報が流出してしまうことで死活問題にもなりかねません。秘密情報の返還・廃棄を内容とする条項を盛り込むことはもちろんのこと、具体的な返還方法・廃棄方法まで踏み込んで定めておくことが大切です。
(5)契約違反に対するペナルティ
秘密保持契約を交わした場合であっても、相手方が契約に違反する可能性はゼロではありません。契約によって相手方を強く拘束するためには、契約条項の実効性を担保するためのペナルティを定めておくことが必要です。
秘密保持契約に違反した場合、違反行為によって生じた損害を賠償する旨の条項や秘密情報の利用を差し止めることができる旨の条項を盛り込むことが一般的になっています。
4 まとめ
ビジネスの世界では一般的にもなっている秘密保持契約ですが、契約書を作成する際には、契約内容の性質などによっては収入印紙が必要になるケースもあるため注意が必要です。
また、秘密保持契約は自社の秘密情報を守るために締結されるものです。
どの事業者にとっても、自社の秘密情報は大変貴重なものであるため、情報が漏えいしたり誤った利用方法をされたりすると、事業に多大なダメージを受けることになります。
このようなことにならないためにも、抜け目のない秘密保持契約を作成することが大変重要になってきます。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。