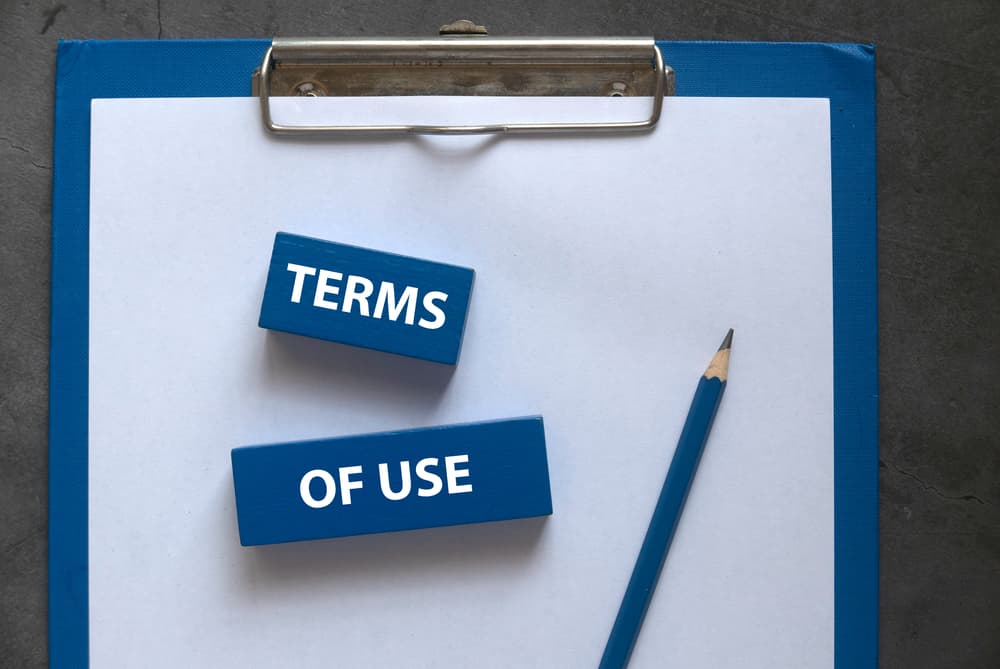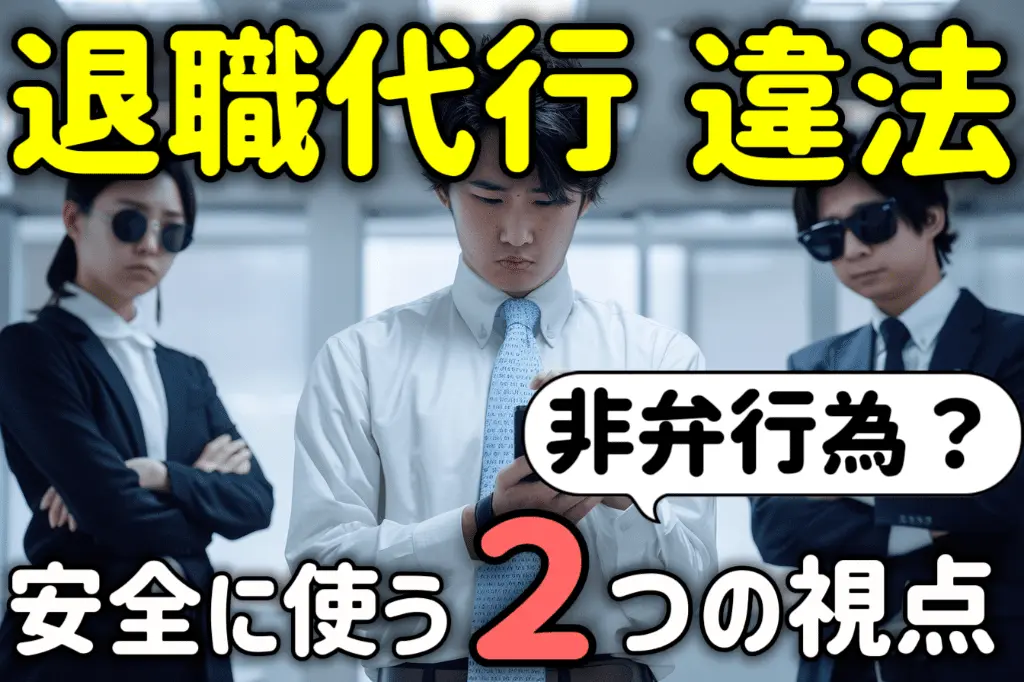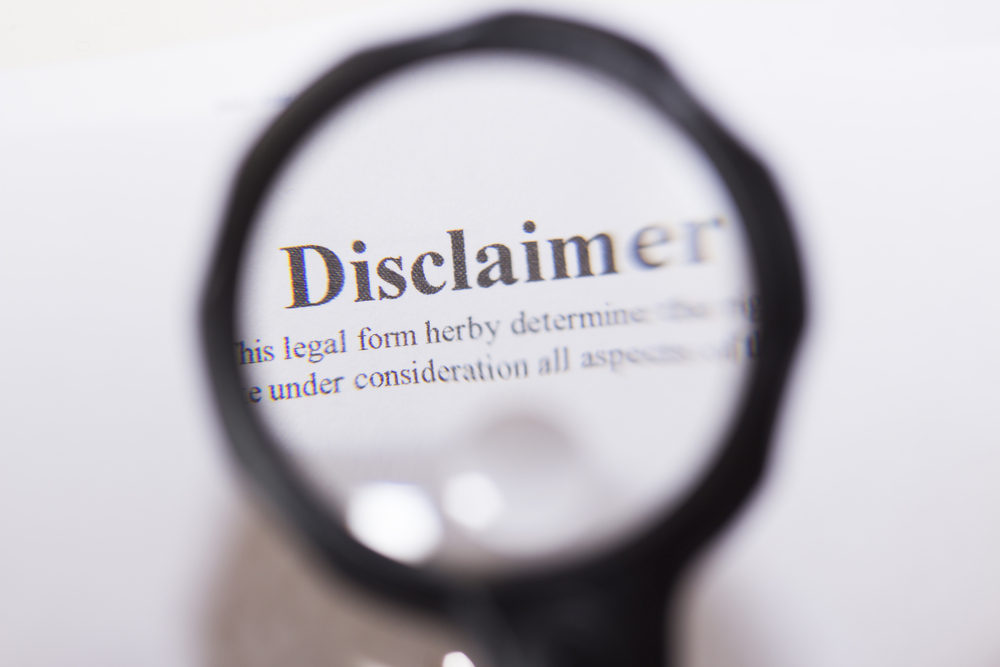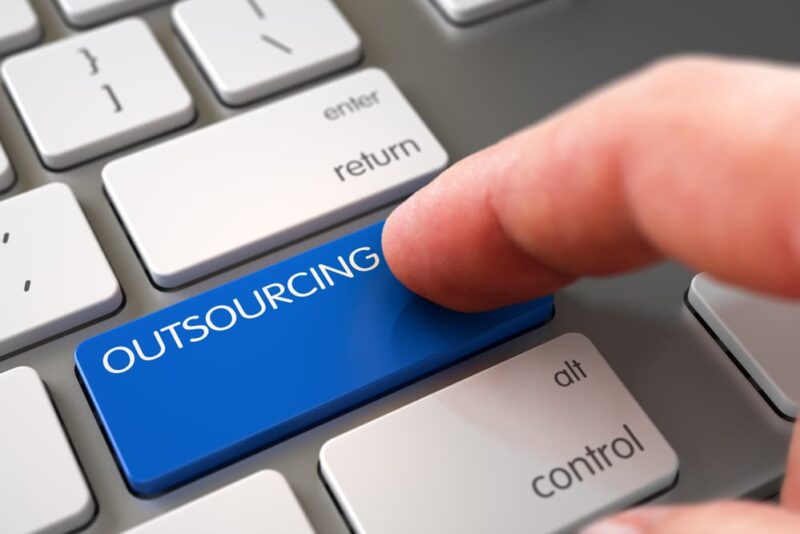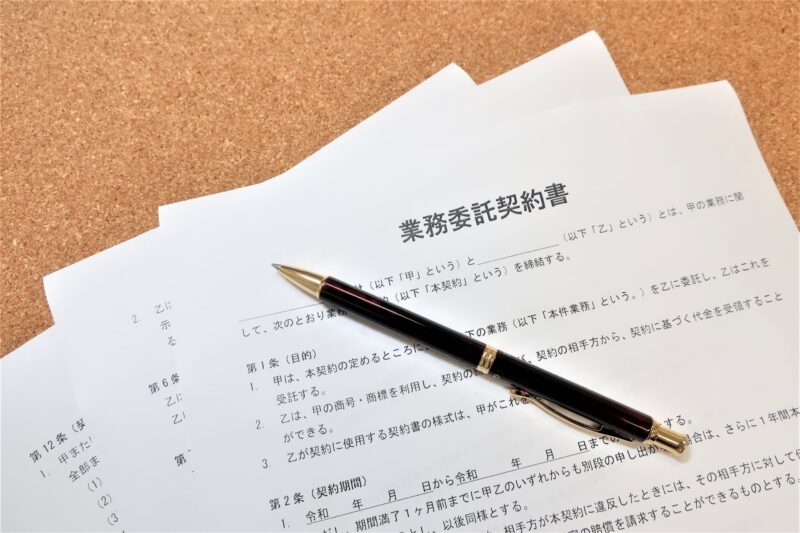秘密保持契約に違反された場合の3つの対応方法を弁護士が解説!
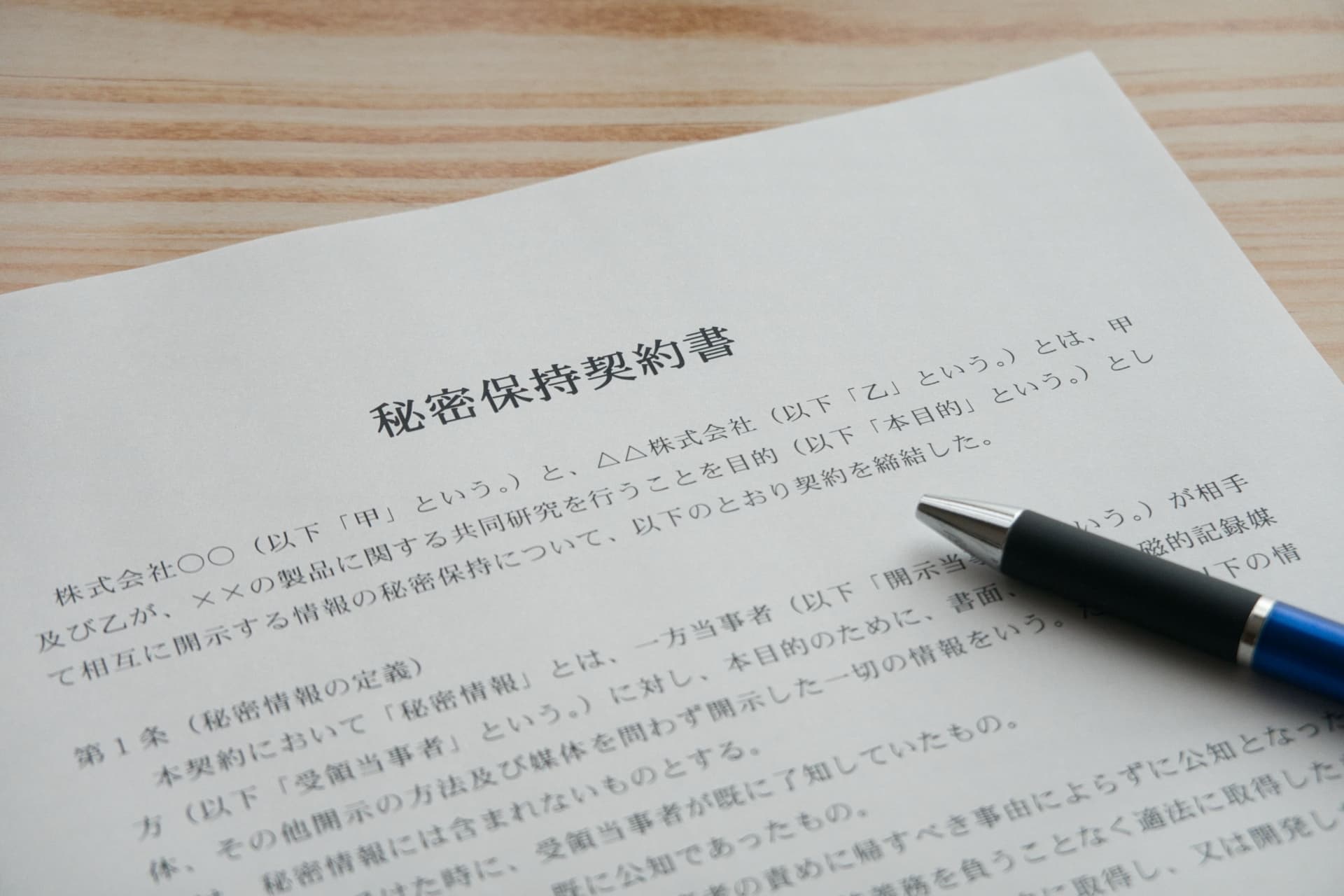
はじめに
他社と取引関係に入る場合には、秘密保持契約(NDA)を締結することが多いです。
事業や取引の内容などによっては、他社と協力関係を構築する必要も生じるため、秘密保持契約がもつ意義は極めて大きいといえます。
もっとも、秘密保持契約を締結すれば、それですべてが万全になるということではありません。
秘密保持契約を締結する場合には、契約の相手方が契約に違反することも想定しておく必要があります。
そこで今回は、秘密保持契約を締結した相手方が契約に違反した場合の対応を中心に、弁護士がわかりやすく解説します。
1 秘密保持契約(NDA)とは
「秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)」とは、取引関係にある他社が、自社から得た情報を外部に漏らしたり、不正に利用したりすることのないように、他社に守秘義務を課す契約のことをいいます。
他社と取引関係に入ると、取引の内容などに応じて、自社が保有する情報を他社に提供する必要性が生じます。
ですが、他社に提供する情報のなかには、重要な情報が含まれることもあるため、このような情報を外部に漏らされてしまうと、事業者は重大な損失を受けるおそれがあります。
このようなことがないよう、自社の情報を守るために締結する契約が「秘密保持契約」です。
2 秘密保持契約によって相手方が制限を受ける行為
秘密保持契約は、情報漏洩リスクなどを回避するために締結する契約です。
そのため、契約を締結した相手方は、主に以下のような制限を受けることになります。
- 情報の複製・分析
- 情報の目的外使用
- 情報の開示範囲
- 情報の破棄等
(1)情報の複製・分析
一般的に、契約を締結した相手方は、提供された情報を複製することを禁じられます。
たとえば、情報が記載された書面をコピーしたり、スキャナーでパソコンに取り込んだりすることはできません。
また、製品開発のノウハウなど、重要な情報を取得されることを防止するために、情報の分析も制限されることが一般的です。
たとえば、リバースエンジニアリングによりソースコードなどを取得することはできません。
(2)情報の目的外使用
秘密保持契約では、提供される情報に関して使用目的が定められることが一般的です。
そのため、契約を締結した相手方は、契約で定められた目的以外の目的で情報を使用することはできません。
たとえば、契約当事者双方が協力の下、提供される情報を基にアプリ開発を行うという使用目的が定められている場合には、相手方がその情報を用いて単独で独自のアプリを開発することはできません。
(3)情報の開示範囲
秘密保持契約では、情報の開示範囲(誰に対してどの情報を開示してよいか)を定めることが一般的です。
契約を締結した相手方において、すべての従業員が開示範囲に含まれてしまうと、それだけ情報漏洩のリスクも高くなります。
そのため、役員や管理職、一部の従業員などに開示範囲を限定することが一般的になっています。
また、弁護士や公認会計士といった第三者を開示範囲に含むケースもあります。
(4)情報の破棄等
契約が解除・終了した場合には、情報の提供を受けた相手方は情報を破棄・返還することが必要になります。
そのため、秘密保持契約では、情報の破棄や返還に関する事項を定めることが一般的です。
たとえば、情報が記録された書面や媒体については、相手方がこれを破棄(消去)するという条項を設ける場合には、破棄(消去)したことを証する書面の提出を義務付けるケースもあります。
3 秘密保持契約に違反した場合の対応
秘密保持契約を締結したとしても、その相手方が必ず契約条項を遵守するとは限りません。
万一、相手方が秘密保持契約に違反した場合、情報を提供した事業者はどのような対応をとることができるのでしょうか。
具体的に考えられる対応としては、以下の3つが挙げられます。
- 違約金の請求
- 損害賠償請求
- 差止請求
(1)違約金の請求
秘密保持契約において、相手方が契約に違反した場合には違約金が発生する旨の条項を設ける場合があります。
違約金条項が設けられている場合において、相手方が秘密保持契約に違反した場合は、原則として、秘密保持契約で定められた違約金の支払いを相手方に請求することができます。
(2)損害賠償請求
秘密保持契約において、違約金条項が設けられていない場合であっても、通常は損賠賠償に関する条項が設けられています。
そのため、相手方が秘密保持契約に違反し、自社が損害を受けた場合には、相手方に対して損賠賠償を請求することができます。
もっとも、この場合には、情報を提供した事業者側で損害額を立証しなければなりません。
一方で、損害賠償額を予定する条項や違約金条項が設けられていれば、原則として、契約で定められた損害賠償額の支払いを相手方に請求することができます。
(3)差止請求
漏洩した情報が、不正競争防止法が定める「営業秘密」にあたるといえる場合には、情報を提供した事業者は、不正競争防止法を根拠として相手方に差止めを請求することができます。
ですが、営業秘密の要件は厳しく、不正競争防止法を根拠として差止めを請求できるケースは限られています。
一方で、秘密保持契約に差止請求に関する条項が設けられていれば、契約を根拠として差止めを請求することが可能です。
4 まとめ
情報漏洩は、事業者にとって致命傷ともなりうる重大なリスクです。
その意味でも、秘密保持契約を締結することは極めて重要な意義をもっています。
また、不測の事態に備えて、相手方が契約に違反した場合の対応方法を知っておくことも大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。