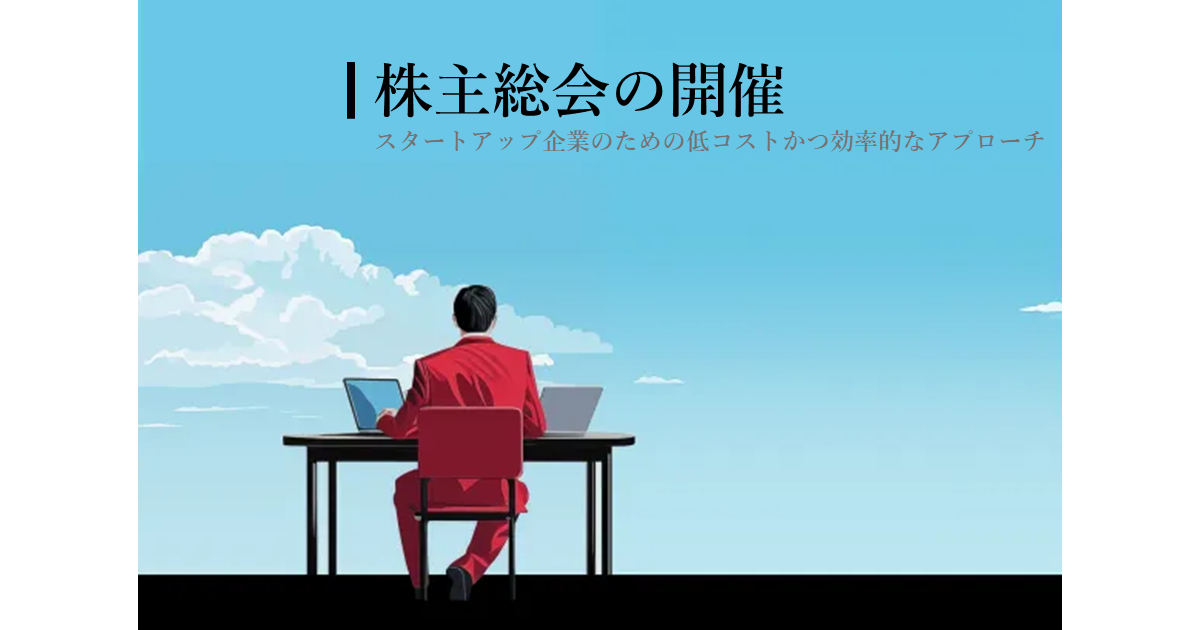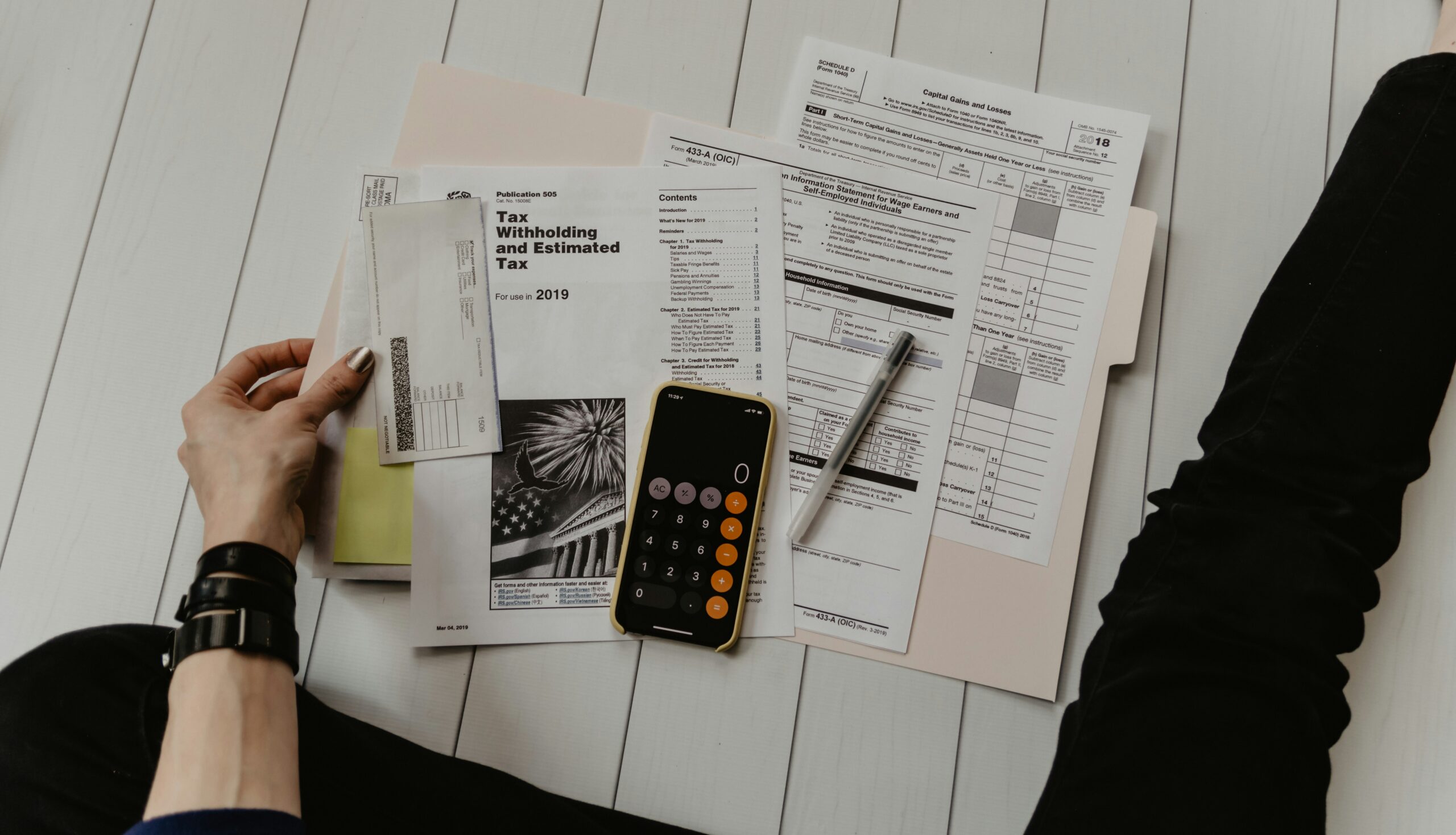債権回収とは?利用できる3つの裁判手続を弁護士がわかりやすく解説

はじめに
事業に携わっていると、さまざまな債権債務関係が生じます。
たとえば、取引先に対する商品等の売掛代金は典型例ともいえるでしょう。
商品の売掛代金などのように、金銭の支払いが予定されている場合には支払期日が設けられることが一般的ですが、相手方において資金繰りがうまくいっていないと、期日を過ぎても支払ってもらえないことがあります。
このような場合、受け身でいても支払いを受けられる可能性は低いため、自主的に債権を回収する手立てを考える必要があります。
とはいえ、具体的にどのような方法があるのか、わからないという方も多いと思います。
そこで今回は、債権回収を実現するための裁判手続きについて、弁護士がわかりやすく解説します。
1 債権回収とは
「債権回収」とは、本来支払ってもらうべき金銭(貸したお金や商品代金など)を、債権者が債務者から回収する(支払ってもらう)ことをいいます。
貸したお金を返してくれない、売買代金を支払ってくれない、といったように、債務者が返済(支払)義務を負っているにもかかわらず、その債務を支払ってくれない場合に「債権回収」が問題となります。
一般的に、債権者が債権を回収しようとする場合、まずは、債務者に電話を入れたり内容証明郵便を送付したりするなどして、任意の支払いを促します。
もちろん、この段階で支払いに応じるケースもあります。
ですが、この段階に至っても支払いに応じないケースもあり、そのような場合は、裁判手続きを利用することも検討せざるを得なくなります。
※任意に支払いを求める方法について、詳しく知りたい方は、「債権回収の方法とは?5つの手順やコツを弁護士がわかりやすく解説!」をご覧ください。
2 利用できる裁判手続
任意で支払いに応じない場合、債権者は以下の3つの裁判手続について、利用の是非を検討する必要があります。
- 少額訴訟
- 支払督促
- 通常訴訟
3 少額訴訟
「少額訴訟」とは、少額な金銭をめぐる争いについて、原則、1回の期日で審理を終えて判決をする手続のことをいいます。
-
【民事訴訟法368条1項】
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
このように、少額訴訟は、債権額が60万円以下である場合に利用できる手続で、簡易裁判所が管轄となります。
また、1回の期日で審理を終えることが予定されているため、提出する証拠は即時に取調べ可能なものでなければなりません。
以上からすると、回収しようとする債権が60万円以下で、かつ、債権の存在や未払いの事実についてとくに争いがないような場合は、少額訴訟を利用することにより、早期に債権を回収できる可能性があります。
もっとも、被告が通常訴訟の手続きに移行することを希望した場合は、通常訴訟の手続きで審理されるため、注意が必要です。
4 支払督促
「支払督促」とは、債権者の申立てに基づき、裁判所が債務者に金銭を支払うよう督促する手続のことをいいます。
-
【民事訴訟法382条】
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。
このように、支払督促を申し立てるためには、その対象が「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」でなければなりません。
たとえば、売掛債権や貸付債権などは、ここでいう「金銭の一定の数量の給付を目的とする請求」にあたるため、これらを対象として支払督促を申し立てることが可能です。
支払督促は、以下のような流れで手続きが進められます。
- 支払督促の申立て
- 支払督促の発付
- 仮執行宣言
- 確定判決と同一の効力
↓
↓(支払督促正本の送達後2週間以内)
↓(仮執行宣言付支払督促の送達後2週間以内)
支払督促が発付され、その後一定期間内に債務者から異議が出なければ、債権者の申立てによって、支払督促に仮執行宣言が付されます。
それから、仮執行宣言付支払督促が送達され、その後一定期間内に債務者から異議が出なかった場合、仮執行宣言付支払督促は確定判決と同一の効力を生じます。
これに対し、債務者から督促異議の申立てがあった場合、手続きは通常訴訟に移行することになります。
以上からすると、請求内容に争いがなく、債務者から異議を申し立てられる可能性がないような場合には、支払督促を利用することにより、早期に債権を回収できる可能性があります。
5 通常訴訟
回収しようとする債権の存在やその額について相手方と争いがある場合や、少額訴訟や支払督促の手続きが通常訴訟に移行した場合には、通常訴訟により債権を回収することになります。
なお、訴訟をしている間に相手方の財産が減少し、十分に債権回収を行うことができなくなるおそれがある場合には、仮差押えを申し立てることも必要になってくるでしょう。
みなさんもご存知のとおり、通常裁判では、証拠が大変重要な役割を担います。
債権回収を内容とする訴訟を起こす場合には、債権が有効に成立していることを立証しなければなりません。
たとえば、金銭の貸し借りであれば「借用書」や「金銭消費貸借契約書」などが証拠となります。
このように、通常訴訟では、証拠の有無が結果を大きく左右する可能性もあるため、その点も考慮のうえ、利用の是非を検討することが大切です。
6 まとめ
債権回収のための裁判手続きについて見てきましたが、実際に裁判手続きを利用する際には、あらかじめ債務者の支払能力についても確認しておく必要があります。
債務者に支払能力がなければ、たとえ債務名義を取得したとしても、強制執行により債権を回収することができないため、それまでの時間や手間が無駄になってしまいます。
債権回収を検討する際は、強制執行により回収・換価できる財産が相手方にあるかどうかを見極めることが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。