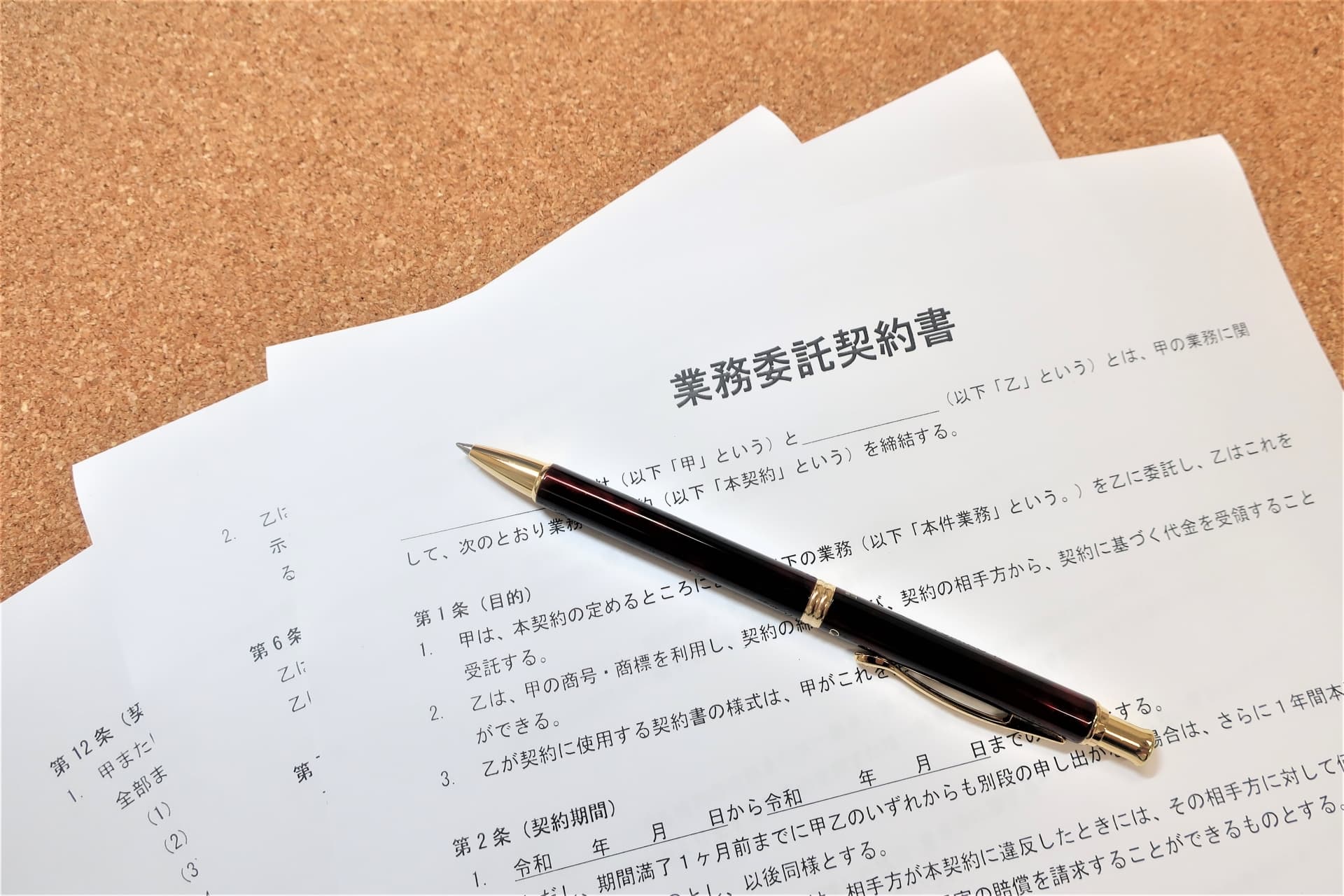AI生成物に著作権は認められる?2つのパターンに分けて解説!

はじめに
ここ数年において、知的財産の分野をはじめとするさまざまな分野でAIに関する議論が活発になっています。AIと著作権の問題についても、例外ではありません。
AIによって創作された生成物に著作権は認められるか?
認められる場合、著作権は誰に帰属するのか?
みなさんはご存知でしょうか。
今回は、AI生成物と著作権について、わかりやすく解説します。
1 AI生成物と著作権
AIが関与することにより創作される生成物は、以下の2つのパターンに分類することができます。
- AIを道具として用いて創作した生成物
- AI自体が創作した生成物
以上のように、AI生成物の著作権を考察するにあたっては、2つのパターンに分けて考えることが必要になります。
本題に入る前に、著作権の前提となる「著作物」について、簡単に確認しておきましょう。
2 著作権が認められるために必要な「著作物」とは?
著作権について定める著作権法は、「著作物」について以下のように定義しています。
-
【著作権法2条1項1号】
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう
このように、「著作物」といえるためには、思想や感情が創作的(オリジナリティ)に表現されていることが必要になります。
もっとも、ここでいう表現者はあくまで「人」であることが前提になっています。
そのため、AI生成物が「著作物」として認められるためには、AI生成物について人が創作的に関与していることが必要になります。
3 AIを道具として用いて創作した生成物
AIを道具として用いて生成物を創作した場合、人が創作的に関与しているといえるでしょうか。
このパターンにおいてポイントとなるのは、AIが道具として用いられているに過ぎないということです。
道具としてしか使われていない以上、AI生成物において、思想や感情が創作的に表現されていると認められる場合には、その表現者はあくまで「人」であるということになります。
つまりは、AI生成物を創作する過程において、「人」に創作の意図があり、かつ、具体的な出力となるAI生成物を得るための創作的寄与が認められれば、「人」が思想や感情を創作的に表現するための道具としてAIを用いてAI生成物を創作したと考えることができます。
この場合、AIを道具として用いて創作した生成物は、「著作物」にあたり、著作権が発生することになるのです。
そして、ここでいう著作権は、AI生成物を創作した「人」に帰属するということになります。
4 AI自体が創作した生成物
著作権との関係で特に問題となるのが「AI自体が創作した生成物」です。
この場合、上記の考え方からすれば、人が創作的に関与しているといえないため、著作権は発生しないと考えるのが自然でしょう。
AI自体が生成物を創作する場合であっても、そもそもは「人」によるAIへの指示が前提となっているため、その意味で人が関与しているといえます。
ですが、ここでいう「人の関与」は、AIに指示を出すという程度に留まるものです。
指示に基づいて、実際に生成物を創作するのはAIであるため、この過程で完成した生成物を「人の思想や感情を創作的に表現したもの」ということには無理があります。
このように、AI自体が創作した生成物については、人による創作的な関与が認められないため、「著作物」にはあたらず、著作権は発生しないことになります。
そこで問題となるのが、AI自体が創作した生成物は一切保護されないのかということです。
仮に、AI自体が創作した生成物が何ら法的に保護されないとなると、多くの時間と労力をかけてAIを開発しても、その生成物を横取り的に第三者に自由に使われてしまうことになります(このような行為を「フリーライド」といいます)。
AI生成物を創作するためには、多くの資本を投下しなければならないケースもあり、また、創作されたAI生成物自体に経済的価値が認められる場合もあります。
にもかかわらず、無断利用が許されるという帰結はあまりに妥当性を欠くようにも思えます。
この点については、現時点において、ハッキリとしたルールが確立されていません。
政府が公表している「知的財産推進計画2019」によれば、AIの今後の利活用の状況を見ながら、ルールを整備していくとしています。
5 AI生成物を保護する方法
AI生成物を保護する方法としては、以下のようなものが考えられます。
(1)商標権
「商標権」とは、商品やサービスに使用する目印(商標)を独占的に使用できる権利のことをいいます。
AI生成物を、自社の商品やサービスに使用する場合は,商標権によって保護することが考えられます。
現在では、登録できる商標のタイプも増えてきているため、たとえば,AIが創作したロゴを商標登録すれば、他社は指定した商品やサービスの範囲で同一または類似のロゴを使用できなくなります。
(2)不正競争防止法による保護
AI生成物を、自社の商品・営業を表示するものとして使用する場合は、不正競争防止法により保護を図ることが考えられます。
たとえば、既に広く周知されている自社の商品表示と同一又は類似の商品表示が使用されていることによって、消費者に混同が生じるおそれがある場合や、全国的に著名な自社の商品表示と同一又は類似の商品表示が使用されている場合には、これらの行為を差止めることができ、また、損害賠償を請求することが可能になります。
6 まとめ
現状において、AIそのものが創作した生成物は著作権法上の著作物にあたらないため、著作権により保護を図ることはできません。
とはいえ、AI生成物を生みだすまでには、多大な資本を投下するとともに、多くの時間や労力を割かなければならないこともあります。
そのため、事業者は、可能なかぎり、フリーライドを排除するよう努める必要があります。
今後、新たなルールが整備されていく可能性もあるため、動向に注意するようにしましょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。