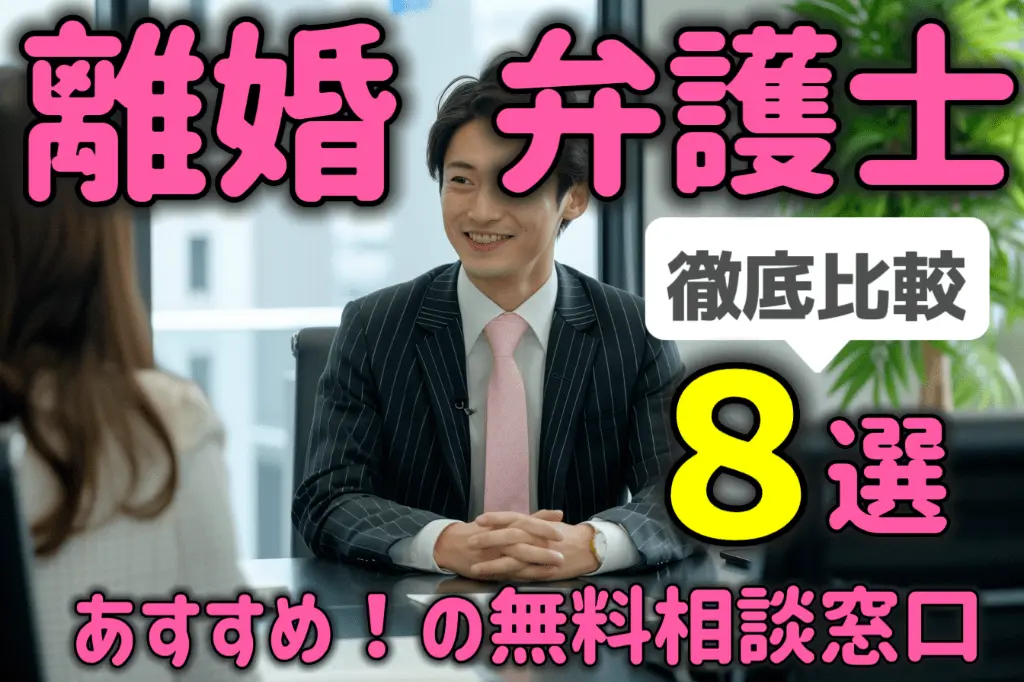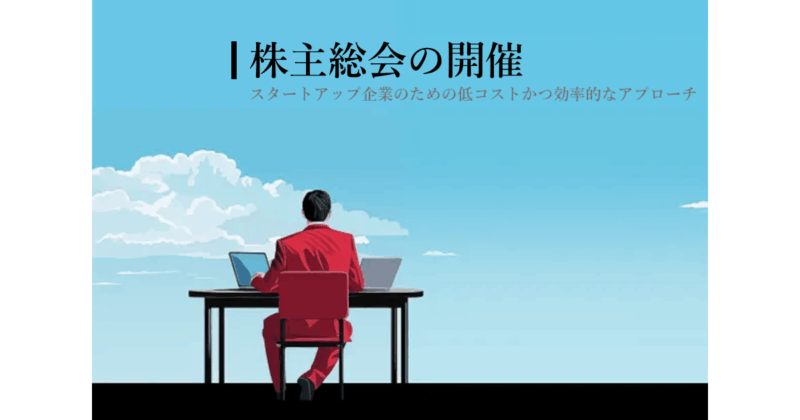税制適格ストックオプションにおける3つの要件を弁護士が解説!

はじめに
税制適格ストックオプションは、付与された従業員などが税制上の優遇措置を受けることができるストックオプションです。
特に、ベンチャー企業などにおいて、インセンティブ目的で発行することが多い税制適格ストックオプションですが、税制上の優遇措置を受けるためには、税制適格要件を満たしていることが必要になります。
今回は、税制適格ストックオプションの要件について、解説します。
1 税制適格ストックオプションとは
「税制適格ストックオプション」とは、事業者が役員や従業員に付与するストックオプションのうち、税制上の適格要件を満たすものをいいます。
ストックオプションは、インセンティブ効果に期待して事業者が発行するものですが、付与を受けた役員や従業員において、税金の負担が重くなってしまうと、十分なインセンティブ効果を期待することができません。
税制適格要件を満たさないストックオプションでは、課税のタイミングが2回あります。
すなわち、権利行使により株式を取得するタイミングと、株式売却によりキャピタルゲインを得るタイミングの計2回です。
権利行使時には、株式をまだ現金化できていないことから、ストックオプションの付与を受けた従業員等にとって、このタイミングで課税されると大きな負担となってしまいます。
これに対し、税制適格ストックオプションでは、課税のタイミングは、株式を売却した時の1回だけです。
この時点では、株式を現金化できているため、税金の負担を軽くすることができます。
また、税制適格ストックオプションは税制適格要件を満たさないストックオプションに比べ、税率が低いため、その意味でも税金の負担を軽くすることができるのです。
以上のように、税制適格要件を満たすか否かで、付与対象者にとっては大きな違いがあります。
ベンチャー企業の多くは、十分なインセンティブ効果を得るために、税制上の優遇措置を受けることができる税制適格ストックオプションを活用しているのです。
2 税制適格ストックオプションの要件
発行するストックオプションにつき、税制上の優遇措置を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
- 発行内容
- 付与対象者
- 権利行使に関する事項
(1)発行内容
税制適格ストックオプションは、株主総会の決議により、無償で発行することが条件となっています。
近時では、有償ストックオプションを付与する事業者も増えてきていますが、有償ストックオプションの場合も課税タイミングは1回のみです。
ですが、有償ストックオプションの場合、ストックオプションを付与する際に、付与対象者が発行価額を払い込む必要があるという点で、税制適格ストックオプションとは異なります。
(2)付与対象者
税制適格ストックオプションの付与対象者にも条件があります。
具体的には、付与対象者は、会社やその子会社の取締役、執行役または使用人であることが必要です。
もっとも、この条件にあてはまる場合であっても、会社の大口株主や大口株主と特別の関係にある者(たとえば、親族)は、税制上の優遇措置を受けることはできません。
ここでいう「大口株主」とは、上場会社の場合は発行済株式の10分の1を超える株式を、非公開会社の場合は発行済株式の3分の1を超える株式を保有している株主のことをいいます。
また、社外の人材を税制適格ストックオプションの付与対象者とすることも可能です。
もっとも、社外の人材に税制適格ストックオプションを付与する場合には、「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」を作成し、主務大臣の認定を受ける必要があります。
※社外人材に対する税制適格ストックオプションの付与について、詳しく知りたい方は、「社外人材に税制適格ストックオプションを付与する手続を弁護士が解説」をご覧ください。
(3)権利行使に関する事項
権利行使に関する事項として、「権利行使期間」と「権利行使価額」のそれぞれについて、以下の条件を満たすことが必要です。
①権利行使期間
ストックオプションを付与する旨の決議後2年を経過した日から付与する旨の決議後10年が経過する日までに権利を行使することが条件となります。
②権利行使価額
1株あたりの権利行使価額が、ストックオプションを付与する旨の契約締結時における1株あたりの時価以上であることが条件となります。
また、権利行使価額については上限額が決まっており、年間で1200万円を超えることはできません。
権利行使価額が年間で1200万円を超えた場合、それ以降は、税制適格の対象から外れることになるため、注意が必要です。
3 その他の要件
そのほかにも、以下のような条件を満たしていることが必要になります。
(1)譲渡禁止
発行するストックオプションについて、譲渡を禁止していることが必要です。
(2)株式の交付
ストックオプションを発行する場合、事業者は、発行するストックオプションの内容や数、割当日などを定めて、株主総会の決議で決定する必要があります。
そのため、権利が行使され株式を交付する際には、株主総会の決議により決定した上記事項に従って交付することが必要です。
(3)保管委託
事業者は、証券会社または金融機関と管理等信託契約を締結する必要があります。
これは、権利行使により取得された株式は、証券会社や金融機関で保管、または管理等信託するということが条件となっているためです。
4 まとめ
ベンチャーやスタートアップ企業などは、高い成長率が求められるため、優秀な人材を確保することが必須となります。
ストックオプションは、人材を確保するうえで有効な手段ですが、導入を検討する際には、インセンティブ効果を十分に発揮できるかという観点から、導入の是非を判断する必要があります。
また、実際に税制適格ストックオプションを導入する場合には、今回見てきた税制適格要件を十分に理解しておくことが大切です。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。