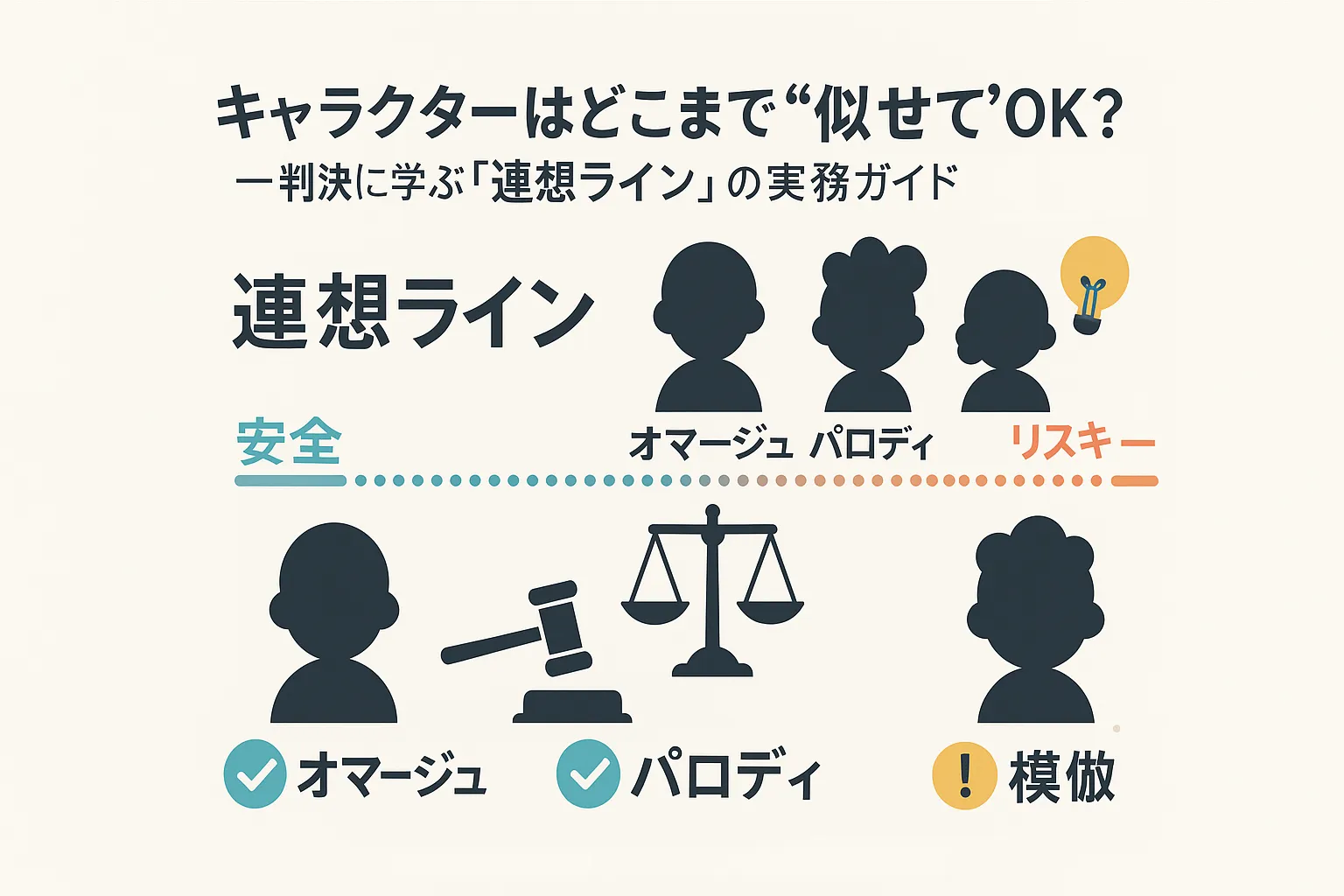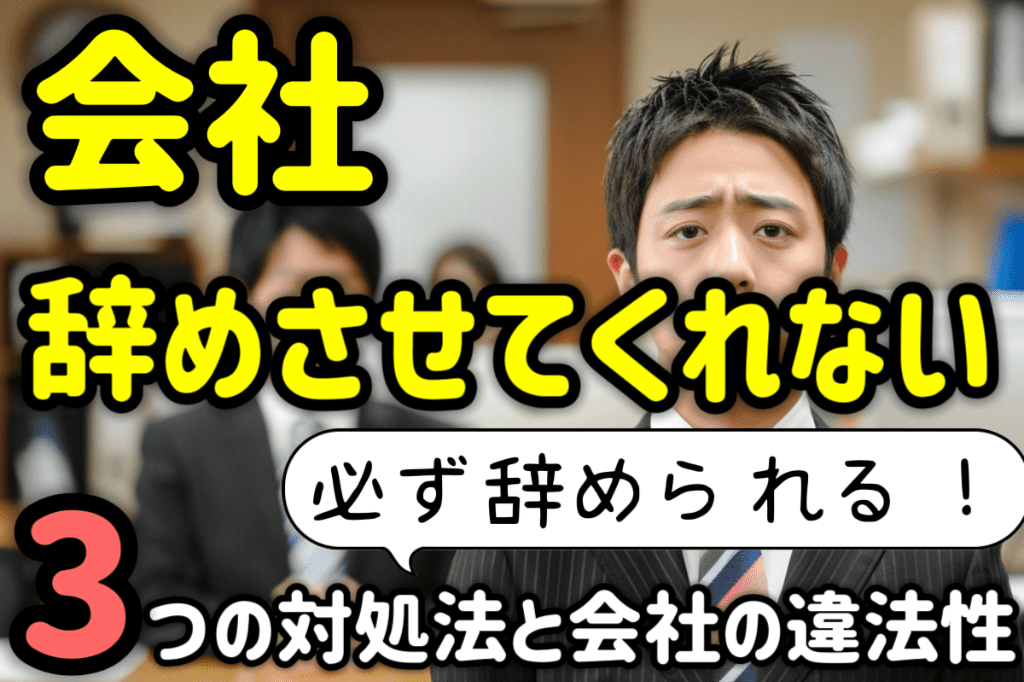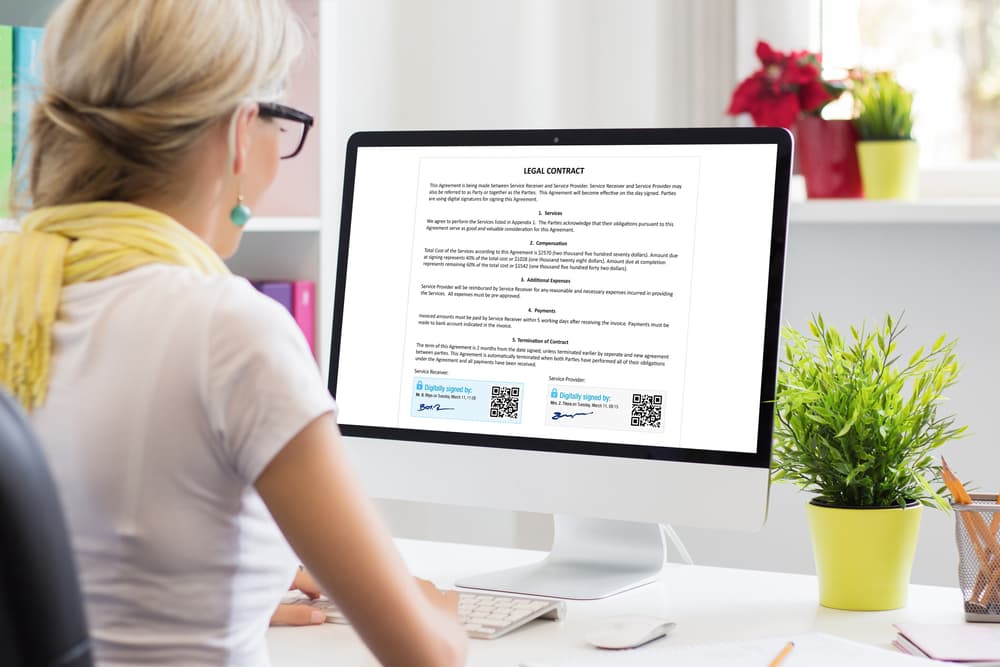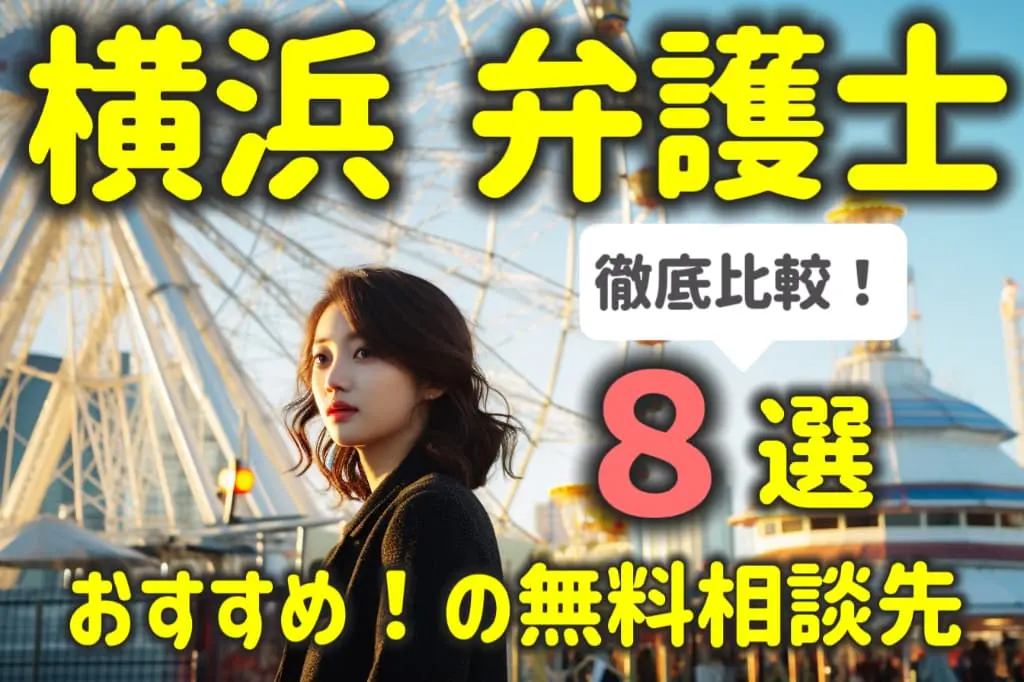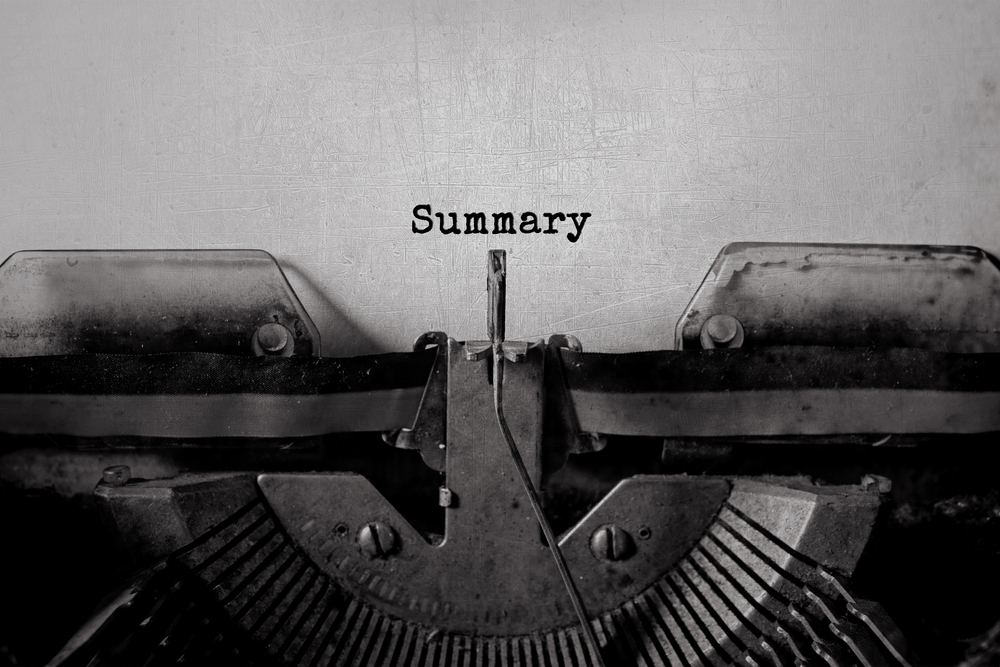ドローンを使った気象観測で注意すべき2つの法律規制を弁護士が解説

はじめに
「ドローンによる気象観測」は今、とても注目を浴びています。
上空で観測した風速や湿度などのデータを地上に送ることのできる機能や、強風にも耐えられる性能をもつドローンの開発がすすんでいます。
もっとも、気象観測のためであるからといって、いつでも自由にドローンを飛ばすことはできません。そこには気を付けなければならない法律や規制が存在しているからです。
ドローンを活用して気象観測ビジネスを始めようと考えている事業者にとっては、この点が大変気になるところではないでしょうか。
そこで今回は、ドローンで気象観測ビジネスを始めたいと考えている事業者向けに、ドローンを飛ばす際の法律・規制や注意点などを中心に、ITに詳しい弁護士が解説していきます。
1 ドローンを活用した気象観測
ドローンによる気象観測がなぜ注目されているかというと、それは、気象観測用ドローンによるビジネスの可能性の広さにあります。
具体的に、気象観測用ドローンは、以下のように幅広く活用することができるのです。
- 南極などの局地での気象観測
- ロケットを打ち上げる際の事前調査
- 風力発電を計画する場合の事前・事後調査
- 風によるダイオキシンなどの汚染物質の飛散の予測
- 配達ドローンに対する気象情報の伝達
このように、気象観測用ドローンは、様々な分野に応用ができるため、活用範囲はかなり広いといえます。
もっとも、気象観測でドローンを活用する場合には、ドローンの飛行について規制している「航空法」という法律のほか「気象観測」にまつわる特有の法律も検討する必要があります。
2 気象業務法による法律規制
気象観測を行う際には、「気象業務法」という法律が定めているルールを守らなければなりません。
(1)気象業務法とは
「気象業務法」とは、気象だけでなく、海洋や火山などの自然現象を観測することにより、警報を出すなどして、人々の生活を助けるためのルールが定められた法律です。
そのため、気象観測をするにあたり、無責任な情報を流して、人に誤った判断をさせてしまうことのないように様々な規制を設けています。
(2)「気象業務法」による法律規制
「気象業務法」が定めているルールには以下のように原則と例外があります。
①原則
政府機関・地方公共団体以外の企業などは、原則として、自由に気象観測をすることができます。
②例外1
以下の2つにあたる気象観測に関しては、ドローンで行う場合も含めて、自由に行うことはできません。
- 成果の発表を目的とした気象観測
- 成果を災害防止に利用するための気象観測
「成果の発表を目的とした気象観測」とは、例えば、ドローンで観測した気温の情報をテレビで多くの人に伝える行為が挙げられます。
「成果を災害防止に利用するための気象観測」とは、例えば、地震が発生した地域に向けて、ドローンで観測した降雨量の情報をラジオで伝える行為が挙げられます。
これらの観測によって得た情報に万一誤りがあると、事業者の自己責任だけでは済まされません。例えば、上に挙げた例でいうと、地震が発生した地域において、ラジオで流れた情報に従って避難したところ、実はとても危険な場所であり怪我をしてしまったなどということが考えられます。
このような理由で、上に挙げた2つの観測を自由に行うことは許されていないわけです。
これらの観測をする場合には、気象庁が定める以下の3つの条件を守らなければいけません。
-
(ⅰ)技術上の基準
(ⅱ)施設の届出
(ⅲ)検定に合格した気象測器の使用
(ⅰ)技術上の基準
気温、相対湿度、風速、降雨量などについて観測する場合、一定の機能を備えた観測機器を使わなければなりません。また、その場合の観測値の最小位数が決まっています。
例えば、風速を観測する場合には、風速器を使わなければなりません。そのときの観測値は、1m/sを最小とします。
(ⅱ)施設の届出
観測する施設を決めたら、30日以内にその施設から一番近い気象台へ届出をださなければなりません。届け出は、持参や郵送、メールなど様々な手段によって行うことが可能です。
(ⅲ)検定に合格した気象測器の使用
より正確な観測をしてもらうために、気象測期の性能について検定を受けて合格していることが必要です。また、測器ごとに検定有効期間があるので注意しなければなりません。有効期間が切れた場合は、再検定を受ける必要があります。
例えば、風速を図る測器のうち、風車型風速計であれば有効期間は5年となっています。
③例外2
もっとも、「成果の発表を目的とした気象観測」や「成果を災害防止に利用するための気象観測」にあたる場合でも、以下の5つのケースでは、例外1に挙げた気象庁が定める条件に従わずに、自由に気象観測をすることができます。
-
(ⅰ)特殊な環境により変化した気象を対象とした観測
(ⅱ)気温、気圧、風向、風圧その他の一定の種目以外の種目について行う気象の観測
(ⅲ)臨時に行う1か月未満の気象観測
(ⅳ)船舶で行う気象観測
(ⅴ)航空機で行う気象観測
※結論先取り的に言えば、ドローンを使って成果発表を目的とした気象観測などをする場合には、上記5つのケースのうち「⑤航空機で行う気象観測」の該当性が問題となります。
(ⅰ)特殊な環境により変化した気象を対象とした観測
「特殊な環境により変化した気象を対象とした観測」とは、観測場所周辺の屋外における気象観測以外の観測のことを言います。例えば、屋内や、周囲の熱源などの影響を受けるような坑道の中のように特殊な環境での気象観測が挙げられます。
(ⅱ)気温、気圧、風向、風圧その他の一定の種目以外の種目について行う気象の観測
「気温、気圧、風向、風圧その他の一定の種目以外の種目について行う気象の観測」とは、法で禁止されている気象現象以外の気象を観測することを言います。例えば、霧や黄砂などの気象現象は、法で観測が禁止されていないので、自由に観測をすることができます。
(ⅲ)臨時に行う1か月未満の気象観測
「臨時に行う1か月未満の気象観測」とは、1か月未満の期間における観測のうち、同じ場所で継続的に行わない気象観測のことをいいます。例えば、自動車に搭載された気象センサーでの気象観測が挙げられます。
(ⅳ)船舶で行う気象観測
「船舶で行う気象観測」とは、海上気象だけでなく、様々な海洋観測も含みます。例えば、海水温や海潮流などの観測が挙げられます。
(ⅴ)航空機で行う気象観測
「航空機で行う気象観測」とは、航空機の安全な運航のために航空機についているセンサーなどを用いて行う気象観測のことを言います。例えば、大気現象だけでなく、風や露点温度の観測などが挙げられます。
以上に挙げた5つのケースでは、自由に気象観測をすることが可能です。
そうすると、ドローンを使って成果発表を目的とした気象観測などを行う場合には、ドローンが上記の「航空機」といえるのであれば、気象庁が定める条件に従うことなく自由に気象観測ができることになります(上記ケース⑤)。
そこで、ドローンが、気象業務法が定める「航空機で行う気象観測」の「航空機」といえるのかが問題となります。
(3)ドローンによる気象観測
結論から先出しすると、ドローンは「航空機」にはあたらず、ドローンによる成果発表を目的とする気象観測などは、自由に行うことはできません。
そもそも、気象業務法においては、「航空機」がどういうものを指すのかが明確に定められていません。
この点、気象業務法にはさまざまなルールが定められていますが、そのルールを守るための手続きなどがさらに規則という形で細かく定められています。そして、気象業務法の規則には、「航空法」にあるルールを踏まえた内容のものも存在します。
そのため、「航空機」についても、航空法と同じように考えることになり、無人航空機であるドローンは「航空機」にはあたらないということになります。
このように、ドローンで行う成果発表を目的とする気象観測などは「(ⅴ)航空機で行う気象観測」にあたらないため、自由に行うことはできません。
それでは、ドローンで成果発表を目的とする気象観測などをするためには、どのようなルールに従えばよいのでしょうか。
この点は、ドローンによる成果発表を目的とする気象観測などが、上に挙げた例外的なケース((ⅰ)~(ⅲ))に当てはまるかどうかで守るべきルールが変わってきます。
-
【(ⅰ)~(ⅲ)にあたる場合】
気象庁が定めている条件に従わずに自由に気象観測することができる
例えば、ドローンを使って、屋内のスポーツ競技施設などで温度や湿度の観測を行う場合、雨や強風などといった気象変化の影響をあまり受けません。
そのため、「特殊な環境により変化した気象を対象とした観測」にあたり、自由に観測を行うことができます。
-
【(ⅰ)~(ⅲ)にあたらない場合】
気象庁が定めている条件を守って気象観測しなければならない
例えば、自分の住んでいる地域の気温などの情報を、天気予報番組としてネット上で毎日配信することが挙げられます。この場合は、例外的なケースにあたらないため、気象庁が定める条件を守って気象観測をする必要があります。
以上のように、ドローンを使って成果発表を目的とする気象観測などを行う場合には、どのような目的で気象観測を行うのか、何を観測の対象としているかなどをきちんと確定させたうえで、気象業務法のルールを守る必要があるのかどうかを確認することが大切です。
もっとも、気象観測のためであるとはいえ、ドローンを活用する以上、気象業務法だけでなく、「航空法」のルールも守らなければなりません。
3 航空法による法律規制
気象観測のためにドローンを飛ばす場合、いつでも、どこでも自由に飛ばせるわけではありません。そこには「航空法」という守らなければならないルールがあります。「航空法」は、ドローンの飛行について、「飛行場所(飛行禁止区域)」と「飛行方法(飛ばし方)」という2つの側面からルールを設けています。
(1)飛行「場所」の規制
航空法は、原則として以下の3つの場所でドローンを飛ばすことを禁止しています。
- 空港周辺の空域
- 一定高度以上の空域
- 人口集中地区(DID地区)
これらにあたる場所でドローンを飛ばす場合には、国土交通大臣の許可をもらわなければなりません。
①空港周辺の空域
空港周辺の上空でドローンを飛ばすことはできません。
このルールは、航空機の安全を守るために設けられています。空港上空で気圧などを観測する目的などでドローンを飛ばすと、飛行機の航行を邪魔してしまうおそれがあり、危険であるため、空港周辺の空域でドローンを飛ばすことは禁止されています。
②一定高度以上の空域
地上から150m以上の高さにある上空で、ドローンを飛ばすことはできません。そのような高さで降雨量を観測する目的などでドローンを飛ばしてしまうと、飛行機の航行を邪魔するおそれがあり危険であるため、150m以上の高度でドローンを飛ばすことは禁止されています。
③人口集中地区(DID地区)
人がたくさん集まっている場所でドローンを飛ばすことはできません。
なぜなら、そのような場所で、局地的な大気現象などを観測する目的などでドローンを飛ばしてしまうと、人や車などに落下して、人に怪我をさせたり、車などを壊してしまう可能性があり危険なため、DID地区でドローンを飛ばすことは禁止されています。
なお、「人口集中地区(DID地区)」にあたるかどうかは、国土地理院が出している「人口集中地区マップ」で確認することができます。
以下は、東京近隣を示した人口集中地区マップですが、赤くなっているエリアが人口集中地区にあたります。ここからもわかるように、東京23区のほとんどが人口集中地区にあたります。
(2)飛行「方法」の規制
航空法は、ドローンの飛ばし方として、以下の6つのルールを設けています。
- ドローンを飛ばすのは日中であること(★)
- ドローンとその周辺を直接目で見て監視できること(★)
- 人や物件とドローンの間に30m以上の距離を保つこと(★)
- 人が多く集まる祭りなどのイベント上空で飛ばさないこと(★)
- 爆発物などの危険物を輸送しないこと
- ドローンから物を落とさないこと
これらのルールの中でも、ドローンで気象観測をする場合に特に問題となるのは、①日中における飛行、②ドローンとその周辺を直接目で見て監視した状態での飛行、③人などとドローンの間に30m以上の距離を保った状態での飛行、④人が多く集まるイベント上空での飛行禁止です。
以下では、この4つのルールに絞って、詳しく解説していきます。
①ドローンを飛ばすのは日中であること
ドローンを飛ばすのは日出から日没までの日中でなければなりません。
夜間に飛ばすと、ドローンの姿だけでなく、周囲の障害物などが見えにくくなり、ドローンが落下して事故を起こす可能性が高いので原則禁止されています。
そのため、夜間にドローンを飛ばしたい場合には、国土交通大臣の承認が必要になります。
例えば、朝から晩までの気温や湿度などの現象をドローンで観測したい場合、夜間については国土交通大臣の承認をもらわなければ観測し続けることはできません。
②直接目で見てドローンとその周辺を常に監視すること(目視外飛行)
ドローンを安全に飛ばすため、ドローンの姿や周辺の障害物の監視は、人の目で直接行わなければなりません。
この点、モニターや双眼鏡などを使ってドローンを監視するとなると、監視できる範囲が狭くなり、十分に安全確認ができないおそれがあります。そのため、より安全にドローンを飛ばすために、ドローンの姿やその周辺の監視は人の目で直接行われなければなりません。
もっとも、ドローンで気象観測をするとなると、たとえば、高所の気温を観測する場合には、人の目で直接監視しきれなくなってしまいます。
そのため、このような状況でドローンを飛ばすことは、「目視外飛行」にあたり、国の承認が必要です。
なお、目視外飛行についての承認を得るためには、飛ばす場所やドローンの性能などにおける様々な条件をクリアすることが必要です。たとえば、「安全確保の体制」の一環として、「補助者」を配置しなければなりません。ここにいう「補助者」とは、操縦者以外の者でドローンの姿や周囲の気象状況を監視できる者のことをいいます。
もっとも、「補助者」の配置は絶対ではありません。補助者を配置しないのであれば、さらに課される厳しい条件をクリアすることが必要になってきます。
例えば、ドローンを飛ばす場所に、第三者が入らないようにすることが必要になり、そのために立入禁止の看板を出すなどの工夫を施すなどといったことが挙げられます。
※目視外飛行の承認に関する審査基準について、詳しく知りたい方は、国土交通省HPをご覧下さい。
③人や物件とドローンの間に30m以上の距離を保つこと
ドローンを中心とした半径30mの球の範囲の中に人や物が入っている状態でドローンを飛ばすことはできません。
このルールは、ドローンが人や物とぶつかってしまうことを防ぎ、人や物を保護するためのものです。
ここにいう「人」には、ドローンを飛ばす事業者の関係者は含まれません。具体的には、ドローン操縦者やその補助者などは、ここでいう「人」にあたりません。
また、ここでいう「物」とは、中に人がいる可能性のある車や建物などをいいます。
例えば、ドローンを使って山などの高所で気象観測をする場合、登山に来た人とドローンの間に30m以上の距離を保てない場合には、国の承認が必要となります。
④祭りや展示会など、人の多く集まるイベントの上空で飛ばさないこと
イベント会場などの上空でドローンを飛ばすことはできません。
そのような会場には人が多く集まるため、そのような場所でドローンが落下した場合、人にあたって、ケガをさせたりするなどの事故をおこす可能性があり危険です。そのため、人が多く集まるイベント会場などの上空でドローンを飛ばすことは禁止されています。
例えば、イベント会場上空で降雨確率などを観測するためにドローンを飛ばすような場合には、国の承認が必要になります。
このように、航空法はドローンの飛行について、「飛行場所(飛行禁止区域)」と「飛行方法(飛ばし方)」という2つのルールを設けています。
気象観測でドローンを飛ばす場合には気象業務法のルールだけでなく、これらの「航空法」のルールも守らなくてはなりません。
仮に、これらのルールを守らなかった場合、一定のペナルティが科されてしまう可能性があります。
4 気象業務法に違反した場合の罰則(ペナルティ)
検定に合格してない機器を使って気象観測した場合、気象業務法違反となり、
- 最大50万円の罰金
を科される可能性があります。
そのため、使用する機器が検定に合格したものであるか、有効期限は大丈夫かなどといったことをきちんと確認することが大切です。
5 航空法に違反した場合の罰則(ペナルティ)
国土交通大臣の許可・承認が必要な場所・飛行方法でドローンを飛ばした場合、航空法違反となり、
- 最大50万円の罰金
を科される可能性があります。
このようなことにならないためにも、気象観測のためにドローンを飛ばす際には、飛ばす場所や飛ばす方法に問題はないか、などをしっかりと確認することが必要です。そのうえで、国土交通大臣の許可・承認が必要なケースであれば、次の項目で解説するように、適切な方法で許可申請を行うことが必要になってきます。
6 航空法上の許可・承認申請のやり方
国土交通大臣の許可・承認が必要となる場合、ドローンを飛ばす予定日より10日前には、申請をしておかなければなりません。
もっとも、初めて申請する場合には、不備があったりすると、その補正など時間がかかってしまうため、余裕をもって10日前よりも前に申請するのがおすすめです。
(1)申請前に行うこと
まずは、申請前に以下の事項を確認しましょう。
- ドローンを飛ばす理由
- 予定している飛行場所で飛ばす必要性
- ドローンそのものの安全性
- ドローン操縦者の技量
- 飛行マニュアルがあり、安全性の意識があること
これらの事項は申請書の記載事項にもなっていますので、これらの条件を満たしていなかったり、きちんとした理由がないとなると、ドローンを飛ばす許可・承認は下りないものと考えられます。
(2)申請の種類
申請には、
- 個別申請
- 包括申請
という2つの種類があります。
①個別申請
ドローンを飛ばす日や飛ばす航路が決定している場合には、個別申請を行います。
②包括申請
ドローンを飛ばす期間や経路について、特定はできないけれど、ざっくりとした期間や経路は決まっているという場合には、包括申請を行います。
包括申請には以下の2つの種類があります。
- 期間包括申請
- 飛行経路包括申請
「期間包括申請」とは、天候などの条件から、いつドローンを飛ばすか具体的に決められない場合に、「何日から何日まで」などというように期間を指定して申請することをいいます。この場合、最大で1年間の期間を指定できます。
「飛行経路包括申請」とは、「横浜市全体を飛ばす」などといったように飛行場所に一定の範囲を設けて申請することを言います。
なお、包括申請を行った場合には、飛行許可を与えた機関に対して、3か月ごとに飛行実績を報告する必要があります。
(3)申請方法
申請方法には、以下の4つの方法があります。
- 郵送
- 窓口持参
- オンライン申請
- 電話、メール、FAX
このうち、電話やメール、FAXでの申請は緊急のときのみ認められています。
(4)提出先
申請書の提出先は、
- 空港事務所
- 地方航空局
のいずれかとなります。
このように、許可・承認の申請には、様々なルールが決められているため、申請の際には、事前にきちんと確認するようにしましょう。
※航空法上の許可・承認申請のやり方について、詳しく知りたい方は、「ドローンの飛行許可申請のやり方は?5つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。
7 小括
ドローンを活用した気象観測の領域は、気象観測用ドローンの開発がすすめられている段階ですので、新規参入の事業者にもまだまだビジネスチャンスがあります。
ドローンで気象観測をする場合には、観測の仕方や目的・対象などによって、守らなければならないルールが変わってきます。
航空法を始め、気象業務法についても丁寧に検討したうえで、適切にドローンを飛ばすことが大切です。
8 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- 原則として、自由にドローンを使って気象観測をすることができるが、①成果の発表を目的とした気象観測と②成果を災害防止に利用するための気象観測にあたる場合は気象庁が定めているルールに従わなければならない
- 気象庁が定めているルールとしては①技術上の基準、②施設の届出、③検定に合格した気象測器の使用の3点が挙げられる
- 気象庁のルールに従わなくていい例外は、①特殊な環境の気象観測、②一定の種目以外の種目について行う気象の観測、③臨時に行う気象観測、④船舶で行う気象観測、⑤航空機で行う気象観測の5つのケースである
- 航空法によって、①空港周辺の上空、②地上から150m以上の空域、③人口集中地区の3つでは、許可がなければドローンを飛ばせない
- ドローンで気象観測を行う際に、航空法との関係で特に問題となるのは、①日中の飛行、②ドローンとその周囲を目で直接監視できること、③人と物件から30mの距離を取らなければいけない、④人の多く集まるイベントの上空での飛行禁止という4つのルールである
- 気象業務法と航空法に違反すると最大50万円の罰金を科される可能性がある
- ドローン飛行の許可・承認の申請は、飛行予定日の10日前までに行う
- 申請前に、①ドローンを飛ばす理由、②飛行場所で飛ばす必要性、③ドローンの性能、④操縦者の技量、⑤マニュアルの存在と安全意識があること、の5点を確認する必要がある
- 申請方法は、①個別申請、②包括申請があり、包括申請はさらに期間包括申請と飛行経路包括申請がある
- 包括申請の場合は、許可した者に対して3か月ごとに飛行実績の報告をする必要がある
- 申請方法は①郵送、②窓口提出、③オンライン申請、④電話、メール、FAXの4つである
- 申請書類の提出先は、①空港事務所、②地方航空局のいずれかである
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。