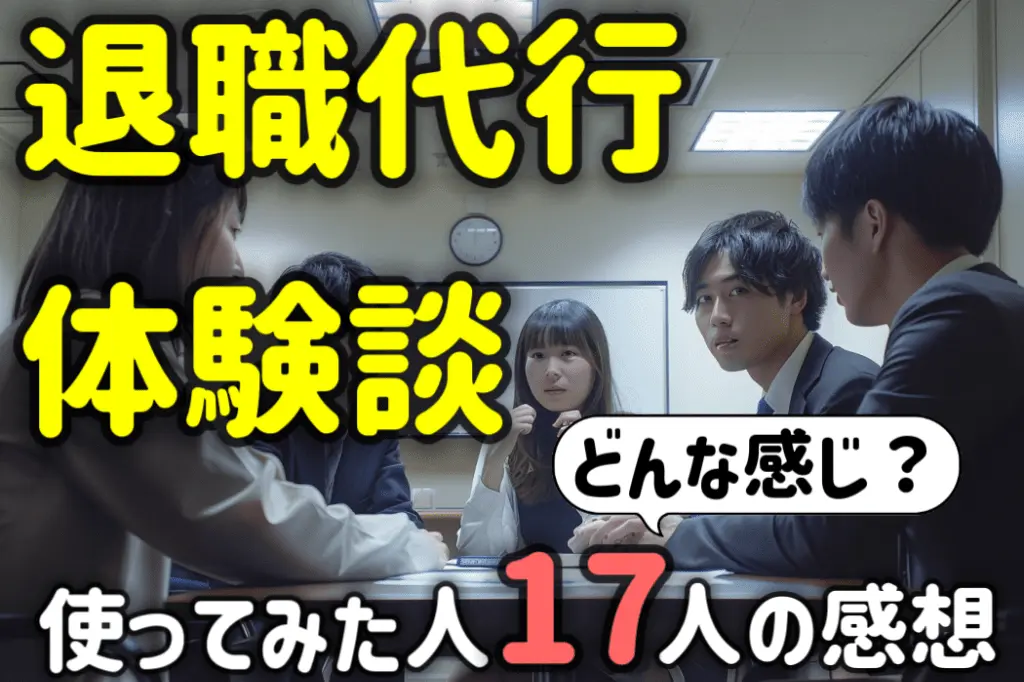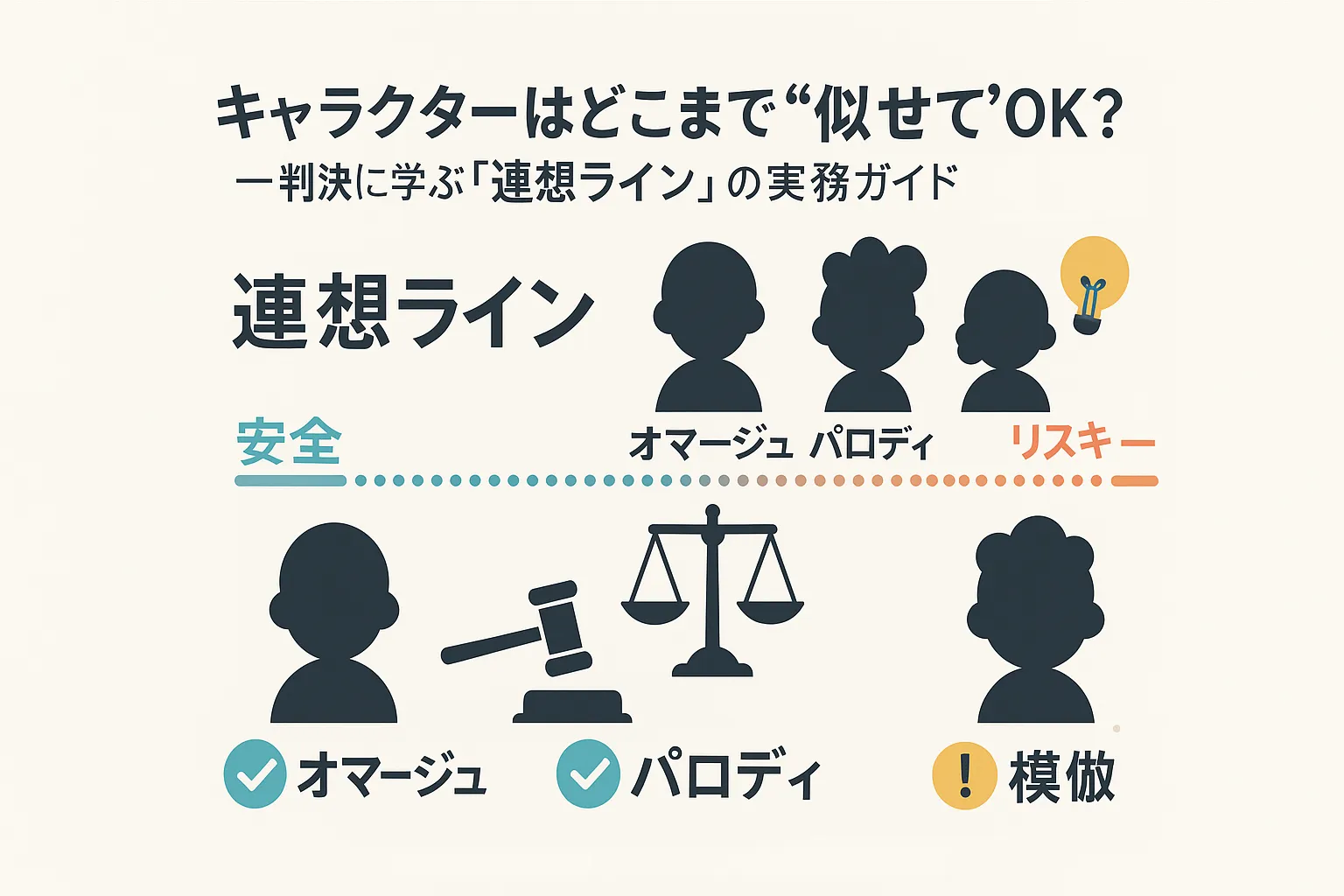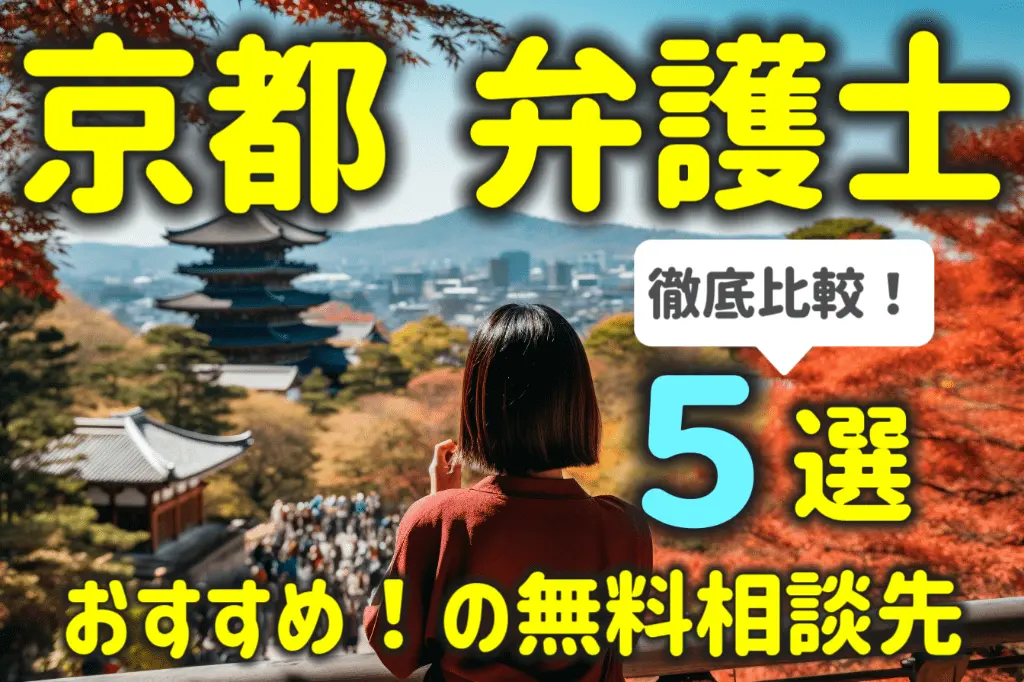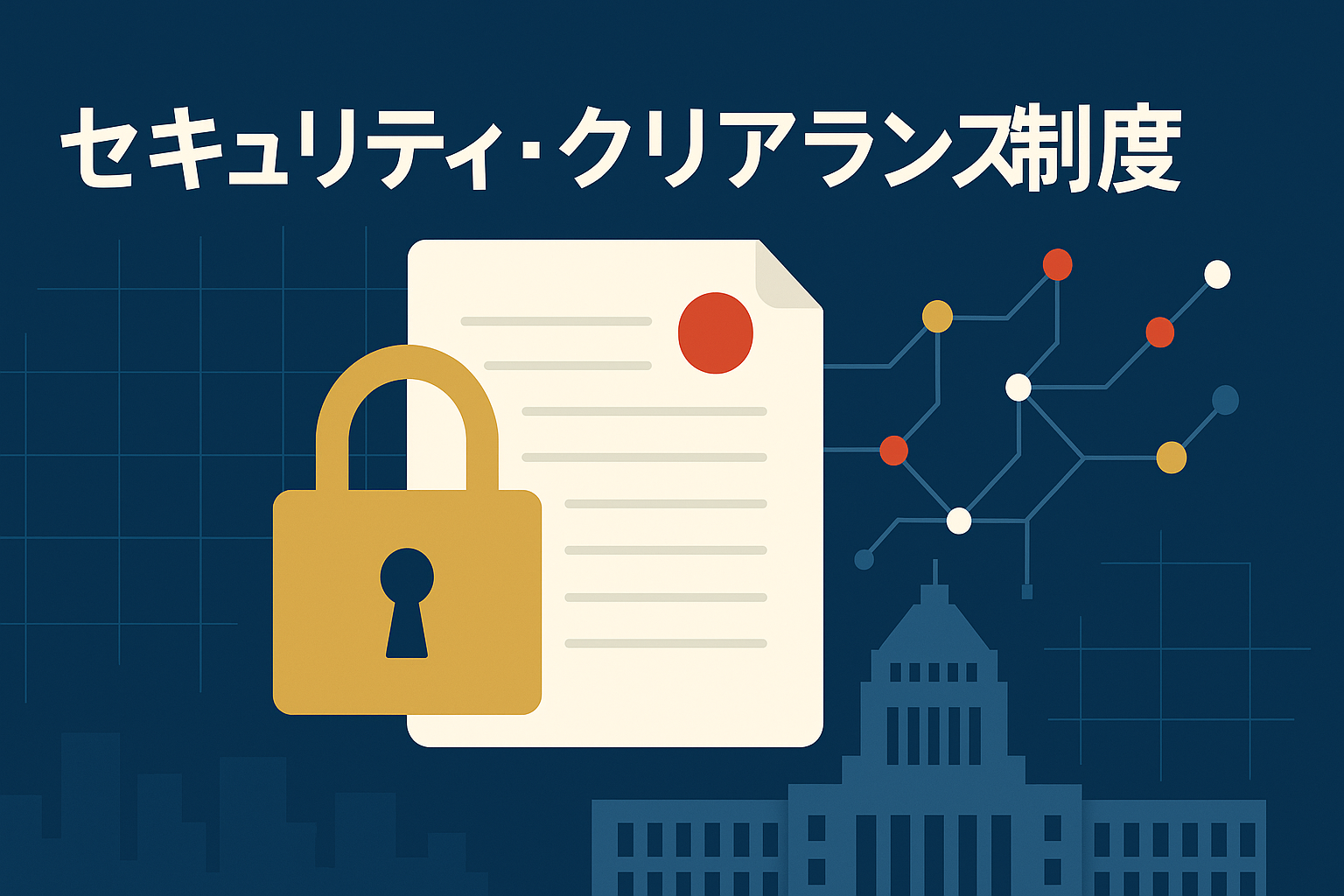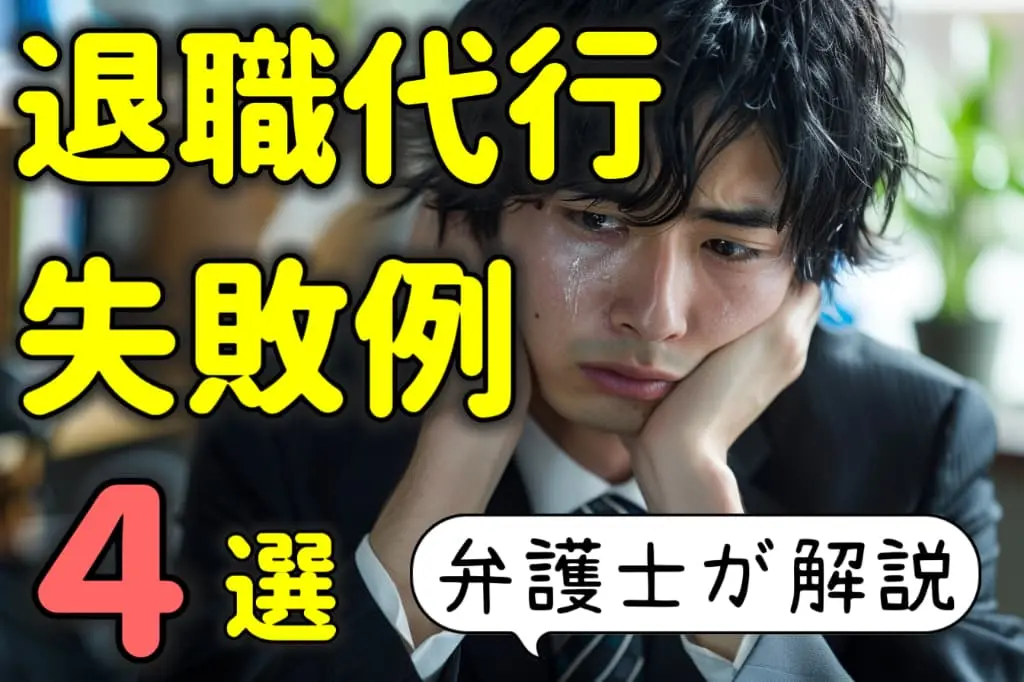ドローンにより報道資料を収集する際の2つの法律規制を弁護士が解説

はじめに
災害大国とも言われる日本では、大きな災害がいつ起きても不思議ではありません。
もっとも、災害現場にはあらゆる危険が潜んでおり、取材をするにしても、場所や状況によっては、人が入り込むことができないことも少なくありません。
そのような場合に、遠隔からドローンを操作して事故や災害現場の状況を撮影することができれば、迅速にその状況を報道することが可能になります。
とはいえ、ドローンを飛ばすためには、法律で決められている一定のルールをきちんと守る必要があります。
そこで今回は、報道資料を収集する目的でドローンを使う際に、どのような法律規制を守る必要があるのか、などについて、ITに詳しい弁護士が解説します。
1 ドローン・ジャーナリズム
「ドローン・ジャーナリズム」とは、ドローンを飛ばすことで情報を取得し、その情報を基に報道を行うことを意味します。ドローン・ジャーナリズムは、とりわけ、人が立ち入ることのできない危険区域や事故・災害現場で活用されることが期待されています。
2016年に発生した熊本地震の際には、何機もの報道用ヘリコプターが飛ばされましたが、そのヘリコプターを消防活動などに提供した方がいいのでは? という指摘もありました。さらに、災害現場などに接近した取材ヘリの音がうるさく救命現場でのコミュニケーションを阻害するといった問題も指摘されていました。
この点、小型のドローンを災害現場などに飛ばすことができれば、これらの問題点を払拭することができ、さまざまなメリットを受けられるかもしれません。
具体的には、有事の報道用にドローンを準備しておくことで、ヘリコプターをチャーターするコストを削減できるだけでなく、すぐに現場に向けてドローンを飛ばすことができ、迅速に情報収集できるようになります。また、ドローンはヘリコプターに比べ小型で小回りが利くため、あらゆる対象により接近して撮影することも可能です。
このように、報道資料を迅速に収集するためにも、ドローンの存在は大変意義のあるものだと言えます。
もっとも、ドローンを飛行させるには「航空法」という法律をチェックしておく必要があります。
2 航空法による法律規制
航空法は、ドローンの飛行について、以下の2つの規制を設けています。
- 飛行「場所」(飛行禁止区域)
- 飛行「方法」(飛ばし方)
(1)飛行「場所」(飛行禁止区域)
ドローンが航空機と衝突したり、人・民家に墜落してしまうと、大きな被害が出るおそれがあります。
そのため、航空法では、飛行場所について以下の3つの規制を設けています
- 空港の周辺地域
- 150m以上の高度以上の空域
- 人や家屋が密集する地域(DID地区)
①空港の周辺地域
空港やヘリポートの周辺での飛行は、飛行機にぶつかるなどして、事故が発生する可能性があるためドローンの飛行が禁止されています。
②150m以上の高度以上の空域
空港やヘリポートの周辺以外でも、地表もしくは水面から150m以上の空域は、航空機の飛行高度となっており、衝突する可能性があるためドローンの飛行が禁止されています。
③人や家屋が密集する地域(DID地区)
「DID地区」とは、人や家屋が密集する人口集中地区のことをいいます。人口が集中している地区でドローンを飛ばすと、ドローンが墜落した場合に、人や家屋に大きな危害を与えるおそれがあるため、DID地区でドローンを飛ばすことはできません。
このように、航空機の航行の邪魔になったり、人・建物に危害を加えるおそれがある区域でドローンを飛ばすことは禁止されています。このような禁止区域でドローンを飛行させたい場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
なお、DID地区にあたるかどうかは、国土地理院「人口集中地区(DID)」で確認することができます。
上は国土地理院が出しているDID地区を示す地図です。赤くなっている地域がDID地区にあたるため、東京都心はほぼ全域がDID地区にあたることになります。
(2)飛行「方法」(飛ばし方)
ドローンを飛ばす際には、飛行場所とは別に飛行方法(飛ばし方)に関する以下の6つのルールを守る必要があります。
- 日中に飛ばすこと(日の出から日没までの間に飛ばすこと)(★)
- 直接目で見てドローンとその周辺を常に監視すること(目視外飛行)(★)
- 第三者と建物などとの間に30m以上の距離を保つこと(★)
- 祭りや展示会など、人の多く集まるイベントの上空で飛ばさないこと(★)
- 爆発物などの危険物を輸送しないこと
- ドローンから物を落とさないこと
今回は、これらの規制のうち、ドローンを使って報道資料を収集する際に主に問題となると考えられる4つの規制((★)部分)について、解説します。
①日中に飛ばすこと(日の出から日没までの間に飛ばすこと)
夜間にドローンを飛ばすと、ドローンの状態を正確に把握することが困難なため、事故の発生確率が高まります。そのため、夜間にドローンを飛行させたい場合には、国土交通大臣の承認が必要になります。
②直接目で見てドローンとその周辺を常に監視すること(目視外飛行)
ドローンを飛行させる際には、直接目で見ながら操縦できる範囲で飛ばさなければなりません。たとえば、災害報道や人が立ち入れない危険区域において、ドローンを飛ばす場合、人の目で直接ドローンを監視できなくなることが想定されます。
このような状況でのドローン飛行は「目視外飛行」にあたるため、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
なお、承認を受けるためには、「機体」・「操縦者」・「安全確保のための体制」といった3つの基準を満たしていることが必要です。
-
【機体】
- 自動操縦システムの装備
- 機体の位置および異常を地上で把握できること
- 自動帰還機能などの危機回避機能の装備
-
【操縦者】
- モニター越しに意図した飛行が可能な能力
-
【安全確保のための体制】
- ドローンの飛行状況や周囲の気象状況の変化を常に監視できる補助者の配置
安全を確保するために配置が求められている補助者は配置しないこともできます。もっとも、補助者を配置しない場合には、山など第三者があまり立ち入らない区域でしかドローンを飛ばすことはできません。その他、不測の事態にドローンを着陸・着水させる場所をあらかじめ決めておくといったことも必要になってきます。
※目視外飛行の承認を受けるための条件について詳しく知りたい方は、「ドローンを用いたソーラーパネル点検の法律規制を弁護士が5分で解説」をご覧ください。
③第三者と建物などとの間に30m以上の距離を保つこと
ドローンを飛行させる際には、人や物件との間に30m以上の距離を保つ必要があります。報道資料を収集する目的でドローンを使う場合には、対象となる資料を撮影などする際に、人または物件に接近する可能性があります。。
ここにいう「人」には、ドローンを飛行させる事業者の関係者は含まれず、また、「物件」とは、中に人がいる可能性のある建物などのことを指します。
このように、ドローンを使って報道資料を収集する場合に、人や物件とドローンの間に30m以上の距離を保つことができない場合には、国土交通大臣の承認を受けなければなりません。
④祭りや展示会など、人の多く集まるイベントの上空で飛ばさないこと
祭りや展示会といった人がたくさん集まるイベントの上空でドローンを飛ばすことはできません。
たとえば、対象となる報道資料を取得するために、人がたくさん集まるイベント会場などの上空でドローンを飛ばす際には、国土交通大臣の承認を受けなければなりません。
以上のように、報道資料を収集するためにドローンを使う場合には、大きく分けてドローンの飛行場所と飛行方法の2点について一定の規制を受けることとなります。。ドローンをどこで飛ばすのか、また、ドローンを飛ばす時間帯はいつなのか、目視外飛行が想定されるかといった点をチェックすることが必要です。
仮に、このような確認を怠った場合、ペナルティを科されるおそれがあります。
3 航空法に違反した場合の罰則(ペナルティ)
航空法上の許可や承認が必要であるにもかかわらず、許可や承認を受けることなく、ドローンを飛ばした場合には、航空法違反となり、
- 50万円以下の罰金
が科される可能性があります。
仮に、報道関係の事業者の社員が航空法に違反する形でドローンを飛ばした場合には、社員だけでなく事業者にも同じように最大50万円の罰金が科される可能性があります。この場合、罰金刑という刑事罰だけでなく、レピュテーション・リスクも発生するおそれがあり、事業者にとっては、大きな損失となってしまいます。
そのため、ドローンを飛ばす場所や飛ばし方をきちんと特定し、必要に応じて、国から許可や承認を受けることが必要です。
4 航空法上の許可・承認申請のやり方
災害や事故などの発生は、事前に予測することができません。そのため、臨機応変にドローンを使って報道資料を収集するためには、場所や時間を問わずいつでもドローンを飛ばすことができるように許可を得ておく必要があります。
以下では、航空法上の許可・承認申請について見ていきたいと思います。
(1)申請の種類
ドローンの飛行申請には大きく分けて以下の2つの種類があります。
- 個別申請
- 包括申請
①個別申請
「個別申請」は、ドローンの飛行申請で最も基本的な申請方法です。あらかじめ飛行の日程とルートが決まっている場合は、個別申請によることになります。
もっとも、震災時などに用いるドローンについて、日時やルートをあらかじめ決めておくことは困難です。そのため、震災時などに報道資料を収集する目的でドローンを飛ばす際には、個別申請はなじまないと考えられます。
②包括申請
「包括申請」は、あらかじめドローンを飛ばす日時・ルートは決まっているものの、状況によっては、日時やルートが変更となることが想定されるような場合に行う申請方法です。
さらに、包括申請は以下のように、飛行する日程に一定の期間を設ける申請と飛行するルートに一定の範囲を設ける申請とに分かれます。
-
(ⅰ)期間包括申請
(ⅱ)飛行経路包括申請
(ⅰ)期間包括申請
ドローンを飛ばす日程が天候に左右されることは少なくありません。そのような場合には、「期間包括申請」により申請を行います。期間包括申請では、「令和元年6月1日から令和2年5月31日」といったように最大1年の期間で許可を申請することが可能です。ドローンを複数回飛ばすことが想定される場合に適した申請方式です。
例えば、事故が頻発に発生する場所を対象として、期間包括申請を行うことが考えられます。
(ⅱ)飛行経路包括申請
飛行場所が複数の場所にまたがっているような場合に、場所ごとに個別申請するのは大変です。このような場合に、複数の場所を一括して申請できるのが、「飛行経路包括申請」です。予定している飛行経路が複数あったり、飛行範囲が決まっている際に使います。報道資料を収集するためにドローンを用いる場合、どこで災害や事故があっても対応できるよう、広範囲にわたる場所を指定して申請することが考えられます。
以上のように、ドローンの許可申請には個別申請と包括申請の2種類が用意されています。申請を行う際には、取材場所やタイムスケジュールなどを確認したうえで適切な申請を行うことが必要です。
なお、包括申請を行った場合、申請者にはドローンの飛行実績を定期的に報告する義務が課されますので、注意が必要です。
(2)申請先
申請書の提出先は、以下の2つに分かれます。
- 空港事務所
- 航空局
①空港事務所
以下の場合には、地域ごとに設置されている空港事務所が申請書の提出先となります。
- 空港周辺の空域における飛行
- 150m以上の空域における飛行
②航空局
以下の場合には、東日本であれば東京航空局、西日本であれば大阪航空局が申請書の提出先となります。
- 人や家屋が密集する地域における飛行
- 夜間の飛行
- 目視外飛行
- 人や建物との間の距離が30m未満の飛行
- イベント会場上空における飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
※空港事務所の連絡先や申請書の提出先について詳しく知りたい方は、国土交通省の「本省運行安全課、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧」をご確認ください。
(3)申請方法
飛行許可申請は、以下の4つの方法で行うことができます。
- 郵送
- 窓口に持参
- オンライン申請
- 電話、電子メールまたはFAX
これらの申請方法のうち、④の電話、電子メールまたはFAXによる申請は、事故や災害などの報道取材を目的とするように緊急性の高い場合にのみ、利用できます。
このように、飛行許可申請には、申請の種類や申請先・申請方法にいくつかの種類があります。そのため、報道資料を収集する目的でドローンを飛ばす際には、ドローンの飛行場所や飛行方法、飛行日程などを明らかにして、適切に飛行許可申請を行うようにしましょう。
※ドローンの飛行許可申請のやり方について、詳しく知りたい方は、「ドローンの飛行許可申請のやり方は?5つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。
5 小括

報道資料の収集や取材を目的としてドローンを活用することは、コストカットだけでなく取材時の安全確保のためにも、大きな意義があります。
もっとも、ドローンを飛ばす際には航空法の規制をきちんと守る必要があります。
事故や災害時において、報道資料を収集する目的でドローンを飛ばす場合は、迅速に情報を取得し、報道することが求められるため、飛行場所や飛行方法はもちろんのこと、許可・承認を受けるための申請手続きについてもきちんと理解しておく必要があります。
6 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
- ドローンジャーナリズムとは、危険区域や災害現場にドローンを飛ばして情報を取得し、その情報を基に報道を行うことである
- 報道のための取材などでドローンを飛ばす際に検討すべき法律は航空法である
- 航空法により、①空港の周辺地域、②150m以上の空域、③DID地区でのドローン飛行は禁止されている
- 報道資料を収集する目的でドローンを飛ばす場合には、航空法上の規制の中でも特に、①夜間飛行、②目視外飛行、③人または物件との距離が30m未満での飛行、④人が多くあつまるイベントの上空での飛行の禁止が問題となる
- 航空法に違反すると、最大50万円の罰金が科される可能性がある
- 航空法上禁止されている場所や方法でドローンを飛ばす場合には、国から許可・承認を受ける必要がある
- 飛行許可申請には、①個別申請と②包括申請がある
- 飛行許可の申請方法には、①郵送、②窓口に持参、③オンライン申請、④電話、電子メールまたはFAXがある
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。