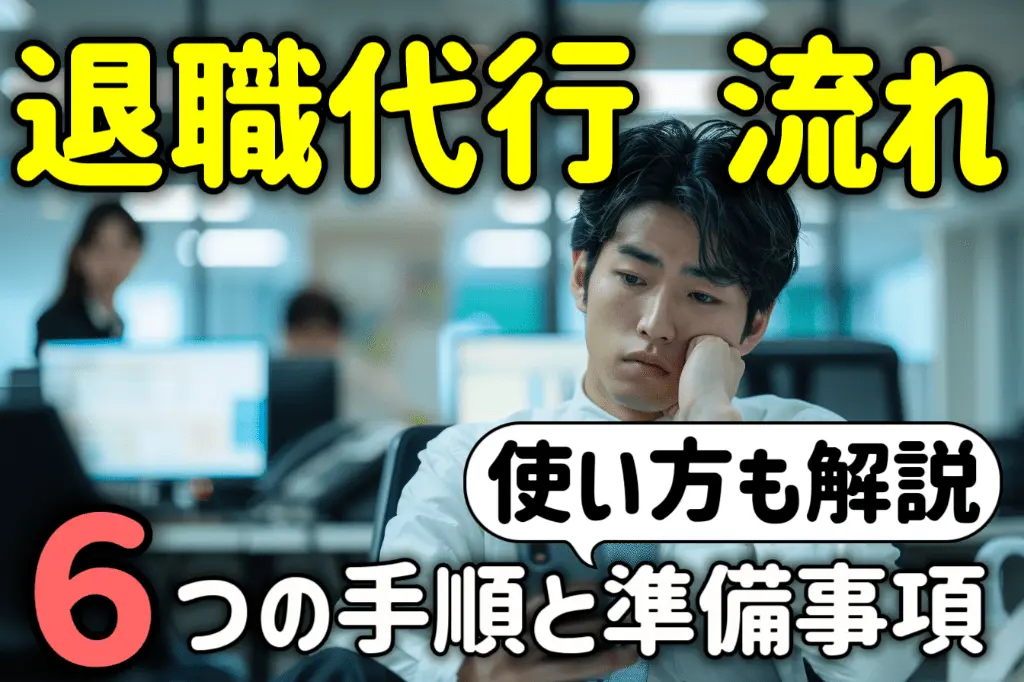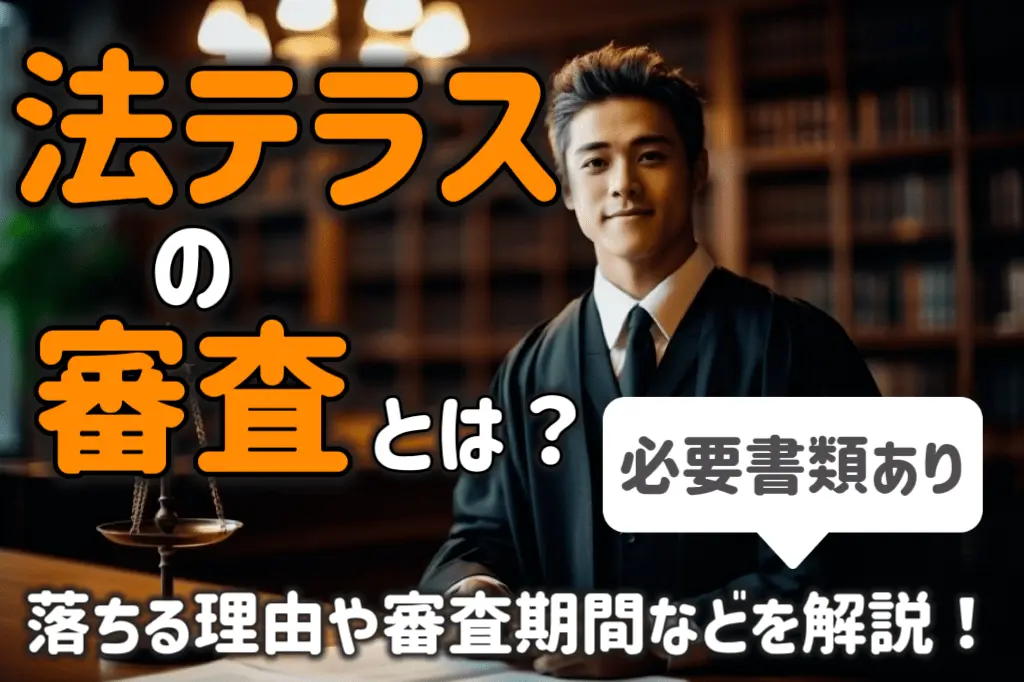電子マネーとは?決済時期別に資金決済法などの関連法律2つを解説!

はじめに
日常生活で利用する「電子マネー」。
利用者の利便性向上やキャッシュレスによるポイント付与など、電子マネーを発行する際のアピールポイントはさまざまです。
日常的に使われている昨今にあっては、電子マネーを扱う事業を展開することが簡単なようにも思えるかもしれません。
しかし、電子マネーには、れっきとした規制が存在し、決済時期に応じて適用される法律も異なります。
この記事では、電子マネーを扱う事業に適用される2つの法律について、注意するべきポイントなどにも触れながら、弁護士が詳しく解説していきます。
1 電子マネーとは

まずは、電子マネーとはどのようなものなのか、改めて確認しましょう。
「電子マネー」とは、現金の代わりに支払いで使用できるデータのことです。
2019年には消費税が10%に引き上げられたことを受けて、「キャッシュレス・消費者還元事業」として、キャッシュレス決済時のポイントバックを上昇させる措置(2019年10月~2020年6月まで)が取られましたが、電子マネーもキャッシュレス決済における選択肢のひとつとして利用されています。
また、電子マネーは決済時期によって以下の2タイプに分かれており、それぞれ適用される法律が異なっているので注意が必要です。
- 前払型
- 後払型
それぞれ、どのような法律が適用されるのか、見ていきましょう。
※なお、この記事では、電子マネーの選択肢が多い「前払型」を中心に解説していきます。
2 「前払型」の電子マネー

「前払型」は、実際の現金をチャージという形で電子マネーに変換したうえで、商品の購入などに利用している方式の電子マネーのことです。
前払型は利用場面などの違いにより、3タイプに分けることができます。
- ICカード型
- プリペイドカード
- 磁気カード型
それぞれ、どのようなものが該当するのか、確認していきましょう。
(1)ICカード型
「ICカード型」は、「ICカード」や「スマートフォン」などの中にチャージデータが記録されているもので、「ICカード」という実物が手元にあるもののことです。
たとえば、
- 交通系電子マネー
- 電子マネー単体
などが該当します。
「交通系電子マネー」とは、SuicaやPASMOなど、主に電車やバスなどの交通機関で利用する電子マネーのことです。
「電子マネー単体」とは、nanacoやWAONなど、店舗での決済時にカードやスマートフォンをかざして利用するものを意味しています。
(2)プリペイドカード
「プリペイドカード」は、コードを入力することでインターネット上で利用できる電子マネーのことです。
たとえば、Amazonギフト券やiTunesギフトカードなどは、プリペイドカードに分類されます。
プリペイドカードの場合、残高は電子マネー発行会社の管理するサーバーに記録されています。
(3)磁気カード型
「磁気カード型」は、QUOカードや図書カードなど、発行された磁気カードを利用するタイプの電子マネーです。
磁気カード型もプリペイドカードと同様、残高は発行会社のサーバーに記録されています。
3 「前払型」電子マネーを規制する「資金決済法」

「前払型」電子マネーは、「資金決済法」で規制されています。
どのような規制なのか、解説していきます。
(1)資金決済法とは
「資金決済法」は、お金の支払いや決済など、お金に関するルールを設けている法律です。
暗号資産(仮想通貨)なども、この法律により規制されています。
資金決済法で規制している項目は以下の4つです。
- 暗号通貨(仮想通貨)
- 前払式支払手段
- 資金移動
- 資金清算
なお、資金決済法は利用者保護をより一層強化することを目的に、法改正が予定されています。
2020年には暗号通貨(仮想通貨)に関する法律の一部が改正されることが決定。前払式支払手段や資金移動などについても、改正に向けた議論が行われており、技術革新や時代の変遷に合わせて、今後も断続的に法改正が行われると想定されます。
そのため、資金決済法に関わる事業を行う場合、常に法改正の動向を追う必要があるので、注意してください。
今回は、以上の4つの中でも、「前払型」電子マネーとの関係で問題となる「前払式支払手段」について解説していきたいと思います。
(2)「前払型」電子マネーは「前払式支払手段」
これまで、実際の現金をチャージして、商品の購入などに利用する方式の電子マネーを「前払型電子マネー」として説明してきましたが、資金決済法では「前払式支払手段」として分類されます。
「前払式支払手段」とは、商品を入手する前に、あらかじめお金を変換しておいたもののことです。
具体的には、以下の条件に当てはまっているものが前払式支払手段となります。
- 金額等の財産的価値が記載・記録されること(価値の保存)
- 対価を得て発行されること(対価発行)
- 代価の支払いなどに使用できること(権利行使)
たとえば交通系電子マネーのSuicaは、利用する前にお金をSuicaにチャージし(条件②)すると、Suicaにその金額が記録され(条件①)、商品等の支払い時にSuicaを端末にかざすことで、支払いを行う(条件③)ことができます。
このような流れで支払いを行う前払型電子マネーは、「前払式支払手段」に分類されるのです。
また、電子マネー以外にも、ゲーム内コイン・ポイントや商品券、カタログギフト券などが前払式支払手段に該当します。
(3)「自家型」と「第三者型」
前払式支払手段は、利用できる範囲によって以下の2つに分類されます。
- 自家型前払式支払手段
- 第三者型前払式支払手段
それぞれ見ていきましょう。
①自家型前払式支払手段とは
「自家型前払式支払手段」とは、発行した事業者が提供するサービス内でのみ利用できる前払式支払手段のことです。
たとえば、発行しているスーパーでしか利用できない磁気カードなどは「自家型」に分類されます。
そのほか、Amazonギフト券やiTunesカードなどの特定の事業者との関係でのみ利用できる電子マネー、発行しているゲーム内でしか利用できないゲーム内コインなどが「自家型」に分類されます。
自家型前払式支払手段を発行する場合、そのために必要な資格などはありません。誰でも簡単に発行することができます。
ただし、毎年3月末か9月末の時点(基準日)で、前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、管轄する財務(支)局長等へ届出を行うことが義務付けられているため、注意が必要です。
未使用残高については、後ほど詳しく解説します。
②第三者型前払式支払手段とは
「第三者型前払式支払手段」とは、発行している事業者以外の者が提供するサービスでも利用できる前払式支払手段のことです。
たとえば、交通系電子マネーのSuicaやPASMOは、電車やバスだけでなく、コンビニやスーパー、飲食店など、提携している他の事業者との関係でも利用することができます。
そのため、SuicaやPASMOは「第三者型」に分類されるのです。
ただし、第三者型の場合、自家型のように気軽に発行することはできません。管轄する財務(支)局長等へ事前に申請し、内閣総理大臣から登録を受ける必要があります。
登録を行うときは、主に以下のような条件が設けられているので、社内体制の構築や各種整備を行うようにしてください。
- 法人であること(海外法人で日本国内に営業所や事務所を有していない場合は法人とはみなされない)
- 原則として1億円以上の純資産額を有すること
- 法令等遵守態勢の整備が行われていること
- 他の第三者型発行者と同一または類似の商号・名称を用いていないこと
このほかにも、「過去、第三者型発行者の登録を取り消された日から3年経過していること」などの条件が設けられています。
4 前払式支払手段発行者に課される義務

前払式支払手段発行者には主に、以下2つの義務が課されます。
- 情報の提供義務
- 発行保証金の供託義務
これらの義務は、「自家型」「前払型」関係なく、「前払式支払手段」を発行している事業者に適用されるので、押さえておきましょう。
(1)情報の提供義務
「情報の提供義務」は、発行している商品券の裏面やHPで公開している利用規約などの、利用者にとってわかりやすい場所に、発行者の氏名などの情報を記載するよう定めた義務です。
利用者が前払式支払手段を使用して何らかのトラブルが発生したときなどに、発行者への問い合わせを容易にするなど、利用者にとって必要とする情報を事業者はわかりやすく提示しなければなりません。
提供することを義務付けられる具体的な情報は、以下の通りです。
- 発行者の氏名、商号または名称
- 支払可能金額等
- 有効期限等がある場合は、その期限等
- 利用者からの苦情相談窓口の所在地および連絡先
- 利用することができる施設または場所の範囲
- 利用上の必要な注意
- 電磁的方法により金額等を記録している場合は、未使用残高またはその確認方法
- 約款等がある場合には、その約款等があること
(2)発行保証金の供託義務
①発行保証金の供託義務とは
「発行保証金の供託義務」とは、毎年3月末か9月末時点で、前払式支払手段の未使用残高が1,000万円以上である場合に、その半額を供託所(法務局など)に供託する義務のことをいいます。
「未使用残高」とは、お金を前払式支払手段に変換後、まだ使われていない前払式支払手段の残高のことです。
たとえば、1000円=ギフトカード1000円分として変換される百貨店ギフトカードの場合、毎年3月末か9月末時点において、まだ利用されていないギフトカードが1000万円分あれば、供託義務が発生することになります。
それでは、何故このような義務が発生するのでしょうか。
この「供託義務」は、お金を前払式支払手段に変換しているにも関わらず、発行者の倒産などにより、利用できる場を失ってしまった利用者への保証を行うためのものです。
そのため、会社が倒産・破産した場合、供託所に預けている発行保証金から利用者に弁済されることになります。
なお、毎年3月末か9月末時点で前払式支払手段の未使用残高が1,000万円以上であると、供託義務が発生するほか、自家型前払式支払手段発行者は、管轄する財務(支)局長等へ届出をすることも必要になってきます。
つまり、基準日に未使用残高が1,000万円以上である場合、
- 自家型・第三者型関係なく、前払式支払手段発行者には「発行保証金の供託義務」が課される
- 自家型前払式支払手段発行者は「管轄する財務(支)局長等への届出」を行う必要がある
という2点が発生するのです。
このように、供託義務をきちんと果たすためには、最低でも500万円を準備しておかなければなりません。スタートアップなどにとっては、極めて厳しい義務だといえます。
それでは、この供託義務を回避する方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
②供託義務を回避する方法
実は、供託義務には、いくつかの適用除外の規定が設けられていますが、特に以下の2つは押さえておきましょう。
- 専ら発行者の従業員に対して発行されるもの
- 利用期間が6ヶ月以内に限定されているもの
例えば、会社内の自販機や食堂でのみ利用できる会社独自の電子マネーを従業員に対して発行するのであれば、供託義務は発生しません。
また、有効期限を6ヶ月以内とするルールを利用規約やチケットなどに記載しておけば、供託義務を回避できることになります。
もしも、有効期限を設けることが難しい場合は、基準日前に、電子マネーの利用を加速させるイベントを開催してみてください。もしかしたら、供託義務が発生する1,000万円のボーダーを下回るかもしれません。
5 「後払型」電子マネーを規制する「割賦販売法」

「後払型電子マネー」とは、事前チャージを必要とせず、クレジットカードのように後から請求が届く電子マネーのことです。
「ポストペイ」とも呼ばれ、具体的にはQUICPayやiD、PiTaPaなどが該当します。
この後払型電子マネーには、前払型とは異なり、割賦販売法という法律が関係してきます。以下で具体的に、見ていきましょう。
(1)割賦販売法とは
「割賦販売法」は、事業者と消費者とのトラブル回避を目的に、後払式の支払手段やその発行者・関係事業者に対して規制を行っている法律です。クレジットカードのように、決済したあとに、後日お金が引き落とされるものに対して適用される法律です。
なお、混同されがちですが、「1回払い」は割賦販売法の適用対象外です。
これは、「1回払い」が「後払い」としての性格よりも、「現金による決済の代替手段」という性格が強いためであり、主に「後払い」について規制する割賦販売法の適用対象からは外されいます。
これらのことから考えると、後払型電子マネーは使用後に代金の請求が来るため(=後払いの性格が強い)、割賦販売法の規制対象となります。
このように、後払型電子マネーを取り扱う事業者は、割賦販売法の規制対象となり、具体的には、「包括信用購入あっせん業者への登録」です。
どのようなものなのか見ていきましょう。
(2)「包括信用購入あっせん業者」としての登録が必要
割賦販売法は、「包括信用購入あっせん」に該当する事業を展開している場合、「包括信用購入あっせん業者」として登録を行うよう求めています。
具体的には、以下のような条件に適合する取引が「包括信用購入あっせん」です。
- クレジットカードや番号・記号を消費者に交付・付与する
- 消費者が、クレジットカードなどを提示・通知することにより加盟店から商品などを購入でき、その際には加盟店に商品代金を交付する仕組みになっている
- 消費者が2ヶ月を超える(3回払い以上)後払い・リボルビング払いで後払手段発行者に代金を支払う
自社が発行する後払型電子マネーが、これら3つの条件にすべてあてはまる場合、後払型電子マネーを用いた取引は「包括信用購入あっせん」にあたり、事業者は包括信用購入あっせん業者として、登録を受ける必要があります。
包括信用購入あっせん業者として登録を受けるためには、「法人であること」や「苦情処理体制を構築すること」などが必要になります。
また、登録を受けた後も、事業者は、安易な利用による多重債務を避けるために消費者の支払能力を調査することや加盟店による不正利用を避けるために加盟店の販売方法などを調査することなどを義務付けられることになります。
6 小括

電子マネーは、決済時期によって適用される法律が異なります。
特に、自社が発行する電子マネーが前払型である場合には、資金決済法上の供託義務などの重い義務が課される可能性もあるため、注意が必要です。
自社が発行する電子マネーの仕組みに応じ、適用される規制をきちんと理解したうえで、適切に対応していくことが大切です。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 「電子マネー」とは、現金の代わりに支払いで利用できる電子データのことである
- 電子マネーは決済時期によって①前払型、②後払型、に分かれており、それぞれ適用される法律が異なっている
- 「前払型」は、事前に電子マネーへチャージを行い、商品購入時に利用する方式の電子マネーである
- 「前払型」は、資金決済法によって規制される「前払式支払手段」に該当する
- 前払式支払手段は、①自家型前払式支払手段、②第三者型前払式支払手段、の2つに分類される
- 「第三者型」を発行するときは、事前に、管轄する財務(支)局長等へ申請し、登録を行う必要がある
- 前払式支払手段発行者には、①情報の提供義務、②発行保証金の供託義務、などの義務が設けられている
- 「後払型」電子マネーを発行する事業者は、割賦販売法上の、包括信用購入あっせん業者として登録を受けなければならない可能性がある
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。