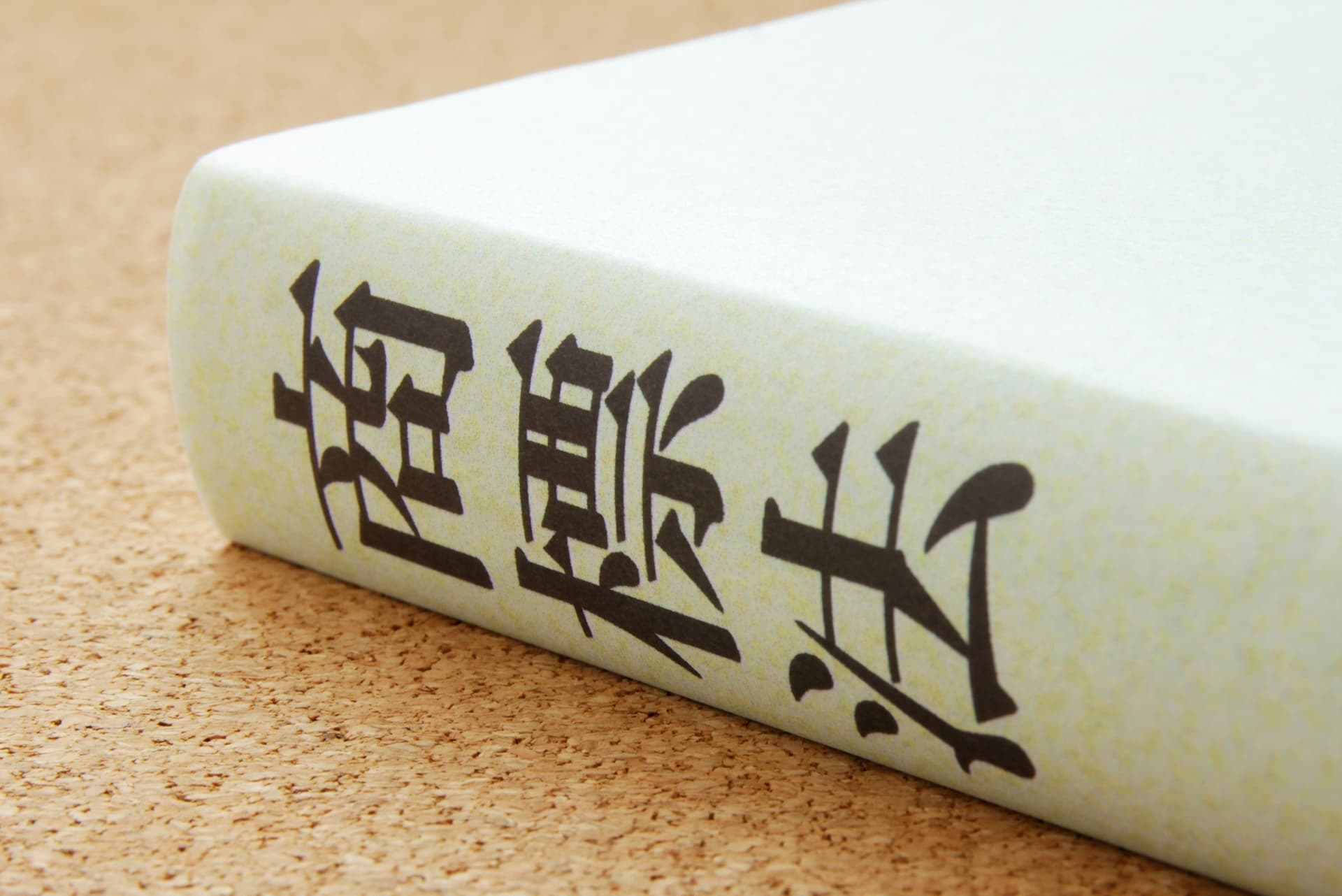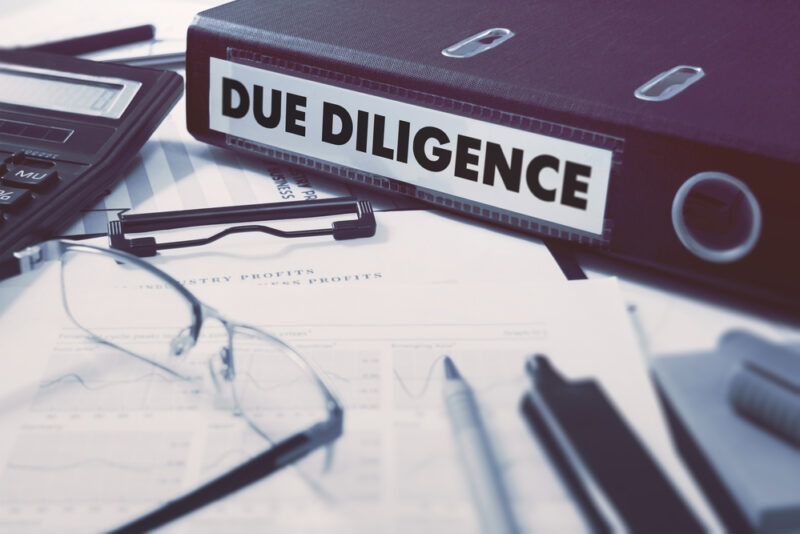優先株式とは?資金調達を目的として発行する際の4つの注意点を解説

はじめに
日本においては、これまで普通株式による資金調達が一般的でしたが、近時、優先株式を発行した資金調達が行われることが多くなっています。
もっとも、そもそも優先株式って何?なんで優先株式が選択されているのか?といった事項がよくわからないスタートアップも少なくないのではないでしょうか。
優先株式には、メリットとデメリットがあるため、しっかり確認しておかなければなりません。
そこで今回は、スタートアップに詳しい弁護士が優先株式についてわかりやすく説明します。
1 優先株式とは
(1)会社法上の株式
「優先株式」が何かについて理解するためには、「普通株式」と「種類株式」について、まずは知る必要があります。
「普通株式」とは、特殊な権利が一切設定されていない株式のことをいいます。
一方で、「種類株式」とは、普通株式と異なる権利内容が設定された株式のことをいいます。
これら普通株式と種類株式は、会社法という法律で定められています。
種類株式については、法律上、設定できる権利内容は限定されており、以下の9つを組み合わせて権利内容が設定されます。
- 優先配当
- 優先残余財産分配
- 議決権の制限
- 譲渡制限
- 取得請求権
- 取得条項
- 全部取得条項
- 拒否権
- 役員選任権
たとえば、①優先配当を③議決権の制限を組み合わせた場合、普通株式を持っている株主に優先して配当を受けられるが、その代わり、議決権はなしとするといった具合で、種類株式の権利内容は設定されます。
(2)優先株式とは
「優先株式」とは、種類株式の一種で、特定の事項に対し、普通株式に対して優先する権利が付与された株式のことをいいます。
たとえば、配当や会社清算時の残余財産については、普通株式に優先して受けることができる一方で、議決権に一定の制限が加えられる株式などが優先株式にあたります。
もっとも、「優先株式」は、普通株式・種類株式と異なり、会社法上の用語ではなく、頻繁に使用されるようになって定着した用語となります。
それでは、スタートアップはなぜ、このように普通株式に対して優先する権利が付与された優先株式を資金調達時に発行するのでしょうか。次の項目では、優先株式が発行される理由を確認していきましょう。
2 優先株式が発行される理由
スタートアップが優先株式を発行する際には、
- 創業株主などの既存株主
- 投資家
- 発行会社(スタートアップ)
といった当事者が関係してきます。
それぞれの当事者が、なぜ優先株式の発行を望むのか確認していきましょう。
(1)創業株主などの既存株主が優先株式の発行を望む理由
「創業株主などの既存株主」とは、資金調達前から株主となっている者のことをいいます。スタートアップでは、会社設立時に創業者(代表取締役あるいは役職員)が株を保有していることが多いといえます。
このような既存株主が優先株式の発行を望む理由は、希釈化(ダイリューション)防止にあります。
「希釈化防止」とは、新規の株主が入ってきても、持ち株比率を保つことで、経営に関する発言権を維持するための条項です。持分比率が高くなれば高くなるほど、会社経営の深い部分に口出しが可能となるため、既存株主は可能な限り自らの持分比率を下げたくないのです。
たとえば、以下の事例を考えてみてください。
- 会社の発行株式数は1000株
- 創業者である代表取締役が1000株を持っている(持分比率は100%)
- 1億円の資金調達をしたい
この事例において、1億円の資金調達をする場合、株価が1株あたり10万円であれば、1000株を新たに発行しなければいけません。投資家が1000株を持つようになれば、代表取締役と投資家の持分比率はそれぞれ50%となってしまいます。
一方で、株価が1株あたり50万円だった場合は、どうでしょうか。この場合、1億円の資金調達をするのに必要な新株発行は、200株で足ります。持分比率は、代表取締役が83%、投資家は17%となります。株価が1株あたり10万円のときと比べて、代表取締役の持ち分比率の減少が少ないことが分かるかと思います。
そのため、既存株主としてみれば、できる限り高い株価にしたいわけです。では、どうすれば株価は高くなるのでしょうか。
企業価値(バリュエーション)が高ければ、高いほど、株価は高くなります。
そして、優先株式の発行は、普通株式に比べバリュエーションが高くなることが一般的です。なぜなら、優先株式には、普通株式と比べ有利になる特別なオプションがついているからです。そのため、既存株主は、バリュエーションを高め、自身の持分比率の希釈化を防止するため、優先株式の発行を望むのです。
(2)投資家が優先株式の発行を望む理由
投資家が優先株式の発行を望む理由は、投資回収における優先権確保にあります。
全てのスタートアップの事業が上手くいくわけではありません。事業が失敗し、会社を清算しなくてはいけなくなってしまうこともあるでしょう。
このように事業に失敗した場合に、投資した資金が一切戻ってこないとなってしまうと、投資家は、リスクが高すぎて、なかなか投資をすることができなくなってしまいます。
そのため、投資家は、会社清算時に優先的に投資した分のお金を回収することができることを内容とする優先株式(優先残余財産分配)の発行を望むのです。
また、近時、スタートアップでは、IPOではなく、M&Aでイグジットに至る場合も増えてきました。このようにM&Aの場合にも、優先株式を用いることで、投資家が売却の対価を優先的に受けられるようにすることが可能になるため、投資家は優先株式の発行を望むのです。
(3)発行会社が優先株式の発行を望む理由
「発行会社」とは、株式を発行する会社のことをいいます。
発行会社が優先株式の発行を望む理由は、ストックオプションの実効性確保にあります。
「ストックオプション」は、インセンティブ目的で従業員へ無償で与えられる新株予約権のことをいいます。新株予約権は、保有者が行使してお金(行使価格)を支払うことで、普通株式を取得することができる権利のことをいいます。従業員は、手に入れた株式を売却することで、利益を得ることができます。
現時点でお金はないが、優秀な人材を集めたいスタートアップがストックオプションを活用しています。
もっとも、実務上、会社は、税務上の優遇措置を受けられる「税制適格」に適合するようにストックオプションを発行しなければ、従業員は重い税金を課せられてしまうので、インセンティブという目的を果たせなくなってしまいます。この税制適格の条件には、様々なものがありますが、その中には、
ストックオプションを与えた時の普通株式の価格≦行使価格
といった条件もあります。
もし、従業員にストックオプションを与えたタイミングで、投資家に優先株式ではなく普通株式を発行している場合、ストックオプションをもらった従業員まで投資家と同額以上の行使価格の支払いが必要になってしまい、インセンティブなど無いに等しくなってしまいます。
逆に投資家に優先株式を発行すれば、普通株式<優先株式という価値のため、普通株式の価格を抑えることができます。結果、優先株式の発行は、新株予約権の行使価格を下げることにつながり、従業員のインセンティブとなるのです。
以上より、発行会社は、ストックオプションのインセンティブ機能の実効性確保のため、優先株式の発行を望むといえます。
このように優先株式の発行に関しては、当事者それぞれに発行したい目的があるのです。それぞれの目的を踏まえて、複数ある優先株式の具体的な内容を確認していきましょう。
3 優先株式の種類
優先株式にはいくつかの種類があります。以下の6つについて、それぞれの具体的内容を説明します。
- 優先配当
- 優先残余財産分配
- 取得請求権
- 取得条項
- 拒否権
- 取締役などの選任権
(1)優先配当
「配当」とは、発行会社が事業を通して得た剰余金を株主に与えることをいいます。
配当は、会社に投資をしてくれた株主に対するリターンとなっており、「優先配当」は、一部の株主がこの配当を優先的に得ることができることをいいます。以降、優先株式を持つ株主を「優先株主」、普通株式を持つ株主を「普通株主」といいます。
たとえば、配当する際に、優先株式を持つ株主と普通株主がいた場合、次のような優先配当を設定することができます。
【優先配当】
- まずは、優先株主に1株あたり●●円を配当する
↓ - 優先株主への配当後さらに残額があれば、その残額を優先株主と普通株主に平等に配当する(いわゆる参加型の優先配当)
この例では、配当において優先株式を持つ株主が優遇されていることがわかりますよね。
もっとも、スタートアップが配当をできるような財源を確保することが難しく、そもそも配当自体が行われないことが一般的です。
そのため、スタートアップの資金調達において、必ずこの優先配当が定められているわけではありません。
もし、代表取締役などが企業価値(バリュエーション)を高めて、持分比率の希釈化を防止したいのであれば、優先配当について定めるのはありです。
※参加型・非参加型、累積型・非累積型の優先配当について詳しく知りたい方は、「9つの種類株式すべてを網羅!定款への記載例を弁護士がくわしく解説」をご覧ください。
(2)優先残余財産分配
「残余財産分配の優先権」とは、会社を解散したり、清算したりした時に会社に残ったお金を、優先株主が普通株主よりも先に分配を受けられる権利のことをいいます。
たとえば、会社清算時には、次のように優先的に残余財産分配することを優先株式に設定することができます。
【残余財産分配の優先権】
- 残余財産の分配をする際には、まずは、優先株主に●●円を分配する
↓ - 優先株主への分配後さらに残額があれば、その残額を優先株主と普通株主に平等に分配する(いわゆる参加型の優先残余財産分配)
もっとも、資金調達後、事業を途中で断念した場合には別として、基本的に、会社の解散・清算のあとに投資した資金全てを回収することは難しいといえます。
むしろ、優先残余財産分配は、「みなし清算」に関して定めるためにあるといっても過言ではありません。
この「みなし清算」はM&Aで会社が売却されて対価が支払われた場面で機能します。
「みなし清算」とは、M&Aで会社が売却される際に、あたかも会社が清算されたかのように捉えて、残余財産分配の定めを基に投資家を含めた株主に対価を分配することをいいます。
このように、残余財産分配とみなし清算について定めることで、M&A時の対価分配についてスムーズに行うことができるようになります。
※参加型・非参加型の優先残余財産分配について詳しく知りたい方は、「9つの種類株式すべてを網羅!定款への記載例を弁護士がくわしく解説」をご覧ください。
(3)取得請求権(プットオプション)
「取得請求権」とは、保有する株式について、株主が会社に対して買い取ることを求めることができる権利のことを意味します。会社は、取得した株式の対価を基本的に自由に設定できます。そのため、会社は現金のほか、社債や新株予約権、新株予約権付社債などを対価とすることもできますし、優先株式の取得に対して普通株式を対価とすることもできます。
有利な優先株式を普通株式にする株主なんているのかと思われる方もいるかもしれませんが、日本では優先株式を発行したまま会社が上場することは難しくなっています。そのため、実務では、この取得請求権がIPO前に優先株式から普通株式への変更のために利用されています。このように優先株式を普通株式に変更することを転換と呼びます。
(4)取得条項(コールオプション)
「取得条項」とは、一定の事由が生じたことを条件に、会社が株主から株式を取得することができる権利のことをいいます。
一定の事由としては、上場申請を行うことを取締役会で決議したことや、上場に向けて証券会社から要請を受けた場合を条件とすることが多いです。
なぜなら、優先株式をもつ全ての株主が取得請求をしてくれれば問題はないのですが、普通株式への転換に協力してくれない株主がいるとIPOがスムーズにできなくなることがあるからです。そのため、IPOが邪魔をされないような取得条項の条件を設定することが多いです。
(5)拒否権
「拒否権」とは、株主総会や取締役会で決議される重要事項について、種類株式に関連する種類株主総会の決議を必要とするよう定めることができる権利です。これを定めると、仮に取締役会でM&Aが承認されたとしても、種類株主総会で承認されなかった場合には、M&Aが実施できなくなります。
この種類株主総会の決議が必要な事項は自由に設定できますが、会社にとっては株主との調整が増えて負担となるばかりか、会社運営に支障が生じかねません。
そのため、日本では、そもそも優先株式に拒否権を設定しない、あるいは、設定したとしても、次の項目で説明する選任権に基づいて選任された取締役が賛成した事項については種類株主総会は不要と、抜け道を用意することが多いです。
(6)取締役などの選任権(役員選任権)
取締役などの役員は、株主総会の決議によって選任されることが原則です。
もっとも、例外的に種類株主総会で役員などを選任することが認められています。この種類株主総会に参加し、役員を選任できる株主の権利のことを役員選任権と呼びます。
この役員選任権は、投資家などが事業をモニタリングし会社のガバナンスを効かせるために認められてはいますが、実務上、優先株式に設定されることはけして多くはありません。
なぜなら、一度優先株式に役員選任権を設定してしまうと、役員選任は必ず種類株主総会で行わなければならなくなり、手続的負担が重くなるからです。また、役員選任権を廃止する際にも、優先株式の内容の変更が必要となり、これもまた手間となります。
そのため、実務上では、優先株式ではなく、株主間契約などで投資家が役員を指定するという方法を選択されることが多くなっています。
このように優先株式には様々な種類があります。
4 優先株式を設計する際の留意点
実際に優先株式を設計する際には、特に以下の点に留意しなければいけません。
- 議決権の範囲
- 次回以降の資金調達
- 優先株式の株価設定
(1)議決権の範囲
優先株式においては、議決権の範囲をどうするかがポイントになります。
議決権の範囲の決定は、いわば、経営へ積極的に介入することを望む投資家などの株主の思惑と、経営への介入を避けるとともに、スピーディに経営判断を行いたい経営者の思いを調整することだといえます。
繰り返しとなりますが、優先株式のような種類株式を発行すると、一般的な株主総会に加えて種類株主総会を開催する必要が生じます。この種類株主総会における決議事項を、なんでもかんでも認めてしまうと、意思決定に時間がかかるようになり、スピーディな経営判断ができなくなるおそれがあります。一方で、経営へ積極的に介入することを望む株主は、可能な限り、決議事項の範囲を広げることを望むでしょう。
そのため、株主と経営者が互いに譲れないラインがどこかを話し合い調整する必要があります。
(2)次回以降の資金調達
スタートアップによる優先株式を用いた資金調達は徐々に増えてきていると言われています。
もっとも、一度、優先株式を発行し資金調達を行うと、その後に実施する資金調達において、優先株式に劣る普通株式で投資を受けることが難しくなります。
なぜなら、投資家視点では、優先的に回収が可能な優先株主がいる状態で、それに劣る普通株主になることは、相対的に回収リスクが高いだけで、投資の対象として魅力的に見えないことが多いからです。
そのため、優先株式をもちいた資金調達を一度でも行った場合は、シード⇒シリーズAラウンド⇒シリーズBラウンドといったようにラウンドアップする際の資金調達でも優先株式を発行し、前回のラウンドと同じか、より有利な内容で優先株式を発行することになります。もし、この点を考えずに優先株式を発行してしまうと、最悪の場合、投資家が投資してくれるような優先株式を発行することができず、資金調達ができないという事態になりかねません。
こうならないためにも、イグジットを念頭に、資本政策において、この先どのように資金調達を行うかを慎重に検討しておく必要があります。
では、実際、優先株式を発行して資金調達をする場合には、どのような株価設定をすべきなのでしょうか。
(3)優先株式の株価設定
優先株式を発行して資金調達をする際には、優先株式の株価をいくらに設定すればいいのか、という問題とぶつかります。基本的に優先株式は、オプションがついている上、一般の市場で取引されないため、価格の設定が難しくなる傾向があります。
そのため、株価をはじき出す際には格子モデルなどの評価モデルを用いることが一般的となっています。
もっとも、評価モデルを用いたとしても一般の市場で取引されない優先株式を適切に評価できていないことも多々あります。
以上から、評価モデルを用いて算出した価格などにつき、投資家などと十分協議する必要があります。
5 小括
投資家から資金調達をすることは、事業を野心的かつ弾力的に動かすためです。
この際、価値が高い優先株式を発行すれば、資金調達はやりやすくなります。
もっとも、先々を考えていない、短絡的な優先株式の発行は、結果として、資金のやりくりや経営上の足かせとなってしまうことにもなりかねません。
資本政策において、きちんと検討することが重要になります。
6 まとめ
これまでの解説をまとめると以下のようになります。
- 「優先株式」とは、特別なオプションが付与され、特定の事項について普通株式に優先される株式のことをいう
- 優先株式は、①希釈化防止、②投資回収における優先権確保、③ストックオプションの実行性確保を目的としている
- 優先株式には、①優先配当、②優先残余財産分配、③取得請求権、④取得条項、⑤拒否権、⑥取締役などの選任権などがある
- 「優先配当」とは、一部の株主が発行会社が事業を通して得た剰余金を優先的に得ることができることをいう
- 「残余財産分配の優先権」とは、会社を解散したり、清算したりした時に会社に残ったお金を、優先株主が普通株主よりも先に分配を受けられる権利のことをいう
- 「みなし清算」とは、M&Aで会社が売却されるなどの際に、あたかも会社が清算されたかのように捉えて、残余財産分配の定めを基に投資家を含めた株主に対価を分配することをいう
- 「取得請求権」とは、保有する株式について、株主が会社に対して買い取ることを求めることができる権利のことをいう
- 「取得条項」とは、一定の事由が生じたことを条件に、会社が株主から株式を取得することができる権利のことをいう
- 「拒否権」とは、株主総会や取締役会で決議される重要事項について、種類株式に関連する種類株主総会の決議を必要とするよう定めることができる権利をいう
- 「役員選任権」とは、種類株主総会に参加し、役員を選任できる権利のことをいう
- 優先株式の設計では、①議決権の制限範囲、②次回以降の資金調達、③優先株式の株価設定に留意しなければいけない
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。