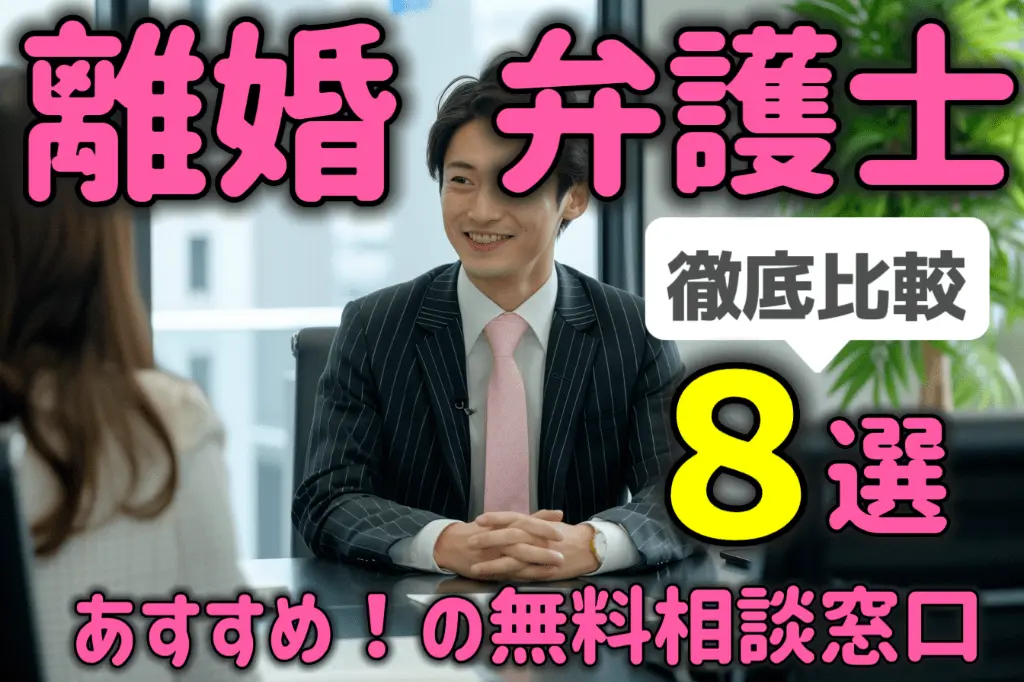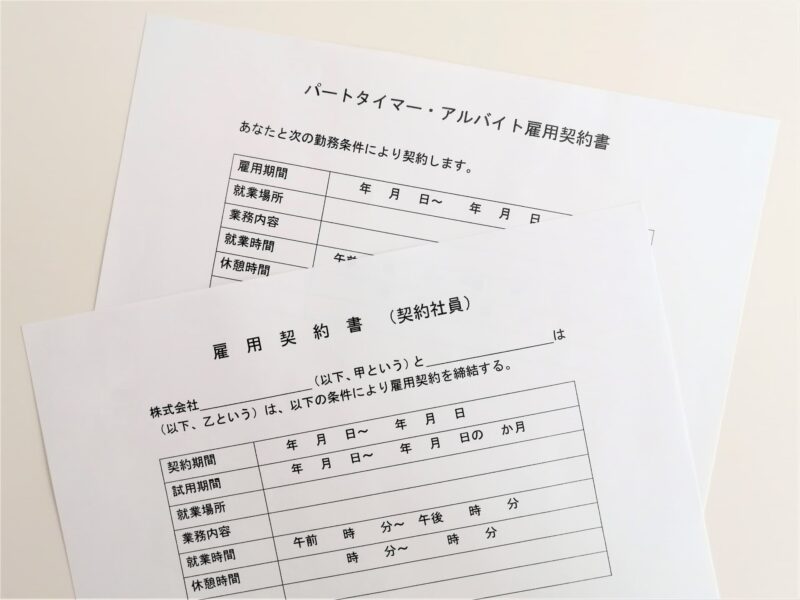労働審判とは?手続きの流れと事業者に求められる3つの対応を解説!

はじめに
労働審判は、従業員との間で起きた残業代の未払い問題や不当解雇に関する問題などを解決するための制度です。
同審判では、迅速に解決を図るという観点から、初回期日で解決案の大まかな内容が決まることが一般的です。
そのため、従業員から労働審判を申し立てられた場合、事業者は迅速に適切な対応をする必要があります。
「うちには関係ない」「従業員から責められるようなことは何一つしていない」などと思っている事業者もいらっしゃると思います。
ですが、万一に備えて、労働審判制度の概要を理解しておくことは有益なことです。
今回は、労働審判制度の手続きの流れを中心に解説します。
1 労働審判とは
「労働審判」とは、裁判所を通す手続きで、事業者と労働者との間に起きた労働問題を解決するための制度です。
開かれる期日は、原則3回以内となっており、この間に事業者と労働者からそれぞれの言い分を聞いて、和解を目指します。
労働審判には、主に以下の3つの特徴があります。
- 早期解決
- 柔軟性をもった解決
- 簡易な手続き
「裁判所の手続き」と聞くと、時間が膨大にかかるイメージが強いかもしれません。
ですが、労働問題は、その性質上、早期に解決する必要性が高いといえます。
そのため、労働審判では、申立後およそ2か月半程度で事件が終結することが多いです。
また、申立てられた事例については、その8割以上が和解的解決により終結しています。
和解的解決は、紛争当事者の双方において、ある程度の納得感がなければ実現しません。
その意味で、労働審判は、和解に向けられた柔軟性のある手続きであるといえます。
さらに、通常裁判のように、数多くの書面・証拠などを提出する必要はなく、事業者は原則として答弁書のみを提出することで足ります。
2 労働審判の手続きの流れ
労働審判は通常、以下のような流れで手続きが進められます。
- 労働審判が申立てられる
- 事業者が答弁書等を提出する
- 第1回期日
- 第2回~3回期日
↓
↓
↓
(1)労働審判が申立てられる
通常、労働審判の手続きは、労働問題を抱える労働者が裁判所に申立書を提出することにより開始されます。
その後、裁判所は事業者に対して申立書を郵送し、第1回目の期日を指定します。
第1回期日は、申立書が事業者に郵送されてから約1ヶ月後に開かれることが一般的です。
(2)事業者が答弁書等を提出する
事業者は、第1回期日の1週間程度前までに、答弁書や反論の証拠などを提出する必要があります。
(3)第1回期日
期日は、裁判官1名と労働審判員2名で行われます。
ここでいう「労働審判員」は、労働問題に精通する民間人から裁判所が任命することになっています。
期日には、当事者双方をはじめ、それぞれの代理人弁護士が出席することが一般的です。
裁判官や労働審判員が、労働者本人や会社の代表者・管理者などに質問するなどして審理が進められます。
初回だからといって、甘く見ていると、不利な結果を招くおそれがあるため注意が必要です。
先に見たように、労働審判では、第1回期日で解決案の大まかな内容が決まるため、それまでに十分な準備をしておくことが非常に重要になってきます。
(4)第2回~3回期日
第2回~3回期日では、裁判所から調停案が提示されます。
調停案に記載されている内容で合意できるかについて、事業者は検討する必要があります。
裁判所から提示された調停案に納得ができず合意に至らなかった場合、「労働審判」に進むことになります。
この場合、裁判所は「労働審判」という形で当事者双方に解決案を提示します。
裁判所から解決案が提示された翌日から2週間以内に、当事者双方から異議が申し立てられなかった場合、その解決案は確定します。
他方で、この期間中に異議が申し立てられた場合、裁判所から提示された解決案は失効し、通常訴訟に移行することになります。
3 労働審判に対する事業者の対応
労働者から労働審判を申し立てられた場合、事業者は以下の点に注意しながら対応する必要があります。
- 管轄の裁判所
- 指定された第1回目の期日
- 答弁書の提出期限
(1)管轄の裁判所
労働審判の管轄について、労働審判法は以下のように定めています。
-
【労働審判法2条1項】
労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。)は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とする
仮に、労働者が既に退職している場合、その労働者は、最後に就業していた事業所を管轄する地方裁判所に労働審判を申し立てることが可能です。
そのため、事業者において多くの営業所などをもっている場合は、管轄に注意する必要があります。
(2)指定された第1回目の期日
裁判所から送られてくる郵便物には、申立書のほか、第1回目の期日が記載された期日呼出状も同封されています。
期日には、会社に所属する管理者や代表者などが出席する必要があるため、指定された期日を押さえておくことが必要です。
(3)答弁書の提出期限
裁判所から送られてくる郵便物には、答弁書催告書という書面も同封されており、同書面に答弁書の提出期限が記載されています。
答弁書は、ここに記載されている提出期限までに提出する必要があるため、確認しておく必要があります。
繰り返しになりますが、労働審判では第1回期日において大まかな解決案の内容が決まります。
そのため、事業者側の主張を認めてもらうためには、充実した答弁書を作成・提出する必要があることに注意しなければなりません。
4 まとめ
労働審判の利用数は、毎年数千件に上ると言われています。
今回見てきたように、労働審判は、迅速に解決を図るという観点から、手続きは比較的短期間で終結します。
労働審判を申立てられた場合は、スピード感をもって対応する必要があるということを覚えておきましょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。