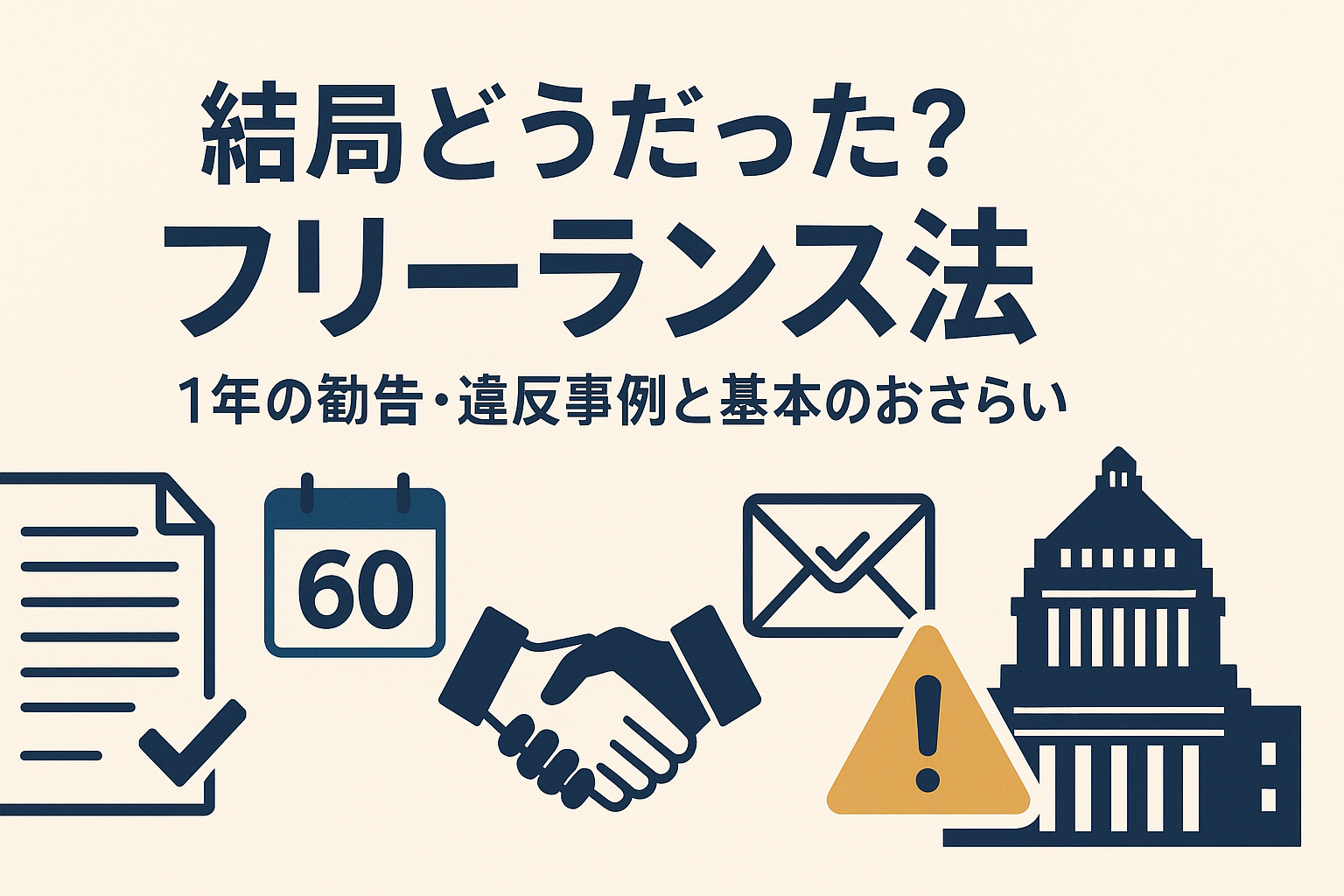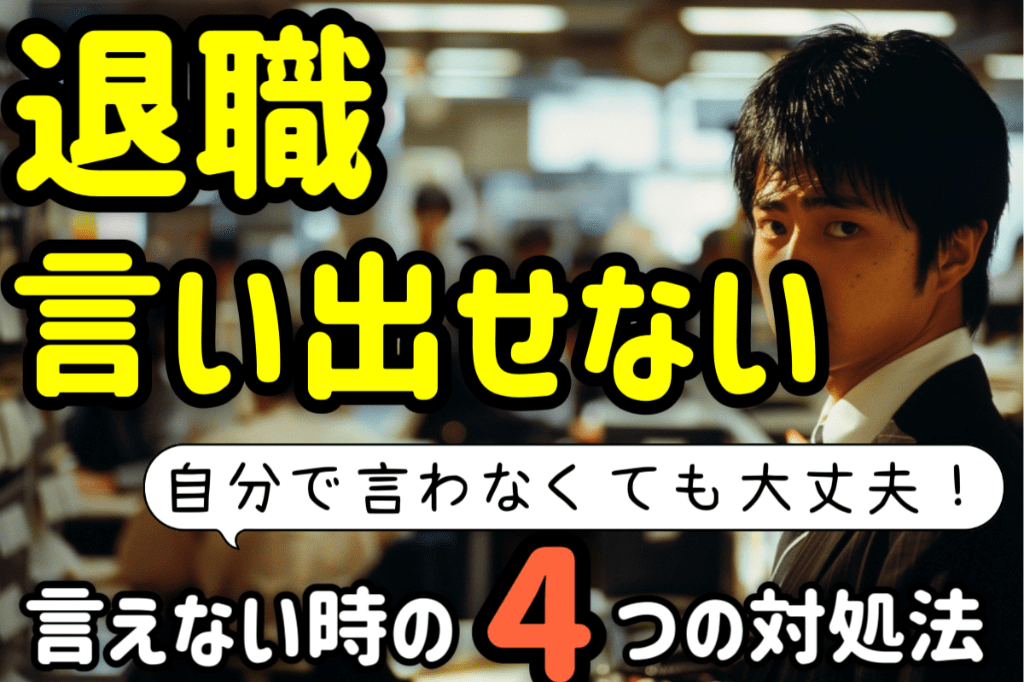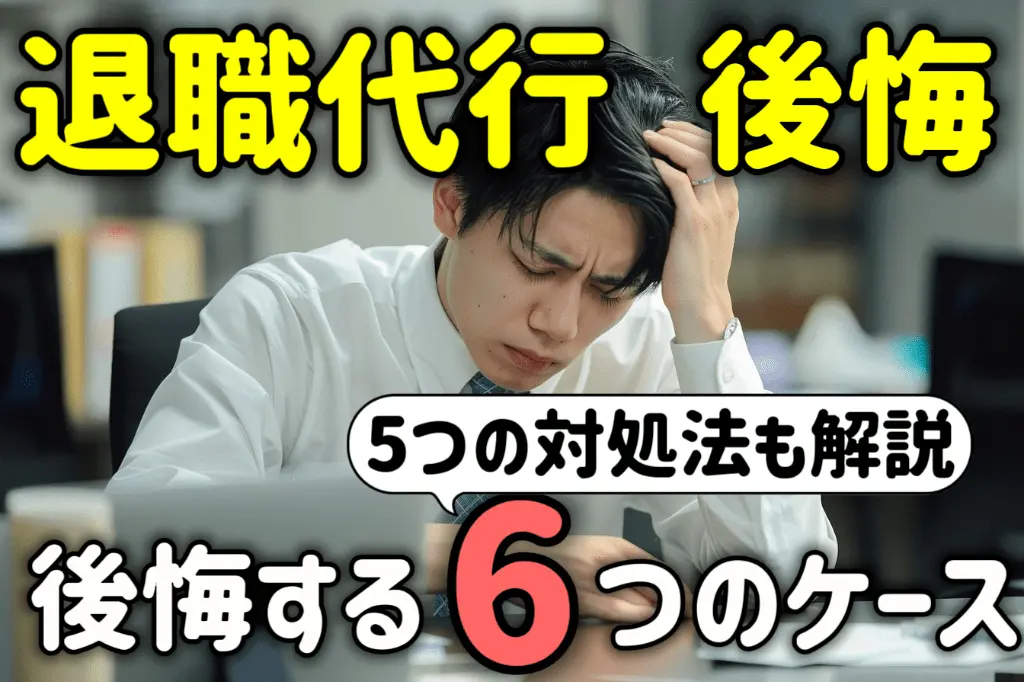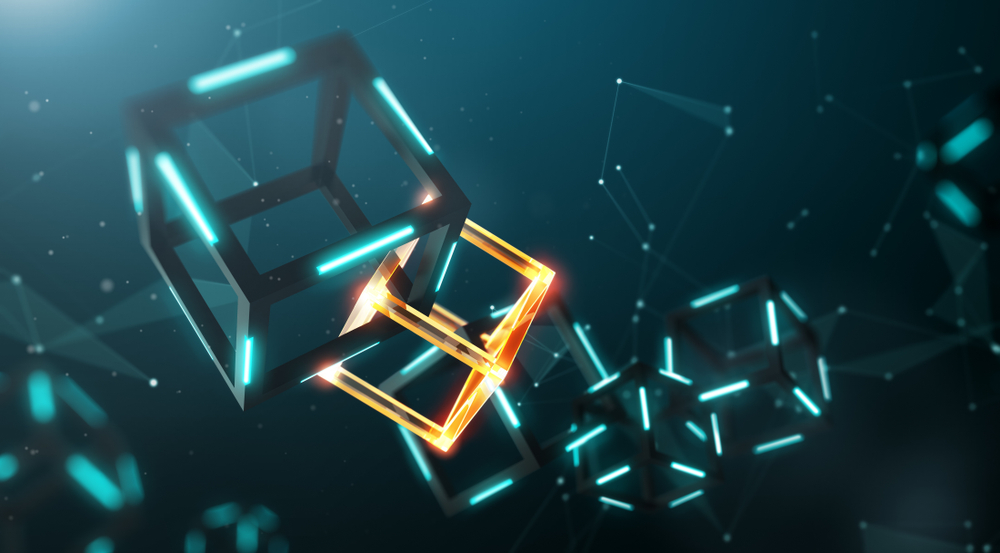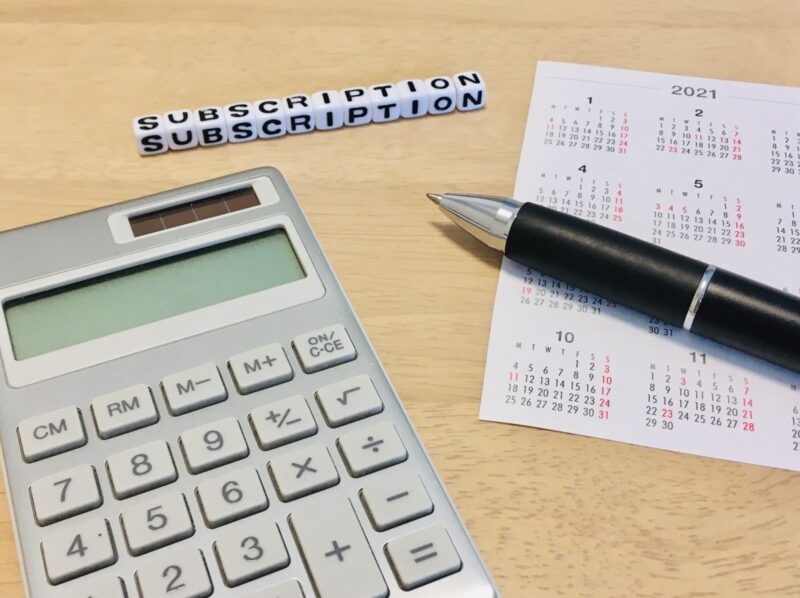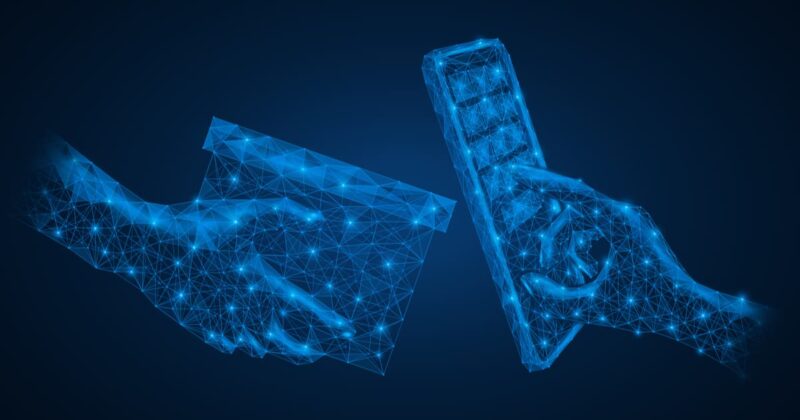求職マッチングサービスに対する2つの法規制をわかりやすく解説!

はじめに
マッチングサービスには、出会い系をはじめ、就活や転職サイト、家事代行サービスなどのように実にさまざまな種類があります。
現在では、プラットフォームを用いてサービス提供されることが一般的になっていますが、マッチング型プラットフォームを横断的に規制する法規制は今のところ存在しません。
そのため、マッチングサービスを始める場合には、サービス内容に応じて法規制の有無を検討することが必要になってきます。
今回は、マッチングサービスの中でも就活サイトや転職サイトに代表される、求人者と求職者を繋ぐマッチングサービスにフォーカスして、その法規制などを中心に見ていきたいと思います。
1 注意すべき法規制

就活サイトや転職サイトは、求職者や転職希望者にとって貴重なツールとなっており、利用者は多数に上ります。
このようなサービスを提供する事業者は、求人者の依頼に基づいて、就職・転職活動に必要不可欠な情報を掲載するばかりでなく、求職者の個人情報をも取り扱うことになります。
そのため、主に以下の2つの法律に注意する必要があります。
- 職業安定法
- 個人情報保護法
2 職業安定法による規制
(1)募集情報等提供事業者
まずは、以下の規定をご覧ください。
-
- 【職業安定法4条6項】
- この法律において「募集情報等提供」とは、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。以下この項、第五条の三第一項及び第五条の四第一項において同じ。)の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供することをいう
この規定からもわかるように、労働者の募集を行う者(求人者)の依頼を受けて、募集に関する情報を求職者に提供することは「募集情報等提供」にあたります。
そのため、事業者は募集情報等提供事業者として職業安定法の規制対象となり、厚労省が公表している「募集情報等提供事業の業務運営要領」などを遵守する必要があります。
(2)「職業紹介」の該当性
「職業紹介」とは、求人者と求職者の申込を受けて、両者における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。
-
- 【職業安定法4条1項】
- この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう
就活サイトや転職サイトの中には、求職者向けに募集情報を掲載するだけでなく、求職者の希望に合った募集情報が検索結果の上位に表示されるような仕組みをとっているものもあります。
このような仕組みになっている場合、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんしていると見ることもできるため、職業紹介にあたる可能性があります。
職業紹介にあたる場合、事業者は職業紹介事業者として以下のような義務を課されることになります。
- 許可の取得
- 帳簿の備付け
- 事業報告書の作成・提出
これらに違反した場合には、罰則を科される可能性もあり、たとえば、無許可で有料職業紹介事業を行った場合、
- 最大1年の懲役
- 最大100万円の罰金
のいずれかを科される可能性があります。
もっとも、サービスの仕組みによっては、職業紹介の該当性を判断することが難しいケースもあります。
この点、厚労省は一定の基準を公表しており、インターネットを使った求人情報などの提供について、以下のいずれかにあてはまる場合には、「職業紹介」にあたるとしています。
- 事業者の独断で求人情報などを選別・加工すること
- 事業者から求人者や求職者に対し求人情報・求職者情報に係る連絡を行うこと
- 事業者のホームページを介してなされる求職者と求人者の意思疎通のための通信内容に加工を行うこと
このように、事業者があらかじめ求人者より設定されている条件によらずに、独断で求人情報・求職者情報の内容や同情報の提供相手を選別したり加工したりすることは「職業紹介」にあたるため、注意が必要です。
3 個人情報保護法による規制

就活サイトや転職サイトを運営する事業者は、求職者に係る個人情報を取り扱うことになります。
そして、多数に上る求職者の個人情報は、すぐに検索できるように体系的に構成されていることが一般的であると考えられるため、事業者は「個人情報取扱事業者」にあたることになります。
(1)個人情報取扱事業者に課される義務
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うという業務の性質上、さまざまな義務を課されることになります。
たとえば、以下のような義務が挙げられます。
- 利用目的の通知・公表
- 第三者提供の制限
- 安全管理措置義務
- プライバシーポリシー等の公表
このほかにも、苦情の処理に関する措置や個人情報の漏えい等について本人への通知を義務付けるなど、事業者に課される義務は多岐にわたります。
また、個人情報保護法については、さまざまな状況を勘案したうえで、3年ごとに見直しが行われることになっています。
そのため、今後も事業者に課される義務が新設される可能性もあり、動向に注意しておく必要があります。
(2)募集情報等提供事業者が注意すべきポイント
厚労省は、募集情報等提供事業者が個人情報を取り扱う際に注意すべきポイントを業務運営要領などにまとめています。
特に、以下の点には細心の注意を払うべきでしょう。
- 個人情報の収集や使用などが、業務の目的を達成するために必要とされる範囲内であること
- 個人情報を収集する場合には、本人から直接収集するか、本人以外の者から収集する場合には本人の同意があること
- 求職者の秘密にあたる情報を知り得た場合、他人に漏えいしないように厳重に管理すること
就職活動や転職活動は、求職者にとっては大変センシティブな状況にあるということがいえます。
そのような状況下で個人情報を取り扱うこととなる事業者は、個人情報保護法を遵守することはもちろんのこと、求職者の意思に反するような情報利用にならないよう、より一層の配慮が求められるといえます。
4 まとめ
今回は、マッチングサービスの中でも、求人者と求職者を繋ぐサービスにフォーカスして、法規制などを中心に見てきました。
「マッチングサービス」全般を横断的に規制する法規制は存在しないため、サービス内容によって検討すべき法規制も異なってきます。
もっとも、個人情報保護法は、マッチングサービスの多くに適用されうる法規制であるため、どのような義務を課されることになるのか、義務を履行できるだけの体制が整備されているかなど、しっかりとした対策を行うことが求められます。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。