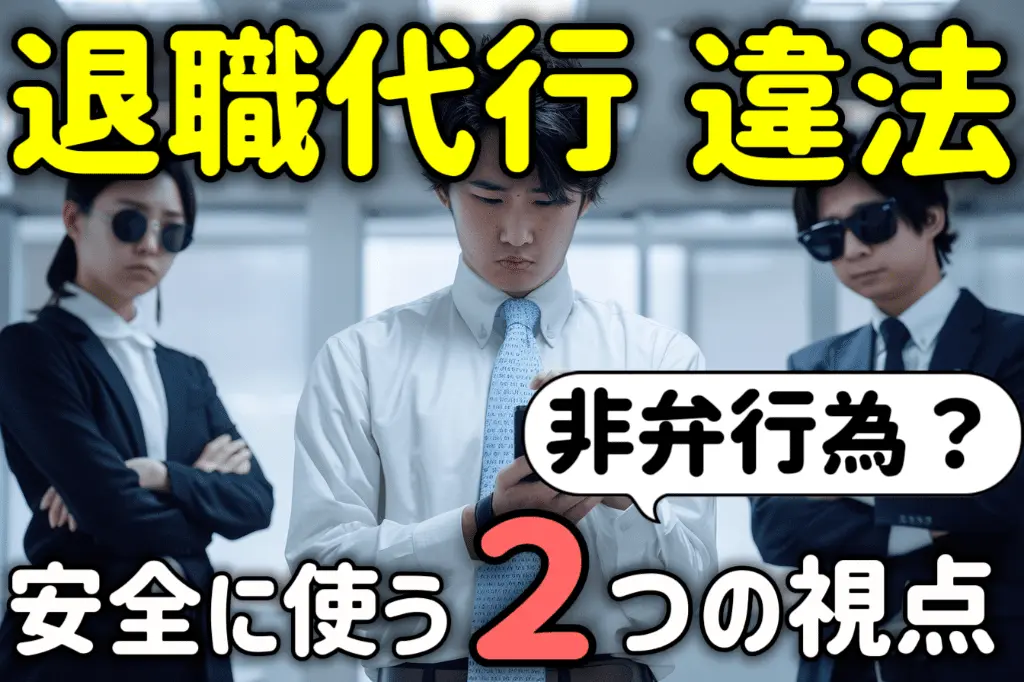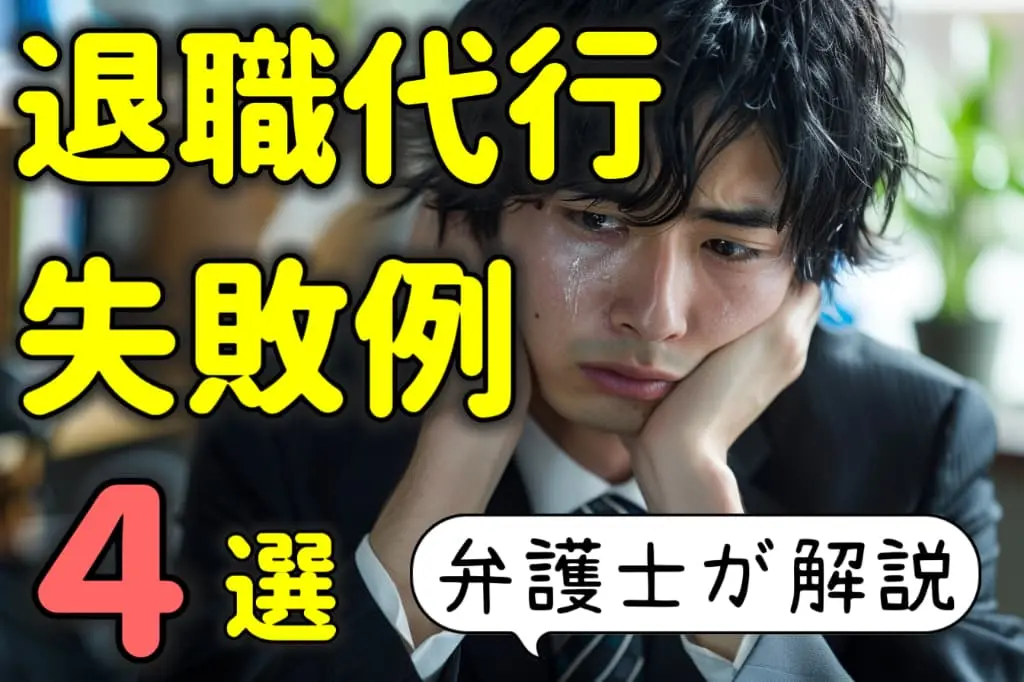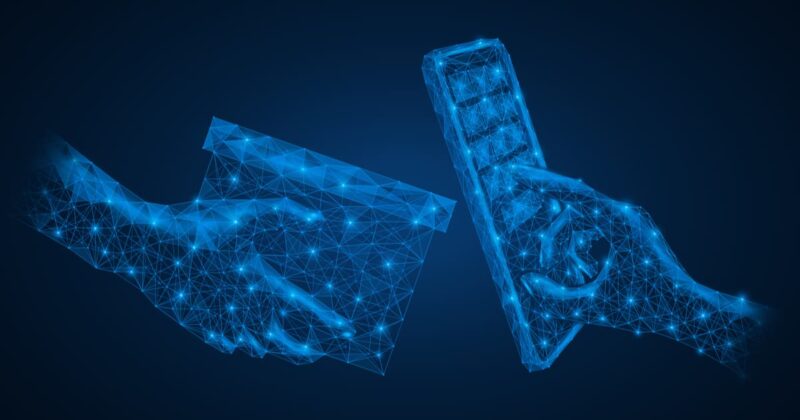スタートアップが知っておくべき契約の基礎知識3点を弁護士が解説!
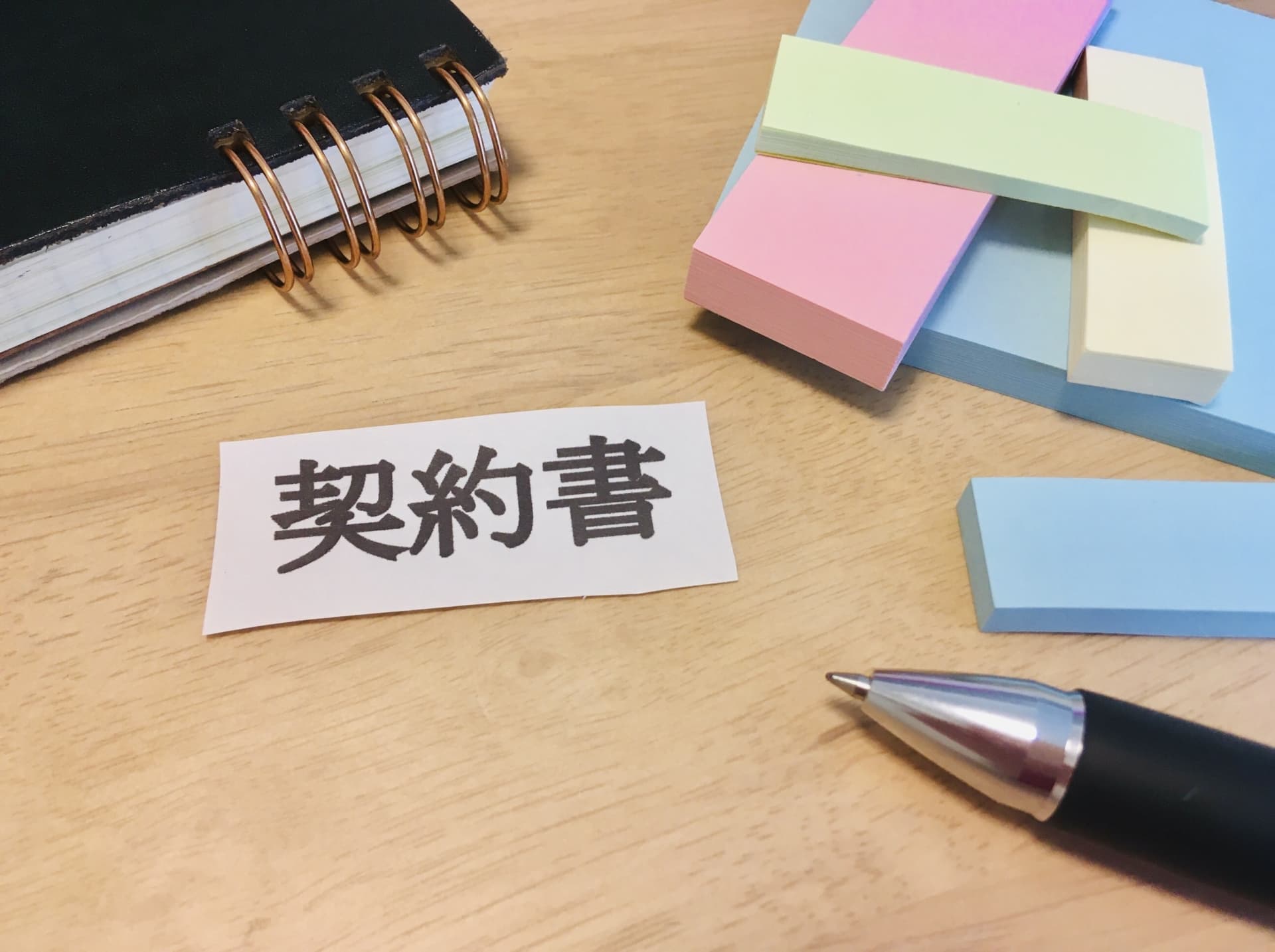
はじめに
起業する際には、オフィスに関する賃貸借契約、オフィス機器に関する売買契約・リース契約、従業員に関する雇用契約など、さまざまな「契約」を締結することになります。
もっとも、相手方と取り交わす契約書には多くの条項が設けられ、慣れない法律用語が羅列されていることが少なくありません。
特に、スタートアップなどでは、法務担当者がいないことも多く、意味がよく分からないままにサインをしてしまうということも少なからずあるようです。
「契約」はビジネスの根幹でもあるため、事業者においては、契約に関する基礎知識をきちんと習得しておくことが必要です。
そこで今回は、スタートアップが知っておくべき契約の基礎知識を弁護士がわかりやすく解説します。
1 契約書を作成する意義
契約を締結する際には、契約書を作成することが一般的ですが、その理由をご存知でしょうか。
まずは、その点を簡単に確認しておきましょう。
- 紛争の予防と早期解決
- リスク負担の配分
- 証拠としての役割
(1)紛争の予防と早期解決
契約書には、契約当事者に発生する権利義務、発生した権利義務の消滅事由など、さまざまな事項が細かく定められます。
加えて、想定されるリスクについて、その解決方法なども定められます。
契約書において、契約当事者の法律関係を明確にすることにより、契約書に従った取引が円滑に行われ、紛争が生じる可能性が低くなります。
また、仮に紛争が生じたとしても、契約書で定める方法に従って、早期解決を図ることができます。
(2)リスク負担の配分
契約書では、想定されるリスクが現実化した場合に、そのリスクを誰が負担し、どのような内容・方法で負担するかを定めることが一般的です。
契約書を交わしていないと、リスクが現実化した場合に、契約当事者間でリスクの負担をなすりつけ合うということが生じ、トラブルに発展する可能性があります。
契約書を作成しておくことで、あらかじめリスク負担の配分を決めることができ、実際にリスクが現実化した場合でも契約書の定めに従って対応することが可能になります。
(3)証拠としての役割
契約当事者間において生じたトラブルが裁判にまで発展するケースがあります。
裁判になれば、証拠の有無が大きく結果を左右します。
その点、契約当事者の署名・押印がある契約書は、契約締結の有無、契約内容などを証明するための証拠となります。
ですが、契約書を作成していない場合、相手方が契約の成立について争えば、まずは契約が有効に成立したというところから証明する必要があり、証明の難易度も高くなります。
このように、契約書は、裁判上の証拠としても重要な役割を担うことができるのです。
2 契約書を作成する際のポイント
契約書を作成する場合や相手方作成の契約書をチェックする場合、特にポイントを置かなければならないのは以下の3点です。
- 定義
- 契約解除|期限の利益の喪失
- 損害賠償
(1)定義
契約書では、色々な文言が使用されますが、契約当事者において幅のある解釈が可能な文言については、きちんと定義を設ける必要があります。
たとえば、複数の商品を対象とする売買契約書のなかで「本件商品」という文言が使われていながら、これについて定義が設けられていないと、「本件商品」がどの商品を指しているのかわかりません。
このような場合には、文言の解釈に疑義が生じないよう、本件商品が何を指すのかしっかりと定義しておくことが必要です。
さもなければ、契約当事者間において解釈の食い違いが生じ、トラブルに発展する可能性があります。
(2)契約解除|期限の利益の喪失
契約書には、一定の事実が発生した場合に契約を解除する旨の条項を設けることが一般的です。
多くの場合、債務不履行などの契約違反、強制執行や破産・民事再生などの各種手続きの開始などが解除事由として定められます。
ここでは、自社にとって不利な内容になっていないかという観点から、解除事由を作成・確認することが必要です。
また、契約解除と併せて定められる条項として「期限の利益喪失条項」があります。
「期限の利益」とは、契約書で定めた期限が到来するまでは支払いをしなくてもよい、という債務者に認められた利益のことをいいます。
期限までに支払いをしないと、債務者は期限の利益を喪失し(期限の利益を喪失するために必要な遅延回数は契約によってまちまちです)、債権者は、その時点から残りの債務を全額請求できるようになります。
また、期限の利益を喪失する事由は、支払いの遅延だけでなく、契約違反や破産・民事再生などの各種手続きの開始が含まれることが一般的です。
ここでは、期限の利益が失われることとなる条件(遅延の回数や期限の利益喪失事由)をしっかりと確認することが大切です。
(3)損害賠償
債務不履行をはじめ、契約に違反した場合において、相手方に損害を与えたときは、違反した当事者に損害賠償責任が発生します。
そのため、契約書には、一定の場合(契約違反や契約解除、期限の利益喪失など)に損害賠償責任が発生する旨を定めることが一般的です。
損害賠償条項で重要なポイントとなるのは、「損害賠償の範囲」です。
民法上、債務不履行に基づき発生する損害は、大きく「通常損害」と「特別損害」の2つに分類されています。
「通常損害」とは、債務不履行によって、通常生ずべき損害のことをいいます。
これに対し、「特別損害」とは、特別の事情によって生じた損害のことをいいます。
損害賠償の範囲を通常損害に限定するか、または、特別損害も含めるかによって、損害額が大きく異なります。
この点は、契約当事者間で争いになりやすいため、可能なかぎり明確にしておくことが必要になります。
また、そのような争いを避けるために、契約当事者の合意の下で、具体的な損害賠償額やその上限額をあらかじめ契約書で定めておくケースもあります。
3 まとめ
今回は3つのポイントに絞って見てきましたが、このほかにも、取引の内容に応じて設けるべき条項があります。
契約書を作成・確認する際には、取引内容に合った適切な契約書といえるかどうかがポイントとなりますので、覚えておきましょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。