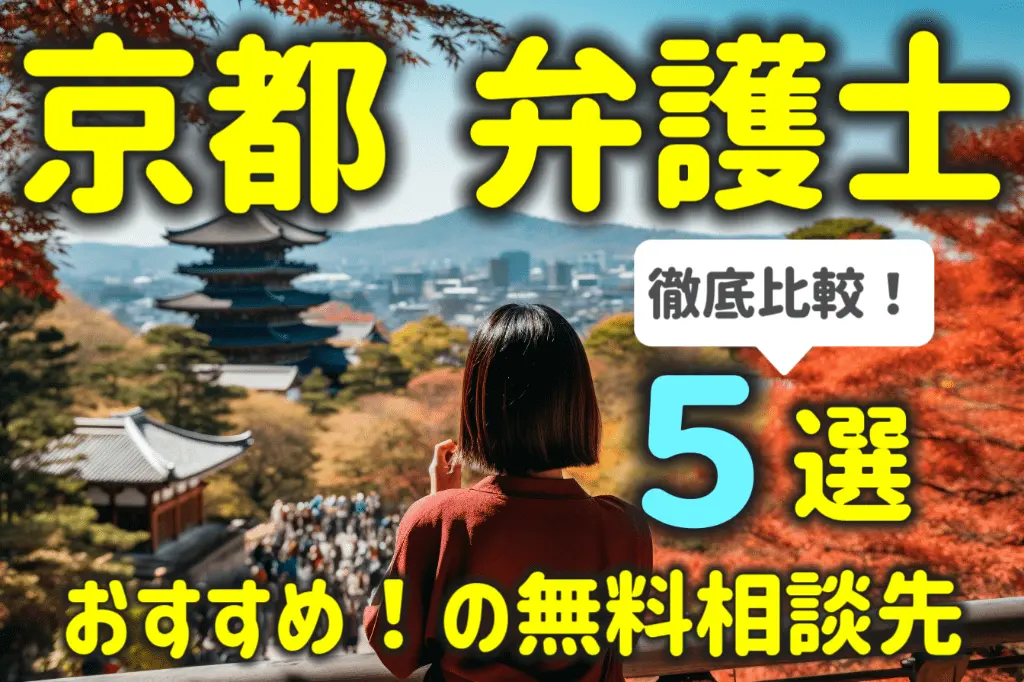メルカリユーザーは古物商?フリマアプリと古物営業法との関係を解説

はじめに
フリマアプリには、メルカリ、ラクマ、ショッピーズなど様々な種類があります。
このようなフリマアプリにおいて、法律的にはどのような問題に気を付けるべきなのでしょうか。
特に、フリマアプリで注意しなければいけないのは、古物営業法です。
古物営業法の規制の対象やルールを正確に理解せずにフリマアプリを運営したり、利用したりしていると、いつの間にか古物営業法に違反し、懲役や罰金など重いペナルティを負わなければいけない場合もあります。
そこで今回は、フリマアプリと古物営業法の関係について、メルカリの事例を取り上げて弁護士がわかりやすく解説します。
1 なぜ古物営業法が問題となるのか
 フリマアプリにおいて、なぜ古物営業法が問題となるのでしょうか。
フリマアプリにおいて、なぜ古物営業法が問題となるのでしょうか。
「フリマアプリ」とは、フリーマーケットや蚤の市のように、オンライン上で利用者同士が物品を売買できるアプリのことをいいます。
ハンドメイドの物を除けば、フリマアプリで売られる物の多くは、利用者がいらなくなった物・使わなくなった物です。
このようにいらなくなった物・使わなくなった物は、「古物営業法」における「古物」にあたる可能性があります。
ここでいう、「古物」とは、
- 一度使用された物品
- 実際に使用されていないが、使用のために取引された物品
- 上記①や②を補修したり修理した物品
のいずれかにあたるものをいい、以下の13種類に分類されています。
この表からもわかるように、フリマアプリでよく売買されているものが並んでいますよね。
そして、古物営業法では、このような古物の取引を行う前提として、公安委員会から許可を得たり、必要事項を届出したりしなければいけないことや、古物の取引相手が誰なのか確認したり、いつ、誰と、何を取引したのか記録しなければいけないことなどのルールを定めています。
そのため、古物を売買できるフリマアプリを利用したり、運営したりする際に、古物営業法のルールを守らなければいけないのか?が問題となります。
まずは、フリマアプリにおいて、古物営業法のルールを守らなければいけないのは誰なのかを確認していきましょう。
2 古物営業法を守らなければいけないのは誰か
フリマアプリにおいて古物営業法のルールを守らなければいけなのは誰なのでしょうか。
フリマアプリの関係者は以下の2者です。
- プラットフォーム運営者
- フリマアプリを利用するユーザー
古物営業法の規制対象を確認のうえ、これらの関係者のうち古物営業法のルールを守らなければいけない者が誰なのかを確認していきましょう。
(1)古物営業法の規制対象
古物営業法において、規制対象となっているのは、以下の者です。
- 古物商
- 古物競りあっせん業者
- 古物市場主
このうち、フリマアプリと関係があるのは、①古物商と、②古物競りあっせん業者です。
①古物商
「古物商」とは、営利を目的として繰り返し継続して、次の3つのうちどれかに該当する取引を行う者のことをいいます。
- 古物の売買
- 古物の交換
- 委託を受けて①または②を行うこと
この条件にあてはまる者は、あらかじめ公安委員会から古物商許可を受ける必要があります。
②古物競りあっせん業者
「古物競りあっせん業者」とは、営利を目的として繰り返し継続して、オークション形式(競りの形式)で古物を売りたいユーザーと買いたいユーザーをマッチング(あっせん)させ、ユーザーから利用料など、何らかの形で対価を取る者のことをいいます。
たとえば、ヤフオクなどのインターネットオークションは、この古物競りあっせん業者にあたることになります。
この古物競りあっせん業を行うためには、公安委員会に届出をしなければいけません。
もっとも、「ユーザーから何らかの形で利用料を取る」ことを一切しないということであれば、古物商あっせん業者にはあたりません。たとえば、広告などで利益を得ており、ユーザーから一切対価を得ない場合は、古物あっせん業者の届出は不要となります。
※古物市場主について知りたい方は、「古物営業法とは?古物取引で知っておくべき9つのルールについて解説」をご覧ください。
(2)プラットフォーム運営者
フリマアプリのプラットフォーム運営者は、古物商、古物競りあっせん業者にあたり、古物営業法のルールを守らなければいけないのでしょうか。
①プラットフォーム運営者は古物商?
フリマアプリを提供するプラットフォーム運営者は、ユーザー同士が商品(古物)を売買する場を提供しています。
運営者自身が古物を売買したり交換したりしていないため、古物商許可は不要です。
もっとも、運営者自身が、事業を拡大することなどを目的として、フリマアプリの機能とは別に、リサイクルショップのように、ユーザーから古物を仕入れたり、ユーザーに対して古物を売ったりする機能をつける場合は、話が別です。
運営者が古物を売買したり、交換したりすることになるため、古物商許可が必要になってきます。
②プラットフォーム運営者は古物競りあっせん業者?
古物競りあっせん業者は、オークション形式(競りの形式)で古物を売りたい人と買いたい人をマッチング(あっせん)させる者のことをいいましたね。
フリマアプリのプラットフォーム運営者が古物競りあっせん業者にあたるかどうかの最も重要なポイントは、オークション(競り)形式かどうかです。
ここでいう「オークション(競り)」とは、買いたい者それぞれが金額や条件を提示して、最も高い金額や最もよい条件を提示した者に、売却されるシステムのことをいいます。
もし、フリマアプリにおいて、全ての物品が固定額や固定の条件で売られていれば、プラットフォーム運営者は、オークション(競り)が行われていないので、古物競りあっせん業者にはあたらず、届出は不要となります。
また、次のような場合、先ほど示したオークション(競り)の定義にはあてはまりません。
- 買いたい者それぞれが提示した金額や条件を、互いに知ることができない場合
- 欲しい物を売ってくれるよう売却者を募集する場合(いわゆる逆オークション)
そのため、これらの機能がフリマアプリにあったとしても古物競りあっせん業者の届出は必要にはならないことになります。
(3)フリマアプリを利用するユーザー
フリマアプリを利用するユーザーは、直接古物の売買などを行うため、古物競りあっせん事業者にはあたりません。では、古物商にあたることはあるのでしょうか。
古物商とは、営利を目的として繰り返し継続して、古物を売買したり、古物の交換をしたり、委託を受けて古物の売買や交換を行うことでしたね。
ユーザーが古物商にあたるかどうかは、ユーザーの行っている古物の取引が営利を目的として繰り返し継続(営業)としているかどうかがポイントです。
たとえば、もう着なくなった服があるから少しでもお金に変えたいとフリマアプリに売りに出したユーザーや、自分で使うためにフリマアプリで定価よりも安く手に入れたユーザーはどうでしょう。
このように利益をあげることを目的としていなかったり、仕入れ・売却を繰り返していない一般的なユーザーは、「古物商」には該当しません。
そのため、古物商の許可を受ける必要はありません。
一方、営利を目的としていわゆる「せどり」や「転売」を繰り返し継続して行うユーザー(転売ヤーなど)の場合は、営業をしていると判断される可能性があります。
営業をしている場合は、個人・法人を問わず古物商許可が必要です。
もっとも、古物の取引が「営業」と判断されるかどうかは、営利を目的としているか、継続して取引を繰り返しているかなど、その取引の目的や実態などから個別に判断されるものです。一律に「いくら以上の利益が出たとき」や「何回以上取引を繰り返したとき」に営業と判断される、というものではなく、判断が難しいところです。
このように、フリマアプリのプラットフォーム運営者もユーザーも、場合によっては、古物営業法の対象になる可能性があるのです。では、古物営業法のルールを破るとどのようなペナルティが科されるおそれがあるのでしょうか。
※転売ヤーの法律問題について詳しく詳しく知りたい方は「転売ヤーを規制する法律は?関係する2つの法律を弁護士が詳しく解説」をご覧ください。
3 古物営業法違反のペナルティ
(1)許可・届出をしなかった場合のペナルティ
本来であれば古物商許可が必要なのに、それをしなかった場合、
- 最大3年の懲役
- 最大100万円の罰金
のいずれかを科される可能性があります。
意外と重いペナルティになっていることに驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、古物競りあっせん業者の届出が必要なのに、それをしなかった場合、
- 最大20万円の罰金
を科される可能性があります。
このように、現状、古物商関連よりも古物競りあっせん業者関連のペナルティのほうが軽くなっています。このように軽くなっているのは、今、古物競りあっせん業を行っている者が、古物営業法のルールを守っており、重いペナルティを科す必要がないと判断された結果です。古物競りあっせん業者の届出が必要なのに、それをしない者が増えれば、当然、ペナルティは重くなるでしょう。
(2)ユーザーの違反はフリマアプリのプラットフォーム運営者の責任?
フリマアプリのユーザーが古物商の許可をしなければいけないような転売を繰り返しているのに、許可を取得しない場合、古物営業法違反となります。
このように、ユーザーが古物営業法に違反したときに、そのプラットフォーム運営者にペナルティは科されるのでしょうか。
このような場合に、運営者に古物営業法上のペナルティが科されることはありません。なぜなら、古物営業法では、プラットフォーム運営者にペナルティを科すというルールは定められていないからです。
もっとも、運営者に法律上のペナルティがないとしても、法令に違反しているユーザーを放置することは、企業の信用やブランド価値の低下を招くおそれがあります。
また、ユーザーが盗品をフリマアプリに出品していた場合、それが盗品だと運営者が知った後も掲載の削除などの適切な対応を行わない場合、詐欺や盗品の処分を手助けしたとして、刑法の詐欺罪や盗品等に関する罪などのほう助となってしまう可能性もあります。
そのため、コンプライアンスの精神にのっとり、これらのリスクを負わないよう、運営者は適切な対応を心がける必要があるといえます。
ここまで、一般的なフリマアプリと古物営業法の関係を解説してきました。
次の項目からは、実際にフリマアプリのプラットフォーム運営者であるメルカリと、古物営業法との関係を確認していきましょう。
4 メルカリはどうしているのか
メルカリと古物営業法の関係を理解するためには、まずはメルカリのサービスについて知る必要があります。
(1)メルカリが提供しているサービスとは
「メルカリ」とは、株式会社メルカリが運営している日本最大のフリマアプリです。そのサービスの内容をまとめると以下の図のとおりになります。
ユーザーは、メルカリのアプリを使って他のユーザーが出品した商品を購入したり、自ら商品を出品して販売したりできます。
この図からもわかるとおり、ユーザー間のトラブルを防止するため直接お金のやり取りはさせず、メルカリが間に入っています。このように取引の安全を保証するサービスのことをエスクローサービスといいます。
※エスクローサービスについて詳しく知りたい方は、「3分でわかる!ECサイトでエスクローを導入する際の法的問題とは?」をご覧ください。
また、エスクローサービスなどに対する規制の最新動向については「割勘アプリに規制が!資金決済法改正ポイント3つを法律案を基に解説」をご覧ください。
(2)メルカリは古物商?
メルカリは古物商ではありません。
なぜなら、メルカリが提供しているサービスはユーザー同士が商品を売買する「場」を提供することに限定されており、自ら商品を売買したり、委託を受けて売買したりしているわけではないからです。この場合は、古物営業法でいう古物商には該当しないため、古物商許可は不要です。
(3)メルカリは古物競りあっせん業者?
メルカリは古物競りあっせん業者ではありません。
なぜなら、メルカリは商品の売却金額についてオークション(競り)形式を採用せず、、出品者により商品の売却金額が設定されるからです。そのため、メルカリは、古物競りあっせん業者としての届出をする必要はありません。
(4)ユーザーに古物商許可を取得させているか
不用品を売りたいユーザーや自分が使うために安く商品を手に入れたいユーザーには古物商許可は不要な一方で、営利目的で繰り返し古物を売買するユーザーは、古物商許可を受ける必要があります。
実際に、古物商許可を受ける必要がある具体例として、2018年8月にサービスを終了した「メルカリNOW」というサービスを確認していきましょう。
このサービスは、「あなたのアイテムが今すぐお金に変わる」というコンセプトで、メルカリのグループ会社である「株式会社ソウゾウ」がユーザーの商品を査定して買い取り、買い取った商品をメルカリに出品するというものでした。
具体的な「メルカリNOW」の取引の流れは次のとおりです。
- ユーザーの商品を査定
- ユーザーから商品を買取
- メルカリのアカウントに売上金を入金
- 集荷・配送
- 買い取った商品をメルカリ上で販売
つまり、株式会社ソウゾウは、メルカリの運営するフリマアプリに1ユーザーとして参加していたことになります。営利目的で古物の売買を繰り返す場合は、古物商許可の取得が必要です。そのため、株式会社ソウゾウは、古物商許可を取得していました。
このように、メルカリを利用しているユーザーの中にも、古物商許可が必要な者がいます。メルカリは、このように古物商許可が必要な者が、適切に古物商許可を取得してから出品をするようにするため、利用規約でルールを定めています。
具体的な利用規約の内容は後ほど、解説します。
(5)メルカリは古物営業法を守らなくていいのか
メルカリは、古物商にも、古物競りあっせん業者にもあたりません。また、メルカリを利用するユーザーが古物商の許可を取得しなければいけない場合であっても、メルカリ自身が古物商許可などが必要になるということもありません。
そのため、メルカリは、古物営業法の規制の対象外であり、古物営業法のルールを守る必要はないようにも思えます。
もっとも、2017年に、今後の古物営業の在り方について、メルカリを含め有識者によって会議が行われました。この会議では、フリマアプリも古物営業法の規制対象とすべきとの意見もでましたが
- フリマアプリ運営者や業界団体の自主規制にまずは任せる
- 自主規制が機能しないようであれば、法律による規制を検討する
といった、方向性で決着しました。
この会議からもわかるとおり、メルカリなどのフリマアプリは、基本的に古物営業法の規制対象ではありませんが、古物営業法のルールに基づいて自主規制を設けなければいけなくなったといえます。
では、メルカリは具体的にどのような自主規制を行っているのでしょうか。その対応策を確認していきましょう。
5 メルカリに学ぶ具体的な対応策
メルカリが古物競りあっせん業者にあたらないのは、オークション(競り)を行っていないからでしたよね。その他、事業者自身は取引に参加せず、ユーザー同士が古物を売買できる場を設けるという点では、メルカリも古物競りあっせん業者も同じです。
そのため、メルカリは、古物あっせん業者に課されるルールに基づいて自主規制を設けています。
- 古物あっせん業者に課されるルール
- 古物営業法に対する具体的な対応
- その他メルカリが行っている対応
- 利用規約によるルールの明文化
の順で確認していきましょう。
(1)古物競りあっせん業者に課されるルール
古物営業法は、古物競りあっせん業者に対して、以下の3つのルールを課しています。
- 出品者を確認するよう努めること
- 盗品などの疑いがあるものが出品された場合には警察に申告すること
- 古物の取引の記録を作成し、1年間保存するよう努めること
これらのルールは、盗品などの売買をしづらくし、犯罪を抑止するとともに、仮に売買されそうになっても速やかに盗品などを発見することで、被害者に返すことができるように、設けられています。
では、メルカリは、これらのルールをどのように遵守しているのでしょうか。
(2)古物営業法に対する具体的な対応
メルカリは、これらのルールを守るために、具体的に以下の対応を行っています。
①出品者の確認
メルカリで出品をする際には、本人情報の登録が必須となっています。
この登録時に、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類の提出をさせているため、出品者が誰なのかを確認することができるようになっています。
②盗品などの疑いがあるものが出品されていないかの確認
メルカリは以下のチェック体制を構築しています。
- AIによる不正検知の取り組み
- 違反商品、違反アカウントの早期排除のためのカスタマーサービスによる24時間365日の稼働
AIによるモニタリングや、カスタマーサービスによるチェックにより、盗品などの疑いがある商品の検知が可能となっています。
③古物の取引の記録
取引の記録は、台帳などの紙で行わなければいけないわけではなく、パソコンやサーバーなどの電磁的方法でもOKです。
古物営業法では、以下の事項を記録するよう努めることを求めています。
- 古物の出品日
- 古物の出品情報及び出品者・落札者のユーザーID等でサイトに掲載されたもの
- 出品物の品名(タイトル)、出品者が付した商品の説明、出品物の画像等の出品者が送信したもの
- 出品者・落札者がユーザー登録等の際に登録した人定事項であって、古物競りあっせん業者が記録することに同意したもの
社外からは、メルカリがどのように記録しているかを確かめるすべはありませんが、プライバシーポリシーにも、以下の記載があることから、情報を記録しているものと考えられます。
1.取得する情報
(2)弊社グループが本サービスの利用に関連して取得する情報
個人情報に該当するか否かにかかわらず、本サービスの利用に関する以下の情報を取得します。
a.お客様がご利用になった本サービスの内容、ご利用日時および回数、本サービス利用時のお客様のオンライン行動等、お客様による本サービスの利用・閲覧に関連する情報(これには、Cookie情報、アクセスログ等の利用状況に関する情報、ご利用の端末情報、位置情報、そしてIPアドレス、ブラウザ情報、ブラウザ言語等を含むお客様の通信に関する情報を含みます)
(3)その他メルカリが行っている対応
また、不正競争防止法で規制されている模造品や、薬機法で規制されている医薬品など、古物営業法とは別の法律で規制されているものが出品されることもあります。
メルカリでは、法令に違反する商品や社会的に出品が好ましくないモノが出品されないように以下のことを行っています。
- 社内に禁止出品物。禁止行為基準策定委員会を設置し、ルールを策定・適用
- 国民生活センターなどの省庁、団体、企業と連携した情報収集
(4)利用規約によるルールの明文化
もしユーザーが古物商許可を受けずに営業として古物を売買していたとしても、プラットフォーム運営者に対するペナルティはありません。とはいえ、企業としての信用やブランド力を守るためには、法令に違反しているユーザーや出品を放置しておくわけにはいきません。
そこで、メルカリは、利用規約を作成し、ユーザーの法令違反を発見したときには、運営者の判断でユーザーに対して適切な措置が取れるようにしています。
メルカリの利用規約の内容のうち、特に古物営業法との関係で重要なのは、以下です。
- 法令遵守
- 利用規約に違反したときの措置
- 免責事項
①法令遵守
一般的には、利用規約の禁止事項の1つとして「法令に違反する行為」と記載したり、または「法令を遵守しなければなりません」という表現を用いたりして、ユーザーに対して法令遵守を求めます。
メルカリでは、
第9条商品の出品
4. 法令遵守
ユーザーは、出品にあたっては、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法、著作権法その他の法令を遵守しなければなりません。
と定めています。法律名を挙げて強調することで、ユーザーに対して、「〇〇」って名前の法律を守らなければいけないんだと、意識させることができます。
②利用規約に違反したときの措置
利用規約には、利用規約に違反したときのペナルティを定めておく必要があります。ペナルティのない利用規約では、ルールが形骸化したり、違反したユーザーに対して何の対応もできないということが起こってしまいます。少なくとも、ユーザーの違反行為を止めるための措置と再発防止のための措置は定めておくべきでしょう。
たとえば、メルカリでは、
- 出品の取消
- 出品に対して発生していた購入行為等の取消
- ユーザー登録の取消
- サービスの利用停止
- サービスへのアクセスの拒否
などの措置を定めています。
①の法令順守のようにユーザーが守るべきルールと、それを破った場合の措置を定めておくことで、メルカリは、ユーザーが古物営業法に違反して出品した場合には、その出品を取り消すことや、ユーザーの登録を取り消すなどの対応ができるようになります。
※利用規約違反への措置の定め方について詳しく知りたい方は、「利用規約違反への制裁は?定めるべき2つの措置の有効性を徹底解説!」をご覧ください。
③免責事項
古物営業法など利用規約に違反しているユーザーに対して出品やユーザー登録を取り消した場合、そのユーザーや、そのユーザーと取引していた別のユーザーなどの第三者に損害が生じる可能性があります。そうなると、プラットフォーム運営者は、その損害賠償を請求されてしまう可能性があります。
そこで、利用規約違反への措置によってそのユーザーや第三者に損害が生じても、運営者は責任を負わないということを利用規約に定めておいたほうがいいでしょう。
たとえば、メルカリでは以下のように免責事項を定めています。
第23条
2.弊社の免責
弊社は、弊社による本サービスの提供の停止、終了又は変更、ユーザー登録の取消、コンテンツの削除又は消失、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障その他本サービスに関連してユーザーが被った損害につき、弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。
このように免責事項を定める際に、単に利用規約中に「一切の責任を負いません」と書けばいいのではと思った方は要注意です。その免責条項は無効になる可能性があります。利用規約の免責事項については、詳しくは、「利用規約の免責事項を作成しよう!4つのビジネスモデル別に徹底解説」をご参照ください。
このように、利用規約を定めておくことによって、ユーザーが古物営業法などに違反した場合に適切な措置を取ることや事業者が損害を負わなければいけなくなるのを防ぐことができます。そのためにも、自社の提供するサービス内容に合わせて利用規約を作ることが重要になります。弁護士などの専門家に利用規約の作成を依頼して、考えられるさまざまなトラブルに備えておくと安心でしょう。
6 小括
フリマアプリと古物営業法は切っても切れない関係です。
これは、フリマアプリを提供するプラットフォーム運営者だけでなく、フリマアプリを利用するユーザーも同様です。個人であっても、古物営業法のルールを守らなければいけない場合があることに注意が必要です。
また、これからフリマアプリを運営する場合、先駆者のメルカリが古物営業法などとの関係でどのような対応をしているかについて学ぶことは、非常に有益だといえます。
盗品など違法なものが紛れ込みやすい業界だからこそ、ユーザーが安心して安全な取引を公正にできるようにする場を提供することが重要です。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 古物営業法とは、古物を取引するときのルールを定めた法律である
- 古物営業法の規制対象は、①古物商、②古物競りあっせん業者、③古物市場主である
- フリマアプリのプラットフォーム運営者は、古物商、古物競りあっせん業者のどちらかにあたることがある
- フリマプリの利用者であるユーザーは、古物商にあたることがある
- メルカリは、古物商でも古物競りあっせん業者でもない
- メルカリなどのフリマアプリ事業者は古物営業法の直接の規制対象ではないが、古物営業法のルールを守ることが求められている
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。